保育園で行われる誕生日会は、園中の皆から誕生日をお祝いしてもらえる特別なイベント。
心に残る会にするために、ねらいや配慮を明確にしておくことが大切です。
本記事では、誕生日会のねらいや配慮が必要なポイントをご紹介するので、企画する際の参考にしてみてください。
- 誕生日会の指導案には「ねらい」「活動内容」「環境構成」などを記入する
- 誕生日会を行う際は、個々の気質や障害の有無などに配慮する
- お祝いの歌やダンスのほかに、保育者の出し物があると場が盛り上がる
- 季節のテーマを取り入れたり誕生日カードを用意したりすると、より思い出に残る
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライター誕生日会は、子どもにとって1年の中で特に記憶に残るイベントです。「楽しかった」「お祝いしてもらえて嬉しかった」と思ってもらえるような会にするために、念入りに事前準備を行いましょう。


ゆぴ先生 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
【保育園の誕生日会】指導案の書き方
誕生日会を企画する際には、他の年中行事同様、指導案を作成するとスムーズに進行します。
ねらいや活動内容、環境構成などを記入して、職員が共通理解できるようにしておきましょう。
項目ごとの書き方や記載例をご紹介するので、保育士の方は指導案作成時の参考にしてみてください。
ねらい
- 身近な人から誕生した時の話を聞き、自分が愛されていることや命の大切さを知る
- 誕生日のお祝いを通じて、成長の喜びや将来への期待を持つ
- 自分を祝ってくれる人がたくさんいることを知り、周囲の人へ感謝の気持ちを持つ
- 友だちの誕生日を祝い、仲間の大切さを知る
年齢や発達によって誕生会のねらいは異なるので、対象児に合うものを設定しましょう。
乳児なら「安心感をもってお祝いを受ける」、幼児なら「自分や友だちの成長を喜び合う」といったねらいが適しています。
ほかにも、「人との関わりを大切にする」「感謝の気持ちを育む」など、園の理念や年間計画に沿う形にする、お祝いの歌やインタビューといった実際の活動内容とリンクさせることも、ねらいを設定する上で大切です。
活動内容
- 「たんじょうびの歌」を歌ってお祝いする
- 保育者から好きな食べ物や将来の夢などのインタビューを受ける
- 保育者の出し物を見て楽しむ
誕生日会の一番の目的は、「誕生日を迎える子をみんなでお祝いする」ことです。
「たんじょうび」「ハッピーバースデートゥーユー」などのうたを全員で歌って、お祝いしましょう。
ほかにも、保育者による劇やダンスなどの出し物を見たり、主役のインタビューコーナーを設けたりしても盛り上がりますよ。
活動内容を記入する際は、具体的な活動内容やそれに伴う保育者の動き、所要時間など、何を行うのか一目で把握できるよう意識してみてください。
環境構成
- 誕生月の子に送る冠や誕生日カードを用意する
- 会場をバルーンやガーランド、花紙などで飾り、華やかな雰囲気をつくる
- 子どもたちが見やすく、落ち着いて座れる座席配置を設定する
- 歌やゲームの進行、写真撮影、補助などを分担する
環境構成は、「物的環境」「人的環境」「雰囲気づくり」の3点に分けられます。
小物道具の用意などをする物的環境、保育者の役割や配置といった人的環境に分けて記入しましょう。
また、子どもの座り方やステージの位置、小物置き場などを図にして記載しておけば、どの職員が関わっても迅速に対応できます。
予想される子どものすがた
- 冠やカードを受け取って嬉しそうにする
- みんなからの歌や拍手に照れながらも笑顔になる
- インタビューでは恥ずかしさから話せなくなってしまう
- 歌や拍手で友だちをお祝いしようとする
「お祝いされて嬉しそうにする」「堂々とインタビューに答える」といったプラスな姿だけでなく、「恥ずかしくて固まってしまう」「緊張から泣き出す」のように様々なシチュエーションを考えておくとよいです。
あらゆる状況を想定しておけば、保育者がどう対応するべきかイメージしやすいでしょう。
指導案の展開例
以下は、誕生日会の指導案の展開例です。
園によって書式は異なりますが、時間や子どもの姿、保育士の援助、環境構成は必ず記入するようにしましょう。
誕生日会の企画で配慮が必要なポイント3つ
保育園で行う誕生日会では、子どもの個性や家庭環境、発達障害などに配慮する必要があります。
誕生日会は、「子ども全員が楽しい」と感じることが目的なので、主役だけでなく参加する全員が安心できる環境を整えてあげましょう。
ここでは、3つの視点から配慮するポイントを解説します。
子どもの個性・気質への配慮
- 人前に出るのが好きな子には、自己紹介やインタビューで発表の場を多めに用意する
- 人前が苦手、恥ずかしがり屋の子には無理に発表させず、頷くだけやカードを見せる形でもOKにする
- 注目されることに不安を感じやすい子には、人前に出る時間を短くし、一斉からの注目を避ける配慮をとる
人前に出たり注目されたりするのが好きな子、人前が苦手、恥ずかしがり屋な子など、子どもの個性は様々です。
保育者は個々の個性や気質を理解し、どのように関わるかを事前に考えておきましょう。
注目されることが苦手な子に対しては、発表は無理にさせず頷くだけなど参加方法を柔軟に変更したり、事前に誕生日会の流れを説明し見通しを持たせたりしておくことが大切です。
園内で合同誕生日会を開く場合は、別のタイミングで規模を小さくしてお祝いする機会を設けてみてもよいでしょう。
家庭環境への配慮
- 入園時や年度初めに「誕生日会の実施内容」や「お祝い方法」について説明し、保護者の意向を確認しておく
- 宗教的・文化的な理由で誕生日を祝わない家庭には、参加方法や代替案を提案する
- ひとり親家庭や祖父母と暮らす子など、家庭構成に応じた声かけをする
宗教的な問題で誕生会に参加できない、撮影やSNSへの掲載がNGなど、家庭にはそれぞれの事情があります。
後で問題にならないよう、入園時や年度初めに誕生日会の実施内容やお祝い方法を説明し、参加が可能であるか確認しておきましょう。
宗教上の問題で誕生日を祝えない子に対しては名前と生年月日を読み上げる、ひとり親の子に対しては「お父さんお母さん」ではなく「おうちの人」と表現するなど、どのように配慮するかを保育者間で話し合っておくことが大切です。
発達障害や特別な支援が必要な子への配慮
- 見通しを持つのが苦手な場合…事前に絵カードや写真で会の流れを説明する
- 大きな拍手や音楽が苦手な場合…音量を下げる・耳栓やヘッドホンを使う
- 長時間座ることが難しい場合…途中で動けるスペースを確保する
誕生日会では、発達障害や特別な支援が必要な子への配慮が欠かせません。
誕生日会は特別感のある楽しい行事ですが、大きな音や予定外の出来事が苦手な子にとってはストレスになることもあるでしょう。
絵カードを使用して見通しを持たせる、耳栓やヘッドホンを装着するなど、事前の準備と柔軟な対応が安心感につながります。
「みんなと同じ形」にこだわらず、その子が安心して参加できる方法を選べるようにすることが大切です。
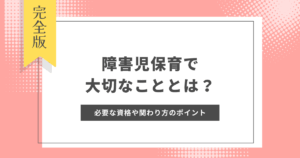
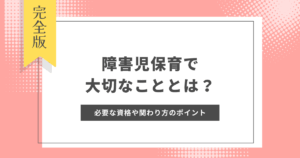
誕生日会の導入におすすめする絵本は?
誕生日会の導入におすすめの絵本を下記にいくつか挙げてみました。
- 「たんじょうびおめでとう」 わかやまけん/作(こぐま社)
- 「おたんじょうびのおくりもの」芭蕉みどり/作(ポプラ社)
- 「ケーキがやけたら、ね」ヘレン・オクセンバリー/作(評論社)
- 「おたんじょうびのひ」中川ひろたか/作(朔北社)
年齢・発達に合った内容と長さであるか、温かく前向きなメッセージのものであるかなどを基準に絵本を選んでみるとよいでしょう。


保育園のお誕生日会・当日の流れ
新人保育士の方は、「誕生日会ってどんな流れで行えばよいの?」と困ることもあると思います。
保育園で行う誕生日会は、はじまりのあいさつから始まり、主役のインタビュー、お祝いの歌やダンスなどの出し物…が一般的な流れです。
ここでは、誕生日会の流れの一例を紹介するので、指導案を立てる際の参考にしてみてください。
①はじまりのあいさつ
誕生日会は、はじまりのあいさつからスタートします。
特別感を出しつつも、普段の保育の安心感を保つトーンで進めるようにしましょう。
いきなり主役の子どもの名前を呼んでしまうとプレッシャーがかかってしまうため、まずは会全体の流れを簡潔に説明してあげるとよいですよ。
- 明るく分かりやすく伝える
- 主役の子どもへのプレッシャーを減らす
- 会全体の流れを説明する
②主役の紹介とインタビュー
主役の紹介やインタビューは、会の盛り上がりポイントでありつつ、主役の子にとっては少し緊張する時間でもあります。
安心して参加できるように「基本情報や質問内容はゆっくり伝える」「恥ずかしがる子に対しては保育者が代弁する」などを意識すると、主役の子が自信を持って参加でき、会全体も温かくまとまりますよ。
- 名前・年齢・クラスなど基本情報は保育士がゆっくり、はっきりと伝える
- 恥ずかしがる子には「○○くん、今日は○歳になりましたね」と保育士が代弁する
- 質問は短く、答えやすいものを選ぶ
③お祝いの歌やダンス
お祝いの歌やダンスは、会場を盛り上げて「お祝いムード」を作る大事な時間ですが、子どもの年齢や特性によっては負担になることもあります。
曲の長さやテンポを考慮したり、主役にプレッシャーを与えないよう前に出ることを強要したりしないなど、楽しく参加できるよう配慮しましょう。
- 低年齢児や集中が続きにくい子には、短めの歌や簡単な振り付けにする
- 「前に出て踊る」などを強制せず、座って聴くだけ、一緒に手拍子だけでもOKにする
- 「みんなで○○ちゃんのお祝いをしよう!」と声かけをして、主役と周りの子が一緒に楽しめる空気を作る
④プレゼント・カード渡し
主役の子が特別感を感じられるプレゼント・誕生日カード渡しは、ちょっとした配慮でより安心し温かい空間になります。
恥ずかしさや緊張で表情が固まっても、「カードを貰えて嬉しいね」とポジティブに返してあげましょう。
また、その都度プレゼントやカードの渡し方が異なると不公平になってしまうため、年度初めに渡し方を話し合い、毎回同じ形式で行うのもポイントです。
- 手作りカードや寄せ書きは、年齢や発達段階に応じた表現(絵・シール・手形など)にする
- 子どもが渡す場合、全員の注目が集まり負担がかからないよう保育士と一緒に渡してもOK
- 嫉妬や不公平感が出ないよう、毎回同じ形式で行う
⑤保育士による出し物
保育士による劇やダンスなどの出し物は、誕生日会の中で特別感を味わえる内容の一つです。
年齢や発達に合った内容にする、声を出したり体を動かしたりして子どもが参加できるものを取り入れるなど、ワクワク感を得られる出し物選びの工夫をしてみてください。
子どもが興味を持ちやすく楽しめる出し物には、劇やダンス、楽器演奏、マジックショーなどがありますよ。
- 年齢や発達段階に合った内容にする
- 子どもの集中力に考慮し、長い時間の演出のものは避ける
- 子どもたちが声を出す、手を動かすなど参加できる要素を入れる
【元保育士が解説!】保育園の誕生日会・おすすめの出し物
毎月誕生日会で出し物を披露していると、次第にネタ作りが大変になりますよね。
ここでは、元保育士が「新聞紙マジック」「ハンズパフォーマンス」「風船シアター」を紹介します。
どれも子どもたちが釘付けになること間違いなしなので、ぜひ参考にしてみてください。
新聞紙マジック
新聞紙を使った「マジックショー」は、必要な道具が少なく場所を問わずできるのがポイントです。
以下の動画では、「新聞紙の中に水を入れても漏れないマジック」「破った新聞紙がすぐに原型に戻るマジック」「筒状の新聞紙から異なる形の新聞紙が出てくるマジック」の3つを紹介しています。
タネが分かれば簡単に実践できるので、ぜひ真似してみてください。



私が幼少期時代、担任の先生がこの新聞紙マジックを披露していました。ドキドキしながら見ていたのを今でも覚えています!
ハンズパフォーマンス
手袋をはめた手のみでパフォーマンスを行う「ハンズパフォーマンス」です。
音楽に合わせながら予想不可能な動きをする手のパフォーマンスに、子どもたちは目を奪われること間違いありません。
「次はどういうふうに動くんだろう?」「あれはどの先生の手だろう?」と、好奇心でいっぱいになりますよ。
練習時間が必要になりますが、演者側も達成感を得られる出し物なので一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
風船シアター
プレゼントの箱の中から風船でできた動物やケーキが登場する「風船シアター」です。
箱を開けると風船が少しずつ膨らんでいき、「何が出てくるんだろう?」とドキドキワクワクする演出になっています。
最後には大きな誕生日ケーキを登場させて、「お誕生日おめでとう!」とお祝いしてみましょう。
保育者は、進行する際に抑揚をつけたり表情を意識したりして、子どもが期待を持って参加できるよう工夫してみてください。
【元保育士がアドバイス】誕生日会を成功させるコツとは?
ここでは、元保育士の私が実際に取り入れた出し物や思い出に残っている誕生日会の内容をご紹介します。
オリジナルバースデーケーキを作るパネルシアター
私が勤めていたとある園では、クラス内で誕生日会を開いていました。
主役の子も周りの子も楽しく参加できるよう、自作のパネルシアターを使ってお祝いするのが定番に。
ケーキの土台に、主役の子どもがろうそくやいちご、チョコレートなどを自由にデコレーションし、最後はろうそくの火を吹き消します。
主役の子どもはもちろん、見ている周りの子どももどんなケーキができるのかワクワクしながら見れて、全員で楽しい時間を過ごせました。



パネルシアターやペープサートは、作成するのに時間がかかり大変ですが、一度作ってしまえば何度でも繰り返し活用できるのでおすすめ。保育雑誌などにある型紙を使用すれば簡単に作れるため、1つでも持っておくと自分の保育の引き出しが増えますよ。
ピアノとバイオリンによるコンサート
バイオリンが弾ける友人に協力してもらい、保育者が演奏するピアノとバイオリンデュエットのミニコンサートを開いたことが、今でも強く印象に残っています。
ディズニー、ジブリ音楽からクラシックまで様々なジャンルの曲を披露し、子どもはもちろん大人も釘付けに。
普段生で聴く機会の少ない楽器の音楽鑑賞は、特別な時間になりますよ。
「ハッピーバースデートゥーユー」など親しみのある曲を演奏すれば、子どもたちも歌で参加でき最後まで飽きずに楽しめます。



楽器演奏に限らず、絵画やダンスなど自分の特技、能力を出し物に取り入れてみてはいかがでしょうか。子どもは目新しいものに興味があるので、精度は高くなくても大丈夫。何か自分の中でアピールできるものがあれば、活かしてみてくださいね。
誕生日会をより豊かにするアイデア
誕生日会の流れや演出が毎回似たようなものだと、子どもも次第に関心が薄れ期待を持ちづらくなります。
新鮮さを追求するには、季節のテーマを取り入れる、誕生日を盛り上げるグッズを作るなど様々な方法があります。
ここでは、誕生日会をより豊かにするアイデアを4つご紹介するので、パターン化にお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
季節のテーマを取り入れよう
誕生日会に季節のテーマを取り入れると、行事感が増して子どもたちもワクワクします。
- 春…てんとう虫やちょうちょの帽子を被りお祝いする
- 夏…魚やイルカのペープサート、ブルーの装飾
- 秋…野菜や果物の手作りカードで主役をお祝いする
- 冬…「クリスマスソング」「ベルの手遊び」などを組み合わせる
上記は、季節ごとのアイデアの一部です。
季節に合う歌を歌う、装飾をする、誕生日カードをアレンジするなどして、誕生日のお祝いと一緒に季節を感じられるようにしてみてはいかがでしょうか。
保護者からのメッセージ動画や手紙
保護者からのメッセージ動画や手紙を誕生日会に取り入れると、子どもにとって特別感が増し、温かい雰囲気を作れます。
- 各家庭でメッセージ動画を短く撮影してもらい、誕生日会で上映する
- 「○歳のお祝いメッセージ」「好きな遊びや得意なこと」などテーマを伝え、手紙を書いてもらう
- 歌やダンスの後に読み上げて、余韻が残るよう工夫する
保護者にメッセージ動画や手紙を依頼する場合、仕事と育児の両立で忙しいことを考慮し、期間に余裕を持ってお願いするようにしましょう。
誕生会を盛り上げるためのグッズを作成しよう
誕生日会を盛り上げるのに、お祝いグッズは欠かせません。
年齢や発達、会の雰囲気に合うものを選んで準備してみましょう。
- 紙やフェルトで作る手作り冠
- 「○歳おめでとう」バッジやシール
- 主役の登場時に演出する紙吹雪やシャボン玉
- 名前や年齢を入れたバルーン・ガーランド
その都度演出の仕方やお祝いグッズが異なると、「僕もあれがよかった」と不公平感や嫉妬に発展してしまう恐れがあるため、演出の大まかな土台は毎回統一しておくのが無難です。
誕生日会を通じた食育(誕生日メニューの工夫)
誕生日会に食育の視点を取り入れると、ただ楽しいだけでなく、食への関心や感謝の気持ちも育てられます。
以下は、誕生日メニューの工夫アイデアの一例です。
- いちごのデザート、きのこ入りスープなど季節の食材を使った献立
- 主役の好きな食材を使った「○○ちゃんスペシャルメニュー」
- 手巻き寿司やサンドイッチ、カップケーキやクッキーのデコレーションなど、子どもの参加型メニュー
季節の食材や主役の子の好きな食材を取り入れた献立にしたり、子どもが参加できるメニューにしたりするだけで、一気に特別感が増しますよ。


まとめ
保育園の誕生日会は、子どもの成長を祝いながら自己肯定感や仲間との絆を育む大切な行事です。
ねらいを明確にし、子どもの個性や気質、家庭環境、発達の特性に応じた配慮を行うことで、それぞれが安心して楽しめる場になります。
活動内容や演出、食育などにも工夫を凝らして、保護者や友だちと共に喜びを共有しながら心温まる誕生日会にしてみてくださいね。








