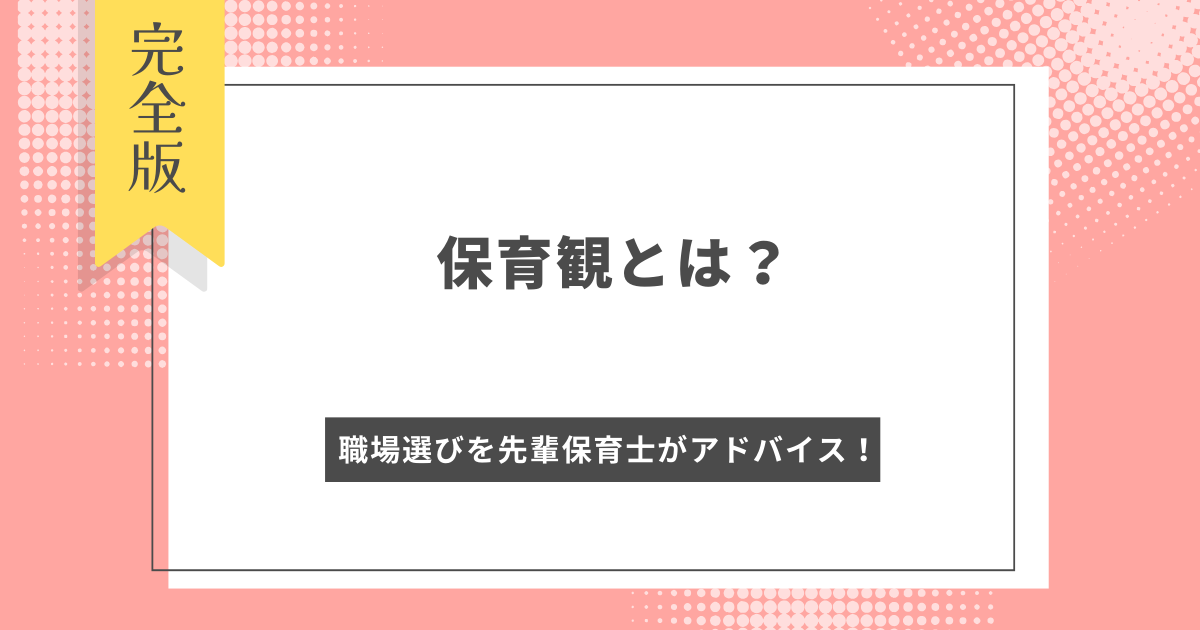保育観は、保育をするうえで大切にしている考え方や価値観を指します。
自分の保育スタイルに一貫性を持たせるために、保育観を持つことは大切です。
「自分の保育観がいまいち分からない」とお悩みの方に、本記事では保育観とは何なのか詳しくご紹介します。
- 保育観とは、保育を行ううえで大切にしている考え方や価値観
- 保育者一人ひとりが異なる保育観を持っているため、互いに尊重しなければならない
- 具体的には、コミュニケーションを重視する保育、子どもの自立を促す保育などがある
- 面接試験で保育観について聞かれた際スムーズに答えられるように、自分の保育観を明確にしておく
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライター保育観を持っていれば、どのような職場で働きたいのかが明確になり、就職先も探しやすいです。自分のやりたい保育を考えれば、自然と保育観も浮かび上がってきます。本記事を参考にしながら、自分の考えを見つけてみてくださいね!


ゆぴ 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
そもそも保育観とは?
保育観とは、保育者一人ひとりが持つ「保育を行ううえで大切にしている考え方や価値観」です。
保育観の一例を、以下に挙げました。
- 子どもの主体性を大切にする保育
- 一人ひとりの個性を尊重する保育
- 子どもの気持ちに寄り添う保育
- 子どもの気持ちを一番に優先する保育
保育士に就く前から「子どもの気持ちに寄り添う保育がしたい」と決めている保育者もいれば、保育経験を積み重ねる中で「子どもの個性を尊重した保育にフォーカスしたい」と次第に保育観が定まる保育者もいるでしょう。
保育現場では、このようにそれぞれの保育観を持った保育者が協力し合いながら子どものサポートをしていく必要があります。
保育観が違うと起こる問題は?
保育者同士の保育観が違うと、子どもの関わり方に一貫性がなくなる、質の良い保育が行えないなど様々な問題が起こります。
子どもがいけないことをした場合、すぐに注意する考えの保育者と口を出さず見守る考えの保育者が同じクラスにいると、対応がバラバラになるのがその一例です。
保育者同士が正反対の価値観を持っていると子どもの関わり方にずれが生じ、子どもも混乱したり不安になったりするでしょう。
- 子どもの関わり方に一貫性がなくなる
- 保育者同士の信頼関係が築きにくい
- 質の良い保育が行えない
- 職場へのストレスが生じ転職を余儀なくされる
主な保育観の例
保育観は子ども主体の保育、しつけ重視の保育、コミュニケーションを重視する保育など様々です。
ここでは、保育観とはどういうものを指すのか、具体的な考えとその実践例を5つご紹介します。
あらゆる保育観を知れば保育の見方がこれまでとは異なるかもしれないので、自分の保育観を持っていない方は下記を参考に明確にしてみてください。
コミュニケーションを重視する保育
子どもや保護者、保育者との会話や関係性など、コミュニケーションを大切にする保育です。
- 勤務時間以外や作業中であっても、子どもに話しかけられたら手を止めて耳を傾ける
- 子ども同士のトラブル時は一方的に止めず、「どうしたの?」「〇〇くんはどんな気持ちかな?」と気持ちを言葉にして手助けする
- その日の子どもの姿や成長を保護者に直接伝える
- 保育者同士で子どもの姿をこまめに共有する
子どもの姿を共有したり保護者の思いに寄り添ったりするために、コミュニケーションを重視する保育者は大勢います。
子どもの個性を尊重する保育
子どもは1人ひとり性格や成長のスピード、興味を持つものなどが異なります。
これらの特徴を大切にして関わる考え方が、子どもの個性を尊重する保育です。
- 製作時は必ず見本通りに作らせようとせず、子どもの発想を大事にする
- 活動への参加を強要せず、興味や意欲に合わせて対応する
- 個々の得意なことを見つけて伸ばせるようにする
- 人前で発言するのが苦手な子には、違う角度から表現できるようサポートする
個々の性格や個性を大切にしたい保育者は、この保育観を尊重していることが多いです。
子どもの自立を促す保育
子どもの自立を促す保育は、子どもが自分で「できた」と実感し主体的に行動できるようサポートする考え方です。
- 着替えや排泄、食事などを自分でできるよう適度に見守る
- 困っているときはすぐに手を出さず、「どうしたら良いかな?」と問いかけ考える力を育む
- 失敗しそうになってもすぐにフォローしないで見守り、必要であれば手を差し伸べる
- 子どものできたことに気づき「できたね」「頑張ったね」と気持ちに寄り添う
子どもは「自分でやってみたい」という経験を通し、自信や自己肯定感を身につけます。
失敗や試行錯誤を見守りながら、子どもの選択を尊重したい人が持つことが多いでしょう。
自然や地域社会との関わりを重視する保育
自然の中で遊びや体験を通し五感を育てたい、地域の人と関わり社会性や思いやりを育みたいという保育者の考え方です。
- 積極的に散歩に出かけ、季節の移り変わりを実感できるようにする
- 水遊び、泥遊びなど自然に関われる活動を取り入れる
- 野菜や花を育てる経験を作る
- お年寄りとの触れ合いや地域行事に参加し、人との繋がりを感じる
園外でたくさんの学びを経験してほしいと考えている方は、散歩や地域行事へ積極的に参加する園への就職が適しているでしょう。
社会性やルール重視の保育
集団生活において、ルールや決まりごとを守る大切さを学んでほしいと考える保育です。
- 当番活動を取り入れ、責任感を育めるようにする
- 順番を守る、友だちの話を聞くなど、社会性を身につける機会を取り入れる
- 挨拶や礼儀などを日頃から指導していく
- 集団活動を積極的に取り入れ、団結する力や同じ目標に向かって取り組む経験を作る
人間の土台を育てることを大切にし、社会の中で生きる力を身につけてあげたい気持ちが強い保育者に当てはまる保育観になります。
面接や実習で保育観について聞かれたら?
就職試験の面接や保育実習のオリエンテーション時に、どのような保育観を持っているのかを聞かれることがあります。
保育観が定まっていないと上手く答えられることができず、園の担当者に「この人は理想の保育がないのかな?」と思われてしまうかもしれません。
自分をPRするためにも、以下を参考に保育観について準備しておきましょう。
自分の保育観を明確にする
面接や実習に臨む前に、自分の保育観を明確にしておくのがポイントです。
保育観と聞くと難しく捉えてしまうかもしれませんが、「子どもが自由に過ごせる保育をしたい」「子どもの気持ちに寄り添える保育者になりたい」といった大まかな考えで構いません。
面接や実習では、以下のように伝えてみましょう。
- 子どもが自由に伸び伸びと過ごせる保育を行いたいです
- 子どもの気持ちに寄り添える保育者になりたいです
- 些細なことでも褒めて、自己肯定感を上げられるように関わりたいです
明確な保育観を答えられれば、園の担当者から「理想の保育像をしっかり持っているんだな」と理解してもらえます。
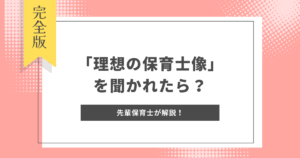
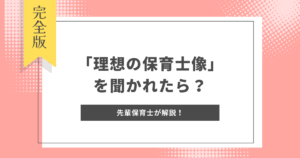
志望先の保育方針と関連付ける
保育観を伝えるときは、志望園又は実習園の保育方針と関連づけると良い印象を与えられます。
保育方針は、以下のように園によって異なります。
- 思いやりがある心豊かな子どもを育てる
- 自分で考え行動できる子どもを育てる
- 一人ひとりの個性を大切にした保育
- 健康で明るく、伸び伸びと活動できる保育
園の保育方針に関係ない保育観を伝えたり自分の考え方が園の方針と真逆だったりすると、「この園じゃなくても良いのでは?」と思われてしまうかもしれません。
「この保育方針に惹かれた」とアピールすることが大切です。
具体的な経験やエピソードを交える
園の担当者は、「なぜこの保育観を大切にしているのか」を知りたいと感じています。
そこで、これまでの経験やエピソードを交えてその保育観を挙げた理由を伝えてみましょう。
具体的には、以下の例を参考にしてみて下さい。
保育士になった当初は、子どもの着替えや食事の介助などの際すぐに手を差し伸べて援助していました。ですが、周りの保育者が子どもが自分でできるように見守りながら関わっている姿を見て、自分も子どもの自立を促す保育を行いたいと思うようになりました。
保育観が合う職場を選ぶポイントは?
長年同じ保育現場で働くためには、自分の保育観に合う保育方針を掲げている職場で働くことが重要です。
保育観が合わない職場で働いてしまうと、保育者間の人間関係で悩んだり楽しく保育ができなかったりする可能性も考えられます。
ここでは保育観が合う職場を選ぶポイントを4つ紹介するので、後悔なく働きたい方は参考にしてみてください。
保育方針が合うかどうか
保育方針が自分の保育観と合っているか照らし合わせてみましょう。
保育方針と保育観がずれたり異なったりしていると、自分のしたい保育ができずモヤモヤしてしまいます。
「散歩に出かけて自然に触れる経験をさせてあげたいのに、一切散歩をしない方針の園に就職してしまい理想の保育ができなかった……」などが、その一例です。
保育方針は、園のホームページや求人情報などで確認してみてください。
見学や実習を活用する
具体的な保育方針や保育の様子を知りたい場合は、園の見学や実習を活用してみて下さい。
多くの保育施設では、職場見学以外に観察実習や参加実習を受け入れています。
見学や実習に参加すれば、以下のようにホームページや求人情報からは得ることのできない園のリアルな情報が入手できるでしょう。
- 保育者の子どもへの関わり方
- カリキュラムや活動の進め方
- 保育者間の連携の仕方
就職前に園の保育方針が分かるので、就職するか否かを吟味できますよ。
保護者との関係性を確認する
保育観が合うかを検討するには、園と保護者との関係性を確認してみるとよいでしょう。
これは、園がどのような保育方針で保育を進めているのかが、保護者との関係に現れるためです。
園と保護者の関係性から、以下のことが把握できます。
- 保育方針が保護者に伝わっているか
- 保護者に対し保育者は丁寧に寄り添っているか
- クレームや要望にどのように対応しているか
保護者との関係性を確認するのは決して簡単ではありませんが、見学や実習を通し保育者の対応や掲示物を見たりしてチェックしてみて下さい。
勤務条件は希望に合っているか
どんなに保育観が合っていても、希望する勤務条件と異なっていては長期間働くのが厳しいです。
保育観と同時に、以下のような勤務条件が合っているかチェックしておきましょう。
- 勤務時間や給料、福利厚生は希望と一致しているか
- 残業や持ち帰りの仕事量はどれくらいか
- 職場の風通しは悪くないか
勤務条件が希望と一致していれば、安心した環境下で長期に渡り働きやすくなります。
保育観が合わないと感じたら?
保育にあたるうえで、自分の保育観が周りと合わないと感じる場面があるかもしれません。
お互いの保育観を否定してしまうと保育の方向性が一致せず、子どもが混乱することも考えられます。
そのような場合は自分の保育観を周りに押し付けたりせず、保育観について話し合ったり上司に相談したりするとよいでしょう。
それでも保育者間で保育観が共有できない、思うように働けないようであれば、転職も検討してみて下さい。
転職エージェントを活用すれば、自分の保育観にぴったりの職場を担当者が探してくれますよ。
- 自分の保育観を伝える
- 周りの保育者の保育観も受け入れてみる
- 職場の同僚や上司に相談する
- 転職を検討する
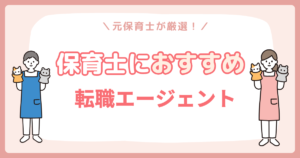
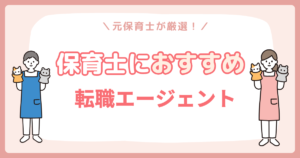
先輩保育士が語る「私の保育観」
2つの職場を経験した際、「子どもの主体性を尊重する保育」を行いたいと思うようになりました。
きっかけは、運動会や発表会の出し物です。
お遊戯の振り付けから衣装まで保育者が全て用意していた最初の職場に対し、もう一方の職場では子どもと一緒に振り付けを考えたり衣装を作成したりしていました。
前者が正しくないわけではありませんが、子どもの主体性を尊重しながら物事を進めていく保育が自分の保育観に合っていると気づくきっかけになったのを覚えています。



また保育現場に戻るのであれば、主体性を大事にしている園で働きたいです。
まとめ
保育観とは何か、具体例や見つけるためのコツをご紹介しました。
保育士として働くうえで、「どのような保育をしたいか」「どんな保育者になりたいか」という保育観を持つのはとても大切なことです。
保育に何を求めるのか明確に定まっていない方は、この機会にぜひ考えてみてください。
勤務条件や保育方針の合う職場を見つけ、自分の保育観を大切にしながら働きましょう。