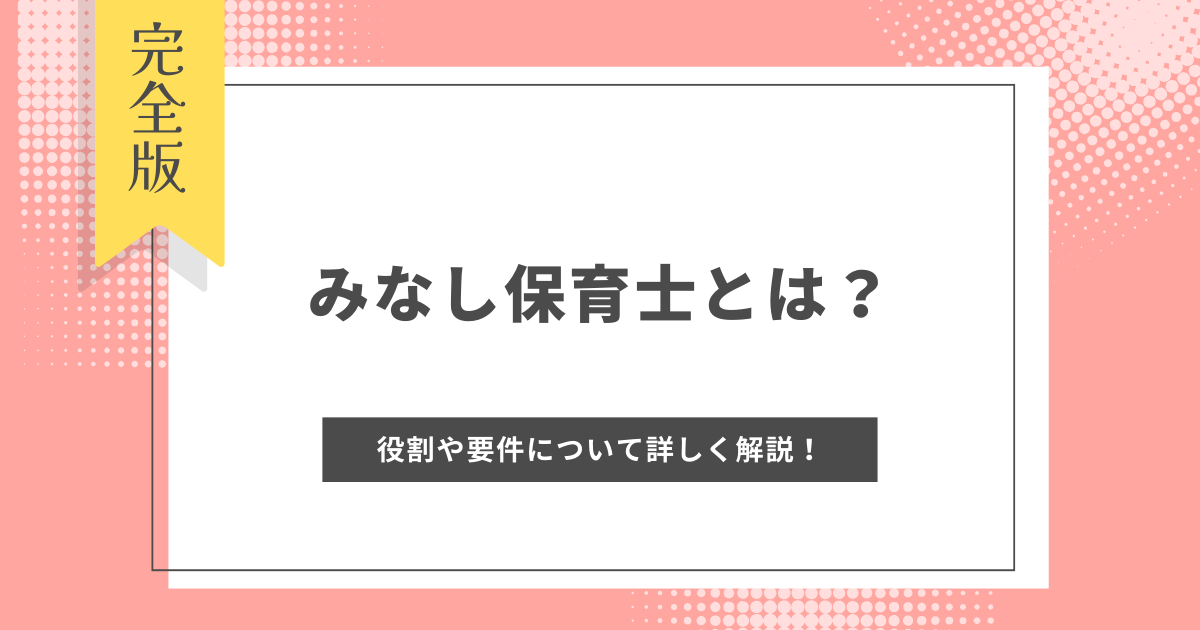みなし保育士は、保育士資格を持っていなくても条件を満たせば保育士とみなされる人です。
「保育士とみなし保育士って具体的に何が違うの?」「どのような人がなれるの?」のように、疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。
本記事では、みなし保育士とはどのような業種なのかを詳しくご紹介します。
保育士資格を持っていないけれど保育に携わりたい人、みなし保育士として補助を任された人は、ぜひ最後までご覧ください。
- 「みなし保育士」は正式な国家資格ではない
- 保育士の補助が主なみなし保育士の業務内容
- 幼稚園教諭や小学校教諭の免許を持っているなど、特定条件に当てはまる人が保育士とみなされる
- みなし保育士として働く際は、保育士資格を持つ職員との連携を大事にする
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライターみなし保育士は、人手不足の場合に配置されることが多いです。保育経験のない人が、急に「保育士として働いて」とお願いされても戸惑ってしまいますよね。働く際の注意点をしっかりと理解しておきましょう。


ゆぴ先生 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
そもそもみなし保育士とは?
「みなし保育士」という言葉を何となく耳にしたことはあると思いますが、そもそもみなし保育士とは何なのか気になる方もいるでしょう。
「保育士は保育士資格を持っていないと働けないのでは?」と疑問を感じますよね。
どのような経緯でみなし保育士が誕生したのか、みなし保育士の定義やみなし保育士が生まれた背景を解説していきます。
みなし保育士の定義
保育士資格を持っていないが、一定の資格や経験、研修を満たした保育士と平等に扱われる者
みなし保育士とは、保育士不足解消に向けて厚生労働省が出した特例です。
みなし保育士の定義は、「保育士資格を所持していなくても保育士と平等に扱われる者」で、正式に法律上載っている名称ではありませんが、行政や自治体の運用で使用されています。
国が規定しているものの、実際に運用するのは各自治体であるため、全地域でもみなし保育士が配置されているわけではありません。
参考:こども家庭庁 認定こども園における職員配置に係る特例について
みなし保育士が生まれた背景
前述した通り、みなし保育士が生まれた背景には深刻な保育士不足が挙げられます。
待機児童対策として保育の受け皿拡大を進めている中で、保育士の数が追いつかなくなり、人員不足が問題視されるように。
そうした経緯から、政府が保育士配置基準を再検討し、「保育士資格がなくても一定の研修や資格・経験があれば保育士としてみなす」という制度を作りました。



保育士資格を所持していても、給与の低さや労働環境の厳しさから現場に戻らない人は多いのが現状です。
参考:こども家庭庁 認定こども園における職員配置に係る特例について
みなし保育士と保育士の違い
みなし保育士と保育士の大きな違いは、「保育士資格を所有しているか」です。
国家資格の保育士資格を持っている人は正式な保育士として認められ、担任業務や書類制作を行います。
みなし保育士は、保育士資格を持っていなくても保育士としてみなされますが、あくまでも補助的な立場です。
ここでは、みなし保育士と保育士の違いを詳しくご紹介します。
保育士にできてみなし保育士にできないこと
保育士とは、保育士の登録を受け保育士の名称を用いて、専門的知識や技術をもち、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う者をいう。
みなし保育士は必ず全員が保育士資格を持っているわけではなく、保育の専門的知識が十分に備わっているわけではありません。
そのため、保育のサポートは行いますが指導計画や児童票といった書類作成には携わらないのが特徴です。
| 保育士 | みなし保育士 | |
|---|---|---|
| 資格 | 国家資格の保育士資格が必須 | 幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭などの免許が必要 |
| 特徴 | 全国どこでも働ける | 自治体により異動や転職が制限される場合がある |
| 役割 | 担任業務 | 保育士の補助 |
| 責任範囲 | 全ての業務を受け持つため、責任は重い | 施設や自治体により異なる |
| 雇用形態 | 正社員・パート・契約社員・派遣社員等 | 正社員・パート・契約社員・派遣社員等 |
| 目的 | 子どもの保育を行うとともに、保護者に対し子育てに関する支援や助言・指導を行う | 保育現場の人員不足を解消し、保育のサポートを行う |
参考:厚生労働省 保育所の保護者、地域との関係等(児童福祉法)
みなし保育士と保育補助の違い
保育施設などで主に保育士をサポートして、子どもたちの世話や保育を円滑に進めるための環境を整える仕事
| みなし保育士 | 保育補助 | |
|---|---|---|
| 資格 | 幼稚園教諭や小学校教諭・養護教諭などの免許が必要 | 資格不要 |
| 特徴 | 自治体により異動や転職が制限される場合がある | 全国どこでも働ける |
| 役割 | 保育士の補助 | 保育士の補助 |
| 責任範囲 | 施設や自治体により異なる | クラス担任は任されない |
| 雇用形態 | 正社員・パート・契約社員・派遣社員等 | 正規雇用に比べアルバイト・パート雇用が多い |
| 目的 | 保育現場の人員不足を解消し、保育のサポートを行う | 保育現場の人員不足を解消し、保育のサポートを行う |
幼稚園教諭や養護教諭の免許が必要なみなし保育士に対し、保育補助は資格不要で働けるのが特徴。
主に正規保育士のサポートをするので、アルバイトやパート雇用が多い印象です。
保育補助の仕事内容はみなし保育士と特に変わらず、子どもの世話を始め掃除や片付け、行事の準備等を行います。
保育補助は保育士資格がない人でも働けるのがメリットですが、子どもの命を預かる責任の重い仕事なので、ある程度保育に関する知識を持っているとよいでしょう。
みなし保育士になれる人の条件
みなし保育士は誰でもなれるわけではなく、特定の免許や資格、保育士と均しい知識を持っている人が働けます。
単純に子どもを預かるだけでなく、ある程度専門知識を持ち保育を行える技術が求められることを覚えておきましょう。
ここでは、みなし保育士になれる人の条件をご紹介するので、みなし保育士に興味のある人は、自分の所持免許や過去の経歴と照らし合わせてみてください。
小学校や幼稚園、養護学校の教諭免許を所持している人
小学校や幼稚園、養護学校などの教諭免許の所持者は、保育士とみなされます。
政府は平成28年に、保育士の配置に関して次のように見直しを行いました。
| 改正前(一部修正) | 改正後(一部修正) | |
| 雇用すべき児童年齢別基準職員の資格 | <都> 保育士。しかし「保健師など1人」を保育士とみなす。 <国> 雇用に関する規定なし。 | 保育士。しかし幼稚園・小学校・養護教諭資格所持者並びに「保健師など1人」を、認可規範上必要な職員数の3分の1を超えない程度で保育士とみなす。 |
該当する免許を所持しており保育に興味のある方は、ぜひ検討してみてください。
保育士と同じ程度の知識・経験を有すると都道府県知事から認められている
- 保育施設で十分保育業務に服務した経験がある人
- 家庭的保育者
- 子育て支援員研修のうち地域型保育コースを修了した人 など
みなし保育士になるもう一つの条件は、都道府県知事から保育士と同様の知識と経験の所持者と認められた人です。
上記の通り、「保育施設で長期間保育業務に就いたことがある人」「家庭的保育者」「子育て支援員研修のうち地域型保育コースを修了した人」がその一例になります。
改正内容は以下の表の通りです。
| 改正前 | 改正後(一部修正) | |
| 児童年齢に係る基準上必要な職員数が1人である時間帯の職員配置基準 | <都><国> 常時2名以上配置 | 1名。しかし、他に知事から保育士と平等な知識及び経験の所持者と認められた者を1名以上置かなければならない。 |
参考:全国保育士養成協議会 保育所等における保育士配置に係る特例について
みなし保育士を配置できる条件
職員が足りない保育園であっても、必ずみなし保育士を配置できるとは言い切れません。
みなし保育士を配置するならば、保育士の数や時間帯などの細かい条件があります。
ここでは、みなし保育士はどのような条件で配置できるのかを詳しく解説するので、配置ポイントを押さえて働く現場環境をイメージしてみてください。
保育事業が不足している時
保育事業を上手く回すことが、みなし保育士の制度が生まれた本来の目的でもあります。
具体的な保育事業不足の例は、以下の通りです。
- 新規採用試験で保育士が確保できなかった
- 人口が少ない地方など、人材確保が困難
- 新設園・新規開園直後で保育士が十分集まらない
- 急な職員の退職
条件に当てはまった園は、各自治体に申請し承認を受けることで配置条件をクリアし、みなし保育士として扱われます。
必要な保育士が1人だけの時間帯
朝夕等、必要な保育士が1人だけの時間帯にも、みなし保育士を配置できます。
幼保連携型認定こども園における園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)は2人を下ってはならないとされているところ、朝・夕の時間帯に園児が順次登所し、又は退所する過程等で、当該幼保連携型認定こども園において保育する園児が少数である時間帯に、職員1人に限り、保育教諭等に代え、都道府県知事(指定都市にあっては、当該指定都市の市長、中核市にあっては当該中核市の市長とする。以下同じ。)が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者を置くことができるものとする。
引用元:保育所等における保育士配置に係る特例について|こども家庭庁
児童が少ない時間帯でも安全確保や保育の質を守るために、みなし保育士のサポートは重要です。
幼稚園教諭や小学校教諭、養護教諭が保育士全体の3分の1を上回らない範囲
幼稚園教諭や小学校教諭、養護教諭は保育士全体の3分の1を上回らない程度で保育士としてみなせます。
「幼稚園教諭等」、「知事が適当と認める者」、「保健師等1人」を、現に登園している児童に対する基準職員数の3分の1を超えない範囲で保育士とみなすことができる。
引用元:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正について|東京都福祉局
保育の質を維持するためには、3分の2以上は有資格者でなければいけないと法で決まっています。
みなし保育士と保育士の比率が逆転してしまうと、子どもの怪我やトラブル時の対応力、決断力に欠け、保育体制が上手く整いません。
乳児4人以上いる場合の保健師または看護師1名
0〜1歳児が4人以上いる場合のみ、保健師か看護師1名をみなし保育士として配置できます。
急な発熱や痙攣など体調の変化が激しい0〜1歳児クラスでは、医療的な対応を求められる場面が多いです。
そのため、乳児の医療ケアや健康管理の専門知識を持つ保健師、看護師は保育士としてみなされます。
自治体や施設によっては、乳児クラスに看護師が常駐している園もありますよ。
みなし保育士として働くときに確認すること
みなし保育士の役割は、あくまで保育士のサポートをすることです。
資格がないため、業務範囲は子どもの世話や掃除など限られています。
中には、「保育士として長時間働いてみたい」「担任業務もやってみたい」と意欲が出る方もいるかもしれませんが、みなし保育士であることを理解し、業務を遂行しましょう。
特例措置であることを認識しておく
みなし保育士は、特例措置であることを認識しておきましょう。
国の方針で、みなし保育士が適応されるのは当分の間と指定されています。
みなし保育士に就く中で、「もっと保育士として働いてみたい」と考える人もいるかもしれませんが、保育事業不足が改善されれば元の職に戻らなければなりません。
保育士に興味を持ったら、保育士資格取得に向けて勉強を開始したり、パートやアルバイトとして保育補助の仕事に就いたりしてみてもよいですね。
自治体によって認定基準が異なる
みなし保育士は、自治体によって認定基準が異なることを覚えておきましょう。
みなし保育士の認定基準例を、下記に挙げました。
- 幼稚園・保育施設等での実務経験が1年以上
- 実務経験2年以上または保育所での研修受講者
- 支援員研修修了+保育士補助としての従事経験が一定期間以上
みなし保育士に興味がある方は、各自治体のホームページや職員配置マニュアルを確認してみてください。
自身の資格と業務範囲を確認しておく
みなし保育士として働く場合は、自身の所持資格と業務範囲を確認しておきましょう。
国の方針では、幼稚園教諭免許所持者は3歳児以上、小学校教諭免許所持者は5歳児を中心に保育することが望ましいとされています。
幼稚園教諭等が保育することができる児童の年齢については、幼稚園教諭等の専門性を十分に発揮するという観点から、幼稚園教諭については3歳以上児、小学校教諭については5歳児を中心的に保育することが望ましい。
引用元:保育所等における保育士配置に係る特例について|こども家庭庁
幼稚園や小学校で勤務経験がある方は、慣れ親しんだ子どもの年齢と近いクラスに入ることで、ギャップを感じず落ち着いて対応できると考えられます。
保育士資格を持つ職員との連携を大事にする
みなし保育士は、保育士資格を持つ職員との連携を大事にしましょう。
保育士資格を所持していないみなし保育士は、どこまで保育業務に足を踏みこんで良いのか線引きが難しいです。
業務中にどう動けば良いのか迷うことは当然なので、分からないことがあれば保育士に積極的に質問し、保育に支障をきたさないように心がけるとよいですよ。
みなし保育士であっても、保育士と共にクラスを運営する重要な人員なので、連携を忘れずに働くことが大切です。
先輩保育士直伝!みなし保育士として働くときの注意点
- 保育士資格がなくても、子どもにとっては「先生」であることを自覚する
- 子どもの安全を第一に考えて行動する
子どもにとって、保育者の保育士資格の有無は関係なく、クラスにいる職員全員を「大好きな担任の先生」として均一に見ています。
初めは慣れない環境で戸惑いがあるかもしれませんが、信頼される保育者になれるように子どもと積極的にコミュニケーションをとり、先生である自覚を持って働きましょう。
初めての保育業務で分からないことが多いと思いますが、保育士の1番の役割は「子どもの命を守ること」です。
午睡中の呼吸チェックやアレルギー児の誤食の注意、活動中の怪我や事故の防止などは、大袈裟すぎるくらい慎重に行っても構わないので、子どもが安全に過ごすことを第一に考えてみてください。
働く際の注意点は多々ありますが、「子どもが好き」「働いてみたい」という気持ちがあれば、必ず現場の役に立ちますよ。
まとめ
みなし保育士について、仕事内容や配置条件を詳しくご紹介しました。
保育士不足が深刻化している近年、みなし保育士の需要は年々高まっています。
人員不足でギリギリな環境の中、みなし保育士が活躍すれば保育の質が守られ、保育士からも感謝されるでしょう。
保育士資格を持っていなくても、特定の条件と「保育所で働いてみたい」気持ちがあれば保育士としてみなされるので、興味のある方は検討して働き、保育士の力になってみてはいかがでしょうか。