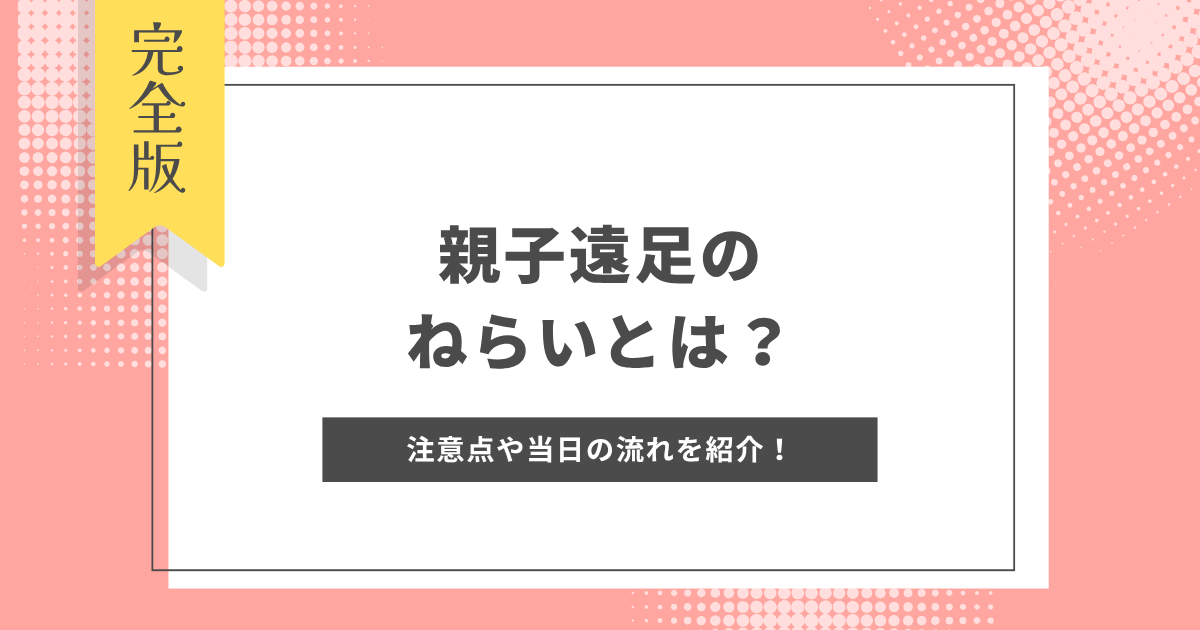「親子遠足って何をすれば良いのか分からない」
「そもそも親子遠足のねらいって何?」と親子遠足について疑問を持つ保育士さんは多いでしょう。
親子遠足は保育園の年間行事の1つで、年に数回取り入れている園もあります。
本記事では、保育園の親子遠足のねらいと、注意点や安全確保も交えて解説します。
当日の流れも載せているので、これから親子遠足を控えている保育士さんは、ぜひ参考にしてみてください。
- 親子遠足のねらいは、年齢別に考える必要がある
- 保育士が事前に下見へ行き、当日の流れや注意点を話し合っておく
- 親子遠足に必要な物は事前にリストアップしておき、保護者に余裕を持って知らせる
- 当日の反省点を園で話し合い、今後の保育に活かせるようにする
 すもも【元保育士ライター】
すもも【元保育士ライター】親子遠足は保育士にとってドキドキする行事の1つ。保護者も一緒に参加する行事なので、いつも以上に緊張しますよね。「失敗したくない」「当日スムーズにできるか心配」と思う方も多いはず。事前の準備をしっかりと整えておけば、当日も落ち着いて対応できますよ。


すもも先生 元保育士ライター
8年間保育士として勤務し、主に乳児クラスの担任を務めて参りました。認可保育施設や認可外保育施設での職務経験を活かして、保育士さんに役立つ記事を執筆させていただきます。
保育園の親子遠足とは
親子遠足は行事として取り入れている園が多く、主に春や秋に実施されます。
通常の遠足に保護者も一緒に参加するのが「親子遠足」で、親子での思い出作りや、保護者同士の交流を目的として行われるケースが多いです。
- 行先が動物園や水族館の場合は、保護者と一緒に見学をする
- 行先が公園であれば、子どもと保護者が楽しめるレクリエーションを行う
- お弁当を食べる
- 保護者同士の交流
- 記念撮影など
親子遠足を行うねらい
「親子遠足のねらいって何を書けば良いの?」と悩む方もいるでしょう。
親子遠足を行う際、指導計画書にねらいを書く必要があります。
下記でねらいについて細かくまとめていますので、指導計画書を書く時の参考にしてみてください。
共通のねらい
親子遠足の共通のねらいは、以下の通りです。
- 園外での活動を楽しむ
- 時間やルールを守って行動する
- 子どもが保護者と一緒に過ごすことを楽しむ
- 保護者同士の交流を図る
親子遠足は園外での活動となるため、「公共の場でのルールを守る」などの項目もねらいに入れておきましょう。
普段の保育園での生活は保護者と離れて過ごしているため、親子遠足の日は保護者と一緒に過ごす時間を存分に楽しめるようにするのが大切です。
さらに、保護者同士の交流の機会を設けるのも親子遠足のねらいであり、保護者同士の交流を通して、子ども同士の関わりも深めていけるようにしましょう。
季節ごとのねらい
次に、季節ごとのねらいの例は下記の通りです。
- 草花や生き物に興味を持ち、自然に親しむ
- 戸外で身体を元気に動かして遊ぶことを楽しむ
親子遠足は、過ごしやすい気候である春か秋に行われるケースが多いため、その季節に応じた植物や生き物に親しめるようにしましょう。
また、行先が公園などの広い場所であれば、身体を思い切り動かして遊ぶのもおすすめです。
春や秋であれば、熱中症の危険性もそれほど高くないので、戸外での活動を積極的に取り入れたいですね。
年齢ごとのねらい(0歳児・1歳児)
- 保育者のそばで安心して過ごす
- 外気浴を十分に行う
- 草花や生き物に興味を持つ
- 身体を動かすことを楽しむ
0歳児・1歳児クラスでは、いつもとは違う場所で過ごすと、不安になって泣き出す子どもがいます。
特に0歳児では月齢の差が大きいため、個々の成長に応じたねらいを考えましょう。
そのため、保護者の元で安心して過ごし、ゆったりとできる場所選びが大切。
また、1歳児クラスでは、歩行を始める子どもが増えてきますので、安全面に気を付けながら、戸外でたくさん身体を動かす遊びを行うと、楽しいですよ。
年齢ごとのねらい(2歳児・3歳児)
- 草花や生き物に触れながら感心を深める
- 身体を十分に動かして遊ぶことを楽しむ
- 保育士や子どもと一緒に遊びを楽しむ
- 保護者の元で安心して過ごす
- 公共の場でのルールを知る
- 電車やバスなどの乗り物に興味を持つ
2歳児・3歳児クラスになると、子ども同士での遊びを楽しむようになります。
また、草花や生き物への関心も深まってきますので、当日までに生き物に関する絵本をたくさん読んであげてくださいね。
また、簡単なルールや決まり事も分かるようになってくるため、公共の場での約束もしっかりと伝えておきましょう。
体力がついてきて活発な時期になりますが、友達同士のトラブルも増えてくる時期です。
年齢ごとのねらい(4歳児・5歳児)
- 季節の変化に気づく
- 草花や生き物に興味を持ち、自然に親しむ
- 保護者や友達と一緒に遊ぶことを楽しむ
- 公共の場でのルールを守る
- 公共交通機関の乗り方やマナーを知る
4歳児・5歳児クラスでは、季節の変化に気づいたり、ますます自然への興味が湧いてきたりする時期です。
また、公共の場でのルールも理解できるようになります。
水族館や動物園では「足は何本あるかな?」「どんな食べ物を食べてるのかな?」など子ども自身が発見できるような声掛けをしてみましょう。
保育士が全て教えるのではなく、子ども達が自分で興味を持ち、楽しめるように見守ることも大切です。
保育園の親子遠足前に必要な準備
「親子遠足があるけど何から準備すれば良いのか分からない」という疑問を持つ方に、当日までにどんな物を用意すれば良いのかを解説しますね。
ギリギリになって焦らないように、事前に準備を整えておくのが大切です。
下記で、親子遠足で必要な準備物をまとめていますので、ご参考になれば幸いです。
行き先を決める
- 子どもや保護者が負担にならない場所を選ぶ
- 年齢に応じた場所を選ぶ
- 子どもが保護者と一緒に楽しめる場所を選ぶ
親子遠足の場所を決める際は、上記のポイントに気を付けて選ぶようにしましょう。
保育園からあまりに遠い場所を選ぶと、幼い年齢であればあるほど、子どもと保護者にも負担になってしまうので、片道1時間~1時間半程度の場所がおすすめです。
また、年齢に合った場所を選ぶのも大切で、子どもが興味を持ち、十分に楽しめる場所を選んであげてくださいね。
乳児であれば室内のレジャー施設や広い公園がおすすめで、幼児以降は動物園や水族館といったレジャー施設を選択するのも良いでしょう。
下見を行う
親子遠足の行先が決定したら、担当保育士複数名で下見へ行きましょう。
当日の流れをイメージし、注意点などもしっかりと把握しておくのが重要です。
下見へ行った際は、次のポイントに気を付けて見ておきましょう。
- 行先までの所要時間(最寄り駅・駐車場からの距離など)
- 営業時間や入場料
- トイレの場所や授乳室の有無
- 昼食をとれる場所
- 集合場所
- 記念撮影ができる場所
- 当日の行動範囲
当日、電車などの公共交通機関を使用する場合は、最寄り駅からの道順や所要時間をチェックしておきましょう。
また、季節によっては営業時間が変更になる場合もあるため、事前確認が必要です。
乳児はオムツ交換場所や授乳室が必要になる保護者もいるので、それらの有無も確認しておきましょう。
昼食の場所の確保も重要となり、いくつかの候補を決めておくと安心ですよ。
元保育者の筆者は、当日の行動範囲をしっかりと決めておく必要があると感じました。
親子遠足であっても保育園の行事であるため、保育者の目の届く範囲で楽しめるよう保護者にも協力が必要です。
保育士の役割分担を決める
保育士の役割分担を事前に決めておけば、万が一のトラブルにも瞬時に対応できますよ。
保育士のそれぞれの役割についてまとめていますので、参考にしてください。
| 役割名 | 内容 |
|---|---|
| リーダー | 列の先頭を歩き、全体の様子を把握する |
| 写真係 | 当日の写真を撮る |
| 救急係 | 怪我や体調不良の子どもの対応を行う |
| 時間係 | 時間配分の管理を行う |
親子遠足では、万が一の状況にも対応するために、十分な数の保育士が引率するケースが多いです。
そのため、手厚い関わりが必要な子どもや、臨機応変に対応するフリー保育士も決めておきましょう。
スケジュールを決めてしおりを作成する
保育士の役割分担が確定したら、当日のスケジュールを決定し、しおりを作成しましょう。
しおりを作る際は、誤字脱字に気を付け、誰が見ても分かりやすいように記載するのが大切です。
遠足のしおりに記載する内容としては、下記で例を挙げています。
- 日時と場所
- 当日の集合場所
- 当日のタイムスケジュール
- 持ち物
- 服装
- 注意点
- 当日の連絡先
親子遠足では自由時間を設ける場合もあると思いますので、行動範囲内を示したマップも記載しておくと分かりやすいですよ。
保護者へのお知らせをする
親子遠足の日程が近づいてきたら、保護者にお知らせをしましょう。
近年はメール配信を取り入れている園も多いですが、エラーなどで届かないケースも考えられますので、手紙でのお知らせが無難と言えます。
お知らせをするタイミングは園によって様々ですが、早すぎず・遅すぎない時期がおすすめです。
バス内や当日行うレクリエーションを考える
当日の移動手段が園バスまたはチャーターバスであれば、移動中に楽しめるレクリエーションを導入しましょう。
バスでの遠足は、片道1時間から長くても2時間程度の移動時間となるので、子ども達が退屈しない内容を取り入れるのがおすすめ。
また、行先が広い公園であれば、親子で楽しめるレクリエーションを取り入れてみましょう。
- 手遊び歌
- クイズ(なぞなぞ・シルエットクイズ)
- 鬼ごっこ
- 親子リレー
- しっぽとり
- 宝探しゲーム
幼児クラスであれば、行先でのレクリエーションも取り入れやすいです。
乳児クラスは取り入れる内容が限られてくるため、自由時間を設けるケースが多いでしょう。
いつもと違う環境では、場所見知りをする子どももいますので、できる限り無理のないように過ごしたいですね。
共通の持ち物と保育士の持ち物を確認する
- 予備の着替えやオムツ
- 緊急連絡先表
- しおり
- 携帯電話
- 救急セット
- 笛
- タオル
- ビニール袋
- 雨具
- お弁当
- 水筒
- レジャーシート
- ウェットシートやポケットティッシュ
- 日焼け止め
- 腕時計
遠足では、着替えやオムツが足りなくなったというケースがよくあるので、予備を多めに持って行っておくのがおすすめ。
また、急に体調が悪くなったり、怪我をしたりすることも予想できるため、救急セットや緊急連絡先のリストも忘れずに持っていきましょう。
行先によっては、長時間戸外で過ごすため、保育士も日焼け止めなどを持っていくと良いでしょう。
また、時間は携帯電話でも見れますが、携帯を出し入れする手間を省くために、腕時計を付けるのがおすすめですよ。
親子遠足中の安全確保と注意点
親子遠足では、保護者も一緒に参加しますが、安全確保を行うのは保育士の重要な役目です。
いつもとは違う場所では何が起こるか予想できないため、保育士同士で連携を図り、安全に過ごせるようにしましょう。
下記で安全確保と注意点についてまとめていますので、確認してみてくださいね。
子どもの安全確認を怠らない
一つ目は、子どもの安全確認を決して怠らないように気を付けましょう。
親子遠足では子どもの近くに保護者はいますが、保護者同士の交流で子どもから目を離している場合も考えられます。
楽しく過ごすのはもちろんですが、無事に終わるためには子ども達に常に目を配り、危険な行動をしていないかなど、しっかりと確認するのが大切です。
また、人数確認はこまめに行い、保育士同士での掛け声も忘れないようにしましょう。
混雑や見通しの悪い場所の事前チェック
2つ目は、混雑や見通しの悪い場所を事前にチェックしておきましょう。
動物園や水族館などのレジャー施設は、遠足シーズンは混雑が予想されますので、その場合はどこから周るのかなど、保育士同士で話し合っておくと安心です。
また、広い公園では見通しの悪い場所や、危険な箇所がないかをチェックするのが大切。
特に乳児は転倒による怪我が多いため、安全に遊べる場所を確認しておきましょう。
雨天時の対応を決めておく
行先が屋外であり、当日雨天だと中止になるケースが多いですよね。
雨天の場合ではどうするのかを決めておき、しおりにも記載して保護者へ知らせておきましょう。
屋内のレジャー施設であればそこまで雨の影響はないですが、乳児の親子遠足の場合、保護者の負担が大きくなるので中止となる場合も。
- 日程を変更して通常保育を行う
- 園内で遠足ごっこを行う
- 室内の行先に変更する
緊急時の対応を決めておく
遠足当日は子どもが急に体調を崩したり、怪我をしてしまったりするケースも考えられます。
緊急時の対応はどのように行うのかを事前に保育士間で話し合っておきましょう。
緊急の時こそ、保育士のチームワークが重要となるため、実際にシミュレーションを行っておくと安心ですよ。
園や自治体によっては「園外活動時のマニュアル」を作成している所もあるため、マニュアルをしっかりと読み、瞬時に対応できるようにしておきましょう。
親子遠足当日のスケジュールの例
親子遠足当日のおおまかなスケジュールの例を下記で記載しています。
| スケジュール | 動き |
|---|---|
| 集合 | 子どもが全員揃っているか人数確認をする |
| バスなどの公共交通機関に乗車して移動する | 交通機関に乗車し、子どもの様子を見守る |
| 目的地に到着 | 子どもの人数確認を行う |
| 記念撮影をする | 事前に決めておいた場所で写真撮影を行う |
| 見学または遊びを開始する | レジャー施設の場合は、子どもの様子を伺いながら、一緒に楽しめるようにする 公園では安全に気を付けながらレクリエーションなどの遊びを行う |
| 昼食 | 事前に決めておいた場所で昼食を食べる |
| 集合時間まで自由時間 | 常に子どもの様子を見ながら保育士も一緒に遊ぶ |
| 集合 | 子どもの人数確認を行う |
| 公共交通機関に乗車して移動する | 交通機関に乗車し、子どもの様子を見守る |
| 解散場所で帰りの挨拶を行う | 子どもの人数確認を行い、帰りの挨拶をする |
移動を行う際は、常に子どもの人数確認を行うようにしましょう。
また、上記のスケジュールでは省いていますが、必要に応じてトイレ休憩を取ってあげて下さいね。
当日は道路の混み具合によっては到着時間が多少異なる場合も考えられますので、その際は、今後のスケジュールをどうするのかを保育士間でしっかりと話し合っておく必要があります。
先輩保育士からアドバイス!親子遠足後のふりかえりと今後への活かし方
「無事に親子遠足が終わってホッとしたけれど反省するポイントが多かった」
「親子遠足での課題を今後の保育でどのように活かせばいいのかな」と思う方がいるでしょう。
親子遠足が終わった後は反省会を行い、今後の課題を明確にすることが大切です。
下記で、親子遠足の振り返りを行う理由と今後の保育への活かし方をまとめています。
ふりかえりを行う理由
親子遠足が終わったら、当日または後日に遠足の反省会を行う園が多いです。
当日の振り返りを行う理由は、来年度の親子遠足に活かすためです。
今回の親子遠足で「良かった点」や「こうすれば良かった点」を引率保育士と園長、主任、副園長、その他の保育士と話し合います。
元筆者の私が勤めていた園では、遠足当日に反省会を行っていました。
当日であれば、遠足の内容をしっかりと覚えているため、細かい部分まで見直すことができました。
後日に遠足の反省会を行う園であれば、当日忘れないうちにメモに書き留めておくようにしましょう。
保育への活かし方
親子遠足での反省点を今後の保育で活かすためには、自分自身の行動をしっかりと見なおしましょう。
例えば「あの時はこんな風に声掛けをすれば良かった」や「子ども達がすごく興味を持ってくれたから継続して楽しめるようにしよう」などです。
遠足ではいつもとは違う場所での活動になるため、保育士自身も緊張しますし、思うようにいかない時がほとんどでしょう。
親子遠足での反省点は今後の保育で改善していき、良かった点はそのまま継続して行ってみてくださいね。
まとめ
本記事では、親子遠足でのねらいについて解説し、必要な準備物や当日のスケジュールを記載しました。
親子遠足のねらいは年齢によって分け、行先も子どもや保護者の負担にならない場所を選びましょう。
当日を思い出の残る1日にするには、事前の準備をしっかりと整え、保育士間で話し合っておくのが大切です。
子ども達が興味を持つような声掛けや援助を行い、保育士自身も子ども達と一緒に楽しめるようにしてくださいね。