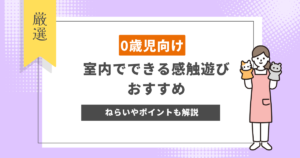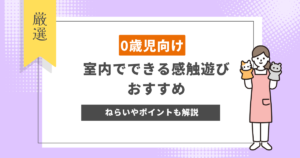プルプルした独特の触感や冷たい触り心地が味わえる寒天遊びは、子どもからも人気のある保育活動です。
「寒天遊びを行う際のねらいは何にしよう?」「普段とは一味違う寒天遊びをさせてあげたい」と悩む保育士の方に、本記事では寒天遊びのねらいや元保育士がおすすめする寒天遊びのアイデアをご紹介します。
参考にしながら、子どもと一緒に寒天遊びを楽しんでみてください。
- 寒天遊びは、食用の寒天を使って感触や色彩を楽しむ感触遊びの一つ
- 寒天遊びは、同じ素材でも子どもの発達段階によってねらいや遊び方が異なる
- 火を使わなくても電子レンジで寒天が作れる
- 寒天遊びをする際は、清潔な環境作りや誤飲・窒息に注意する
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライター「寒天遊びは準備や片付けが大変そう……」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。シンプルな素材で手軽に始められるので、ぜひ保育活動に取り入れてみてくださいね。


ゆぴ先生 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
寒天遊びってどんなもの?
寒天遊びとは、食用の寒天を使って感触や色彩を楽しむ保育活動のことです。
透明感のあるプルプルした素材は、手で握ったりちぎったりするだけで子どもにとって新鮮な体験になります。
寒天に食紅で色を付けると、見た目の美しさや色の混ざり方にも気付け、感覚遊びと同時に科学的な興味も育まれますよ。
安全に遊べる素材なので乳児期から取り入れやすく、指先の発達や創造性を育てる活動としても人気です。
寒天遊びのねらい【年齢別】
寒天遊びは、同じ素材でも子どもの発達段階によって「ねらい」が変わってきます。
乳児期は感触を楽しむことが中心ですが、年齢が上がるにつれて言葉で表現したり、友だちと協力したりする姿へと発展していきます。
ここでは、0〜5歳児それぞれのねらいを年齢順にまとめました。
0歳児・1歳児の寒天遊びのねらい
- 触る・握る・つかむなどの感触を楽しむ
- 手先や指の動きを促し、感覚の発達に繋げる
0・1歳児にとって寒天遊びは、まず「触って確かめる」こと自体が大切な体験です。
プルプルとした柔らかな感触を握ったり、手のひらに広げたりすることで、手指や感覚器官の発達を促します。
また、冷たさや形の変化などを感じ取ることが、探索活動の意欲や好奇心に繋がるでしょう。
口に入れてしまう心配もあるため、食用の寒天を使うことで安全に取り入れられるのも大きな利点です。
「不思議だな」「面白いな」という感覚を味わうことが、安心感のある環境での遊びの第一歩となり、保育者とのやり取りの中で心の安定や情緒の育ちにも関係します。
2歳児・3歳児の寒天遊びのねらい
- 手でちぎる・混ぜるなどの操作を通じて指先の巧緻性を高める
- 色や形の変化に気付き、言葉や表現で楽しむ
2・3歳児は、手で寒天を握るだけでなく、ちぎる・混ぜるなどの操作を楽しむ時期です。
寒天を細かくしたり、色を混ぜ合わせたりすることで、指先の巧緻性を高めながら「どう変わるかな?」という思考力や言葉での表現力を養います。
また、友だちや保育者と一緒に同じ寒天を使って遊ぶことで、「貸して」「一緒にやろう」といったやり取りが自然に生まれ、協同性や社会性の芽生えにも繋がります。
自分なりの遊び方を発見し、保育者に伝える経験は自己肯定感を育むきっかけにもなるでしょう。
4歳児・5歳児の寒天遊びのねらい
- 遊び方を工夫し、想像力を働かせて表現を広げる
- 色の組み合わせや形の変化から科学的な興味・探究心を育てる
4・5歳児になると、寒天遊びはより「表現や探究の活動」として発展します。
寒天を型に入れて作品を作ったり、色を混ぜ合わせて新しい色を発見したりする中で、創造力や科学的な思考力が育まれるでしょう。
また、複数人で遊ぶ際には「役割を決めて分担する」「一緒に遊び方を考える」といった協働性が必要となり、友だちとの関わり方がより深まるのも4・5歳児の特徴です。
遊びの中で「もっと大きいのを作りたい」「色を分けたい」など目的意識を持つようになり、試行錯誤を繰り返す過程自体が学びになります。
寒天遊びに最適!火を使わない寒天の作り方
寒天遊びを保育に取り入れる際、「火を使うと危ない」「調理器具が必要で大変」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな時におすすめなのが、電子レンジやお湯を利用した火を使わない寒天作りです。
安全に作れるので、子どもと一緒に取り組みやすく日々の保育に取り入れやすいのが魅力。
ここでは、寒天遊びの経験が少ない方でも簡単に実践できる寒天の作り方をご紹介します。
準備するもの
- 粉寒天
- 水
- 食紅
- 耐熱容器
- ボウル
- スプーン
- 容器又はトレイ
粉寒天・水・電子レンジ対応の耐熱容器・混ぜるためのスプーンや泡立て器・冷蔵庫で固めるための容器を用意しましょう。
粉寒天は、スーパーや100円均一など身近な場所で購入できますよ。
色や感触を楽しむために食紅やカラー水、透明カップ、バットなどを加えるとバリエーションが広がります。
保育に取り入れる際は、子どもが安全に扱えるサイズや素材を選ぶことも大切です。
作り方の手順
- 500~700Wに設定した電子レンジで、耐熱容器に入れた水を2~3分加熱する
- ボウルに電子レンジで温めた70℃程度のお湯を張り、粉寒天を少しずつ振り入れて混ぜる。※ダマにならないようにスプーンでよくかき混ぜる
- 色付きの寒天にしたい場合、少量の食紅を加えて混ぜる。食紅がない場合は、色のついたジュースで代用してもOK
- ②で作った寒天液を容器やトレイに流し入れる
- 寒天液を入れた容器やトレイを冷蔵庫に入れ、2~3時間ほど冷やす。しっかり固まったら、寒天の完成。
耐熱容器に水を入れて電子レンジで加熱し、沸騰させます。
その後、粉寒天を少しずつ加えながらしっかり混ぜ、完全に溶けたらお好みで食紅を加えて色付けしましょう。
全体を混ぜ合わせたら容器に移し替え、冷蔵庫で数時間冷やすと固まります。
固まった寒天は型から外したり、手で崩したりしてすぐに遊びに活用できますよ。
さらに、製氷皿やシリコンカップに流し込むと一口サイズに仕上がり、子どもが扱いやすくなります。
色違いをいくつか作っておくと混ぜ合わせたり比べたりする遊びにも発展するので、様々な色で作ってみてください。
作る際のポイント
- 粉寒天がどれくらいの温度で溶けるのか確認しておく
- 粉寒天がダマにならにようしっかり混ぜる
- 誤飲を防ぐために口に入れてはいけないことを子どもに伝えておく
粉寒天はダマになりやすいため、加熱したお湯に少しずつ入れてしっかり混ぜることがポイントです。
また、食紅は数滴でも鮮やかに発色するので、色の濃さを調整しながら加えると遊びやすい仕上がりになります。
大きな容器に流し入れて固めると豪快に崩せ、小さな容器に分けて固めると個々の遊びに活かせるでしょう。
作っている最中は、誤食防止のため「食べられない寒天」であることを伝える工夫も必要です。
元保育士がおすすめ!寒天遊びのアイデア3選
寒天遊びは、触る・崩す・混ぜると自由度が高く、子どもの発想を引き出す魅力的な活動です。
ただ触るだけでも十分楽しめますが、ちょっとした工夫を加えることで、色彩感覚やごっこ遊び、協同的な関わりへと広がります。
ここでは、保育現場で実際に取り入れやすく、子どもたちが夢中になれる寒天遊びのアイデアを3つご紹介します。
寒天遊びケーキ
一つ目は、透明カップやスプーン、色水などを使って「寒天ケーキ」を作る感触遊びです。
色水で寒天に色をつけたり、透明の器に少しずつ寒天を入れて層を作ったりすることで、「見た目の変化」を楽しめるのが大きな魅力。
触感もポイントで、寒天のぷるぷる・ひんやりとした感触や、指で押すと跳ね返るような感触が子どもたちの五感を刺激します。
手で握る、スプーンで切る、混ぜるといった操作を通して、指先の巧緻性も育めますよ。
動画にあるように、寒天と一緒に色水を組み合わせて遊ぶとさらに盛り上がるでしょう。
- 寒天
- トレイ
- 透明カップ
- スプーン
- 寒天を何色か作りトレイに乗せる
- 初めは手で触ったり掴んだりして感触を楽しむ
- スプーンで寒天を透明カップに入れ、ケーキに見立てて楽しむ
寒天ゼリー宝探し
寒天ゼリー宝探しは、固めた寒天の中に小さなおもちゃ、フィギュアなどを隠し、子どもたちがスプーンや手を使って取り出す遊びです。
ぷるぷるとした寒天の感触は子どもたちの五感を刺激し、手先の巧緻性や力加減の調整も自然に身につきます。
宝を探し出す過程で「どこにあるかな?」と観察したり、友だちと協力して取り出したりすることで、集中力や協同性も育まれるでしょう。
色付き寒天を使えば視覚的にも楽しく、見つけた瞬間の達成感が子どもの笑顔を引き出します。
遊びながら触覚・視覚・思考力をバランスよく育める点も魅力ですよ。
- 寒天
- 透明カップやトレイ
- プラスチック製のおもちゃ
- スプーン
- 寒天の中に宝に見立てた小さなおもちゃ(プラスチック製のもの)を埋める
- 手やスプーンを使って宝を取り出す
寒天粘土ごっこ
寒天粘土ごっこは、固めた寒天を手でちぎる、積み重ねる、型に入れて形を作るなどして遊ぶ感触遊びです。
ぷるぷるとした弾力やひんやりした触感が子どもたちの感覚を豊かにし、手先の巧緻性や指先の感覚を自然に育てます。
自由に形を作れるため、想像力や創造力が広がり、友だちと一緒に遊ぶことで協同性やコミュニケーション力の向上も期待できるでしょう。
色付き寒天を混ぜたり異なる形に切ったりすると、視覚的にも楽しめ遊びの幅がぐんと広がります。
失敗を恐れず触れることで、感触遊びへの興味が深まる点も魅力です。
- 固めた寒天(透明や色付き)
- 小さなボウルやトレイ
- 手で触って形を作るためのスプーンやヘラ
- 型抜きやカップなど
- 寒天を作り固める
- 手でちぎったり積み重ねて遊ぶ
- ヘラや型抜き、カップなどを使ってみても面白い
寒天遊びで配慮する点は?
寒天遊びは手軽で楽しい感触遊びですが、子どもたちが安心して楽しむために十分な配慮をしなければなりません。
誤って口に入れたり滑って転んだりするリスク、アレルギーや衛生面の注意点など、安全面に気を配ることで、遊びの楽しさを損なわずに活動できます。
ここでは、保育園で寒天遊びを行う際に押さえておきたい注意点や工夫についてご紹介します。
清潔な環境づくりを意識する
寒天遊びでは子どもたちが手で触れるため、以下のような衛生管理が重要です。
- 手洗い・道具の消毒を徹底する
- 清潔なトレイや容器を使用する
遊ぶ前後には必ず手を洗い、使用するスプーンやトレイ、型なども清潔なものを用意しましょう。
食べ物に近い感触のため、雑菌の繁殖や汚れを避けることで安心して遊べます。
遊ぶ場所も布や紙で覆うと、後片付けもしやすく清潔に保てますよ。
誤飲・窒息に気を付ける
0〜2歳児の乳児が遊ぶ際は、誤飲・窒息が起こらないよう注意しましょう。
- 寒天は小さく切る・手でつぶせる硬さにする
- 目を離さず見守る
寒天は柔らかいですが、小さな塊を誤って口に入れると窒息の危険があります。
特に0~1歳児では、手で潰せるくらい柔らかくして提供することが大切です。
遊んでいる間は保育士が目を離さず見守り、食べ物と勘違いして口に入れる子がいないか確認しましょう。
安全な遊び方のルールを事前に伝えることも効果的です。
アレルギーに配慮した材料選び
アレルギー児がいる際は、材料選びに気をつける必要があります。
- 材料は子どもに安全なものを使用する
- 食材アレルギーの有無を事前確認する
寒天自体はアレルギーリスクが低いですが、色付けや香り付けに使用する材料への注意が必要です。
食紅や果汁などを使う場合、子どもにアレルギーがないか事前に確認しましょう。
また、自然素材や食品用着色料を選ぶことで、万が一口に入れても安心です。
保護者への事前連絡や同意も忘れずに行ってください。
後始末がしやすい環境にしておく
後始末がしやすい環境を整えておくと、順調に片付けられます。
- テーブルや床にシートを敷く
- 洗いやすい容器・道具を使用する
寒天遊びは手や服、机に付着しやすいため、遊ぶ前に新聞紙やビニールシートを敷くと後片付けがスムーズです。
使用する容器やスプーンも水洗いで落ちやすい素材を選ぶと、保育士の負担を軽減できます。
遊んだ後はすぐに片付け、床やテーブルを拭く習慣をつけると、衛生的で次の活動に支障をきたしません。
年齢や成長に応じた遊びを工夫する
寒天遊びをする際は、遊びを通して何をねらいにするのかを決めておくとよいです。
- 乳児は手でつかむ・触る感覚を重視する
- 幼児は型抜きや混ぜる遊びで創造性を促す
寒天遊びは年齢によって楽しみ方やねらいが異なります。
0〜1歳は感触を楽しむことが中心で、柔らかく小さめに切った寒天を手で触らせるのがおすすめです。
2~3歳は、スプーンですくったり型に入れたりする遊びで手先の発達を促せます。
4~5歳は色を混ぜたり積み重ねたりして創造的に遊ぶことで、想像力や協同性も育めますよ。
寒天遊びの指導案の書き方
寒天遊びは、五感や手先の発達を促す保育活動として人気ですが、指導案をしっかり作ることで、より安全で効果的に子どもたちに楽しんでもらえます。
遊びのねらいや準備物、遊び方、年齢に応じた工夫点、配慮すべき安全面などを整理することで、保育士自身も安心して指導できますよ。
ここでは、寒天遊びの指導案を作成する際のポイントや具体的な書き方をご紹介します。
活動内容
- 遊びのねらいを明確にする(例:触覚を楽しむ、手先の巧緻性を育む)
- 使用する材料・道具を具体的に記載する(寒天、色水、スプーン、型など)
- 遊びの進め方や手順を順序立てて書く
活動内容では、まず遊びのねらいや目的を明確に示すことが大切です。
子どもたちに何を感じてほしいのか、どのような力を育みたいのかを整理します。
また、使用する材料や道具を具体的に書き、遊びの進め方や手順も順序立てて記載しましょう。
どのタイミングで保育士が補助や声かけをするかも含めると、他の保育士が見ても理解しやすい指導案になります。
遊びの流れを細かく書くことで、安全性や達成感の両方を確保できますよ。
環境構成
- 遊ぶ場所の安全性を確保するための工夫を記載する(床やテーブルにシートを敷く)
- 子どもたちが動きやすく、見守りやすいよう配置図を挿入する
- 後片付けがしやすい環境を整えるための配慮を記載する
環境構成では、安全に遊ぶためにどのように空間を整えるか記載することが重要です。
床やテーブルにはシートを敷く、後片付けがしやすいよう道具を用意するなどを記載しておきましょう。
子どもたちが自由に動き回れる配置や、保育士が全体を見渡せる位置取り図の挿入もポイントです。
また、材料や道具が手に取りやすく整理されているか、遊びの途中で危険がないかの確認も怠らないようにしましょう。
環境構成の記載を工夫することで、子どもたちは安心して思い切り遊ぶことができます。
予想される子どものすがた
- 年齢ごとの反応や発達段階を想定する
- 感触や色彩に対する興味、友だちとの関わり方などを具体的に書く
- 安全面や配慮が必要な行動も予測する
予想される子どものすがたでは、年齢ごとの発達段階や反応を想定して記載しましょう。
感触や色彩に対する興味、手先の動きの様子、友だちとの関わり方など具体的に整理すると指導がしやすくなります。
また、口に入れようとする、寒天を床に落とすなど、安全面で配慮が必要な行動も予測しておくことが重要です。
事前に想定しておくことで、遊びの中での安全管理や保育士の声かけがスムーズになりますよ。
指導案の展開例
下記は、1歳児クラスを対象にした寒天遊びの指導案例です。
ねらいや子どもの姿、保育士の配慮など、書く際の参考にしてみてください。
まとめ
寒天遊びは、感触遊びとして子どもたちの五感や集中力、手指の巧緻性を育む遊びです。
年齢に応じて遊び方やねらいを工夫することで、0・1歳は感触や運動感覚の刺激、2・3歳は触感を通じた表現力や観察力、4・5歳は想像力や創造力と、それぞれ異なる面で成長が期待できます。
安全面や衛生面に配慮しつつ、火を使わない簡単な寒天作りや宝探し・寒天粘土ごっこなどの多彩なアレンジで、子どもたちが楽しく学べる体験を提供してみてくださいね。