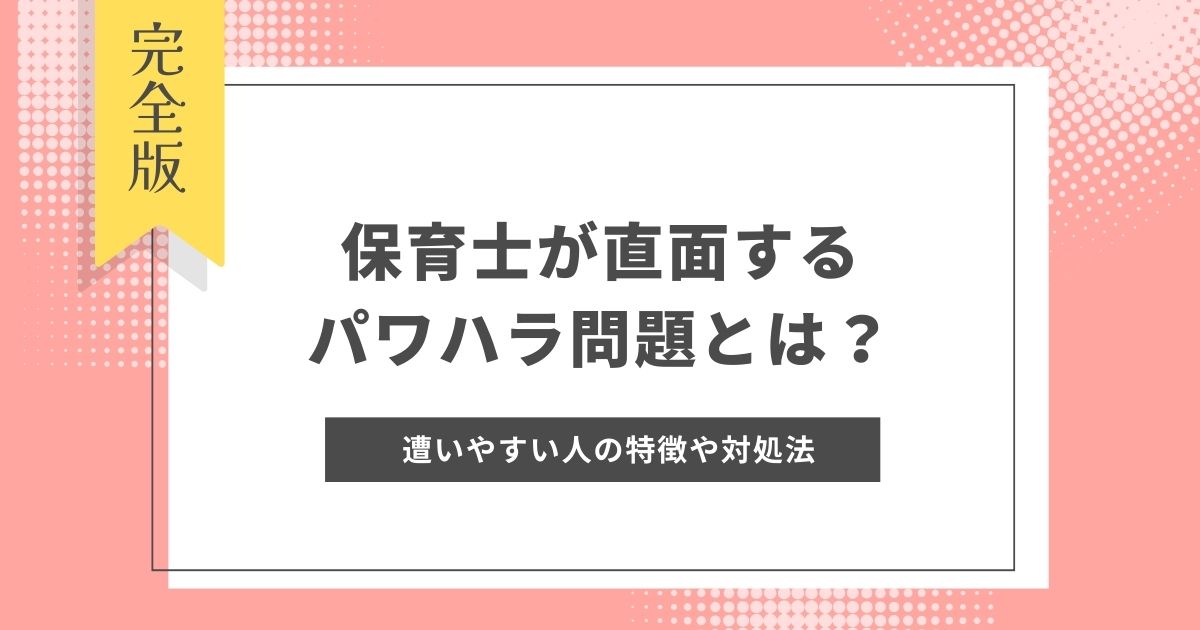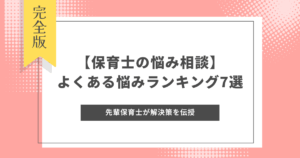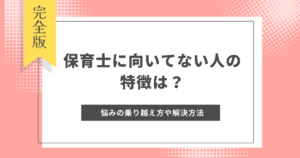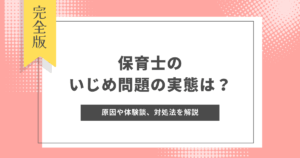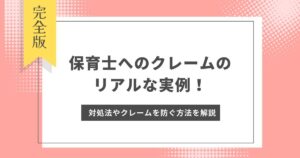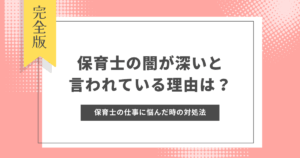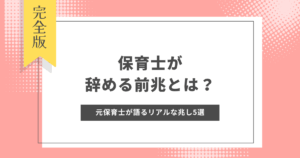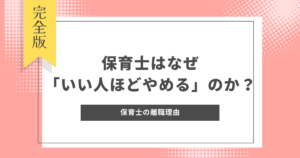保育士のパワハラは、職場環境の悪化だけでなく保育の質までも低下させる深刻な問題です。
「パワハラに遭っていて辛い」と感じている保育士の方もいるでしょう。
本記事では、パワハラに遭いやすい保育士の特徴やパワハラに遭った際の対処法をお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。
- パワハラとは職場での優位な立場や力関係を利用し、相手に精神的・身体的な苦痛を与える行為
- 経験が浅い保育士や自己主張が苦手な人はパワハラに遭いやすい
- パワハラには、身体的攻撃、精神的な攻撃など様々なパターンがある
- パワハラに遭った際は、信用できる上司や同僚、専門機関に相談する
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライター私も実際に、職場でパワハラ現場を目撃した経験があります。楽しく働きたいのに人間関係で悩むのは辛いですよね。一人で抱え込まず、信頼できる人や外部の相談窓口に頼ってください。あなたを守る場所は必ずありますよ。


ゆぴ先生 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
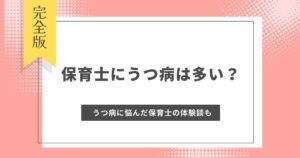
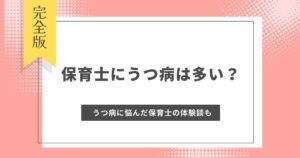
そもそもパワハラとは?
パワーハラスメント(パワハラ)とは、職場での優位な立場や力関係を利用して、相手に精神的・身体的な苦痛を与える行為を指します。
厚生労働省の定義によると、以下の3つの要素すべてを満たす行為がパワハラとされています。
- 職場における優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた内容であること
- 労働者の就業環境が害されること
これらは、保育の現場でも起こりやすい問題のひとつです。
- 上司から部下、先輩から後輩など、力関係を利用して行われる
- 叱責や指導ではなく、人格を否定する言葉や過度な負担を与えるなど、不必要に相手を追い詰める
- 精神的なダメージ(萎縮・不安・自尊心の低下)や、身体的・職業的な不利益(配置換え、退職強要など)をもたらす
実際に保育現場では、新人保育士や経験の浅い保育士が先輩保育士に目をつけられたり、相談相手のいない孤立している保育士がターゲットになりやすい傾向にあります。
パワハラと指導の違いは「目的」と「相手の尊重」。パワハラは相手の人格を否定したり、不必要に追い詰めたりする行為で、苦痛や萎縮を生みます。一方、指導は子どもや保護者のために必要な業務改善を目的とし、相手の成長をサポートする建設的なものです。
パワハラ被害に遭いやすい保育士の特徴
保育現場でパワハラ被害に遭いやすい保育士の特徴を整理すると、「経験が浅い」「自己主張が苦手」など、以下の5つが挙げられます。
ご自身に該当するものがないか、確認してみてください。
以下の特徴に当てはまっている人はパワハラに遭いやすい傾向にあるので、原因と対策を理解しておきましょう。
- 経験が浅く新人である
- 立場が弱い(パート・アルバイトなど)
- 自己主張が苦手・断れないタイプ
- 孤立しがちで相談相手がいない
- 真面目で責任感が強い
保育現場でパワハラ被害に遭いやすい保育士には、共通する特徴があります。
新人や経験の浅い保育士は業務や園のルールに不慣れなため、理不尽な指導を受けやすいです。
パートやアルバイトなど立場が弱い場合、意見を言いにくくターゲットになりやすくなるでしょう。
自己主張が苦手で断れないタイプや、職場で孤立して相談相手がいない人も被害に遭いやすい傾向があります。
さらに、真面目で責任感が強い保育士は、過度な期待や負担を背負いやすく、結果としてパワハラの標的になりやすいです。
保育士が受ける可能性があるパワハラのパターンは?
保育士が受ける可能性があるパワハラには、身体的な攻撃や精神的な攻撃など、6つのパターンがあるのをご存知でしょうか。
なかには、人間関係からの切り離し、個の侵害など深刻な内容もあります。
ここでは、厚生労働省が定義するパワハラの6類型を、保育業界での例と共に解説します。
身体的な攻撃
身体的な攻撃は、怒鳴る・叩く・物を投げるなど、直接行う身体的暴力です。
- 書類や教材を投げつけられる
- 手を叩かれる
- 大きな声で怒鳴られる
身体的ストレスによる免疫低下や、慢性的な疲労に繋がる恐れがあります。
精神的な攻撃
精神的な攻撃は、人格を否定したり、過度に叱責する行為が該当します。
- 「こんなこともできないのか」「あなたのせいで園が困っている」などの暴言
- 長時間にわたる怒鳴り
長期間続くと、不安感や自己肯定感の低下、うつ症状、睡眠障害、食欲不振など心身へ影響が出ます。
燃え尽き症候群(バーンアウト)や抑うつ状態になることもあるため、注意が必要です。
人間関係からの切り離し
職場で孤立させる、情報共有をしないなど、人間関係から切り離す行為もあります。
- 会議に呼ばれない
- 保護者対応や業務の連絡を意図的に伝えない
孤独感や疎外感、職場不信に繋がるだけでなく、精神的ストレスが蓄積しやすいです。
過大な要求
能力や経験を超える仕事や不可能な業務など、過大な要求を押し付ける行為です。
- 一人で多数の園児を任される
- 休日出勤を強要される
過労、慢性的な疲労、ストレス関連疾患(頭痛・胃痛・高血圧など)を引き起こす恐れがあります。
過小な要求
過大な要求とは反対に、明らかに不要な仕事しか与えず、成長や評価の機会を奪う行為です。
- 簡単な清掃や雑用ばかりを任され、保育業務に関わらせてもらえない
「役に立てない」と感じることで、うつ症状や職場への不満が増す人もいます。
個の侵害
プライバシーや人格を尊重せず侮辱や詮索をする行為は、個の侵害に当たります。
- 家庭環境や個人の事情を同僚の前で暴露される
- 服装や体型を馬鹿にされる
プライバシーを侵害されることによる不安感や、職場に対する恐怖・不信感が強まるでしょう。
パワハラで悩んだことがある保育士の体験談
実際の保育現場では、どのようなパワハラが問題視されているか気になりますよね。
ここでは、パワハラに悩んだことがある保育士の体験談を3つご紹介します。
全ての園で起こりうることではありませんが、このようなパワハラに遭わないためには職場の雰囲気や風通しの良い園を選ぶことが大切です。
残業代や有給休暇の申請が取り消される
幼稚園に勤めていた頃、週に1~2回の残業が発生しても残業代が正しく支払われず、それを園長に訴えても受け入れてもらえませんでした。
また、有給休暇も本来なら労働者の権利であるはずですが、希望通りに取得できないどころか不当に消されてしまうことも。
そうした扱いが年単位で積み重なり、これ以上我慢できないと感じた私は退職時に労働基準監督署へ相談。
結果として、未払いの残業代や消された有給分を回収することができたという経験があります。
あんちゃんさん(ほいポケ編集部独自アンケートより)
この体験談は、労働条件が守られない環境で働き続けることのリスクを示しています。
残業代の未払いも有給休暇の不当な扱いも、本来は労働者として当然の権利です。
もし同じような状況に悩んでいるなら、まずは記録を残し、信頼できる人や外部の相談窓口に相談することをおすすめします。
大声で叱責する



私が保育実習中に見た出来事です。2歳児クラスで実習していた際、担任は女性保育士、副担任は男性保育士でした。
明らかに立場の差があることは実習生の私から見ても感じられました。
ある日、男性保育士が保育の進め方を相談したところ、女性保育士は子どもたちや私の目の前で「そんなことも分からないのか」「だからお前は使えないんだ」と大声で怒鳴りました。
保育士同士のやり取りが子どもたちの前で公開叱責となってしまい、実習生としても強い違和感と恐怖を覚えました。
子どもたちの前で同僚を大声で叱責する場面は、保育者同士の信頼関係を損なうだけでなく、子どもにとっても安心できる環境を壊してしまいます。
実習生でさえ恐怖を感じるようなやり取りは、子どもたちの心にも不安や混乱を与えかねません。
職員間で意見の食い違いや不安があったとしても、子どもの前で感情的にぶつけるのは避けるべきです。
理不尽に叱られる



私が入社1年目の新人保育士だった頃のことです。
開園準備を担当する早番は毎日1名で、新人の私は責任感から毎日勤務開始の40分前には出勤して準備をしていました。ところがある日、やむを得ない事情で10分前に到着したところ、先輩保育士から「新人なんだから早く来て当たり前。なぜ10分前なんだ」と強い口調で責められました。十分に早い時間に来ているはずなのに理不尽に叱られ、萎縮してしまったのを覚えています。
また、行事前の準備期間には毎日22時ごろまで残業するのが当たり前のような雰囲気でした。ある日、同期の保育士が予定があり30分だけ残業して帰ったところ、「皆残っているのになんで帰ったの?やる気ないんじゃない?」と陰口を言われていました。その日以外は彼女も同じように残業していたのに、たった1日予定があって帰るだけで責められる職場の空気に、私も強い理不尽さと怖さを感じました。
新人だからといって過度な早出を強いられたり、少しでも残業を減らすと「やる気がない」と陰口を言われるような空気は、働く人のやる気や自信を奪ってしまいますよね。
本来なら責任感を持って準備をしていた姿勢は評価されるべきなのに、理不尽に叱責されたことは大きな萎縮や恐怖につながったことでしょう。
保育はチームワークが基盤なので、理不尽な雰囲気に流されるのではなく、前向きに改善できる声を出すことも保育士として大切な一歩となります。
保育士がパワハラを理由に転職する際の注意点
パワハラを理由に転職を決めた際、まずは自身の健康面や精神面を最優先に考えましょう。
体調が回復していないまま転職しても、慣れない環境で余計にストレスがかかり、ぶり返す可能性があります。
働ける状態になったら、以下の注意点に気をつけながら転職活動を始めてみてください。
- 事実と感情を分けて整理する
- 前職のネガティブな話は簡潔に説明する
- 転職理由を前向きに表現する
- 信頼できる転職支援サービスを活用する
- 健康面や精神面を最優先に考える
転職理由にパワハラを挙げる場合は、批判的になりすぎず、「学びや改善点」をセットで伝えることが大切です。
「貴園では職員と積極的にコミュニケーションを取りたい」など、パワハラ経験をきっかけに今後働き方をどう改善したいかを伝えると、担当者に働く意欲が伝わります。
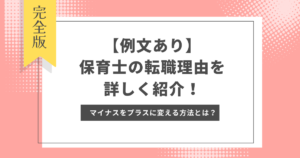
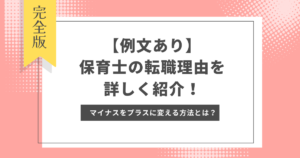
保育士が直面するパワハラ以外のハラスメントの種類
保育士が直面するハラスメントには、パワハラ以外に「セクハラ」「モラハラ」など様々な種類があります。
ハラスメントの種類を理解しておくことで、事前にハラスメントの内容が把握でき、早期対応が可能になります。
自分を守る行動に繋がるので、この機会に頭に入れておきましょう。
セクハラ(セクシャルハラスメント)
性的な言動や態度で不快感を与える行為です。
- 性的な冗談
- 身体に触れる行為
- 性的要求
不安感、羞恥心、自己肯定感が低下し、長期化するとストレスやうつ症状、睡眠障害、体調不良が起こる可能性もあります。
モラハラ(モラルハラスメント)
人格や尊厳を否定する言動で、精神的苦痛を与える行為を指します。
- 「あなたは使えない」「仕事ができない」と繰り返し責める
精神的な追い詰め、自己否定感、抑うつや燃え尽き症候群になる恐れがあります。
慢性的なストレスになると、身体症状が出ることもあるでしょう。
ジェンダーハラスメント
性別を理由に不利益や差別的扱いをする行為です。
- 男性だから重い仕事、女性だから責任のある業務を任せない
不公平感や疎外感を感じやすく、自己評価の低下、ストレス増加にも繋がります。
職場に対する不信感や、職業意欲の低下を引き起こす可能性が高いです。
マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠・出産・育児を理由に不利益を与える行為を指します。
- 妊娠を理由に昇進を見送る、退職を迫る
妊娠や育児に関する不安や罪悪感、抑うつ症状、身体的ストレスを感じやすいです。
出産・育児の計画にも悪影響が及ぶ場合があるため、注意しなければなりません。
セカンドハラスメント
セカンドハラスメントは、ハラスメントの相談や報告をしたことで、さらに嫌がらせを受ける行為です。
- 相談後に陰口や嫌がらせが増える
相談や行動の恐怖感、孤立感、精神的負担が増大する恐れがあります。
相談意欲が低下しやすくなるため、専門機関への相談をおすすめします。
保育士がパワハラを受けた際の対処法
「パワハラを受けているけど、怖くて誰にも相談できない」「今の職場で働き続ける自信がない」と悩まれていないでしょうか。
辛くても、一人で抱え込んでいては何も解決しません。
信頼できる上司や同僚に相談したり、別の保育園への転職を考えるなど対処法はあるので、勇気を出して実行に移してみてください。
パワハラの証拠を集める
パワハラの証拠集めは、自分を守る大切な手段となります。
「言った・言わない」「受けた・受けていない」といった感情論にならず客観的に事実を提示できるので、以下の手段を参考に証拠を残しておくとよいでしょう。
- メールやチャットのやり取り
- 業務日誌やメモ(日時・内容・発言者を記録)
- 同僚の証言や目撃者のメモ
- ボイスレコーダーでの録音
感情に流されず事実を淡々と記録するのがポイントです。
信用できる上司や同僚に相談する
パワハラを受けた際、信用できる上司や同僚に相談するメリットは大きいです。
- 孤立感が減り心理的負担が軽くなる
- 客観的な視点やアドバイスを得られる
- 証拠や証言のサポートになる
- 職場での改善につながる
第三者の意見や経験に基づいた対処法を教えてもらえるため、適切に対応できます。
信頼できる相手を選び、感情に流されず事実を整理して相談することを意識しましょう。
相談窓口に相談する
相談窓口を利用すれば、保育士がハラスメントに直面したときに安全・安心に対応してもらえます。
以下は、保育現場やパワハラ状況に理解があり、適切なアドバイス・支援を提供してくれる相談窓口です。
一人で抱え込まず、まずは信頼できる機関に相談してみてください。
| 相談できる相談窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」 | 0120-811-610(平日9:00~21:00、土日祝9:00~18:00) |
| 産業保健総合支援センター(各都道府県に設置) | 各都道府県の産業保健総合支援センターに問い合わせ |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374(平日9:00~21:00、土日祝9:00~17:00) |
別の保育園へ転職する
状況が改善されず今の職場で働くのが難しいと感じた場合、別の保育園へ転職することも視野に入れてみましょう。
転職には、以下のようなメリットがあります。
- 環境を変えることでストレスから解放される
- 前向きなキャリア形成につながる
- 精神的なリセットができる
つらい経験を一旦離れた環境で整理すれば、気持ちが切り替えやすくなります。
自己成長や仕事のやりがいを取り戻せ、キャリアアップも目指せるので、転職はポジティブな方法として捉えるとよいです。
パワハラのない職場に転職したい人向け転職サイト3選
パワハラにより転職を検討する際は、実績のあり信頼できる転職サイトを活用しましょう。
求人数やアドバイザーのサポート体制、職場の独自調査の有無なども判断材料にするとよいです。
今回は、「保育士ワーカー」「マイナビ保育士」「保育エイド」の3つの転職サイトの特徴やメリットをご紹介します。
保育士ワーカー
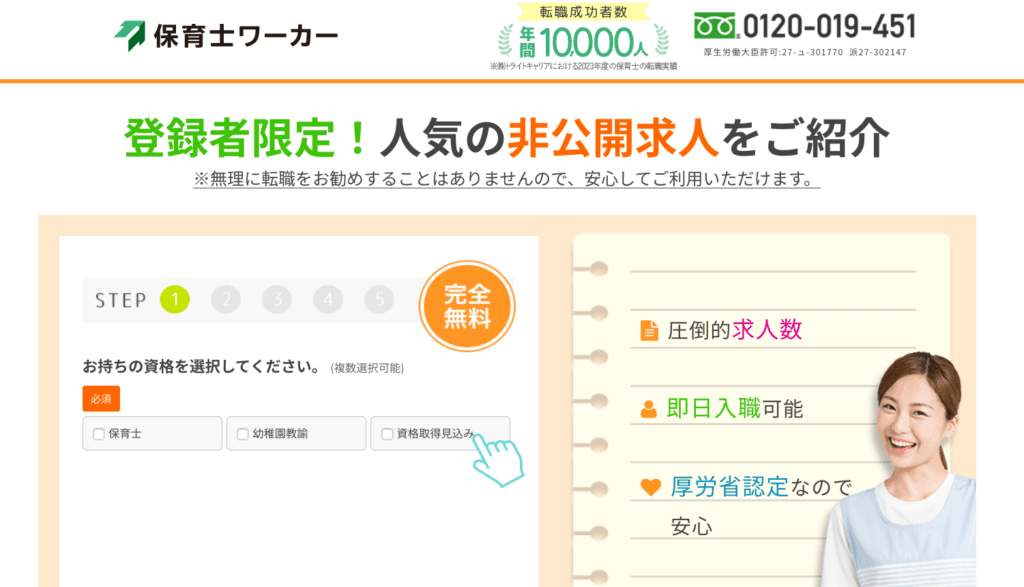
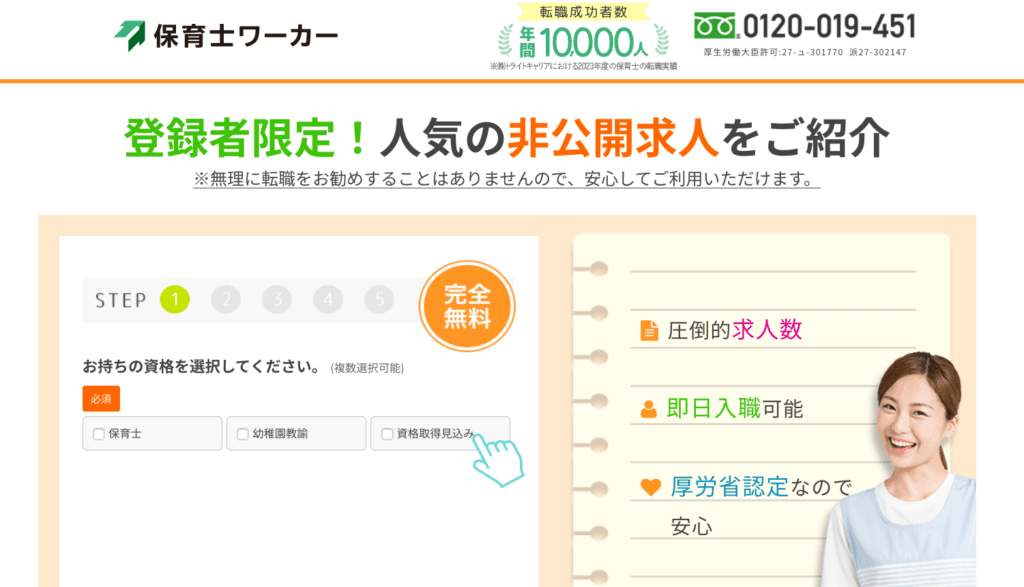
| 運営会社 | 株式会社トライトキャリア |
|---|---|
| 求人数 | 約29,577件(2025年8月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・アルバイト・パート |
| 公式サイト | https://hoikushi-worker.com |
保育士ワーカーは、登録時にパワハラや人間関係の悩みを詳細に聞き取り、希望に沿った職場を提案してくれます。
前職でのパワハラ経験を尊重し、それを踏まえた上でストレスの少ない職場環境を提供してくれるので安心して利用できるでしょう。
一般公開されていない非公開求人も多数取り扱っており、より良い条件の職場を見つけることができますよ。
LINEを利用したやりとりも特徴で、日中仕事や家事で忙しい人でも隙間時間に転職活動が進められます。
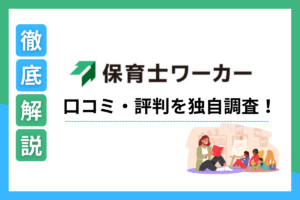
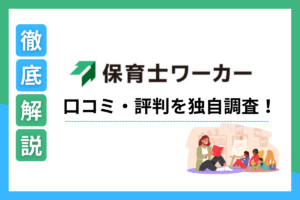
マイナビ保育士


| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
|---|---|
| 求人数 | 約20,392件(2025年8月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員・非常勤・パート |
| 公式サイト | https://hoiku.mynavi.jp |
マイナビ保育士はアドバイザーが直接保育園を訪問し、園の雰囲気や職員間の関係性を独自に調査しています。
これらの独自調査により、風通しの良い職場を紹介してもらえるでしょう。
転職後もアドバイザーが引き継ぎや退職手続きのサポートを行ってくれ、入職後の不安や悩みも相談できるのが特徴です。
また、公式サイトではパワハラの定義や指導との違い、具体的な対処法について詳しく解説しており、状況整理や次のステップを考える際の参考になります。
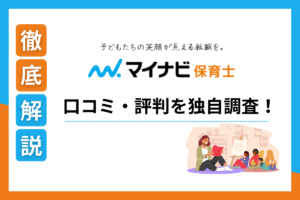
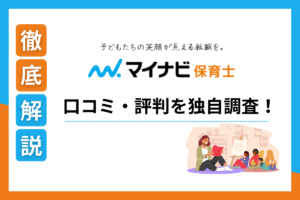
保育エイド


| 運営会社 | 株式会社サクシード |
|---|---|
| 求人数 | 会員のみに公開 |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・パート・派遣 |
| 公式サイト | https://www.hoiku-aid.jp |
保育エイドは、人間関係に悩みたくない人に特化した転職サービスです。
アドバイザーが各保育園に足を運び、園の雰囲気や職員間の関係性を把握しているため、パワハラのリスクが低い職場を紹介してもらえます。
入職前に職場の雰囲気を把握し、条件のミスマッチを避けることができるでしょう。
転職活動中はLINEなどで気軽に連絡できるため、仕事をしながらでも安心して相談できますよ。


まとめ
保育士が職場でパワハラに直面することは珍しいわけではなく、一人で抱え込む必要もありません。
まずは信頼できる同僚や上司、専門機関に相談し、事実を記録しておきましょう。
また、改善が難しい場合は、安全で働きやすい環境を求めて転職を検討するのも有効な選択肢です。
自分の心身を守りつつ、安心して働ける職場を見つけましょう。