長年保育士をしていると、少なからず思わぬ言動で保護者を怒らせた経験があるのではないでしょうか。
「どう謝罪したらよいだろう……」「どのように伝えるべきだったのかな」と、1人で反省してしまいますよね。
本記事では、保護者を怒らせてしまう保育士のNG発言や保護者を怒らせたときの対応方法などを詳しくご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
- 子どもを傷つけるような発言、保護者への共感がない発言に注意する
- 保護者を怒らせてしまったときは、まずは話を聞くことから始め、相手の気持ちに寄り添う
- 日々の丁寧なコミュニケーションが、保護者との良好な関係に繋がる
- 保護者対応で自信をなくしたときは、転職して新しい環境に溶け込むのも一つの手段
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライター保護者を怒らせてしまうと、「このまま関係が崩れたらどうしよう」と不安になってしまいますよね。保育士は誰にでも失敗経験があります。深く落ち込まず、正しい対応策とNG発言を理解して保護者との良好な関係を築けるようにしましょう。


ゆぴ先生 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
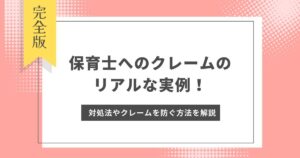
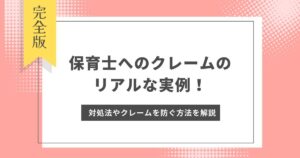
【実録】実は私も保護者を怒らせた経験がありました
元保育士の私も、現役時代に以下の理由で保護者を怒らせてしまった経験があります。
- 自由遊び中に子どもに怪我をさせてしまった際、「なぜ絆創膏代を支払ってくれないのか」と指摘される
- 帰宅後に保育者から聞かされていなかった怪我を見つけ、当時どういう状況だったのか指摘される
- 連日子どもに怪我を負わせてしまい、どのような保育を行っているのか指摘される



保育士経験が浅い頃の出来事もあり、「どうしよう。怒らせてしまった」とパニックになりました。
保護者を怒らせてしまう、保育士のNG発言とは?
よかれと思って発言した内容や言葉遣いが、保護者にとっては傷ついたり憤慨したりする原因になりかねません。
保育士は、「子どもを傷つけるような発言」「自分の非を認めない発言」「上から決めつけるような発言」などに気をつけながら保護者と関わっていきましょう。
ここでは、保護者を怒らせてしまう保育士のNG発言を4つの項目ごとに解説します。
子どもを傷つけるような発言
- 「〇〇ちゃんはいつもできないね」
- 「他の子はできるのにどうしてできないの?」
- 「そんなことしてたらみんなに嫌われちゃうよ」
- 「わがままばかりで困ります」
子どもの行動や気質を、否定的な表現でそのまま保護者に伝えるのは避けるべきです。
例えば「いつもできない」「乱暴」「わがまま」などの言葉は、子どもの人格を否定する印象を与え、保護者に強い不安や罪悪感を抱かせてしまいます。
また、「他の子と比べる」発言は子どもや家庭を劣っているように感じさせ、信頼関係を壊す原因になりかねません。
子どもの課題を伝えるときは「○○のときに少し難しそうにしていました」「△△の場面でサポートすると安心してできていました」など、事実や様子を丁寧に伝え、改善や成長の可能性に目を向けることが大切です。
保護者への寄り添いや共感がない発言
- 「おうちでちゃんと見れていないんじゃないですか?」
- 「忙しいのは分かりますが、それは親の責任ですよね」
- 「そんなことで悩んでいるんですか?」
- 「保育園では普通にできていますけど?」
保護者は、子育ての悩みや不安を抱えながら園に相談することが多いです。
その際に「それは親の責任です」「園では問題ありません」と突き放すような発言をすると、理解してもらえなかったと感じ、孤立感を深めてしまいます。
大切なのは、まず保護者の気持ちを受け止め「大変ですよね」「そういうことがありますよね」と共感を示すこと。
その上で「園ではこういう姿が見られますよ」「一緒に工夫を考えていきましょう」と寄り添う姿勢を持つと、前向きな関係が築けますよ。
自分の非を認めない発言
- 「こちらはちゃんとやっていますので」
- 「保育園側は悪くないと思います」
- 「そう感じるのは〇〇さんの受け取り方では?」
- 「忙しかったので仕方ないんです」
園でミスやトラブルがあったときに「私たちは悪くありません」「忙しかったので仕方ないです」などと責任を回避する態度を取ると、保護者に不信感を与えるでしょう。
子どもを預けている立場の保護者は「誠実に対応してもらえるかどうか」で安心感が大きく変わります。
たとえ園側に過失がなくても、保護者が不安や疑問を感じているなら真摯に受け止める姿勢が大切です。
「ご心配をおかけしました」「園としてはこう改善していきます」と誠意をもって伝えることで、信頼を取り戻すきっかけとなります。
上から決めつけるような発言
- 「〇〇くんはこういう子ですから」
- 「こうした方がいいに決まってます」
- 「もっとしっかりしてください」
- 「それはお母さん(お父さん)の育て方の問題です」
「〇〇くんはこういう子です」「親なんだからできて当然」など、保護者や子どもの状況を一方的に断定する発言は、上から目線で圧力をかけているように受け止められます。
保護者は園と同じく子どもの成長を願う存在であり、対等なパートナーです。
決めつけや強い言い切りは「相談しづらい」「否定される」と感じさせてしまい、関係性が悪化する恐れがあります。
「こういう傾向が見られるのですが、ご家庭ではいかがですか?」「一緒に取り組める方法を考えていきましょう」という、対話を重視した伝え方を意識しましょう。
私だけじゃない?!「保護者を怒らせたことがある保育士」さんに聞いてみた!
保護者を怒らせてしまった経験は、保育士なら誰でも一度はあるはず。
実際にどのような場面で保護者を怒らせてしまったのか、その後どのように対応したのか気になりますよね。
ここでは、保護者を怒らせてしまった経験がある保育士の体験談を2つご紹介します。
同じ失敗をしないよう、今のうちに正しい接し方を覚えておきましょう。
事務的な伝え方で保護者を怒らせてしまった



新卒で認可保育園に勤めていた頃、1歳児クラスの担任をしていたときのことです。
体調不良で数日休んでいた子どもが登園しましたが、昼過ぎに熱が37.5度を超えて、様子を見ているとさらに上がったため、お迎えをお願いしました。
園としては規定に沿った判断でしたが、私の伝え方が拙く、迎えに来たお父さんから「こんなことで呼ばれるなんて」と怒られてしまいました。
今思うと、数日仕事を休んでやっと出勤できた保護者の気持ちに寄り添えず、ただ事務的に伝えてしまったことが原因だったと感じています。
新人の頃に保護者対応で戸惑ってしまうのは、誰にでも起こり得ることです。
園の規定に沿って正しい判断をしていたのに、思わぬ形で保護者の不満を受けてしまうのはとても辛いですよね。
ですが、この体験から「伝え方ひとつで相手の受け取り方が大きく変わる」ということが学べます。
子どもの体調を伝える際には、事務的な説明だけでなく「お仕事で大変な中ですが…」「心配な状況なので」など、保護者の立場に寄り添う言葉を添えるだけでも印象は大きく違いますよ。
タメ口を使い保護者に叱責された



認可保育園に勤めていた頃の出来事です。
新卒で入職した保育士は、明るく気さくな性格で子どもや保護者からも親しみやすい一方、学生気分が抜けず、保護者に対してタメ口で話してしまうことがありました。
職員間で何度か注意してもなかなか改善されず、ついに保護者から「友達ではないのに、なぜそのような言い方をするのか」と強い口調で叱責を受けました。
この出来事をきっかけに、園全体で保護者対応の言葉遣いや姿勢を改めて見直すことになりました。
新人保育士の明るく親しみやすい性格は大きな長所ですが、学生気分が抜けず保護者にタメ口で話してしまうと、信頼関係を損ねる原因になり得ます。
保護者対応では、言葉遣いや態度ひとつで印象が大きく変わります。
新人であっても、子どもや保護者との距離感を意識し、敬語や丁寧な表現を心がけることが大切です。
保護者を怒らせた時に保育士が取るべき対応とは?
保護者を怒らせてしまうと、その後の関係性に悩んだり園の問題に発展したりする場合があります。
問題が生じた際は、不信感を抱かないよう迅速な対応を取らなければなりません。
ここでは、「相手の気持ちに寄り添う」「謝罪と説明はセットで行う」など、保育者が取るべき対応を解説します。
まずは「聞く」ことから始める
保護者が怒っているとき、ついすぐに弁解や説明をしたくなりますが、まずは「どうされましたか?」「今回の経緯を教えてください」と、相手の話をしっかり聞く姿勢が大切です。
話の途中で言い訳をしたり遮ったりすると、「理解してもらえていない」と感じさせ、さらに不信感を招く可能性があります。
うなずきや相づちを交えながら最後まで聞き切り、「自分の気持ちを受け止めてもらえた」という安心感につながる配慮をしましょう。
感情的にならず、相手の気持ちに寄り添う
保護者の怒りの裏側には、不安や心配、戸惑いなどさまざまな感情が隠れています。
保育者が感情的に反応すると対立が生じるため、落ち着いた口調で「ご心配をおかけしてしまいましたね」「不安なお気持ちになられたのも当然だと思います」といった共感の言葉をかけることが大切です。
寄り添う姿勢は、怒りを少しずつ和らげ冷静な話し合いに導く第一歩になります。
人通りの少ない場所に移り、じっくりと話を聞く時間を設けてみてもよいでしょう。
事実確認をしっかり丁寧に行う
感情面を受け止めた後は、実際に何が起きたのかを丁寧に確認することが欠かせません。
伝聞や憶測で対応すると、さらなる誤解や不信感に繋がります。
関わった保育者からの情報を集め、子どもの状況やその場の経緯を正確に整理しましょう。
「その時の状況を確認させていただきます」と保護者に伝えることで、誠実さや責任感が伝わります。



私も過去に、自身が保育室にいない時間帯のトラブルについて、保護者から責められた経験があります。まずは当時どのような状況だったのか、担当保育者から情報を集め、再び保護者に経緯を説明しました。
謝罪と説明はセットで行う
トラブルや誤解があったときは、謝罪の言葉をまず伝えることが必要です。
ただし謝るだけではなく、「なぜそのような状況になったのか」「今後どう改善するのか」を一緒に説明しましょう。
謝罪と説明をセットにすることで、保護者は「責任を認めた上で、解決に向けて動いている」と感じ、信頼回復に繋がります。
形式的な謝罪ではなく、以下のような誠意が伝わる具体的な言葉を選ぶことが大切です。
「この度は〇〇の件でご心配をおかけし、申し訳ございませんでした。○○の場面で△△が起きてしまい、不安なお気持ちになられたことと思います。園としても大切にすべき点だと受け止めております。今後は□□のように改善を行い、再発防止に努めてまいります。」
園全体で対応し、個人で抱え込まない
保護者対応は一人の保育者だけで解決しようとすると、プレッシャーや誤った判断につながる危険があります。
主任や園長など責任者と連携し、園全体で対応することが望ましいです。
「園としてどのように考えているか」を伝えることで、組織としての信頼感が増し、個人への不満が園への建設的な話し合いに変わりやすくなります。
保育者自身の負担を減らす意味でも、相談・共有の姿勢は欠かせません。
保育士と保護者が協力し合える関係づくりのコツ
保育士と保護者の信頼関係があれば、トラブルが起きても感情的になりにくく、速やかな解決に繋がります。
相互が協力し合える関係作りを行うには、「日々のコミュニケーションを丁寧に行う」「子どもの成長を共有し、喜びを分かち合う」などのコツを意識することが大切です。
ここでは、関係作りに大切な3つのコツを詳しく解説します。
日々のコミュニケーションを丁寧に
保育士と保護者の信頼関係は、一度の大きな出来事ではなく、日々の小さなやりとりの積み重ねで築かれます。
送迎時の挨拶や連絡帳でのやり取りなど、一見些細に思えるやり取りこそ大切です。
例えば「今日はこんな遊びに夢中になっていましたよ」と短い一言を添えるだけでも、保護者は「子どもをよく見てもらえている」と安心できます。
反対に、忙しさを理由に対応が雑になると、「自分の子どもを軽んじられている」と感じさせてしまう恐れがあります。
日々の丁寧な積み重ねを意識して、協力関係の土台を作りましょう。
育児の悩みや不安に共感する姿勢を示す
保護者は子育ての中で、「家ではこうだけど園ではどうだろう」といった悩みを抱えています。
その際に「それは心配いりませんよ」と軽く流してしまうと、理解してもらえていないと感じ、不信感に繋がりやすいです。
まずは「そういうとき、不安になりますよね」「大変さがよく伝わってきます」と共感を示すことを意識しましょう。
その上で「園ではこういう姿が見られます」「こんな工夫が役立つかもしれません」と情報を共有すると、保護者は安心し、前向きに取り組めるようになります。
子どもの成長を共有し、喜びを分かち合う
子どもの小さな成長や変化は、家庭だけでなく園でもたくさん見られます。
保護者にとって、子どもの頑張りや新しい一面を保育士から聞けることは大きな喜びです。
例えば「昨日より少し長く跳べるようになりましたよ」「友だちに玩具を貸してあげる姿がありました」と具体的に伝えると、保護者は我が子の成長を実感し、嬉しさと安心感を得られます。
その「喜びを共有する」時間が積み重なると、自然と信頼関係も深まり、保護者も園に協力したいという気持ちが強まるでしょう。
保護者対応で自信をなくしたら…転職して新たな環境も選択肢のひとつに
「信頼関係を修復する自信がない」「どうしても波長が合わない保護者がいる」と保護者対応に挫けてしまったら、転職して新しい環境に飛び込むのも一つの選択肢です。
転職サイトなら、保護者対応が比較的少ない職場やサポート体制が整っている職場を見つけられますよ。
ここでは、「保育士ワーカー」「マイナビ保育士」「保育士人材バンク」3つのサイトを紹介します。
保育士ワーカー
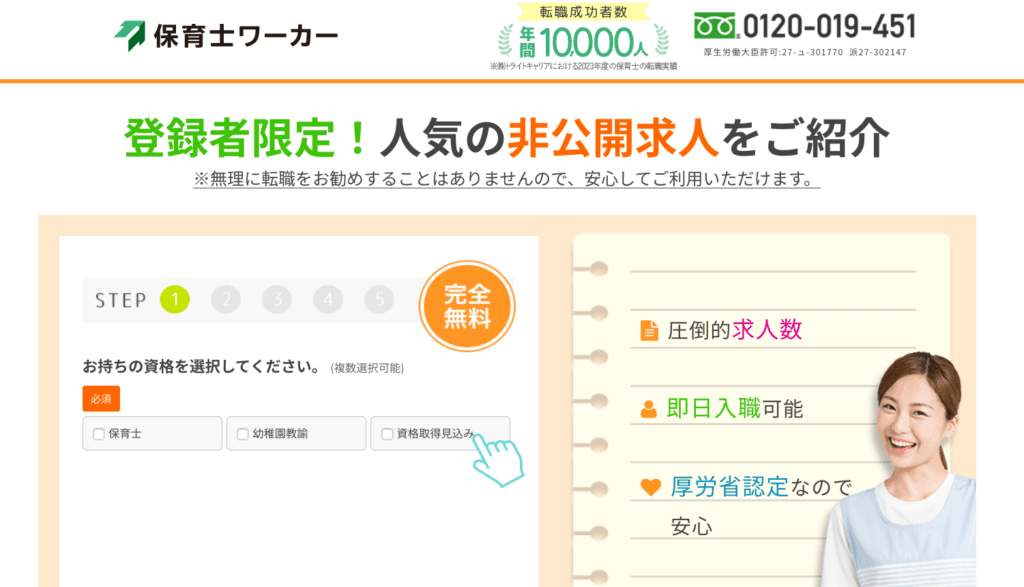
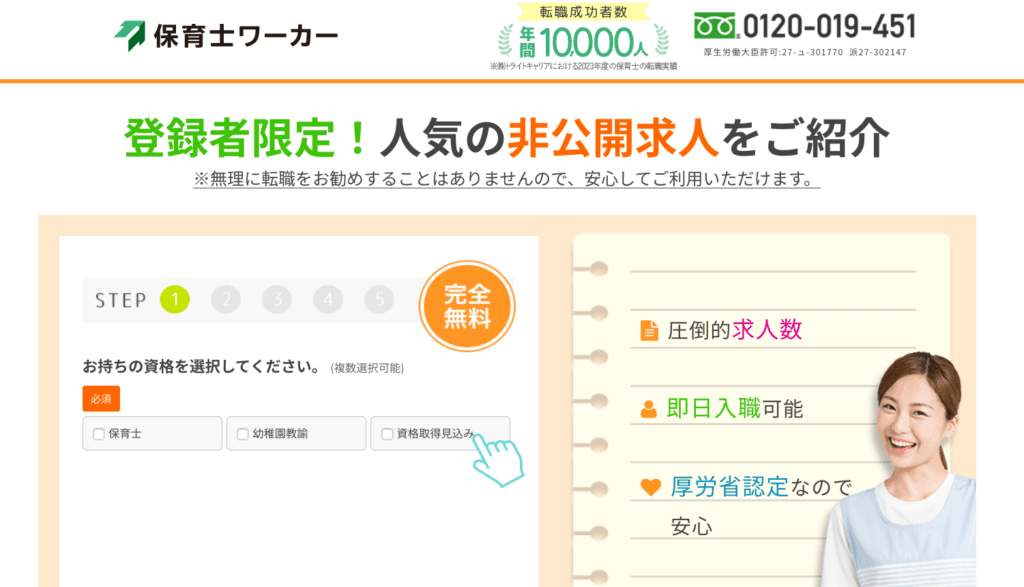
| 運営会社 | 株式会社トライトキャリア |
|---|---|
| 求人数 | 約29,577件(2025年8月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・アルバイト・パート |
| 公式サイト | https://hoikushi-worker.com |
保育士ワーカーは、ヒアリングから面接同行、入職後のアフターフォローまで手厚いサポートが特徴の転職サイトです。
転職活動のプロが、一人ひとりの条件に適した求人を探してくれます。
前職で保護者対応に自信をなくしてしまったことを伝えれば、比較的保護者対応が少ない職場やサポート体制が整っている職場など、負担のかからない求人を提案してくれますよ。
非公開求人に加え、約30,000件の求人の中から働きやすい職場を探せるのもポイントです。
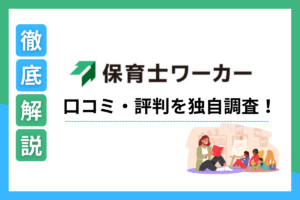
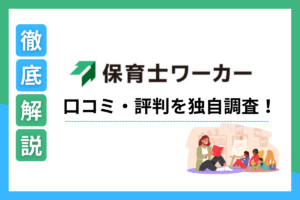
マイナビ保育士


| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
|---|---|
| 求人数 | 約20,392件(2025年8月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員・非常勤・パート |
| 公式サイト | https://hoiku.mynavi.jp |
マイナビ保育士は、株式会社マイナビという大手運営により安心感や信頼感のあるサイトです。
求人の質にこだわっているのが特徴で、アドバイザーが実際に施設を訪問し、現場の雰囲気や条件を自身の目で確かめたうえで紹介しています。
保護者対応は「保育士個人のスキル」だけではなく、園全体の職員関係が土台になっているので、職員関係が良好であるか確認することが大切です。
アドバイザーの意見を参考にしながら、チームとしての一体感が感じられる職場を選んでみましょう。
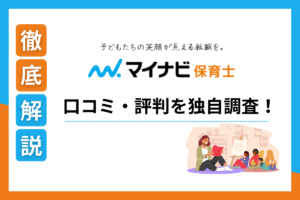
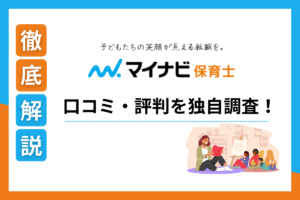
保育士人材バンク


| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス |
|---|---|
| 求人数 | 約35,949件(2025年8月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員・パート・アルバイト |
| 公式サイト | https://hoiku.jinzaibank.com |
保育士人材バンクは、質の高いマッチングと豊富な求人がポイントで、独自ルートで集めた豊富な求人を掲載し、厚労省認定の基準を満たした高いマッチング力を誇っています。
公開求人以外にも、非公開求人や正社員・派遣・パートなど多様な雇用形態に対応。
パートや派遣社員は正社員より保護者対応業務が少ないため、保護者対応に自信をなくした方でも働きやすいです。
保護者と関わる時間を減らしたい場合は、雇用形態も併せて検討してみるとよいでしょう。
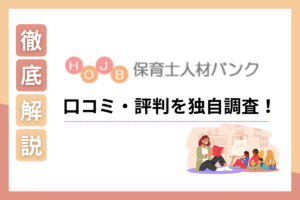
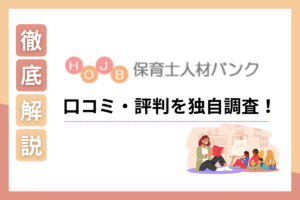
まとめ
保育士が保護者を怒らせないためには、日々の丁寧なコミュニケーションと共感、園全体でのサポート体制が欠かせません。
もしトラブルが起きても、まずは話を「聞く」ことから始め、感情に流されず事実を確認し、誠意ある謝罪と説明を心がけましょう。
保護者を怒らせてしまうのは誰にでも起こり得ることなので、自信をなくさず、その経験から次にどう生かすかを考えていきましょう。








