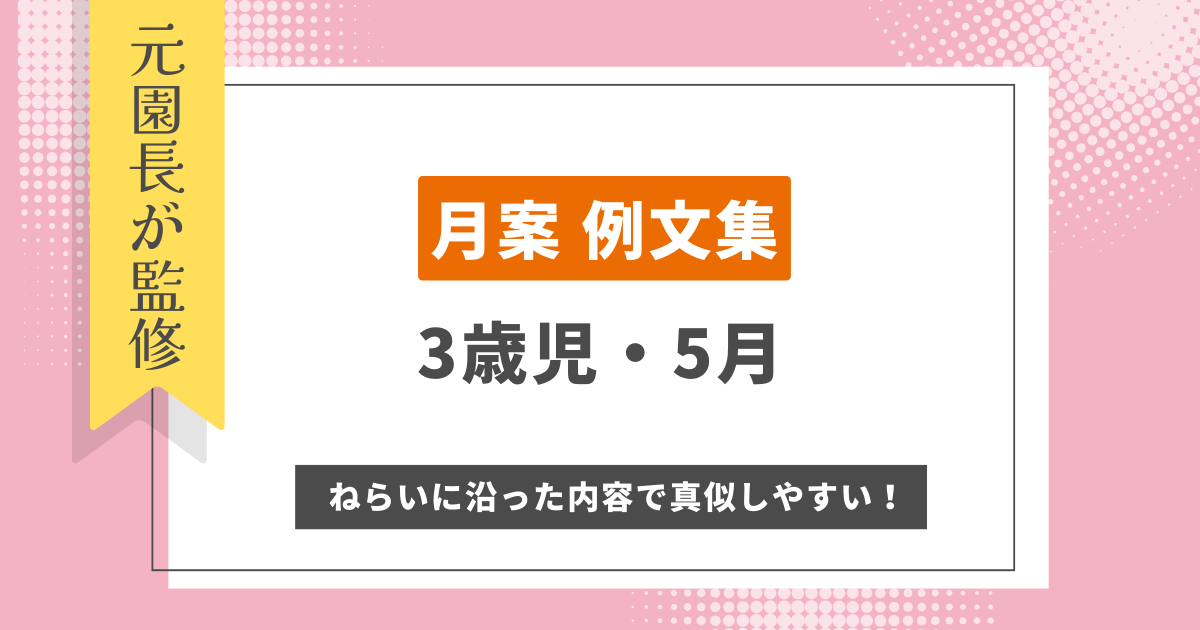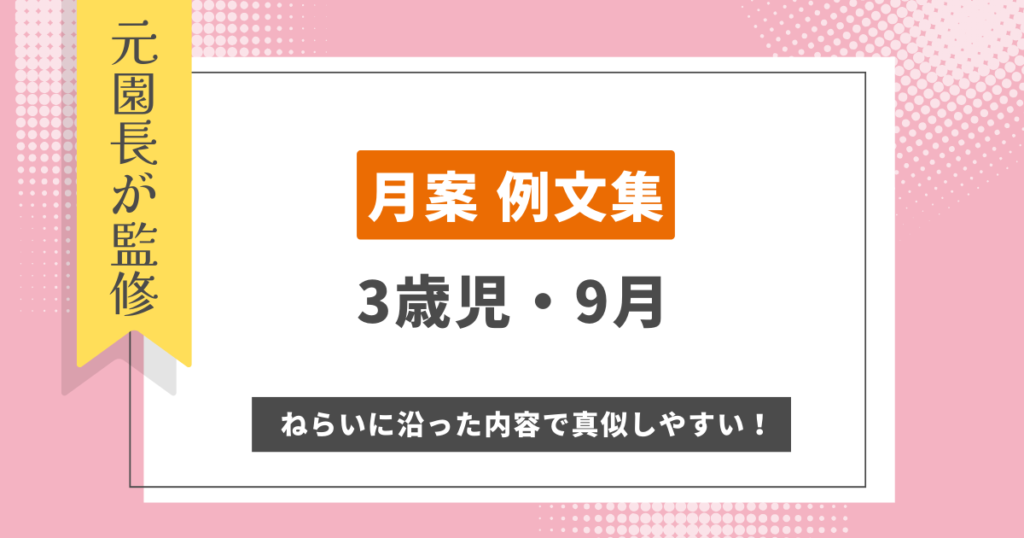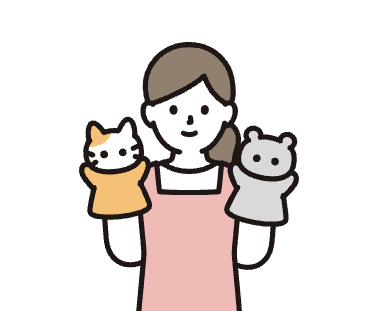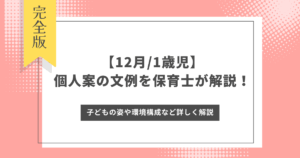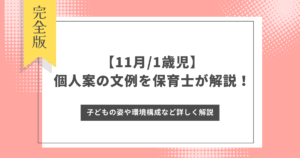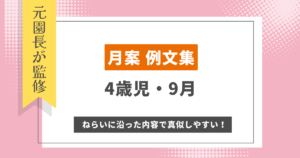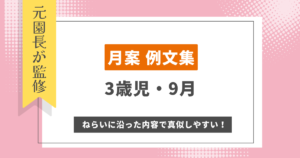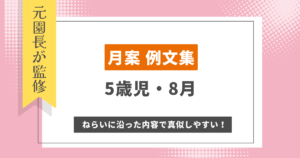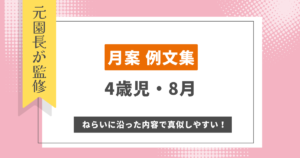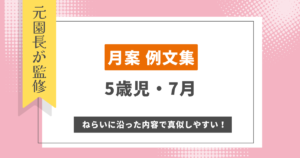新緑が気持ちいい5月、子どもたちは外遊びや友達との関わりが増えてくる時期です。3歳児は前月の姿をふまえ、遊びを通して少しずつ成長し、できることが増えていきます。この記事では、園長歴6年のベテラン保育士が監修した、3歳児クラス向けの5月用の月案文例を解説していきます。

Aki 園長歴6年
保育士歴18年、園長歴6年。これまで多くのカリキュラム添削や、保育士さんたちの悩みに寄り添ってきました。この記事では園長として多くの月案・週案をチェックしてきた経験を活かし、 効率よく質が高い月案・週案を仕上げられるようサポートします。
いち早く例文をご確認したい方は「こちらのリンク」を押してください。
↓タップすると指定の見出しにジャンプします
元園長が教える月案・週案の重要ポイント
まずは大前提、月案を作る上でどんなことが重要か…実際に保育士さんたちの数々の月案をチェックしてきた元園長先生に、重要ポイントを伺いました。
- 年間カリキュラムに基づく計画を立てる
- まずは「前月の子どもの姿」から考え始める
- 「今月のねらい」と「具体的な内容」は連動して考える
この3つが、年齢・時期関わりなく月案を作成する上で意識してほしい点です。
要するに、「保育園での活動を通して、子どもたちにどんな姿になってもらいたいのか」を考えると良いということですね。
3歳児・5月の月案のポイント
次に、「3歳児・5月」ならではの月案のポイントを紹介します。
- 新生活のスタートから1ヶ月経ち、少しずつ新しいクラスでの生活に慣れてくる時期。生活の流れがわかり、保育者に手伝われながらも、徐々に自分で身の回りのことができるようになってくる。適宜サポートしつつ、意欲を育てられるようにしていきたい。
- 長期連休明けの登園では、生活リズムの乱れや行き渋り、情緒が不安定になることなどが予想される。再び園生活のリズムを取り戻せるよう、無理のない活動を心がける。
入園・進級から1ヶ月が経ち、新しいクラスでの生活に少しずつ慣れてくる5月。
ですが、GWの連休を挟むことで、休み明けの登園では再び不安定になる子どもも多くいます。
この時期は無理をせず、ゆっくりとした時間の流れを意識し、家庭と連携しながら園生活のリズムを取り戻していけるようサポートしましょう。
それではここから、具体的な月案の例文をまとめていきます。
《 STEP1》 前月の子どもの姿を思い出す
- 進級を喜ぶ一方で、新しいクラスでの生活に戸惑いを見せる子がいた。登園時に泣いてしまったり、クラスの活動に入れない姿を見せたりと、不安定な様子が見られることがあった。
- ロッカーの使い方や物の片づけ方など、子どもたちが自分で動けるよう保育室内に掲示をした。掲示物を見ながら行動できる子もいたが、何をしたらいいかわからなくなってしまう子もいたため、適宜サポートした。
- 園庭で摘んだ花を押し花にすることを喜んでいた。散歩先での春探しも楽しんでおり、友だち同士で教え合う姿があった。
《 STEP2》 今月のねらいを決める
養護のねらい
教育(5領域に対応)のねらい
- 保育者や友だちと一緒に、春の心地良さを感じながら戸外で体を動かして遊ぶ
- 保育者に様々な欲求を受け止めてもらい、気持ちを言葉で伝えたり、のびのびと自己表現したりしながら安心して過ごす
- 春の自然に触れ、昆虫や草花などの発見・観察を楽しむ
養護のねらい①の具体的な月案
ねらい
安心・安全な環境のもと、のびのびと自己発揮して過ごす
養護・内容
- 清潔で安全な環境で、安心して自己発揮する(生命の保持)
- 保育者に親しみを感じ、甘えや様々な気持ちを自由に表す(生命の保持、情緒の安定)
養護・予想される子どもの姿
- 連休明けの不安定な気持ちを保育者に受け止めてもらい、安心感を感じている
- 甘えをうまく表現できず、泣いたり怒ったりして伝えようとする姿がある
養護・環境構成/保育者の配慮
- 温かくゆったりとした関わりを心がげ、安心して自己発揮できるようにする
- 子どもたちの目線に姿勢を落とし、安心して気持ちを伝えられるよう関わる
- 気持ちをうまく言葉にできない時には、適宜言葉を足したり代弁したりするなどして子どもの気持ちを引き出し、伝わった喜びを感じられるようにする
>>ねらいを書き終えて行事や遊び、
自己評価などに移りたい人はこちらをタップ
養護のねらい②の具体的な月案
ねらい
安定した生活リズムの中で、生活の流れを理解し、身の回りのことを自分で行う
養護・内容
- 園生活のリズムを取り戻し、安心感をもって過ごす(生命の保持)
- 生活の流れを理解し、保育者の見守りのもと、身の回りのことを自分で行う(情緒の安定)
養護・予想される子どもの姿
- 連休明けは不安定な様子が見られたが、少しずつ園生活のリズムを取り戻した様子
- なかなか気分が乗らない時があり、保育者に手伝われながら身支度や玩具の片づけをする
養護・環境構成/保育者の配慮
- 園生活のリズムを取り戻せるよう、不安な気持ちに寄り添い、適宜サポートすることで無理なく園生活のリズムを取り戻せるようにする
- 連休明けは生活リズムの乱れから心身の不調をきたすことがあるため、無理をせず、ゆったりとした活動を心がける
>>ねらいを書き終えて行事や遊び、
自己評価などに移りたい人はこちらをタップ
教育のねらい①の具体的な月案
ねらい
保育者や友だちと一緒に、春の心地良さを感じながら戸外で体を動かして遊ぶ
教育・内容
- 春の心地良い陽気の中、散歩や戸外遊びを楽しむ(健康・環境)
- 保育者や友だちと一緒に、かけっこや鬼ごっこなどをして、体を動かして遊ぶ(健康・人間関係)
教育・予想される子どもの姿
- 戸外遊びを喜び、保育者や友だちと一緒にかけっこやボール遊びを楽しんでいる
- 気温の高い日には汗をかくことが増えてきた
教育・環境構成/保育者の配慮
- 十分に戸外遊びが楽しめるよう、時間に余裕をもって出発する
- 気温の高い日には薄着を勧めると共に、水分補給や着替えをしっかり行い、健康かつ清潔に過ごせるようにする
- 散歩中や公園での安全な遊び方や決まりを伝え、自分たちで意識できるよう促す
>>ねらいを書き終えて行事や遊び、
自己評価などに移りたい人はこちらをタップ
教育のねらい②の具体的な月案
ねらい
保育者に様々な欲求を受け止めてもらい、気持ちを言葉で伝えたり、のびのびと自己発揮したりしながら安心して過ごす
教育・内容
- 保育者に親しみを感じ、自由に自己表現し、安心して過ごす(人間関係・表現)
- 自分の気持ちを言葉で話し、伝える大切さや伝わる喜びを知る(人間関係・言葉)
教育・予想される子どもの姿
- 甘えや要求をうまく言葉にできず、泣いて気持ちを表そうとする姿がある
- 保育者や友だちに、自分の気持ちや言いたいことが伝わったことを喜んでいる
教育・環境構成/保育者の配慮
- 泣いたり怒ったりしながら気持ちを伝えようとする姿を認めながらも、その時々に必要な言葉を知らせ、言葉での表現を促す
- 子どものありのままの姿を受容し、自由に気持ちを表現できる環境を作る
- 絵本や紙芝居、絵カードなどを活用し、場面に合った言葉を知らせる
>>ねらいを書き終えて行事や遊び、
自己評価などに移りたい人はこちらをタップ
教育のねらい③の具体的な内容
ねらい
春の自然に触れ、昆虫や草花などの発見・観察を楽しむ
教育・内容
- 身近な春の自然に触れ、遊びや製作に活かす(環境・表現)
- 身近な草花や昆虫の発見を楽しみ、友だちと一緒に観察したり調べたりして楽しむ(人間関係・環境)
教育・予想される子どもの姿
- 目に入った草花や昆虫など友だちや保育者に伝え、共有しようとする
- 散歩先や公園などで発見した花を摘んだりちぎったりしてしまうことがある
教育・環境構成/保育者の配慮
- 身近な自然と触れ合える散歩先を事前に下見しておく
- 子どもたちの発見や驚きに共感し、興味関心を広げられるようにする
- 散歩先や公園などの花壇に植えられている草花は、大切に育てている人がいることやむやみに摘んではいけないことを伝え、「見るだけにしようね」等の声をかける
>>ねらいを書き終えて行事や遊び、
自己評価などに移りたい人はこちらをタップ
行事・遊び・食育・職員との連携・家族や地域との連携・自己評価の月案例
今月の行事
- こどもの日集会
- 母の日(ファミリーデー)
- 保護者会
- 誕生会
- 身体測定
- 避難訓練
今月の遊び
- 母の日(ファミリーデー)の製作
- 散歩・戸外遊び
- 室内自由遊び
- 運動遊び
- ボール遊び
- 触れ合い遊び
- 手遊び(やおやのおみせ、おちたおちた)
- 絵本・紙芝居の読み聞かせ(ぐりとぐらのえんそく、どうぞのいす、おへそのあな)
- 5月の歌を聴く・歌う(こいのぼり、おかあさん、春の小川)
- 春の自然に触れる遊び
食育
- 子どもの日の行事を通して、日本の伝統的な食文化を知る
- 食事中のマナーを意識しながら、楽しく食事をする
職員との連携
- 連休明けは不安定になりやすいため、配慮の必要がある子を知らせ、担任がいない場合の受け入れについて共有しておく
- 戸外遊びの際には、職員同士で連携し、死角のないような位置に付き遊びを見守る
家庭や地域との連携
- 連休明けは疲れやすく不安定になりやすいため、園と家庭とで様子を細かく伝え合い、無理なく園生活のリズムを取り戻せるようサポートしていく
- 連休明けの子どもたちの心身の状態に配慮し、無理のない活動を心がけることを伝え、家庭でも生活リズムを整えてもらえるようお願いする
- 保護者会を通して、1年間の見通しや、子どもたちの成長などを共有し、共通理解のもと保育を行なえるようにする
自己評価
- 連休明けの登園で不安定になる子が多く、朝の活動にスムーズに入れない日が続いた。そのため、朝の一斉活動前に自由遊びの時間を長めに設けたり、音楽をかけダンスをする時間を作るなどして、気持ちを切り替えられるようにしたところ、徐々に集団での活動にスムーズに入れるようになった。
- 保育者にも慣れ、親しみを感じてくれているようで、スキンシップをとったり、甘えを素直に表現したりする姿があった。中にはうまく表現できず、自分から訴えられない子もいたため、積極的に声をかけた。
- 保護者会で、1年間の保育目標や保育者の想いを伝えた。3歳児になり、連絡帳がなくなることに不安を感じる保護者もいるようであったが、その理由を伝え、不安があればいつでも面談ができることなどを伝えたところ、安心してくれた。
-

元園長監修【3歳児・9月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


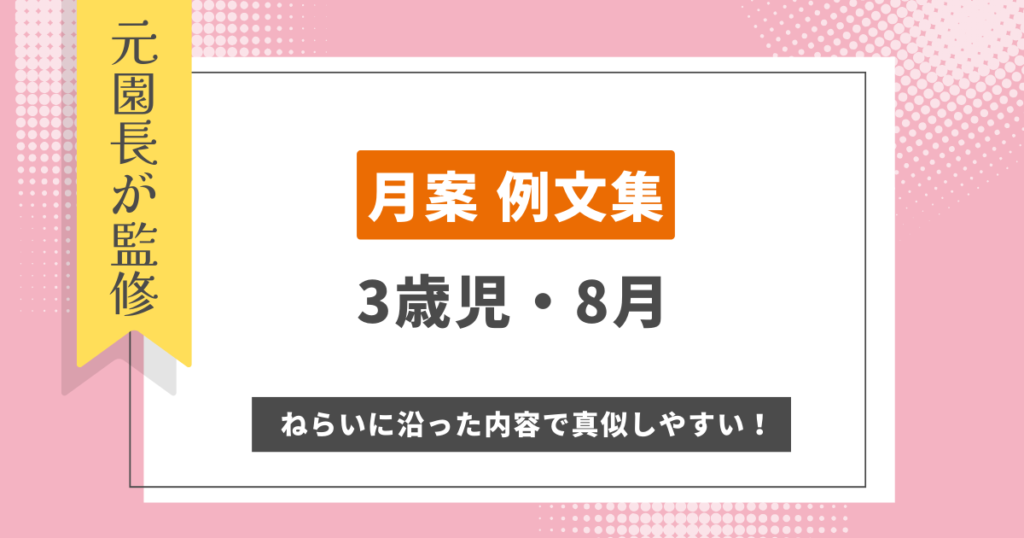
元園長監修【3歳児・8月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


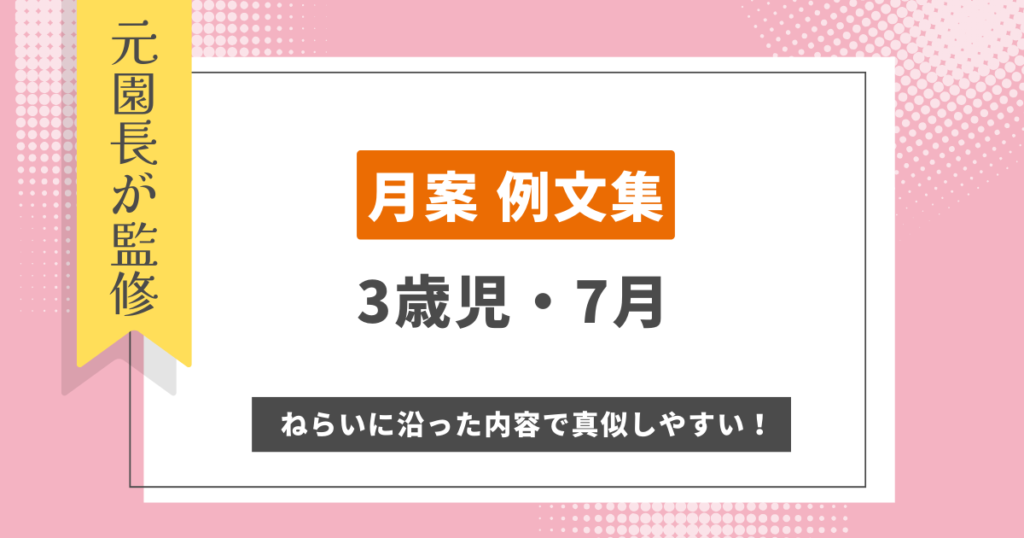
元園長監修【3歳・7月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-



元園長監修【3歳児・6月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


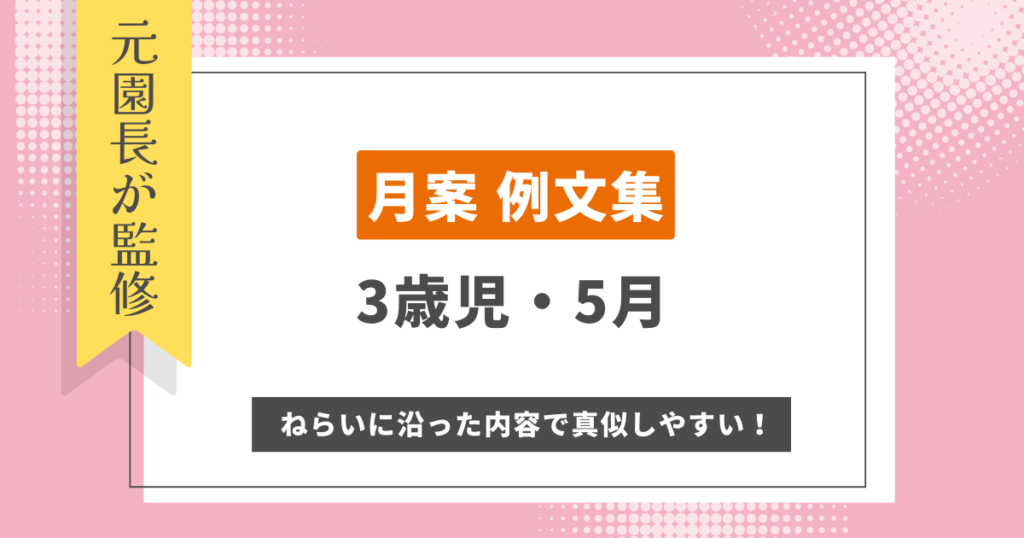
元園長監修【3歳児・5月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


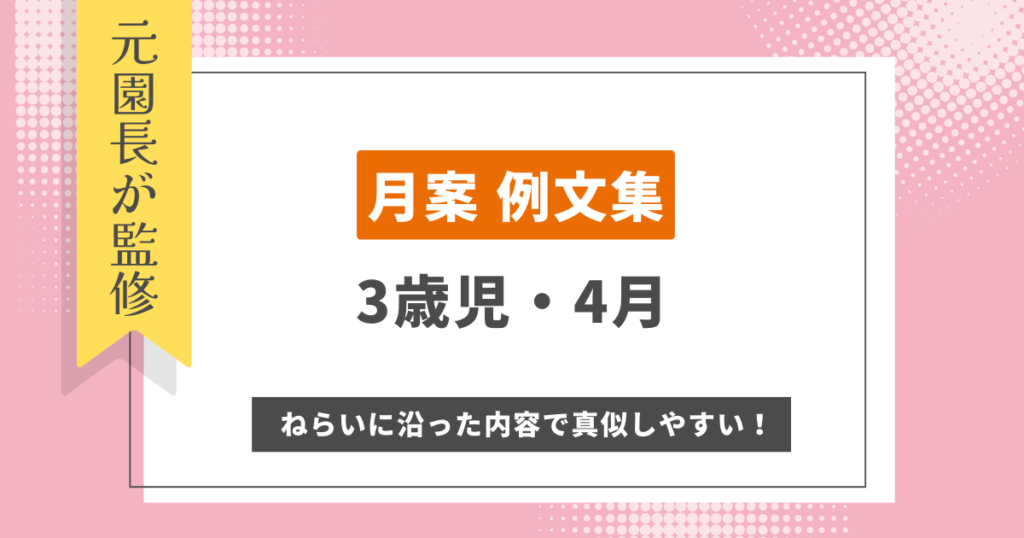
元園長監修【3歳児・4月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


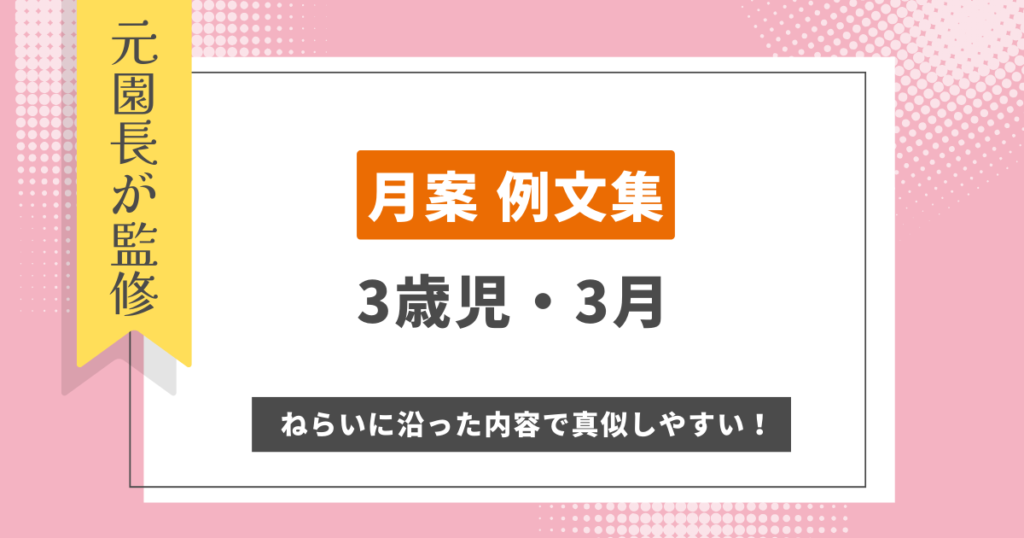
元園長監修【3歳児・3月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-



元園長監修【3歳児・2月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


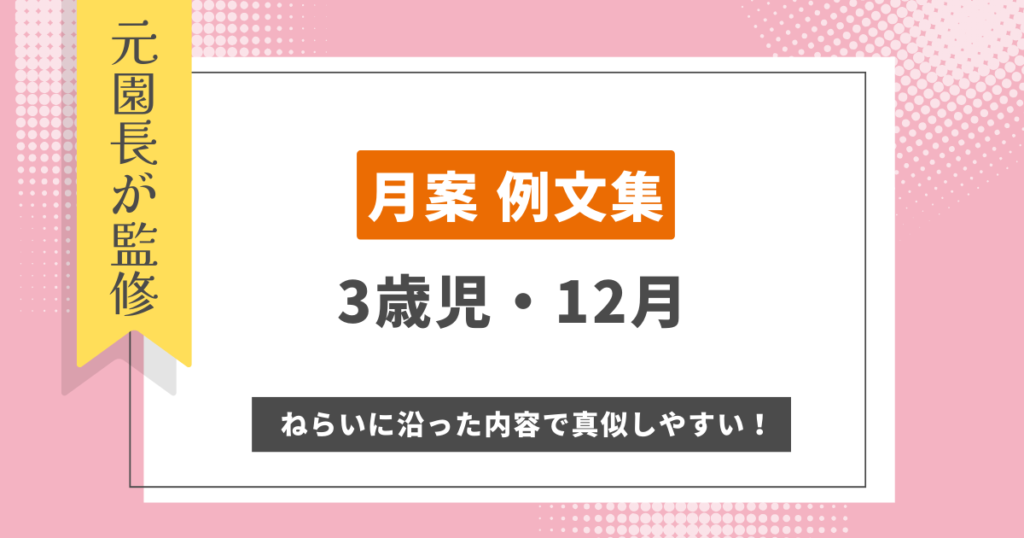
元園長監修【3歳児・12月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


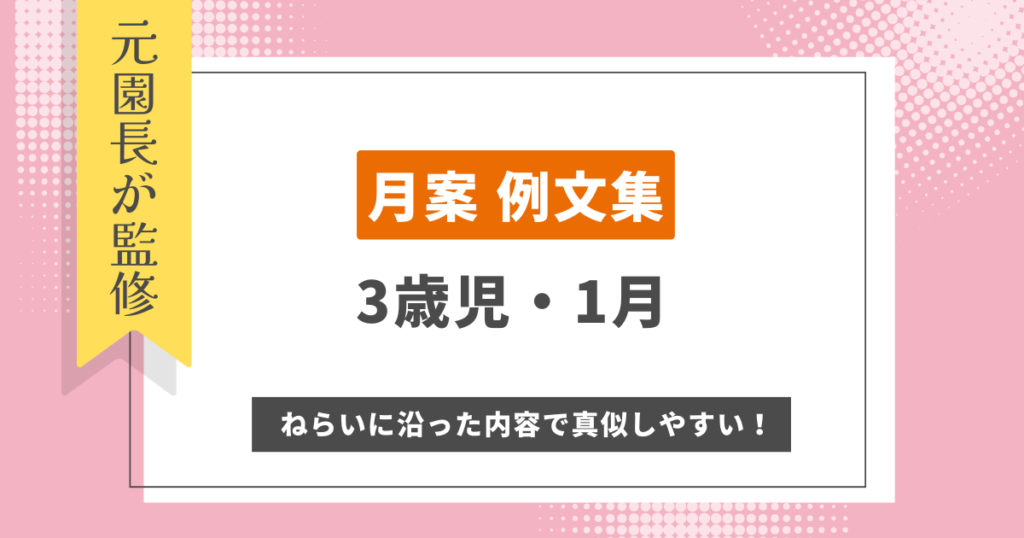
元園長監修【4歳児・12月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


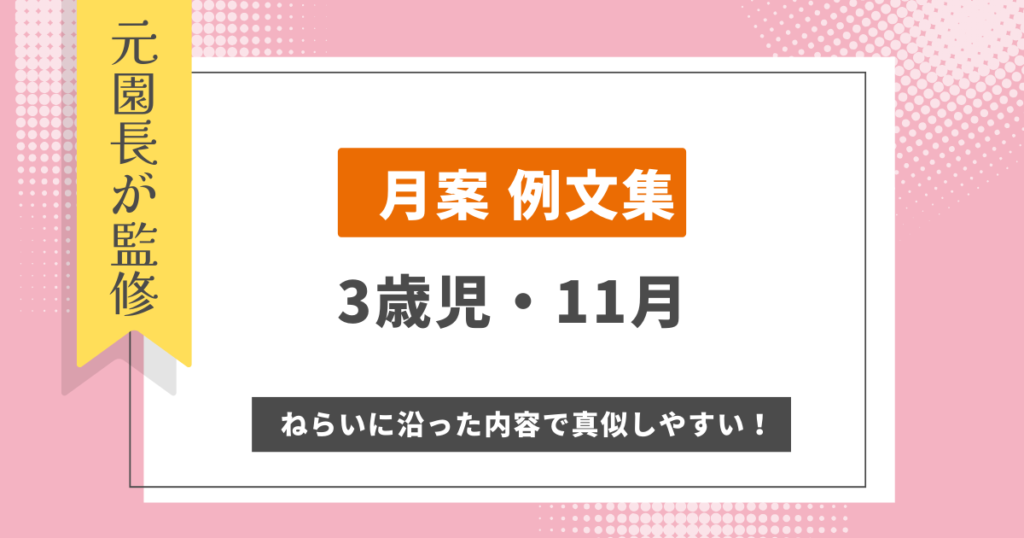
元園長監修【3歳児・11月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)
-


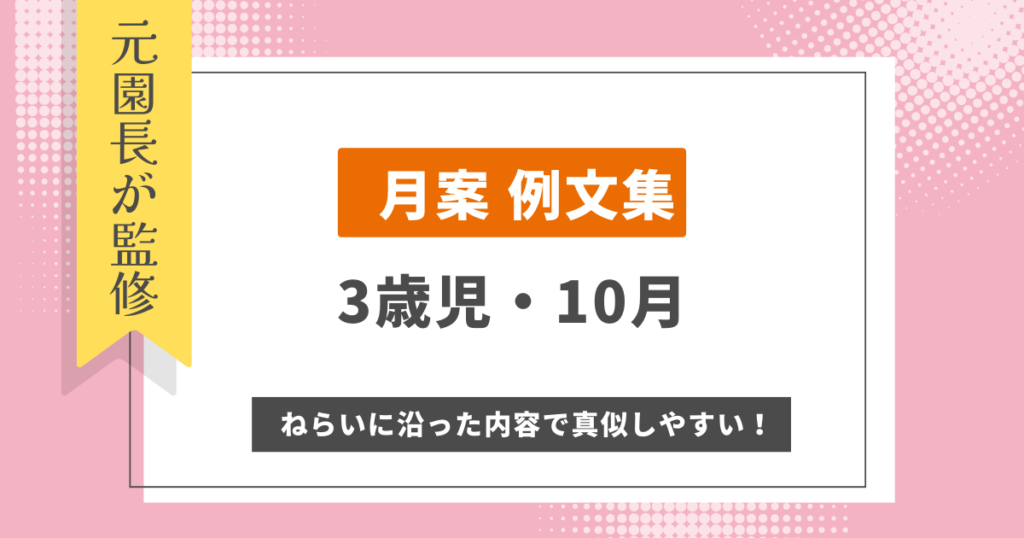
元園長監修【3歳児・10月】月案/週案の文例(ねらい・子どもの姿・養護・教育・ふりかえりの書き方)