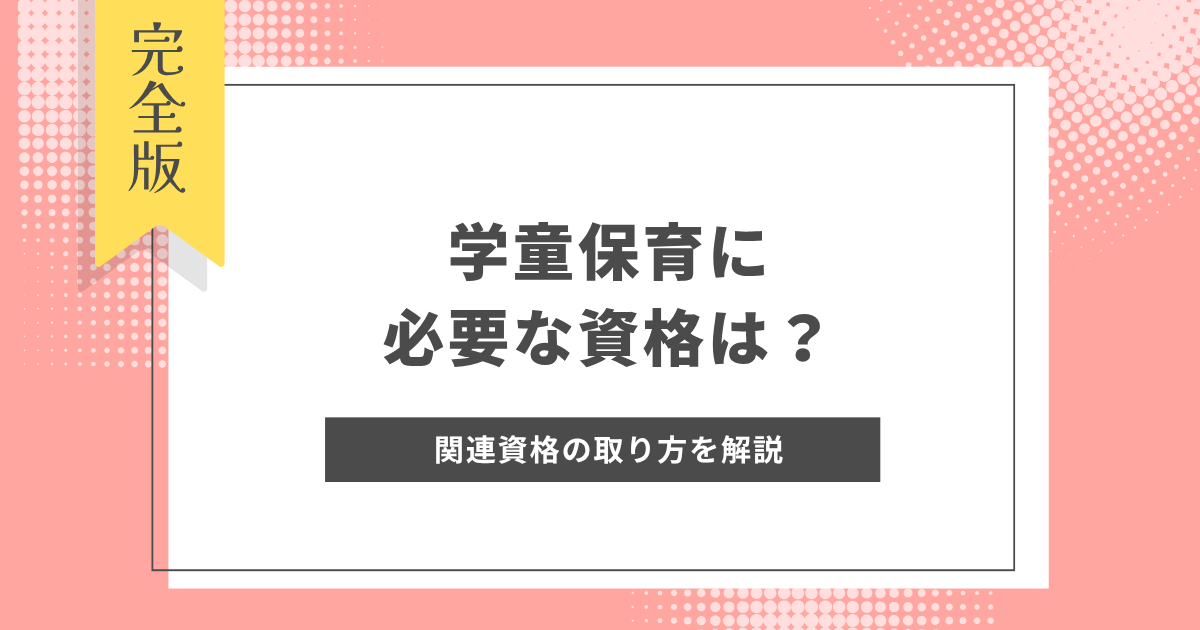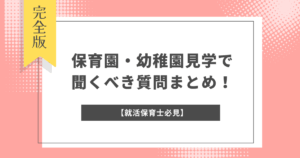学童保育は、放課後や長期休暇期間中に児童を預かり、遊びや生活の場を提供している施設です。
本記事では、学童保育に必要な資格や学童指導員・放課後児童支援員との違いなどを詳しくご紹介します。
「学童保育で働いてみたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 学童保育は、小学生が放課後や長期休みに安全に過ごせるよう支援する場
- 学童保育で働く際必須の資格はないものの、「放課後児童支援員」など取得していると有利な資格がある
- 放課後児童支援員になるためには、放課後児童支援員認定資格研修を受講する
- 学童指導員と放課後児童支援員の主な違いは、名称や法的な位置付け
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライター学童保育は、子どもたちの笑顔や成長に触れられる温かいお仕事です。大変なこともありますが、その分やりがいもたくさん。資格がなくても始められるので、「子どもと関わる仕事をしてみたい」という気持ちを大切に、ぜひ一歩を踏み出してみてくださいね。


ゆぴ先生 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
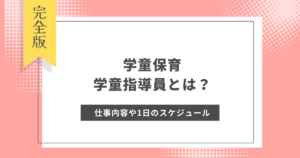
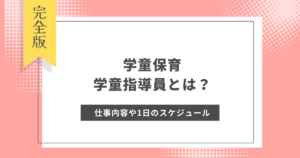
学童保育とは?
学童保育とは、小学生が放課後や長期休みに安全に過ごせるよう支援する場です。
共働きやひとり親家庭の増加により、利用する家庭も年々増えています。主な特徴は以下の通りです。
- 対象:主に小学1〜6年生(低学年中心)
- 目的:子どもの安全確保と成長の支援
- 内容:宿題の見守り、遊び、生活習慣づくりなど
- 運営主体:自治体・社会福祉法人・NPOなど
家庭と学校をつなぐ「第三の居場所」として、子どもたちの放課後を支える大切な役割を担っています。
学童保育で働くために必要な資格はある?
学童保育で働くための必須資格はありませんが、以下の資格を取得していると勤務先や自治体によって採用や待遇面で優遇されやすくなります。
- 保育士
- 教員免許(幼・小・中・高)
- 社会福祉士
- 放課後児童支援員認定資格 など
資格がなくても補助員として働くことは可能ですが、子どもと関わる専門知識を身につけたい人には資格取得がおすすめです。
また、実務経験を積みながら研修を受けて資格を取るケースも多く、キャリアアップを目指しやすいでしょう。
学童指導員とは?
「学童指導員って何をする人なの?」「必要な資格やスキルはある?」など、学童指導員について疑問をお持ちの方もいるでしょう。
必須資格はないものの、放課後児童支援員の資格を取得しているなど、子どもの理解を深めている方にぴったりの職種です。
ここでは、学童指導員の仕事内容や必要なスキルなどを解説するので、事前に学んでおきましょう。


学童指導員の仕事内容
学童指導員の主な仕事内容は、放課後や長期休みに子どもたちが安心して過ごせるよう見守り、生活面や遊びをサポートすることです。
家庭と学校の中間的な存在として、子どもの成長を支える重要な役割を担っています。
主な仕事内容は以下の通りです。
- 宿題や学習の見守り
- 外遊びや室内遊びのサポート
- けがやトラブル時の対応
- 行事やイベントの企画・運営
- 保護者との連絡・相談対応
日々の関わりを通して、子どもたちの自立心や協調性を育むやりがいの大きい仕事です。
学童指導員に必要な資格やスキル
学童指導員として働くために特別な資格は必須ではありません。
しかし、「放課後児童支援員」の資格を取得しておくと子どもの理解が深まり、採用時にも有利になることがあります。
より安心して働くためにも、以下のスキルを意識すると良いでしょう。
- 観察力:子どもの小さな変化に気づく力
- コミュニケーション力:子ども・保護者・職員との関係づくり
- 協調性:チームで連携しながら支援する姿勢
資格とスキルを身につけることで、より充実した支援ができるようになります。
放課後児童支援員の資格とは?
「放課後児童支援員の資格を取得したいけれど、どうすればよい?」「保育の知識を持っていない人でも取得できる?」このような疑問をお持ちの人もいると思います。
資格取得に向けた研修を受けるためには、「保育士資格を持っている」など一定の条件を満たす必要があるので、事前に理解を深めておきましょう。
研修を受講する対象となる人
放課後児童支援員の研修を受けるには、一定の資格や経験など、受講条件を満たす必要があります。
子どもへの支援に必要な知識を身につけ、安全で安心できる放課後の環境をつくる人材を育成するために設けられています。
- 保育士・教員免許・社会福祉士などの有資格者
- 大学や専門学校で教育・福祉・心理・社会学などを専攻して卒業した人
- 児童福祉施設などで2年以上の実務経験がある人
これらの条件を満たしていれば、自治体が実施する「放課後児童支援員認定資格研修」を受講し、修了することで資格を取得できます。
学歴や経験に応じて対象が幅広いため、子どもと関わる仕事をしてきた人にとってステップアップしやすい資格です。
放課後児童支援員の資格を取る流れ
放課後児童支援員の資格は、都道府県や政令指定都市が実施する研修を受けて取得します。
試験はなく、研修を修了すれば資格が認定される仕組みです。
取得までの流れは次の通りです。
- 受講資格の確認(学歴・資格・実務経験など)
- 自治体の研修募集に申し込む
- 研修の受講(講義・演習・実習など)
- 全課程修了で資格認定
研修では、子どもの発達理解や安全管理、保護者対応など、現場で必要な知識とスキルを学びます。
放課後児童支援員認定資格研修の内容
放課後児童支援員認定資格研修の内容は全国で共通しており、主に次の6分野で構成されています。
- 放課後児童クラブの意義と役割…学童保育の目的や社会的な役割を理解する
- 子どもの発達と理解…年齢ごとの発達特性や支援のポイントを学ぶ
- 遊びの意義と環境づくり…遊びを通した成長支援や安全な環境づくりを考える
- 家庭・地域との連携…保護者や地域と協力しながら支援する方法を学ぶ
- 安全管理と危機対応…けがや災害時の対応、日常の安全確保を学ぶ
- 放課後児童支援員としての専門性…支援員としての姿勢や倫理観を身につける
実践的な内容が多く、学んだことをすぐ現場で生かせる研修です。
放課後児童支援員の仕事内容
放課後児童支援員は、小学生が安全で安心できる放課後の時間を過ごせるようサポートする専門職です。
宿題や学習の見守り、遊びや生活習慣の支援、保護者との連絡対応など、多岐にわたる役割を担います。
子ども一人ひとりの成長を見守り、健やかな発達を支えるやりがいのある仕事です。
子どもに対する支援
放課後児童支援員の中心的な役割は、子ども一人ひとりに合わせた支援です。
学習や遊びを通して成長をサポートし、安全で安心できる環境を整えます。
- 宿題や学習の見守り
- 外遊び・室内遊びのサポート
- 生活習慣(食事・片付け・整理整頓)の指導
- けがやトラブルへの迅速な対応
日々の関わりを通して、子どもの自立心や協調性を育む重要な役割です。
また、子どもたちの個性や興味を理解し、自己表現や社会性を伸ばすサポートも行います。
保護者に対する支援
保護者との連絡や相談対応も、放課後児童支援員の大切な業務です。
家庭と学童保育を繋ぐことで、子どもを取り巻く環境をより良くします。
- 子どもの生活や成長に関する連絡・報告
- 保護者からの相談や要望への対応
- 行事や活動への参加依頼・説明
保護者との信頼関係を築くことで、安心して子どもを預けられる環境作りに貢献します。
さらに、家庭での様子や困りごとを把握すれば、子どもへの支援の質を高めることにも繋がるでしょう。
支援体制・運営への関わり
学童保育の運営やチームでの連携も、支援員の重要な役割です。
施設全体の安全や円滑な運営に関わることで、より質の高い支援が可能になります。
- 活動計画や行事の企画・運営
- 他スタッフとの情報共有・連携
- 安全管理や環境整備
- 書類作成や報告業務
運営面にも関わることで、子どもたちが過ごしやすい学童環境の維持・向上に繋がるでしょう。
加えて、チーム全体での改善提案や研修参加などを通じて、組織としての成長にも貢献します。
学童指導員と放課後児童支援員の違い
学童指導員と放課後児童支援員は、仕事内容はほとんど変わりないものの名称や法的な位置付けが異なります。
| 学童指導員 | 放課後児童支援員 | |
|---|---|---|
| 資格 | 特に必須ではない(資格なしでも勤務可能) | 都道府県指定の「放課後児童支援員認定資格研修」修了が望ましい |
| 採用条件 | 学歴・経験不問のことも多いが、子どもと関わる経験があると有利 | 資格取得者や子ども・福祉分野の学歴・実務経験者が優遇される |
| 主な仕事内容 | 子どもの見守り、遊びや学習の補助、生活習慣のサポート、保護者対応 | 学童指導員とほぼ同様だが、資格に基づく専門知識を活かした支援や安全管理、指導計画の立案なども担当 |
| キャリアパス | 補助員 → 指導員 → 班長・主任など(施設内での昇進) | 支援員資格を活かして、主任・管理者、研修講師、複数施設の統括など幅広くキャリア形成可能 |
学童指導員は職種全体、放課後児童支援員はその中で資格を持つ専門職という位置付けです。
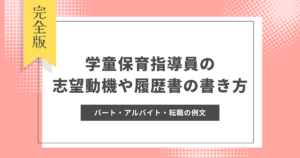
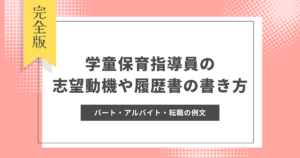
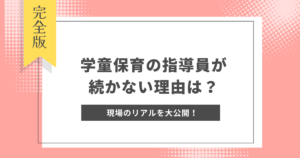
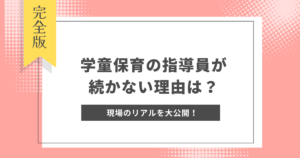
放課後児童支援員の働き方
「放課後児童支援員の勤務は何時から?」「副業も可能?」など、働き方について気になることが多いと思います。
放課後児童支援員は、勤務時間や業務内容は施設や自治体の規定に沿って決まりますが、場合によっては副業ができたりとある程度の自由度があります。
ここでは、勤務先の種類や1日のスケジュールを簡単に解説します。
勤務先の種類
放課後児童支援員の勤務先は、主に小学生が放課後や長期休みに過ごす学童保育施設です。
自治体や民間団体など、運営主体によって特徴が異なります。
- 市区町村運営の放課後児童クラブ:公的施設で、安定した勤務条件が多い
- NPOや社会福祉法人運営の学童保育:地域に根ざした活動や特色あるプログラムが魅力
- 民間企業運営の学童保育:柔軟な運営や独自プログラムがあることも
- 学校併設型の放課後教室:学校施設内での勤務で通いやすく、学校と連携しやすい
運営主体により勤務条件やカリキュラムは異なりますが、どの施設でも子どもたちの安心・安全を支える役割は共通しています。
放課後児童支援員の1日のスケジュール
放課後児童支援員の1日のスケジュール例を表にまとめました。
施設や学年、季節によって変動はありますが、以下のような流れが一般的です。
| 時間帯 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 13:30〜14:30 | 子どもたちの到着・出迎え、持ち物チェック、自由遊びの見守り |
| 14:30〜15:30 | 宿題や学習のサポート、個別の学習支援 |
| 15:30〜16:30 | 外遊びや室内遊びのサポート、運動・創作活動の補助 |
| 16:30〜17:30 | おやつの準備・配布、生活習慣の指導(片付けや整理整頓) |
| 17:30〜18:30 | 保護者への引き渡し、連絡帳や報告書の記入 |
| 18:30〜19:00 | 日報作成、施設内の整理整頓、安全点検、翌日の準備 |
このように、放課後児童支援員の1日は子どもたちの安全と成長を見守りながら、学習・遊び・生活習慣のサポートや保護者対応、施設運営まで幅広く関わる内容となります。
放課後児童支援員の給料・待遇
放課後児童支援員の給料や待遇は以下の通りです。
- 月給:およそ18万~25万円
- 時給:パート勤務の場合は1,000~1,300円前後
- 賞与:勤務先によって支給される場合もあり
- 福利厚生:社会保険、交通費支給、研修制度など
放課後児童支援員の給与は、勤務形態や地域、経験年数によって差があります。
正職員として働く場合は安定した収入が得られますが、パート勤務では勤務時間に応じて支給されるのが一般的です。
待遇面では、子どもと関わるやりがいを感じながら長く働けるよう、研修制度や福利厚生を充実させている施設も増えています。
放課後児童支援員・学童保育の将来性
学童保育で働く放課後児童支援員は、次のように将来性の高い職種です。
- 共働き家庭の増加により、需要は年々拡大
- 国や自治体も支援体制の強化を進めている
- 専門性を持つ人材へのニーズが高まっている
- 資格取得でキャリアアップや転職にも有利
放課後児童支援員や学童保育の仕事は、共働き世帯の増加や子育て支援の拡充を背景に、今後も安定した需要が見込まれます。
特に、子どもの発達支援や安全管理に関する専門知識を持つ人材は重宝される傾向にあるでしょう。
資格や経験を積むことで、将来的には指導員のリーダーや施設運営を担う立場へのステップアップも期待できますよ。
学童保育で働くメリット
学童保育で働くと、以下のように様々なメリットがあります。
- 子どもの成長を間近で見守れるやりがいがある
- 資格や経験を活かして長く働ける
- 勤務時間が比較的安定しており、家庭との両立もしやすい
- 保育士・教員など他職種へのステップアップにもつながる
学童保育で働く最大の魅力は、子どもたちの成長を日々感じながら関われることです。
放課後の限られた時間を通じて、学習支援や遊びを通した成長をサポートできるやりがいがあります。
また、土日休みの施設も多く、家庭やプライベートとの両立がしやすい点も魅力。
経験を積めば、放課後児童支援員や保育関連のキャリアにも繋げられますよ。
【先輩保育士の実体験】現場で感じた学童保育で働くやりがい
実際に学童保育の現場で働いている保育士の声をお届けします。
接する相手が幼児と小学生とではやりがいや悩みが異なるようです。
保育園での経験を経て、より一人ひとりの個性と深く関わりたいと思い学童保育へ。最初は心を開かなかった子が、一緒に遊ぶうちに悩みを打ち明けてくれた時や、保護者の方から「安心して働けます」と感謝の言葉をいただいた時に、大きなやりがいを感じます。一方で、学童期ならではの複雑な友人関係のトラブルには、どこまで介入すべきか日々頭を悩ませています。子どもたちの成長を間近で支えられる、貴重な仕事だと感じています。
(タカさん/男性/37歳/保育士歴15年/学童勤務歴5年/正社員)



友人との人間関係が重要になってくる学童期は、トラブルの介入など難しいことも多い反面、子どもの成長を見届けられる貴重な時期のためやりがいを感じられますね。
福祉保育職として入社し、グループ会社がやってる学童、保育園、療育機関、放デイを兼務しています。
幼児さんとは違い、パワーも有り余る小学生相手なので、こちらもしっかり相手をするには体力勝負です。ただの、放課後の時間を潰すお預かりにならないように、活動内容に幅を持たせ、充実した時間を過ごせるように考えています。たまーに、外出企画をすると、とても大変ですが子どもたちが喜んでくれるのでやりがいも感じます。
(とんすさん/女性/38歳/保育士歴16年/学童勤務歴4年/正社員)



幼児より体の大きい小学生相手の仕事は体力を使います。保育者自身も子どもに負けないパワーが必要です。
保育士で働いた経験の方が長いので、学童の子供たちと話をするときについつい小さい子への話し方で話をしてしまう。言葉が幼いと『赤ちゃんへの話し方みたい〜』と言われ、小学生は小学生なりにプライドがありそのように話しかけられたら嫌なんだな、と感じた。以降話し方を気をつけるようにしているが、まだついつい出てしまうことがある。
(まるさん/女性/36歳/保育士歴13年/学童勤務歴1年/パート・アルバイト)



保育園での勤務が長いと、幼児相手の言葉遣いや関わり方の癖が抜けないのもよくある悩みの一つです。経験を積んでいくうちに次第と話し方も順応していきます。
まとめ
学童保育の仕事は、子どもたちの成長を支えるやりがいの大きい仕事です。
学童指導員として働くために必ずしも資格は必要ありませんが、放課後児童支援員の資格を取得すれば、より深い理解と専門性を持って子どもたちに関われます。
資格取得によってキャリアの幅も広がるため、長く安定して働きたい人や、子どもと関わる仕事を続けたい人はぜひ目指してみてくださいね。