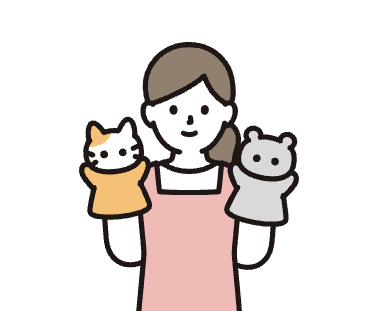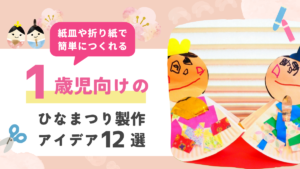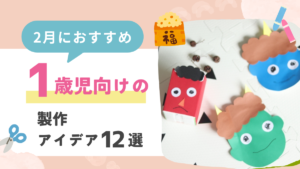運動会やクリスマス会が終わると、次にお正月の製作を考えている保育士さんは多いと思います。
来年2026年の干支は午で、この記事ではお正月にぴったりな製作のアイデアを10選ご紹介しますね。
年内の保育が終了する前に、保育室をお正月の雰囲気たっぷりにしておけば、新年を明るく迎えられるでしょう。
「うま」に関する製作をはじめ、様々なお正月の製作を記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
※誤飲防止・工具管理・素材確認を徹底し、保育者の見守りで安全に製作しましょう。
この記事でわかること
- 2026年の干支(午)をテーマにした製作アイデア
- 午(うま)以外のお正月製作アイデア
- 保育活動で干支・十二支を取り入れるねらい
あわせて読みたい
【正月にぴったり】おすすめの製作10選をご紹介!元保育士が製作のポイントまで詳しく解説
年末年始に向けて、お正月の製作遊びを取り入れたいと考えている保育士さんは多いのではないでしょうか。 お正月の製作は、日本の伝統行事に触れられる貴重な経験になり…
この記事を書いた人
すもも先生 元保育士ライター
8年間保育士として勤務し、主に乳児クラスの担任を務めて参りました。認可保育施設や認可外保育施設での職務経験を活かして、保育士さんに役立つ記事を執筆させていただきます。
目次
保育活動で十二支を取り入れるねらい
まずは、保育の中で十二支を取り入れるねらいについて解説します。
保育活動で十二支を取り入れるねらい
- 日本の伝統行事に親しむ
- 動物への関心を深め、干支の意味を理解する
- 製作を通して、子どもの興味関心を引き出す
上記のねらいはごく一部ですが、保育活動で干支を取り入れると、子どもたちの興味や関心を引き出すことができます。
また、お正月は日本の伝統文化であるため、自分の国の文化に親しむきっかけにもなりますよ。
幼児であれば、干支に関する絵本や絵カードなどを使って、十二支について教えると分かりやすいです。
乳児は理解が難しいため、来年の干支の動物に関する絵本を読むなど、その動物に興味が持てるようにするだけでも良いですね。
製作以外で干支を保育活動に取り入れるなら?
製作以外で干支を保育活動に取り入れるなら、先ほども記載したように、絵本を使うのも1つの方法です。
その他には以下のような内容がありますので、担当の年齢の子どもたちに合った物を取り入れてみて下さいね。
保育園で楽しめる干支(うま・午・馬)の製作アイデア2選!
保育園で楽しめる干支の製作アイデアを2選ご紹介します。
2026年は午年ですので、馬に関連する製作を記載していきますね。
馬・午の折り紙