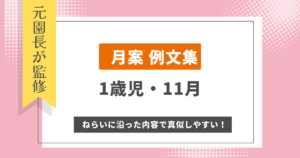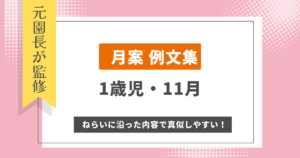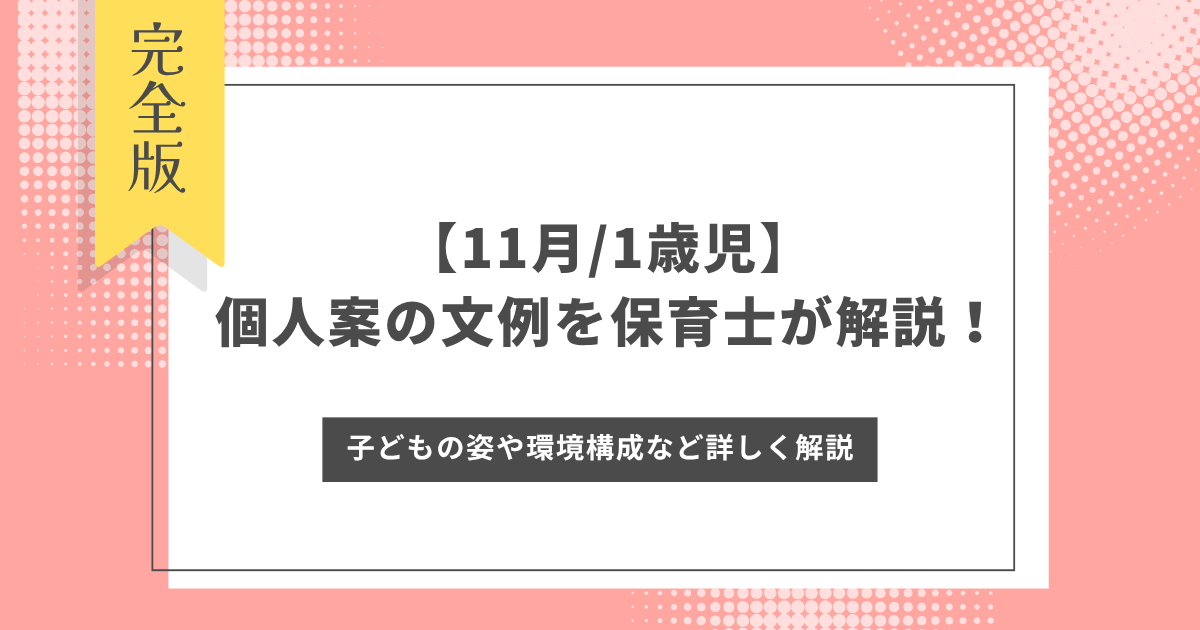11月の1歳児は、歩行が安定して活動の幅が広がる一方で、言葉や自己主張も少しずつ芽生えてくる時期です。
秋の自然に触れながら、五感を使った遊びや生活習慣の自立を促す援助が大切になります。
本記事では、1歳児の発達に合わせた11月の個人案のポイントやねらいを解説し、日々の保育に役立つヒントをお届けします。
- 1歳児は発達の差が大きいため、一人ひとりの成長段階に合わせた援助が大切
- 11月は秋の自然や行事を取り入れながら、探索活動や感覚遊びを楽しめる環境を整えることが重要
- 食事や生活習慣では「自分でやりたい気持ち」を尊重し、挑戦できる機会を支えていく
- 個人案は固定的ではなく、日々の様子に応じて柔軟に調整し、安心して過ごせる環境を整えるのがポイント
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライター1歳児は発達の差が大きく、一人ひとりのペースに合わせた援助が大切です。安全・安心な環境を整え、探索や生活習慣の挑戦を支えながら、声かけや共感で意欲を引き出すことで、主体性や自信の育ちに繋げていきましょう。


ゆぴ先生 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
【1歳児】11月の個人案の作成ポイント
1歳児の11月は、秋の自然に触れながら心身ともに大きく成長する時期です。
個人案を立てる際は、以下の点を意識しましょう。
- 歩行や探索行動を十分に楽しめる環境を整える
- 自己主張や言葉の芽生えを受け止め、共感的に関わる
- 衣服の着脱や手洗いなど生活習慣の自立を少しずつ支える
これらを踏まえ、一人ひとりの成長段階に寄り添った援助を計画し、安心して過ごせる日々を目指しましょう。
【1歳児・11月の個人案】子どもの姿
1歳0ヶ月〜1歳6ヶ月
- 歩行が始まり、つかまり立ちや伝い歩きから自分の足で移動する喜びを感じている。好奇心が旺盛になり、目に入る物へ手を伸ばしたり、指先を使った遊びに興味を示したりする姿が見られる。また、喃語や簡単な単語を発し、保育者の声かけに応じて笑顔を見せるなど、やりとりの基礎が育ちつつある。生活面では食事や睡眠のリズムが整い、安心できる環境の中で成長を重ねている。



この時期は「歩く・話す」の土台作りの段階です。発達の個人差が大きいため、一人ひとりのペースを尊重しながら、探索活動を安心して行える環境を整えることが大切です。声かけや共感的な反応を通して信頼関係を深めましょう。
1歳7ヶ月〜2歳
- 歩行が安定し、走ったり段差を登ったりと体の使い方が活発になっている。「自分で!」という気持ちが強まり、食具を使った食事や衣服の着脱などに挑戦する姿が見られる。言葉も増え、簡単な二語文を使って気持ちを伝えるようになるが、思いがうまく言葉にできず泣いたり怒ったりすることも多い。保育者が気持ちを代弁しながら受け止めることで安心し、その中で自己表現が豊かになっていく。



自我の芽生えと同時に「イヤイヤ期」が始まりやすい時期です。否定ではなく気持ちに共感し、「自分でやりたかったんだよね」「貸してって言ってみようね」と言葉にして伝えることが大切です。また、挑戦する気持ちを支えつつ成功体験を積むことで、自信や主体性の育ちにつながります。
1歳児共通の子どもの姿 文例
- 心身の発達が著しく、歩行や言葉の習得、生活習慣の自立など成長のステップが次々と見られる。公園遊びや散歩で「どんぐり」「落ち葉」といった秋の自然に触れながら、探索活動を通して感覚や運動機能を発達させていく。自分の気持ちを泣き声や簡単な言葉で表現し始め、保育者に受け止めてもらうことで安心感を得ている。一人ひとりの発達段階に応じた丁寧な援助が信頼関係を深め、主体的に生活を楽しむ基盤となっている。



1歳児は発達のスピードや個人差が大きいため「その子らしさ」を理解することが重要です。安心できる環境と丁寧な関わりが、心と体の成長につながります。生活リズムを整えながら、自己表現を受け止める姿勢を持ちましょう。
【1歳児・11月の個人案】ねらい
1歳0ヶ月〜1歳6ヶ月
- つかまり立ちや伝い歩きを通して歩行の基礎を培う
- 指先を使った操作遊びを楽しみ、感覚の発達を促す
- 喃語や単語を通して保育者とのやりとりを楽しむ
- 安心できる環境の中で生活リズムを整える



探索意欲が芽生える時期のため、安全に動ける環境を整えることが大切です。声かけや微笑みを通して関わることで、やりとりの楽しさを感じ、安心感を得ることにつながります。生活のリズムを支えることが成長の基盤になります。
1歳7ヶ月〜2歳
- 安定した歩行を基盤に、走る・登るなど全身運動を楽しむ
- 「自分でやりたい」という気持ちを尊重し、挑戦を支える
- 言葉や仕草を通して気持ちを表現できるようになる
- 食事や衣服の着脱など生活習慣の自立を経験する



自我の芽生えにより「イヤイヤ」や感情の揺れが見られる時期です。否定するのではなく共感し、代弁することで安心感を得やすくなります。挑戦を見守り、小さな成功体験を積むことで、自信や主体性の育ちに繋がります。
1歳児共通の子どもの姿 文例
- 探索活動を通して感覚や運動機能を育む
- 自分の気持ちを泣き声や言葉で表現できるようになる
- 保育者に受け止められる中で安心感と信頼関係を深める
- 日常生活の流れを理解し、リズムを身につける



1歳児は発達の差が大きいため、個々の歩みを理解して関わることが重要です。遊びや生活の中で安心感を得ながら、自己表現や自立の芽生えを支えることで、心身の健やかな成長と意欲的な生活に繋がります。
【1歳児・11月の個人案】環境構成と保育者の配慮
1歳0ヶ月〜1歳6ヶ月
- つかまり立ちや伝い歩きが安全にできるよう、手すりや低い家具を配置する
- 柔らかいマットや広いスペースを確保し、転倒時の安全を守る
- 手に持ちやすい玩具や布絵本など、指先を使える素材を用意する
- 喃語や発語を受け止めるため、笑顔や視線を合わせて応答する
- 安心できる生活リズムを整え、落ち着いて過ごせる環境をつくる



動きが活発になり始める時期のため、安心して探索できる環境づくりが大切です。危険を予測して安全に配慮しながら、指先遊びややりとりを通して発達を支えます。生活リズムを整え、安心できる時間を重ねることが基盤になります。
1歳7ヶ月〜2歳
- 走る・登るなどの動きを発揮できるよう、広い空間や段差を活かした環境を整える
- 「自分でやりたい」気持ちに応えられるよう、衣服や食具を自分で扱いやすく配置する
- 気持ちを表す言葉や仕草を受け止め、代弁しながら共感的に関わる
- 感情が高ぶった時には、安心できる場所で落ち着けるようにする
- 達成感を味わえる遊びや活動を取り入れ、自信を育てる



自我が強く出る時期のため「やりたい気持ち」を尊重することが大切です。挑戦できる環境を整えつつ、失敗しても受け止めて安心できるように関わります。共感と代弁を通して気持ちを支え、自信につなげる援助が必要です。
1歳児共通の子どもの姿 文例
- 年齢や発達に応じて安全に遊べるスペースを確保する
- 季節の自然物や素材を取り入れ、探索意欲を引き出す
- 自分の気持ちを泣き声や言葉で表した際に、保育者が丁寧に受け止める
- 個々の生活リズムを大切にし、無理のない活動を保障する
- 信頼関係を基盤に、安心して過ごせる雰囲気をつくる



1歳児は発達に個人差が大きいため、一人ひとりの状態に合わせた環境づくりが重要です。安心できる雰囲気の中で探索や自己表現を支えることで、主体性や意欲が伸びていきます。無理のない生活リズムの保障が欠かせません。
【1歳児・11月の個人案】食育
1歳0ヶ月〜1歳6ヶ月
- 離乳食から幼児食へと移行する段階であり、さまざまな食材の味や舌ざわりを経験する時期である。保育者が食べる姿を見せることで模倣し、食べる意欲を高めていく。手づかみ食べを繰り返すことで、指先の発達や自分で食べる喜びを感じている。食事の場は安心できる雰囲気であり、保育者の声かけや笑顔によって「食べることは楽しい」という感覚を育めるようにする。



この時期は手づかみ食べが中心であり、こぼれても受け止める姿勢が大切です。保育者が一緒に食べる姿を見せ、安心できる雰囲気をつくることで意欲が育ちます。多様な食材を経験できるよう工夫し、食べる楽しさを伝えましょう。
1歳7ヶ月〜2歳
- 食具を使って自分で食べようとする姿が見られる時期である。スプーンやフォークを持つが、まだ上手に使えずこぼすことも多い。食事中に「自分で!」という気持ちが強まり、達成感を得ることで自信へと繋がっていく。簡単な食材の名前を覚えたり、給食に出た野菜を指差したりして、食への興味が広がる。保育者の励ましや共感を通して食べる意欲をさらに高めていく。



「自分で食べたい」という気持ちを尊重し、多少の失敗は見守ることが大切です。食具を持ちやすい環境を整え、達成感を得られるようにします。「りんごだね」「これは梨だよ」と食材の名前を伝えたり共感の声かけをしたりすることで、食への関心を深められます。
1歳児共通の子どもの姿 文例
- 1歳児は食べることを通して、生活リズムの安定や心身の成長を培っている時期である。さつまいもやりんごなど秋の食材に触れることで、旬の味を楽しみながら食への関心を高めていく。自分で食べる経験を重ね、少しずつ食具の扱いにも挑戦していく。保育者が一緒に食事を楽しむ姿を見せることで、安心感と意欲が育ち「食べることは楽しい」という感覚が持てるように工夫する。



1歳児にとって、食事は心身の発達を支える大切な営みです。食具を使う挑戦や旬の食材に触れる体験を取り入れましょう。保育者が一緒に楽しむ姿を見せることで、安心して食べる意欲が高まり、健やかな食習慣に繋がります。
1歳児の個人案を作成する際の注意点
1歳児は発達の差が大きく、個々の成長段階に応じた援助が必要です。
作成の際は、以下の点に注意しましょう。
- 活動内容は安全性を第一に考え、無理のない範囲で設定する
- 一人ひとりの「やりたい気持ち」を尊重し、挑戦できる機会を取り入れる
- 生活リズムや体調の個性を考慮し、日常生活と遊びが両立できるようにする
- 発語や表情、行動などの小さな変化も観察し、援助の工夫に反映する
個人案は固定的な計画ではなく、日々の様子をもとに柔軟に調整することが大切です。
保育者は安全・安心を確保しながら、子どもが主体的に活動を楽しめるよう工夫するとよいでしょう。