リトミックを活動に取り入れる際、ねらいや活動内容に迷ったことはありませんか?
保育園では年齢や発達段階に応じたねらいを設定し、無理なく楽しく参加できる活動内容にすることが大切です。
本記事では、具体的なねらいや活動のポイント、注意すべき点などを解説しています。
- リトミックでは、聴覚や視覚といった感覚、自己表現や協調性といった学びの土台を育む
- リトミックを行うメリットは、遊び感覚で楽しみながらリズム感や運動能力の基礎を学べる
- リトミックは各年齢の発達段階を踏まえ、ねらいを明確にすることがポイント
 Takako【元保育士】
Takako【元保育士】リトミックでは「どのような力が育まれるの?」「具体的なねらいは?」「0歳もできるの?」など、気になることがたくさんありますよね。
リトミックは、運動能力や表現力を育み、社会性の基盤を作ってくれます。
ぜひ、最後まで読んで参考にしてください。


Takako先生 元保育士ライター
保育士歴7年、現在は男女2児の母をしています。保育現場で培った経験や知識を活かし、悩んだり困ったりしている保育士の方、保育士を目指している方の力になれるような記事を心がけています。
リトミックとは?


リトミックとは、音楽に合わせて自由に体を動かし、子どもの感覚や表現力を育む教育法です。
リズムに合わせて歩く・手をたたく・楽器をならす・体で表現するなど、遊び感覚で取り組めるのが特徴です。
- 聴覚
- 視覚
- 触覚
- 体幹
- リズム感
- 空間認知力
- 表現力
活動に参加せず聞くだけでも、聴覚やリズム感、集中力、想像力が育ちます。
そのため、乳児から幼児まで発達段階に応じて活動に取り入れることができます。
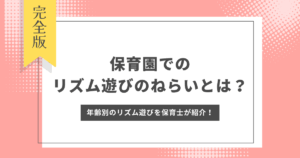
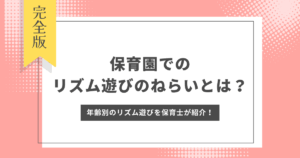
【年齢別】保育園でリトミックを行うねらい
リトミックは「音楽を感じ、体で表す」活動です。
年齢に合わせたねらいを持つことで、子どもたちは無理なく楽しみながら成長していきます。
音に触れて心が動き、体を動かす喜びを知る経験は、感性や表現力、友だちと関わる力などを育む大切な時間です。
0歳児クラスでリトミックを行うねらい
- 音楽やリズムに合わせて、身体を動かすことを楽しむ
- リズムや音楽の心地よい音、動きの中で、五感を刺激する
- 音楽の楽しさを体感し、表現活動の基礎を育む
0歳児で行うリトミックのポイントは、「安心感」「感覚刺激」です。
楽しいリズムに触れて五感を刺激しながら、心地よさや保育者とのふれあいで安心感を味わうことをねらいとします。
抱っこや膝の上で心地よい揺れや音楽を体感することで、保育者とのスキンシップが深まり、信頼関係の基盤を育むことが可能です。
子どもたちが安心した環境の中で、楽しめるような活動内容を取り入れましょう。
- リズムに合わせて、子どもたちの身体を優しく動かす
- 手を軽く叩き、リズムを一緒に感じながら楽しむ
- 鈴やタンバリンなど、簡単な楽器の音を聞かせる
- 鈴やタンバリンなど、子どもたちが握ったり叩いたりしやすい楽器を用意し、音を出すことを楽しむ
音楽の楽しいリズムに合わせて、子どもの手や足を軽く揺らしたり、両手を叩いたりしながら子どもたちと一緒に楽しみます。
まだ、自分で動けない子も抱っこや目線を合わせるなど、安心感を得ながら、音楽の心地よさを感じられるように工夫しましょう。
保育者も一緒に楽しむことで子どもたちは安心感が生まれ、音楽の心地よさを体験できます。
1歳児クラスでリトミックを行うねらい
- 音楽やリズムに乗って身体を動かす楽しさを感じる
- 手足を動かすことで、運動機能やバランス感覚を養う
- 音楽に合わせて保育者の動きをまねることで、模倣力や集中力を育む
1歳児で行うリトミックのポイントは「身体を使った楽しみ」「模倣」です。
この時期の子どもたちは、保育者や大人の模倣を繰り返すことで、学び・集中力・社会性・表現力の基礎が育まれます。
また、音楽に合わせて歩く、走る、しゃがむ、ジャンプするといった動きは、運動能力やバランス感覚を養います。
子どもがまねしやすい動きを取り入れることで、体を使った遊びを無理なく楽しめるように工夫することが大切です。
- 音楽に合わせて歩く・走る・止まる
- 音楽に合わせて保育者と一緒に動物の真似をする
- 太鼓やタンバリンなどの楽器に合わせて手を叩く
活動の際の曲は「さんぽ」や「はとぽっぽたいそう」「アンパンマンたいそう」など、シンプルで覚えやすく、リズムが一定の音楽がおすすめです。
これらの曲は、リズムが規則的で、フレーズが短く繰り返されるため、何度も模倣して楽しむことができます。
また、ピアノや鈴などの楽器の音や保育者の指示に合わせて動くことで、リズム感、想像力、表現力を育みます。
2歳児クラスでリトミックを行うねらい
- 集団での活動を楽しみ、協調性の基礎を育む
- 動作と言葉を結びつけ、自身の表現の幅を広げる
- 音や動きで表現することで、自己表現の芽生えを促す
2歳児のリトミックのポイントは、「自己表現」「協調性」です。
2歳児になると語彙が増え、言葉や身体を使って自分の気持ちを表す力が育ちます。
また、友達や保育者といった他者の存在を意識し、一緒に行動することを楽しめるようになるでしょう。
音楽やリズムに親しむリトミック活動を通して、子どもたちは自己表現の力を伸ばし、集団での関わりを楽しむ中で、協調性や心理的な安定感が育まれます。
- 手拍子や足踏みなど簡単な動きをそろえる
- ペアで動く、順番を守る遊びを取り入れる
- 動物になりきる、ジャンプやステップなど全身を使った遊びを行う
手拍子や足踏みなどの簡単な動作を取り入れることで、子どもたちは無理なく活動に参加できます。
保育者の掛け声やピアノの音に合わせて、動きを揃える遊びやペアになって行う遊びは、協調性の芽生えにつながる行動です。
また、多様な動きを取り入れることにより、自己表現する楽しさを感じることができます。
3歳児クラスでリトミックを行うねらい
- 簡単なルールを理解し、集団活動に参加することを楽しむ
- 音楽に合わせて動き、周囲と動きをそろえる楽しさを体験する
- 友だちの動きを見てまねたり、一緒に表現したりすることで協同性を深める
3歳児でリトミックを行う際のポイントは、「ルールの理解」「協同性」です。
協同性とは、子どもが友達や周囲の人と関わり合いながら、一緒に遊んだり活動したりする力のことをいいます。
3歳児になると、簡単なルールのある遊びを理解し、集団での活動を楽しむことができるようになります。
簡単なルールと共同性を育み、楽しみながらできる活動を取り入れましょう。
- 曲に合わせながら、全身で表現する
- 音が鳴ったら動く、止まったら静止など、簡単なルールのあるゲームをおこなう
- 音楽に合わせたボール回しや、リズムに合わせて動物になりきる遊びなど、相手の動作や合図を意識して動く
音楽に合わせてボールを回したり、リズムに合わせて動物の動きを模倣したりするなど、わかりやすいルールのもとで、周囲の動きを見ながら動きをそろえる・まねる活動は、子どもたちにとって楽しく取り組みやすい方法です。
このような活動を通して、子どもたちの協同性を育み、集団で活動する楽しさを体験できます。
4歳児5歳児クラスでリトミックを行うねらい
- 音楽の強弱や速さの変化に合わせて、体全体で多様な表現を楽しむ
- グループや全体での発表を通して、みんなと一緒に表現する達成感と自信を得る
- 曲の展開や変化を感じ、動きやリズムを工夫することで、創造力・判断力、自信を育む
4歳児5歳児で行うリトミックのポイントは「表現力の広がり」「社会性」「自信」です。
4歳児5歳児は音楽の強弱や速さに合わせて、全身で多様な表現を楽しめるようになります。
また、グループや全体での発表を通して、みんなと一緒に表現する達成感と自信を得られます。
曲の展開や変化を感じ、動きやリズムを工夫する中で、創造力や判断力、自信も育まれるでしょう。
- ピアノの音の高低や強弱を聞き、体全体で多様な表現を楽しむ
- リボンやスカーフを使い、音の流れに合わせて動かす
- 友だちと相談ながら動きを考え、協力して表現する
重音では「ドスンドスン」と力強く歩いたり、高音では小鳥のように軽やかに跳ねたりと、音楽に合わせた動きをすることで、表現力の幅が広がります。
また、リボンやスカーフを使い音の流れに合わせて動かしたり、友だちと相談して動きを考える活動もおすすめです。
協力して表現をすることで、創造力や社会性、自信を育みます。
保育園でリトミックを行うメリット
リトミックは、音楽を通して子どもたちが「楽しい」と感じながら成長できる活動です。
音感やリズム感だけでなく、運動能力の基礎、表現力やコミュニケーション能力なども自然に育ちます。
友だちと一緒に動く楽しさや協調性も自然と身につくリトミックは、遊び感覚で学べるのが大きな魅力です。
リズム感、音感が向上
リトミックは、楽しみながらリズム感や音感を向上させてくれる活動です。
ピアノや歌のリズムに合わせて手足を動かすことで、曲のテンポなどの変化を体全体で感じることができます。
また、繰り返しのリズム遊びや表現活動を通して、リズムをただ聞くだけでなく、反応できる力が育まれます。
楽しみながら、音楽への興味や感性も豊かになり、将来的な表現力や集中力の基盤にもつながるでしょう。
運動能力の発達が期待できる
リズムに合わせて手足を動かす、ジャンプ、スキップ、走る、止まる、しゃがむなどといった様々な動作を行います。
これらの動きは、全身の筋力やバランス感覚、身体をコントロールする力など様々な運動能力の発達が期待されます。
- バランス感覚
- 身体をコントロールする力
- 瞬発力
- 持久力
- 柔軟性
リトミックは、音楽に合わせて遊ぶ中で、子どもたちの運動面の基礎力がバランスよく伸びる活動です。
コミュニケーションスキルが身につく
リトミックは音楽やリズムを楽しみながら他者とのコミュニケーションを図ることができる活動です。
音楽に合わせて、保育者や友だちと楽しむ中で、相手の動きを意識する力が育ちます。
ペアやグループになって表現することで自分の意見を相手に伝えたり、他者の意見や表現を受け入れたりする経験も積めます。
このように、音楽やリズムを楽しみながら、他者とのやりとりや協調性を学べる点が大きな魅力です。
表現力がつく
リトミックは、音楽やリズムを通じて子どもたちが自由な発想で身体を動かす活動です。
音の強弱、テンポなどの変化に応じて、動きを変えながら体全体で表現を楽しみます。
さらに、リボンやタンバリンなどの道具や楽器を用いることで表現の幅が広がり、自分なりの動きを工夫する力も育まれます。
リトミックは、楽しい時間を過ごしながら、子どもたちの表現力をより豊かにすることができるのでおすすめです。
【先輩保育士直伝】保育園でリトミックを行うポイント
リトミックは、子どもたちの表現力や感性、リズム感を育むのに非常に効果的な活動の一つです。
しかし、実際に保育園で行うには、年齢や環境に合わせた工夫や安全面への配慮が求められます。
本章では、年齢別のリトミックのポイントや注意点を解説しています。
保育者も一緒に楽しむ(0歳児・1歳児)
0歳児・1歳児のリトミックでは、保育者が一緒に楽しむことが大切です。
まだ、自分で表現することが難しい子もいるため、保育者が子どもたちの手や足を軽く揺らしたり、タッチをしたりして援助しましょう。
子どもは安心できる環境の中で音楽に触れることで、自然と模倣しようとします。
声のトーンや表情を豊かに使うことも、子どもたちが音楽の楽しさを全身で感じやすくするために効果的です。
大人と一緒に活動する喜びを積み重ねることで、「楽しい」と思える基盤が育まれていきます。
無理に子どもの体を動かす、大きすぎる音や急な変化は驚きや不安につながるため、安心できる環境と適度な音量で行いましょう。
異なるリズムを取り入れて、様々な動きを楽しむ(2歳児・3歳児)
異なるリズムを取り入れることで、子どもたちは自然に動きの幅を広げていきます。
例えば、ゆっくりとしたリズムでは体を揺らしたり歩いたり、速いリズムではジャンプやスキップに発展させたりと、音の違いに合わせて多様な動きを楽しめるのです。
リズムの変化を繰り返し体験することで、リズムを感じ取る力や集中力が育まれるとともに、自分なりの動き方を見つける楽しさも味わえます。
また、友だちと一緒に同じリズムで動くことで、協調性や一体感も育まれます。
走る・跳ぶなど大きな動きが出やすいので、十分なスペースを確保し、転倒や衝突に注意しましょう。
音楽や音に合わせて動き方を工夫し、想像力を広げる(4歳児・5歳児)
4歳児・5歳児のリトミックでは、自分たちで動きを工夫し、想像力をさらに広げることが大切です。
歩く・跳ぶなど基本動作に加え、曲の速さや強弱を意識して表現の幅を広げることができるように工夫しましょう。
例えば、ピアノの音がゆったりと低く響くときには「静かな海の波にゆられる」、速く高い音が弾むときには「荒波にもまれる」と想像させることができます。
こうして、音から受ける印象を動きに変えることで、表現に物語性や想像力を加えられます。
想像力や工夫力には個人差があります。
「ドーンと大きく跳ぼう」などと、具体的な言葉で保育者が補助したり手本を示してあげましょう。
リトミックの指導案の書き方
指導案を作成する際は、年齢や発達段階に応じたねらい、活動内容、環境構成、予測される子どもの姿などを整理しましょう。
指導案では、子どもたちが安全に楽しめる計画を立てることが大切です。
安全面や声かけの工夫も計画に盛り込むことで、子どもが安心して主体的に参加できるリトミックの実践が可能になります。
指導案の展開例
指導案の作成で大切なことは、ねらいを明確にすることです。
ねらいを明確にすると、活動の方向性がぶれず、年齢や発達に応じた工夫がしやすくなります。
それを元に、各項目をしっかり記載していきましょう。
指導案の書き方
活動内容
- 音やリズムに合わせて体を揺らす・手足を動かすことを楽しむ(0歳児)
- 音楽に合わせて歩く・走る・止まるなどの動きを楽しむ(1〜2歳児)
- ピアノの強弱や速さに合わせて体の動きや大きさを変えて楽しむ(3~4歳児)
- 「波に揺れる」など、身近なものや自然の動きを想像して表現する(4~5歳児)
リトミックを取り入れるためには、年齢ごとの発達に応じた活動内容にすることが大切です。
無理なく楽しめる活動を取り入れることで、子どもたちは「楽しい」という気持ちを育み、音やリズムに合わせて体を動かすことに興味を持ちます。
0歳児は体を揺らす、1・2歳児は歩く・走る・跳ぶなどの基本動作を取り入れるなど、年齢や発達段階、子どもたちの興味関心を見ながら活動内容を工夫します。
環境構成
- 子どもが自由に動けるよう、安全で十分な広さを確保する
- 全員が同じ方向に動くように誘導し、衝突が起きないよう配慮する
- ピアノや楽器の音がよく聞こえ、保育者のお手本が見やすいよう配置に注意にする
子どもたちが自由にのびのびと表現することを楽しめるよう、スペースは十分に確保しましょう。
転倒や衝突の危険がないよう、床や周囲の安全を確認し、必要に応じて体操マットなどの柔らかい床材を使用してください。
また、全員が同じ方向に動けるよう誘導することで、子ども同士の衝突のリスクを抑えることができます。
ピアノや楽器の音がよく聞こえる位置に子どもを配置することで、体を動かし、手本を見ながら活動に参加できる環境を整えます。
予想される子どものすがた
- リズムに合わせて体を動かすことを楽しむ
- 音の大きさに驚いて、不安になる子がいる
- 気持ちが昂り、友だちにぶつかってしまう子がいる
- 想像した動きを身体で表現し、友だちと真似し合ったり掛け合いを楽しむ
- 道具や楽器に興味を示し、触ってみようとする
予測される子どもの姿を考える際は、年齢や発達段階に応じた動きや表現、個々の興味関心や感情の違いを踏まえることが大切です。
例えば、「0歳児は体を揺らす」「音におどろき泣いてしまう子がいる」「ピアノなどの楽器に興味を持ち、触ってみようとする子がいる」など、発達に応じた姿を想定します。
大きな音に驚いたり、興奮して周りの子にぶつかる場合もあるため、安全面での配慮や安心できる声かけも予測しましょう。
まとめ
リトミックは、音楽に合わせて体を動かす楽しさを通し、感性や表現力、リズム感、コミュニケーション能力などを育むことをねらいとしています。
これらは、非認知能力と呼ばれ、社会で生きていく力や自己成長の基盤となる重要な力です。
子どもたちの姿を想像し、楽しく安全なリトミックを積極的に取り入れてくださいね。








