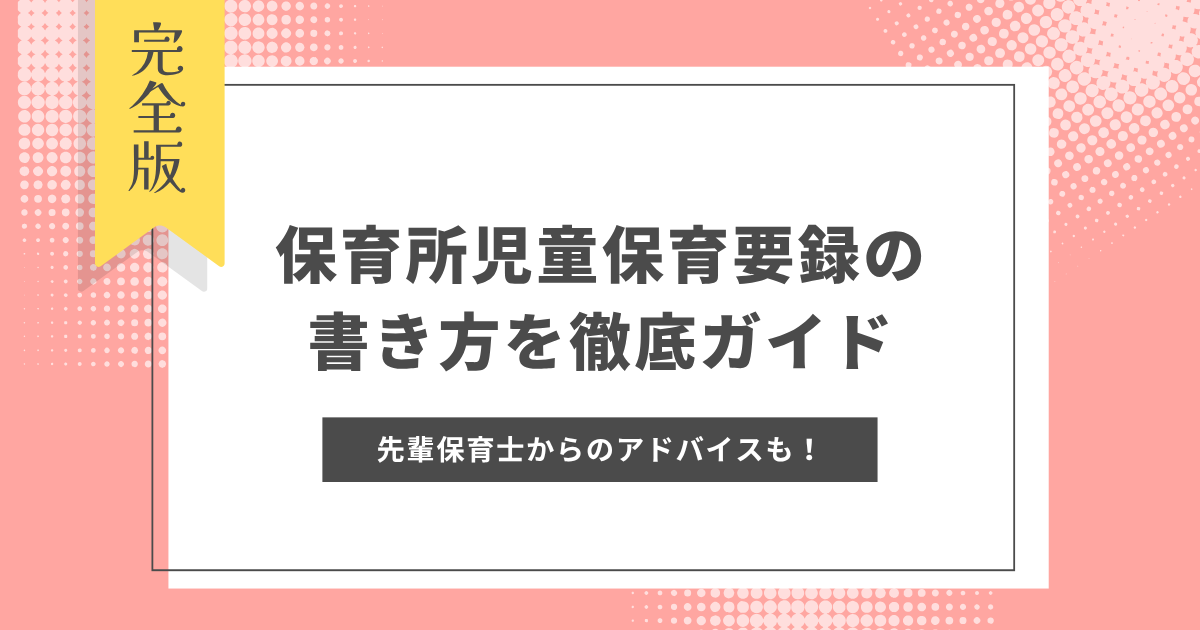保育所児童保育要録は、保育施設と小学校の円滑な連携を図るうえで重要な役割を担う書類です。
「要録の書き方が分からない……」「保育と並行しながらの作成は難しい」と苦労している方は多いのではないでしょうか。
本記事では、保育所児童要録の書き方を年齢別に詳しく解説するので、書き方にお困りの保育士の方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 保育所児童保育要録は就学先への引き継ぎ資料、保護者との共通理解を図るなどの目的がある
- 要録に記載する主な項目は「入所に関する記録」「保育に関する記録」の2つ
- 作成時は簡潔かつ明確に書くことを意識する
- スムーズに作成するためには、担任間での連携や上司への相談が大切
 【元保育士】ゆぴライター
【元保育士】ゆぴライター私も保育士時代、保育所児童保育要録の作成経験があります。大学や職場で書き方を教えてもらえるわけでもなく、残業して苦労しながら作成していました。本記事が1人でも多くの保育士さんの役に立てば幸いです。


ゆぴ先生 元保育士ライター
保育士歴9年。ピアノが得意で、子どもと一緒に歌をうたうことが好きでした。現在は、専業主婦兼Webライターとして活動中です。保育士や保育士を目指す方の、力になれるような記事を執筆しています。
保育士が書く「保育所児童保育要録」とは?
保育所児童保育要録とは、小学校や支援学校などの就学先に提出する書類です。
保育所での子どもの姿や発達面、特性、留意事項などを記載します。
就学先への引き継ぎ資料以外に、保育者の保育の振り返りや保護者と連携するための資料としても活用されます。
- 就学先への引き継ぎ資料として活用する
- 保育の振り返りと記録
- 保護者と連携するための資料
年長児の担任が作成し、卒園前の3月中旬ごろまでに就学先へ提出するのが一般的な流れです。
卒園後も適切な指導をしてもらうために、子どもの姿を正確かつ丁寧に書くよう心がけましょう。
保育所児童保育要録の主な項目
保育所児童保育要録の主な項目は、「入所に関する記録」「保育に関する記録」の2つです。
要録は、厚生労働省が指定した書式に合わせて記載していきます。
それぞれの項目内容は、入所に関する記録が主に子どもの氏名や保育所の入所日といった個人的な情報、保育に関する記録が保育の過程や子どもの姿、最終年度の重点などです。
ここでは、入所に関する記録と保育に関する記録を詳しく解説していきます。
参考:保育所児童保育要録 別紙(様式の参考例)
入所に関する記録
「入所に関する記録」では、主に子どもの基本情報を記載します。
- 子どもの氏名・生年月日・性別・現住所
- 保護者の氏名・現住所
- 入所・卒所年月日
- 就学先
- 保育所名及び所在地
- 施設長氏名
- 担当保育士氏名
子ども本人に加え、保護者氏名や入所月日、保育所名なども書きましょう。
入所に関する記録は、子どもの家庭環境や保育所名を就学先の担任が把握し、一人ひとりに合う保育を行うための情報を整理する目的があります。
一見必要のない情報にも思いますが、子どもの今後の指導に欠かせない重要な項目です。
保育に関する記録
「保育に関する記録」では、保育所での子どもの育ちを具体的に記載します。
- 氏名・生年月日・性別
- 保育の過程と子どもの育ちに関する事項(最終年度の重点・個人の重点・保育の展開と子どもの育ち)
- 最終年度に至るまでの育ちに関する事項
- 特に配慮すべき事項
指定された書式には、子どもの育ちに関する事項に加え、健康、人間関係など5領域のねらいや幼児期の終わりまでに育ってほしい姿も記載されています。
作成する際は、これらのねらいや姿を達成できたかに着目しながら書くことが大切です。
保育に関する記録「最終年度の重点」の書き方&文例集
保育の過程と子どもの育ちに関する事項の「最終年度の重点」は、5歳児クラスにおいてどのような目標を立てて生活してきたかを記載する欄です。
年度始めに立てた年間計画を参考にしながら記載しましょう。
- 共通の目標に向けて友だちと協力しながら成し遂げようとする
- 友だちと相談しながら活動を進める楽しさを味わう
- 生活や遊びの中で友だちと積極的に関わろうとする
- 生活に見通しを持ち友だちと触れ合いながら充実した園生活を送る
この項目はクラス全体の目標なので、個別に変える必要はありません。
併せて上記の例文も参考にしてみてくださいね。
保育に関する記録「個人の重点」の書き方&文例集
「個人の重点」は、各年齢を振り返りどのような点を重点的に指導したか記載する項目です。
保育記録や児童票を参考にすると当時の姿や声のかけ方が把握でき、スムーズに作成できますよ。
ここでは、0〜5歳児それぞれの書き方と文例をご紹介します。
0歳児の「個人の重点」の書き方と文例
家庭とは異なる環境で生活を始めるのが0歳児のポイント。
その中で、どのような姿に成長してほしいのかに着目して記載しましょう。
- 安心した環境の中で規則正しく生活する
- 保育者とスキンシップをとりながら興味のある遊びを見つける
- 好きな遊びを見つけ身体を動かしながら楽しむ
- 離乳食を食べて野菜や果物などの食材に興味をもつ
0歳児は友だちとの関わりは難しい時期なので、生活や食事などに特化してみてもよいです。
特に0歳児の重点は他の子どもと被りやすいですが、言い回しや表現を変えながら作成するのがポイントです。
1歳児の「個人の重点」の書き方と文例
1歳児は手を洗う、着替えるなど身の回りのことに関心を持ち始め、保育者と一緒にやってみようとする姿がでてきます。
そのような生活面にポイントを絞り記載してみるとよいでしょう。
- 身の回りのことに興味を持ち保育者に援助してもらいながら試してみようとする
- 友だちや保育者と関わりながら好きな遊びを楽しむ
- 保育者に代弁してもらいながら自分の気持ちを伝えようとする
- スプーンを使って食事をしようとする
成長に大きな差が見られる月齢なので、一人ひとりの発達や姿をしっかり理解しておくことが大切です。
2歳児の「個人の重点」の書き方と文例
心身だけでなく脳の発達も著しい2歳児は、自分の意志や欲求を伝えられるようになります。
語彙も目立って増えるため、言葉の部分に着目した文章がおすすめです。
- 友だちに興味を持ちながら同じ遊びをすることを楽しむ
- 言葉に興味を持ち保育者や友だちと言葉のコミュニケーションを楽しむ
- 身の回りのことを進んで行おうとする
- 苦手な食材に挑戦しながら食事をする
一人遊びから並行遊びへと発展するのも2歳児の特徴なので、友だちとの関わり方を意識してみてもよいでしょう。
3歳児の「個人の重点」の書き方と文例
3歳児になると、友だちとの関わりが増え一緒に遊ぶ姿が増えていきます。
言葉で上手く気持ちを伝えられず時に衝突することもあるので、どのように指導したかを具体的に記載してみるとよいでしょう。
- 簡単なルールのある遊びに興味を持ち友だちと関わりながら遊ぶことを楽しむ
- 保育者に援助してもらいながら自分の気持ちを友だちに伝えようとする
- 友だちと関わる中で相手の気持ちを知る大切さを学ぶ
- 積極的に身の回りのことに取り組み自信を持つ
着替えやリュックの出し入れなど自分でできることが増える月齢でもあるので、自信が持てる関わり方をポイントにするのもおすすめです。
4歳児の「個人の重点」の書き方と文例
特定の友だちと好きな遊びを楽しみ始めるのが4歳児の特徴です。
時には衝突し仲介に入る場面も増えてくるので、どのように関わったかを重点的に挙げてみましょう。
- 友だちと関わりながら自分の気持ちを伝えたり相手の気持ちを考えたりしようとする
- 気の合う友だちと好きな遊びを楽しむ
- 活動に興味を持ち、最後まで楽しみながら取り組む
- 自分のやりたいことを存分に楽しむ
自分の好きな遊びや活動を見つけるのも4歳児ならではの姿。
一人ひとりが何に興味を持っているのかを日頃から理解しておく必要があります。
5歳児の「個人の重点」の書き方と文例
5歳児になると、就学に向けて本格的な準備が始まります。
時計が読める、立ったまま靴の着脱ができるなど、指導したポイントを記載しましょう。
- 生活に見通しを持ち友だちと声をかけながら活動する
- 就学に期待を感じながら様々な活動に自信を持って参加する
- 友だちと意見を出し合いながら一つの目標に向かって取り組む
- 友だちに自分の気持ちを伝えたり相手の気持ちを聞こうとしたりする
就学時に一番近い5歳児は、どのような指導を行っていたのか特に注目される項目です。
子どもの姿がイメージしやすいように分かりやすく記載することが大切です。
保育に関する記録「保育の展開と子どもの育ち」の書き方&文例集
「保育の展開と子どもの育ち」は、子ども一人ひとりの姿から発達や特性がどのように伸びたかを記載する項目です。
- サッカーが好きで、友だちと関わりながら楽しんでいる。自分の意見を主張することが多く相手の言葉に耳を傾けられないこともあったが、保育者の声かけにより次第に友だちの意見を聞く姿勢が身につくようになった。
- 支援児や年下児と関わることを楽しみ、積極的に世話をしている。時に言い方が強くなったり手を強く引っ張ったりしてしまう姿が見られたが、保育者と一緒に伝え方や力加減を考えながら適切に関われるようになった。
- 数字や文字に興味を持ち、自発的に時計を見て時間を数えたり文字を書いたりしている。友だちや保育者に手紙を書いてやりとりを楽しむ姿がある。
- 発表会や運動会などの準備に意欲を持って参加する。自らアイデアを出しながら率先して進めようとしていた。
5領域や幼児期の終わりまでに育ってほしい姿に当てはめながら、成長が著しく感じられた部分を具体的に取り上げましょう。
保育に関する記録「特に配慮すべき事項」の書き方&文例集
「特に配慮すべき事項」は、子どもの健康状態や発達障害、アレルギーなど特筆が必要な際に記載します。
- 卵、乳アレルギーのため除去食で対応する。
- うさぎアレルギーを持っているため、飼育の際は十分配慮する。
- 生まれつき弱視のため、座る席などを配慮する必要がある。
- 集中力が長時間続かず周りにちょっかいを出す姿があるため、席の工夫や時間を伝えるなど個別対応が必要。
アレルギーや障害の有無をしっかりと伝えないと就学先で配慮ができず事故やトラブルの発展に繋がるので、明確に伝えることが大切です。
保育に関する記録「最終年度に至るまでの育ちに関する事項」の書き方&文例集
「最終年度に至るまでの育ちに関する事項」では、入所時の子どもの姿を具体的に記載しましょう。
- 入所した1歳児の頃は、親子離れができず泣いて過ごす時間が多かった。保育者や友だちが遊ぶ姿に興味を持ち始めると、自分から玩具を手にして遊ぶようになった。
- 3歳児で入所したものの、特に新しい環境に戸惑うことなく自然と友だちの輪に入っていた。
- 4歳児になると虫に興味を持ち始め、虫探しや飼育を楽しんでいた。
- 5歳児の頃は人前にでることを好み、発表会や運動会の出し物を堂々と演じる姿が見られた。
入所時からの姿を振り返り、特に成長が見られた部分や重要であると感じた姿を挙げます。
年齢ごとに記入すると、経過が分かり見やすいです。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」とは?
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、就学までに育みたい資質や能力を10の項目から具体的な姿として表したものです。
- 健康な心と体
- 自立心
- 協同性
- 道徳性・規範意識の芽生え
- 社会生活との関わり
- 思考力の芽生え
- 自然との関わり・生命尊重
- 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
- 言葉による伝え合い
- 豊かな感性と表現
適切な指導や活動を展開していくことで、これらの10の資質や能力は育まれていきます。
子どもが健やかに育つために、保育士は10の姿に配慮した保育の提供を心がけましょう。
保育所児童保育要録を記載する際の注意点
保育所児童保育要録は、就学先に提出する子どもの成長が記録された大切な書類です。
場合によっては保護者に見せることもあるため、ネガティブな表現や回りくどい書き方をしないように注意して作成しましょう。
その他にも作成時の注意点をいくつかご紹介するので、ぜひ覚えてくださいね。
客観的な記述を心掛ける
保育要録を書く際は、できる限り客観的な記述を心がけましょう。
客観的に書くのには、以下のような理由があります。
- 就学先の教員に正確な情報を伝えるため
- 記録としての信頼性を保つため
- 子どもや保護者に対し公正であるため
例えば、「おしゃべりで落ち着きがない」のように主観的に書いてしまうと読み手が誤解を生んでしまう可能性があるため、この場合は「話したいことが多く、集団活動中も自分の話を続けることがある」と書くのが正しい表現です。
教員や保護者など、誰が見ても子どもの姿が正確に分かるように客観的で温かみのある記録を心がけてください。
事実に基づいた記録を記載
保育要録は事実に基づいた記録が非常に大切です。
事実に基づいて書くことにも、以下のような理由があります。
- 就学先での支援に直結するため
- 主観や印象は人によって異なるため
- 記録としての信頼性を保つため
保育要録は就学先の教員がその子どもを理解し、適切な配慮や支援を行うために必要な資料です。
事実と異なる表現や記載があると、その後の支援に支障が出る可能性も考えられるでしょう。
事実に基づいた正確な情報を記載するためには、普段から子どもの姿を観察し記録にとっておくことが大切です。
簡潔かつ明確に記述する
保育要録は、簡潔かつ明確に記述するよう意識してください。
簡潔かつ明確に書くことは、以下のようなメリットに繋がります。
- 読み手に正確に伝わる
- 子どもの姿がイメージしやすい
- 情報を素早く入手できる
- 誤解や読み違いを防ぐ
小学校や支援学校の教員は忙しい時間の合間を縫って要録に目を通すため、回りくどい文章や長すぎる文章では読むのに時間がかかってしまうでしょう。
要点を押さえ、誰が読んでも理解できるような文章を書くことが求められます。
ポジティブな表現を使う
ポジティブな表現を使うことも、保育要録を書く際のポイントです。
- 子どもの成長や可能性を前向きに伝えるため
- 就学先での支援に繋げやすくするため
- 保護者に安心してもらうため
上記のように、ポジティブな表現が大切な理由はいくつかあります。
ただし、事実をねじ曲げてよく見せようとするのではなく、子どもの姿や特性を肯定的に捉えて表現するように心がけてください。
また、保育要録は保護者からの要求があれば開示しなければならないので、家庭との信頼関係を構築するためにもネガティブな表現は避けましょう。
【先輩保育士はどうしてた?】保育要録をスムーズに書くためのポイント
年長担任は、日々の保育や卒園準備と並行しながら要録を作成しなければなりません。
少しでも負担を減らすために、以下のように作業分担や働き方を工夫しましょう。
- 複数担任の場合は、数人ずつ分担して書く
- 文章を書き始める前に、子どもの特性や成長を感じた部分をメモする
- 保育日誌や児童票などの書類を参考にする
- いきなり直接書かず、下書き後上司にチェックしてもらう
- 子どもの具体的な姿が思い出せない、上手く言語化できない際は周りの保育士や園長、主任に相談する
上記はどれも、保育士時代実際に私が取り入れていた方法です。
私の場合、20名ほどの要録を担任2人で分担して作成しました。
スラスラと姿が書ける子もいればそうでない子もいたため、時間がかかりそうな場合はその子のどのような点に着目するか、この1年でどういう風に成長したかを担任間で整理する時間を設けました。
まとめ
保育所児童保育要録の書き方を、年齢別に詳しくご紹介しました。
保育要録は子どもの発達や成長を正確に記録し、就学後の指導に活かすために重要な書類です。
要録の書き方を押さえることで、子どもの成長を正確に記録し、次の成長段階へのスムーズな引き継ぎが可能になります。
本記事でご紹介した書き方を参考に、作成してみてくださいね。