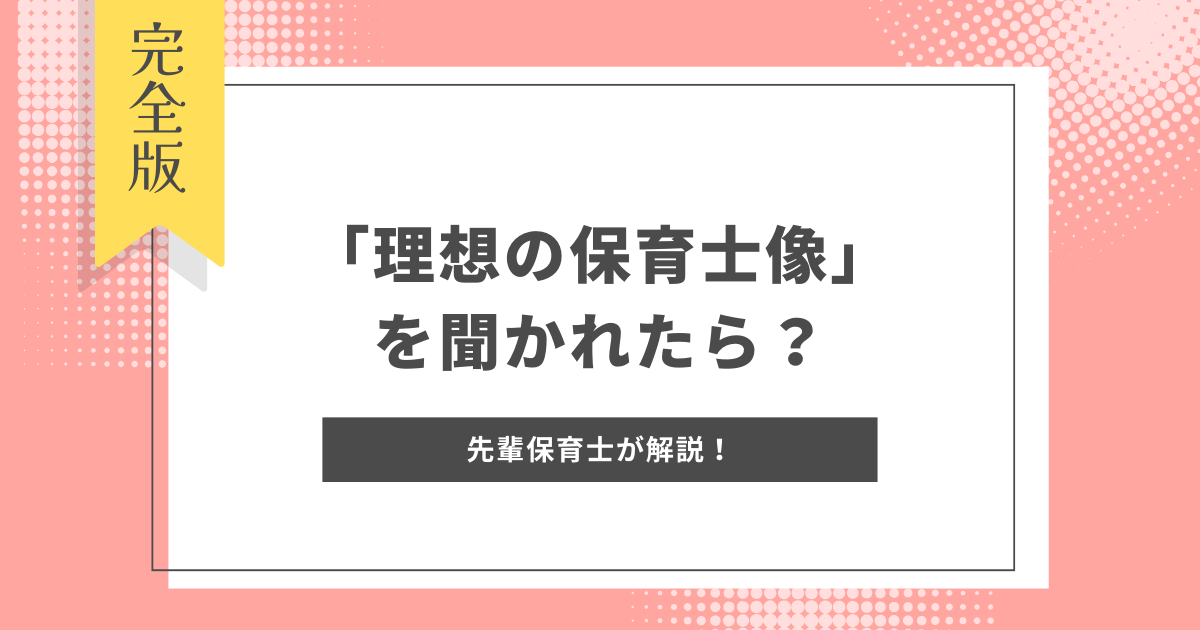採用面接や実習園で「あなたの理想の保育士像について教えてください」と聞かれる場合があります。
しかし「理想の保育士像についてなんて答えたら良いのか分からない」と悩む方も。
面接ではよく聞かれる質問なので、自分の言葉で明確に答えられるようにすれば、採用担当者に良い印象を残せますよ。
今回は、「理想の保育士像」を聞かれた時の例文・書き方のヒントについて解説していきますので、面接を控えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 採用面接や実習園で聞かれる場合がある
- 保育士になりたい理由や大切にしたい点を踏まえて考えてみる
- 自己理解を深め、子どもとの関わりを積み重ねて理想の保育士像を目指す
- 周りと比べず、自分らしい姿を思い浮かべる
 すもも【元保育士ライター】
すもも【元保育士ライター】「理想の保育士像」を考えることで、自分の目標や課題が明確になり、採用試験でも役立ちますよ。
また、保育士として働き始めてからも、理想の保育士になるために自分の保育を見直すきっかけにもなります。


すもも先生 元保育士ライター
8年間保育士として勤務し、主に乳児クラスの担任を務めて参りました。認可保育施設や認可外保育施設での職務経験を活かして、保育士さんに役立つ記事を執筆させていただきます。
そもそも「理想の保育士像」とは?
理想の保育士像とは「〇〇な保育士になりたい」という具体的な保育士の姿を指します。
例えば「子どもと保護者からも信頼される保育士になりたい」「いつでも明るくて笑顔の絶えない保育士になりたい」など人によって様々です。
「上手く思いつかない」と言う方は、下記のポイントを意識してみるとイメージしやすくなりますよ。
- 保育士を目指す理由を考える
- 得意ジャンルや自分の強みを踏まえて考える
- 保育士として大切にしたい点は何か
- 子どもや保護者とどのように関わっていきたいのか
理想の保育士像が問われるシーンって?
理想の保育士像が問われる場面は、保育士の採用面接や保育実習先が多いです。
特に就職時では定番の質問になるので、自分の言葉でしっかりと伝えられるようにしましょう。
時々保育実習先でも聞かれるため、実習で学びたい内容と結び付けて伝えると、実習担当者も指導がしやすくなります。
下記でそれぞれのシーンについて詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
就職や転職での面接
先ほども解説したように、就職や転職時での面接では「理想の保育士像」を尋ねられる機会が多いです。
志望動機や長所・短所と同じように、面接の序盤で聞かれる場合も考えられます。
万が一答えられなかったら「本当にこの園で働けるのかな?」とマイナスな印象を与えてしまうかもしれません。
採用担当者に良い印象を与えるためにも、自分自身の言葉で明確に伝えられるようにするのが大切です。



私自身も採用面接で聞かれたことがあります。また、園によっては小論文で記載する場合もありますので、文章でも書けるようにしておきましょう。
保育実習
保育士を目指す学生であれば保育実習は必須となり、年に1~3回程度行きます。
実習先の保育園でもオリエンテーション時には、「理想の保育士像は何か教えてください」と尋ねられる場合がありますので、いつでも答えられるように考えておきましょう。
採用試験と違って、深掘りされるケースは少ないと思いますが、細かく聞く園もあります。
保育実習では何を学びたいのかを明確にすれば、自分のやる気をアピールできますよ。



私の経験上では、保育実習先で理想の保育士像を聞かれることはなかったですが、その代わりに「実習では何を学んで何を身に付けたいのか」を細かく聞かれました。
面接や実習で「理想の保育士像」を聞かれる理由
- 理想の保育士像から人柄が分かる
- 園と合っているかわかる
- どんなことを学びたいかわかる(実習生の場合)
理由は上記の3つで、まずはその人の人柄や考え方が分かるからです。
採用面接では、人柄や考え方などをある程度把握したうえで、保育士として働いていけるのかを判断します。
園によって保育方針が違うため「この園に合っているかどうか」を見極めるためにも「理想の保育士像」は重要と言えるのです。
実習生の場合では、ただ単位のために実習を行うだけでは意味がないため、何を学び、どんな保育士になりたいのかを聞き出しています。
理想の保育士像を考えるときのヒント5つ
「理想の保育士像がなかなか思いつかない」や「自分のエピソードを交えて考えた方が良いの?」など、どんな内容が適しているのか疑問に思う方が多いと思います。
下記で、理想の保育士像を考える時のヒントを5つまとめていますので、参考にしてみてください。
自分が憧れた保育士像を振り返る
まず1つ目は「自分が憧れた保育士像を振り返る」で、自分の経験を元に考えると分かりやすいです。
例えば「幼少期の担任の先生がいつも優しくて、憧れていた。自分もいつでも笑顔を絶やさず、子ども達に愛情を持った保育士になりたい」というような内容になります。
自分の経験した出来事を交えて考えれば、説得力が増し、気持ちも伝わりやすくなりますよ。
他にも「担任の先生がいつも自分の気持ちに共感してくれて嬉しかった」など、自分のオリジナルのエピソードを交えて考えてみましょう。
保育実習で感動した先輩保育士の行動から考える
2つ目は「保育実習で感動した先輩保育士の行動から考える」で、これは自分が大人になってから経験した内容になるので、子どもの頃とはまた違った視点で考えられるでしょう。
保育実習の担当の保育士さんは、ある程度実務経験のある先生が担当してくれるケースが多いです。
そのため、保育士としてのスキルや言葉がけなどに注目すると、勉強になる部分がたくさんあります。
「実習先の保育士さんが、子どもへの言葉がけがいつも肯定的で、否定的な言葉を使わないところに感動した」など、実際の保育士さんの行動や言動を元に考えてみるのもおすすめですよ。
子どもや保護者との関係性をどう築きたいか
3つ目は「子どもや保護者との関係性をどう築きたいか」で、自分の築きたい関係性をイメージしてみましょう。
例えば「子どもや保護者から信頼される保育士になりたい」や「保護者の方の悩みに寄り添える保育士を目指したい」などがあります。
特に保護者との関係性は、信頼関係の構築が重要となるため、信頼関係を築けるまで丁寧に関わっていく必要があるのです。
自分が得意なこと(ピアノ・製作・運動)をベースに考える
4つ目は「自分が得意なことをベースに考える」で、特技を交えれば自分の強みをアピールできますよ。
ピアノが得意な方であれば「得意なピアノを活かして、子ども達に音楽の楽しさを伝えられる保育士になりたい」という保育士像が思い浮かぶでしょう。
近年はピアノスキルが不問な保育園も数多くありますが、戦力になるためにもピアノが得意な方はアピールしましょう。
他にも、制作や運動が得意な先生も戦力になるので、スキルを活かしてどんな保育士になりたいのかを考えてみてくださいね。
保育理念や保育方針に共感した園で、どんな役割を果たしたいか
最後は「保育理念や保育方針に共感した園で、どんな役割を果たしたいのか」です。
園によって方針は違うため、自分が気に入った部分を交えて考えましょう。
さらに、園で成し遂げたい内容や、具体的な目標も決めると、理想の保育士像が思い浮かびますよ。
採用面接で保育理念や保育方針を交えて発言すれば、「園のことをよく知ってくれている」と好印象を持ってもらえるので、就職にも有利です。
先輩保育士直伝!面接や実習で使える「理想の保育士像」の例文
ここでは、実際に面接や実習で使える「理想の保育士像」の例文をご紹介します。
例文を参考にして、ご自分の「理想の保育士像」を考え、実際のシーンで使えるようにしておきましょう。
笑顔を絶やさない保育士
私が考える理想の保育士像は、常に笑顔を絶やさない保育士です。
私が幼少期の頃の担任の先生は、いつでも笑顔溢れる先生で、その明るい雰囲気が大好きでした。
担任の先生がいつも笑顔で優しかったので、保育園に通うのが毎日楽しみだったのを覚えています。
私も子ども達と一緒に毎日を明るく笑って過ごし、一人ひとりの成長を見守っていきたいです。
上記の例文は、「笑顔を大切にしたい」という思いを重視した内容になっています。
幼少期の経験を元に、昔先生にしてもらったことを今度は自分が保育士になって実践したいという気持ちが表れていますね。
常に笑顔を絶やさない先生であれば、子どもも保護者も安心して保育園に通えるため、理想の保育士像をアピールするにはぴったりの内容です。
子どもの気持ちに共感し、寄り添う保育士
私が目指す理想の保育士像は、子どもの気持ちに共感し、寄り添う保育士です。
実習先で担当してくださった保育士さんは、常に子どもの気持ちに共感していました。
子どもが発言する度に「そうだね、〇〇だね」と子どもの気持ちに寄り添い、常に同じ目線で関わっていた姿が印象的でした。
先生に共感してもらった時の子ども達はみんな嬉しそうだったので、私も子どもの気持ちに寄り添う保育士になりたいです。
上記の例文では、実習先の保育士さんの姿に感動したエピソードを交えています。
子ども達は、自分の気持ちに共感して寄り添ってもらうことで、自己肯定感を身に付け、気持ちを言葉で伝えられるようになるのです。
話をしっかりと聞き、気持ちに共感してもらうと、子ども達は保育士に信頼を寄せていきます。
上記のように、実際の保育士さんの姿を交えて、理想の保育士像を考えるのもおすすめですよ。
保護者から信頼される保育士
私の考える理想の保育士像は、保護者から信頼される保育士です。
保護者の方は、子育てにおいて様々な悩みを抱えていらっしゃると思うので、保護者の方の悩み事に傾聴できる保育士になりたいと考えています。
私の母も私が幼少期の頃、担任の先生が悩み事や不安に思うことをしっかりと聞いてくれて、アドバイスをしてくれたようです。
先生に聞いてもらえるだけで気持ちが楽になり、安心して子どもを預けられたと言っていました。
私も保護者の方に寄り添い、子ども達一人ひとりの様子や成長している姿をしっかりと伝えて、安心してもらいたいです。
上記の例文は、自分の母親の経験を元に考えられた文章となっています。
保護者の方は、日中子どもの姿を見られないので、悩み事や不安な部分が多いです。
そんな時に保育士がしっかりと保護者の方の話を聞き、悩みを少しでも解消できるようにしたいですね。
保護者に信頼される保育士を目指したい方は、上記の例文を参考にしてみてください。
理想の保育士像になるためにできることは?
- 自己理解を深める
- 同僚や先輩から学ぶ
- 子どもとの関わりを積み重ねる
- 定期的に振り返る習慣を持つ
理想の保育士像を目指すためにできることは、上記の4つがあります。
まずは自分自身がどんな人物なのか、自己理解を深める必要があるでしょう。
自分自身を見つめ直せば、得意な分野やスキルなどが見つかり、その部分を活かした保育士を目指せます。
同僚や先輩の姿をよく観察すれば、保育士として学べる部分が見つかるでしょう。
特に新卒の保育士さんは、右も左も分からない状態であるため、先輩保育士の姿を見て仕事を行います。
先輩や同僚の良い部分を参考にし、理想の保育士像に近づくために目標を考えてみるのもおすすめ。
そして、保育士として最も重要なのは、子どもとの関わりで、子どもから学べることもたくさんありますよ。
また、日々の自分の保育を定期的に見直し、理想の保育士像に近づけているか確認してみましょう。
先輩保育士からのメッセージ
保育士の理想像は人それぞれで良く、周りと比べないのが大切だと思います。
正解はないので年々変わっていっても大丈夫ですし、自分の決めた目標が達成できたら、また新たな目標を決めて頑張っていくという形で良いと思います。
肉体的にも精神的にもきつくなりがちな保育士さんですが、切羽詰まってしまった時には、理想の保育士像を思い返して、ゆったりとした気持ちで自分らしく頑張ってください。
まとめ
今回は、面接や実習で聞かれる「理想の保育士像」の例文や、書き方のヒントについて解説してきました。
なかなか思いつかない方は、自分の経験を元にして考えてみると分かりやすいですよ。
幼少期のエピソードや、実習先で目標にした保育士さんなどを参考にして考えてみてください。
理想の保育士になるためには、自己理解や子どもとの関わりを積み重ねるのが大切で、自分らしい目標を決めてみましょう。