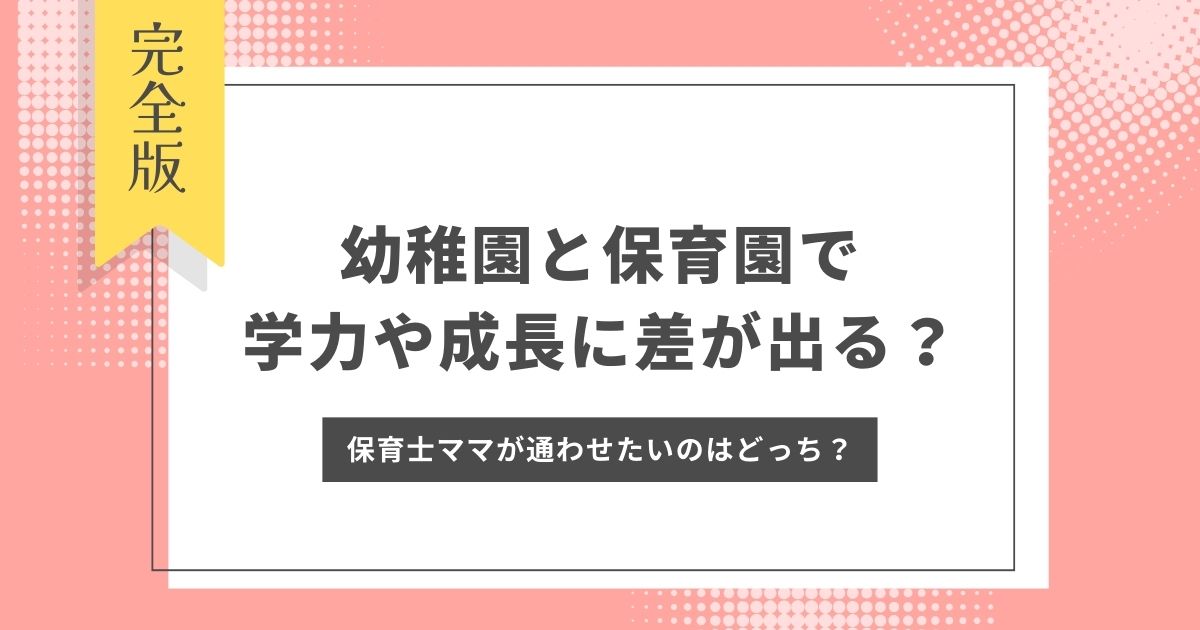子どもが生まれると「幼稚園と保育園のどちらに通わせた方がいいの?」「そもそもどこが違うの?」と気になる人も多いですよね。
幼稚園と保育園の選択で将来的に子どもの学力に差が出てしまったり、将来を左右したりするかもと考えると不安になるのも当然です。
本記事では、どちらの施設でも勤務経験のある保育士の視点と実体験から、双方の違い、本当に差が生まれるかどうかについて丁寧に解説していきます。
ぜひ参考にしてくださいね。
- 幼稚園と保育園には制度的な違いがある
- 学力や心の成長にはっきりとした差は出にくいが、家庭の関わり方で左右される
- 子どもに合った園を選択することが大切
 ちあき【元保育士ライター】
ちあき【元保育士ライター】「幼稚園と保育園のどちらを選ぶのが正解なの?」と悩んで当然です。双方の違いはわかりにくいので、この記事で確認し、子どもにとって何が一番良いか、一緒に考えていきましょう。


ちあき先生
認可保育園で勤務後退職して留学。その後は英語の幼稚園で働く。結婚を機に派遣保育士に転身し、さまざまな園で経験を積む。保育士歴は通算7年ほど。
子どもが重度アレルギー児になったことでライターに転身した2児の母。
幼稚園と保育園の違い
幼稚園と保育園、どちらも小学校就学前の子どもを預かる施設という点では同じです。
しかし、双方には目的や制度などから保育対象となる子どもまで、大小さまざまな違いがあります。
それぞれの基本的な制度の違いを知ることで、どちらが自分の家庭に適しているかが明確になります。
基本的な制度の違い
| 幼稚園 | 保育園 | |
|---|---|---|
| 管轄 | 文部科学省 | 厚生労働省 |
| 根拠法令 | 学校教育法 | 児童福祉法 |
| 標準保育時間 | 4時間程度 | 最長11時間程度 |
| 保育対象 | 3歳~小学校就学前の幼児 | 保育が必要とされる0歳~小学校就学前の乳児と幼児 |
| 先生の資格・免許 | 幼稚園教員免許状 | 保育士資格 |
表から分かるように、そもそも管轄が文部科学省と厚生労働省で異なります。
また、根拠法令として定めている法律も異なり、一見似ている施設のように感じますが、制度から見ると全く異なる性質の施設であることも分かりますね。
一般的には、保護者の就労状況に関係なく通える幼稚園と、就労などで保育の必要性がある家庭が利用する保育園に区別されています。
しかし、近年共働き家庭が急速に増えていて、保育園に入れずに職場に復帰できない問題が注目されています。
そんな家庭をサポートするために、保護者が就労していても幼稚園に通えるように延長保育などを行う幼稚園も増えています。
幼稚園の特徴
幼稚園は、学校教育法に基づいて、文部科学省が管轄しています。
したがって、小学校教育を見据えたアカデミックな教育に重点を置いた施設が多い傾向があります。
以下に幼稚園の主な特徴をまとめました。
- 小学校就学に向けた集団生活や学習習慣を育てる教育が中心
- 保育時間が短めで、延長保育は園による
- 長期休暇がある
- 保護者参加の機会が多い傾向がある
幼稚園は、文字や数字に親しむ活動や行事の準備、さまざまな体験学習などを通して、小学校就学への準備となる活動をたくさん取り入れている施設が多いです。
保育園の特徴
保育園は、児童福祉法に基づいて、厚生労働省が管轄しています。
したがって、子どもの生活に重点を置いた方針を取る施設が多い傾向です。
以下に保育園の主な特徴をまとめました。
- 親が就労しているケースがほとんどなことから開園時間が長い
- 開園日は基本的にカレンダーどおり
- 生活習慣の確立や自立を保育目標として掲げている施設が多い
- 0歳~小学校就学前までの幅広い年齢の子どもたちが生活している
保育園は子どもにとって生活の場として考えられており、子どもの安心・安全な環境づくりにフォーカスしている施設が多いです。
中には、異年齢保育を取り入れ、社会性や協調性を育むことに力を入れている園もあります。
幼稚園も保育園もそれぞれの園で特色がある
幼稚園は教育中心、保育園は生活中心と一般的には区別されがちですが、実際の現場ではその境界は曖昧です。
近年では、幼稚園でも遊びを重視して子ども主体の活動を大切にしている園もありますし、保育園でも絵画・音楽・体操といった教育的プログラムを取り入れている園も珍しくありません。
どちらの園でも、それぞれの方針に基づいた特色ある取り組みが行われているため、一括りの評価はできません。
保護者としては、制度の違い以上に「その園がどんな保育をしているか」「自分の子どもに合いそうか」という視点から、園見学などで実際の様子を確認することをおすすめします。
学力に差は出る?幼稚園・保育園が就学後に与える影響
小学校就学前に通う園が幼稚園か保育園かによって、学力に差が出るのでは?と不安に感じる保護者も少なくありません。
しかし、実際には園の方針や子ども自身の特性、家庭での関わり方が大きく影響します。
本章では、小学校就学後に起こり得る影響について見ていきましょう。
小学校入学前の「学び」の違い
幼稚園は文科省の管轄であることから、小学校への接続を意識した教育的な活動が多く取り入れられています。
文字や数の導入、椅子に座って話を聞く練習など、「就学モード」に徐々に慣れていくイメージです。
一方、保育園でも小学校入学を見据えて最終学年になるとお昼寝時間を徐々に短くし、椅子に座って行う活動を増やしたりするなどの工夫がされています。
それぞれの施設で取り入れられている小学校への準備は異なりますが、どちらも園児の成長に合わせた学びの土台作りが進められています。
就学後の差が出たとしても「一時的」なことが多い
入学直後は、幼稚園児の方が授業の流れにスムーズに乗れるケースもありますが、こうした差は一時的なものですぐに消えていくことがほとんどです。
保育園児も、数ヶ月で環境に慣れ、個々の成長に応じてしっかり小学校での学びについていけるようになります。
短期的な視点では差がついたように見えても、1年などの長期的な視点で見れば、幼稚園出身の子どもも保育園出身の子どもも出身園による差はほとんどありません。
結局は親の関わり・子どもの特性がカギ
園での経験ももちろん大切ですが、それ以上に大きいのは家庭での声かけや学びへの関心を育む関わりです。
例えば、絵本の読み聞かせの習慣や一緒に時計を読んだり身の回りの物を一緒に数えたりする中で、子どもは自然と学びを吸収していきます。
また、落ち着いて絵を描いたりパズルをしたり、座って活動することが好きな子もいれば、外で元気に体を動かすのが得意な子もいます。
子ども自身の特性や好きなもの、興味があることによっても学びのペースは左右されます。
幼稚園と保育園で心の成長に差は出る?
就学前に育まれるのは、学力の土台だけではありません。
友達との関わり方や、自分や周りの人を大切に思う気持ち、自分のコントロールの仕方などの「心の成長」もとても大切です。
幼稚園と保育園では、心の成長に差が出るのか、それぞれの園で育まれる心の成長に着目してみましょう。
幼稚園の方が親子の時間が多い傾向がある
幼稚園は保育園と比較すると保育時間が短めであるため、親子で過ごす時間が比較的多くとれます。
特に専業主婦世帯や時短やパートタイム勤務の家庭では、夕方の時間に一緒に過ごせることで、子どもの情緒の安定にもつながります。
また、幼稚園では保護者参加の行事が多く、保護者自身も幼稚園や子どもへの意識が向きやすくなるので、子どもと心を通わせる時間が取れるでしょう。
夕方の時間に一緒にスーパーに行く、習い事に行く、おうちで遊んで過ごす、どれもが子どもの心の成長に深く関わっています。
保育園では異年齢の関わりが増える
保育園では、同学年との関わりだけでなく、早朝保育や夕方の延長保育などから異年齢の子どもと関わる機会が多く、年下の子をお世話したり、年上の子に教えてもらったりする経験が自然と生まれます。
保育の一環として異年齢児保育を取り入れている保育園も珍しくありません。
特に近年は兄弟がいない子どもも少なくないので、保育園で異年齢の関わりを持てることは、優しさや思いやり、社会性を育てることにつながります。
保育園ならではの魅力のひとつと言えるでしょう。
正直、園の方針と子どもの特性による
「保育園か幼稚園かで心の成長に差が出るか?」という問いには、一概には答えられません。
なぜなら、園の方針や日々の保育で大事にしていること、そして何より子ども自身の気質や家庭環境が大きく関係するからです。
幼稚園に通う子ども、保育園に通う子どもで、それぞれ育ちやすい部分は異なりますが、どちらも子どもの心が健やかに発達するように心がけています。
大切なのは、子どもの特性に合った方針を掲げている園を選ぶことです。
幼稚園と保育園のメリットとは?保育士ママが解説
小学校入学を見据えた園選びでは、それぞれの施設が持つメリットを知ることが成功の近道です。
本章では、保育士としての経験と母親としての目線から、幼稚園と保育園の特徴的なメリットを紹介します。
ぜひ園選びの参考にして、役立ててくださいね。
幼稚園を選ぶメリット
- 小学校に近いカリキュラムで「学び」の準備ができるケースが多い
- 早い時間に帰宅するため、親子の時間を取りやすい
- 園独自の教育方針や特色に触れられる
幼稚園は、家庭での関わりも大切にしつつ、就学前教育を重視したい家庭に向いています。
小学校とのつながりを意識した活動や、英語や体操などの専門的な指導を受ける機会がある施設も多いのが大きなメリットです。
また、保育時間が短いため、幼稚園の放課後に習い事に通いたい親子にもおすすめです。
保育園を選ぶメリット
- フルタイム勤務など働く保護者でも預けやすい
- 異年齢との交流で社会性が育まれる
- 食事・着替え・排泄など生活の自立が促される
保育園は、学びや教育の観点よりも「生活の場」としての側面が強く、日々の生活の中で子どもが育つ工夫が詰まっています。
子どもの大半が保護者が就労していて、長時間の保育の中で過ごしているからこそ、子どもが安心して自分らしく過ごせる環境が整えられているのが特徴です。
生活習慣を身につけるスピードが、幼稚園に通う子どもよりも比較的早い傾向があります。
子ども園という選択肢もある!
近年注目されている施設が、認定こども園です。
幼稚園と保育園の機能をあわせ持ち、教育と保育の両方を一体的に提供する施設として、共働き世帯はもちろん、専業主婦家庭からも人気を集めています。
親の就労状況に関係なく入園できる点が最大の特徴で、「幼稚園の教育も受けさせたいけれど、保育園のように長時間預かってほしい」という家庭には特におすすめです。
こども園によっては、0歳児から5歳児までの一貫したカリキュラムを設けているところもあり、成長に合わせた柔軟な保育・教育を受けられる点も魅力のひとつです。
保育園→幼稚園へ転園するという選択肢もある!
「仕事に復帰したいから最初は保育園に預けたいけれど、3歳児以降は延長保育を利用して幼稚園に通わせたい」といった家庭は年々増えています。
近年は、幼稚園でも延長保育の充実が進み、18時頃までの保育が可能な園も増えてきました。
実際に、0~2歳児クラスまでは保育園に通い、3歳児クラスから幼稚園へ転園するケースも珍しくありません。
共働き世帯でも、園の体制によっては柔軟な選択が可能になってきています。
幼稚園か保育園か?選ぶときに重視するポイント
幼稚園を選ぶか、保育園を選ぶか、園選びに正解はありません。
大切なのは、家庭や子どもに合った園を選択することです。
本章では、保育士として幼稚園と保育園の両方で勤務してきた経験と、母親としての視点から、園を選ぶ際に重視したいポイントを解説します。
- 家庭の生活スタイルに合っているか
- 園の雰囲気と先生の対応
- 子どもに合う環境かどうか
家庭の生活スタイルに合っているか
まず大前提として、園の形態や開園時間が家庭の生活リズムや保護者の就労状況に合っているかを確認することが大切です。
送迎時間や保育時間、園の立地は、毎日の生活に大きな影響を与えます。
見落としがちなのが、毎日の持ち物や制服の有無です。
中には手作りの通園バッグや巾着袋が必須の園もあるので、チェックしてみてください。
無理なく通えることは、子どもだけでなく保護者にとっても心の余裕を生む重要な要素です。
園の雰囲気と先生の対応
園の教育方針や施設の充実度も気になるところですが、何より大切なのは先生たちの雰囲気や先生たちの子どもとの関わり方です。
見学の際は、先生たちの表情や子どもへの声かけの様子をよく観察しましょう。
先生の様子だけでなく、年長児の様子を見ることもおすすめします。
年長児の様子がその園に自分の子どもを預けたときに、自分の子どもが成長する姿とかなり近いのでイメージがつきやすいです。
設備やカリキュラムよりも、毎日接する「人」の存在が、子どもにとっては何より大きな影響力になります。
子どもに合う環境かどうか
園のカリキュラムや先生の良し悪しだけでなく、「わが子に合っているかどうか」を重視しましょう。
集団の中で緊張しやすい子どもなら少人数制の園が合うかもしれませんし、活発に動くことが好きな子なら戸外活動が多く園庭が広い施設がいいかもしれません。
好奇心旺盛ならさまざまな活動が体験できるといいかもしれませんし、遊び重視でひたすら自分の興味関心を突き詰めて遊ぶ園が合う子どももいます。
親だからこそわかる子どもの個性をふまえた園選びが、子どもにとっての心地よい園生活につながります。
【体験談】保育士ママが実際に通わせたのは幼稚園?保育園?
当時、1歳と2歳の子どもたちを保育園に通わせていました。
私自身が保育士として職場に復帰するには、保育園への入園が欠かせなかったからです。
近隣の幼稚園は満3歳からしか入れず、選択肢は自然と保育園に絞られました。
今の園が遊びを重視した保育をしてくれているので、現在は転園も考えていません。
子どもたちがのびのびと好きな遊びに打ち込める姿を見て、親の私も嬉しく思っています。
毎日通う場所だからこそ、「ここが好き」と思える園に出会えたことは、何よりの安心材料です。
まとめ
幼稚園と保育園には、それぞれ異なる良さと特徴があります。
だからこそ、選ぶのに迷ってしまいますが、どちらの施設に預けても、学力や心の成長に差が出るかどうかは一概には言えません。
最終的には、小学校入学後の子どもの学力や心の成長は、家庭での関わり方や子どもの個性による部分が大きいといえるでしょう。
家庭の状況と子どもの性格を照らし合わせながら、最適な園を選んであげてくださいね。