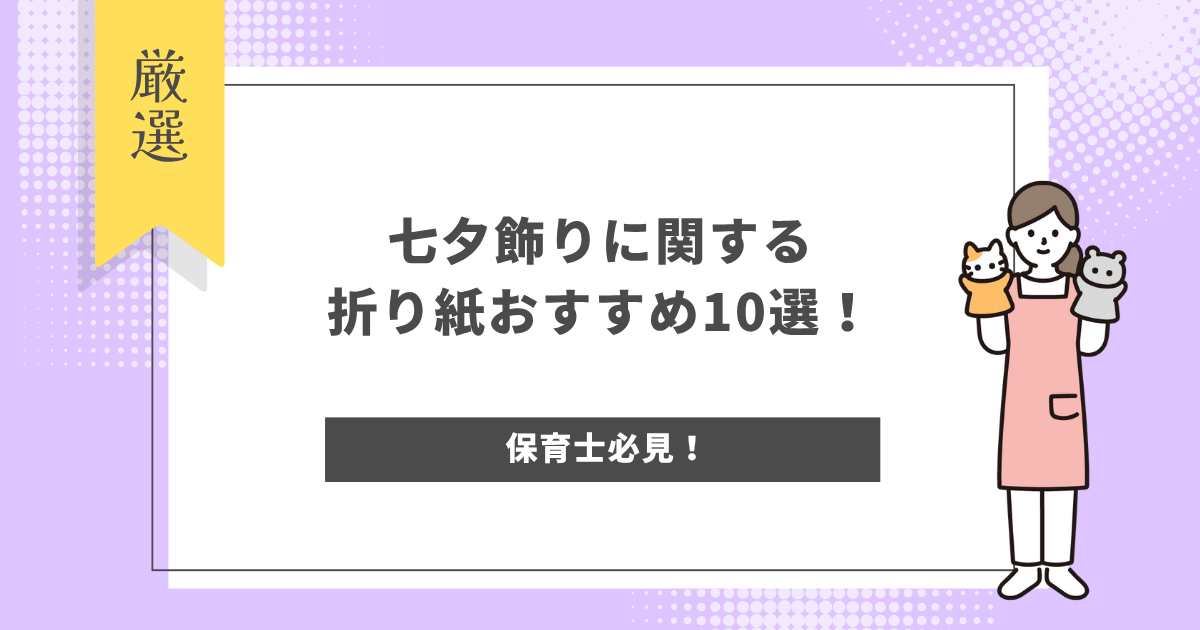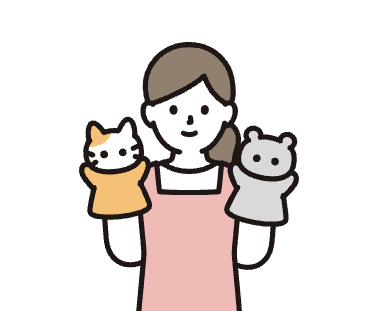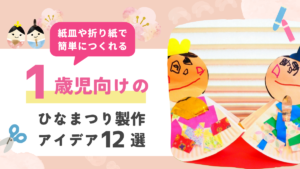7月7日の七夕は、保育園でも季節を感じられる大切な行事のひとつです。
子どもたちは短冊に願いごとを書いたり、カラフルな折り紙で飾りを作ったりして、天の川をイメージした世界を楽しみます。
特に園内では、年齢に合わせた簡単な折り紙製作が大活躍しますよ。
手先を使って集中したり、色や形を組み合わせて自由に表現したりと、遊びながら学べる要素がいっぱいです。
この記事では、簡単にできて見映えもする七夕飾りの折り紙アイデアをたっぷり紹介します。
この記事でわかること
- 保育園で七夕を楽しむためにぴったりな、折り紙を使った製作活動のヒントが得られる
- 七夕の由来や行事の意味を子どもにもわかりやすく伝えるための情報がわかる
- 年齢別に取り入れやすい、簡単で可愛い七夕折り紙アイデアを10種類紹介している
- 折り紙を通じて養える、子どもたちの集中力・表現力・手先の発達など保育的ねらいも学べる
目次
折り紙のねらい・七夕について
七夕の起源
七夕は、古代中国の「織姫と彦星」の伝説をもとに、日本の「棚機(たなばた)」という習わしと合わさってできた行事です。
織姫と彦星が年に一度、7月7日に天の川を越えて会えるというロマンチックな物語は、日本中で親しまれています。
日本では古くから7月7日に願いごとをしたり、織り機で着物を織って神様にささげる「棚機たなばた信仰」もあり、現在の七夕行事のベースとなっています。
今では短冊に願いごとを書く習慣が定着し、子どもたちにも親しみやすい行事になりました。
折り紙のねらい
折り紙は、子どもたちの創造力や集中力、手先の器用さを育むとても大切な製作活動です。
紙を折るというシンプルな動作の中に、「形を理解する」「順序を守る」「完成形を想像する」など、たくさんの学びが詰まっています。
特に保育園では、遊びの一環として取り入れながらも、子どもたちの成長や発達を支える貴重な時間になります。
また、完成した作品を飾ることで達成感を得られるので、自信にもつながるでしょう。
友達と一緒に作ることで、協調性や表現力も育まれます。
七夕飾りの折り紙アイデアおすすめ10選
七夕製作で人気なのが、折り紙を使った華やかな飾り作り。
保育園では、年齢に応じたシンプルな工程で取り組めるものが好まれますよ。
星や天の川、吹き流しなど、色とりどりの折り紙で作る飾りは、子どもたちの創造力も引き出してくれるでしょう。
はさみやのりを使わずにできるアイデアや、たくさん繋げて飾れる連続折りなども人気です。
ここでは、保育士さんがすぐに取り入れやすく、子どもたちも夢中になるおすすめの折り紙飾り10選を紹介します。
笹の葉