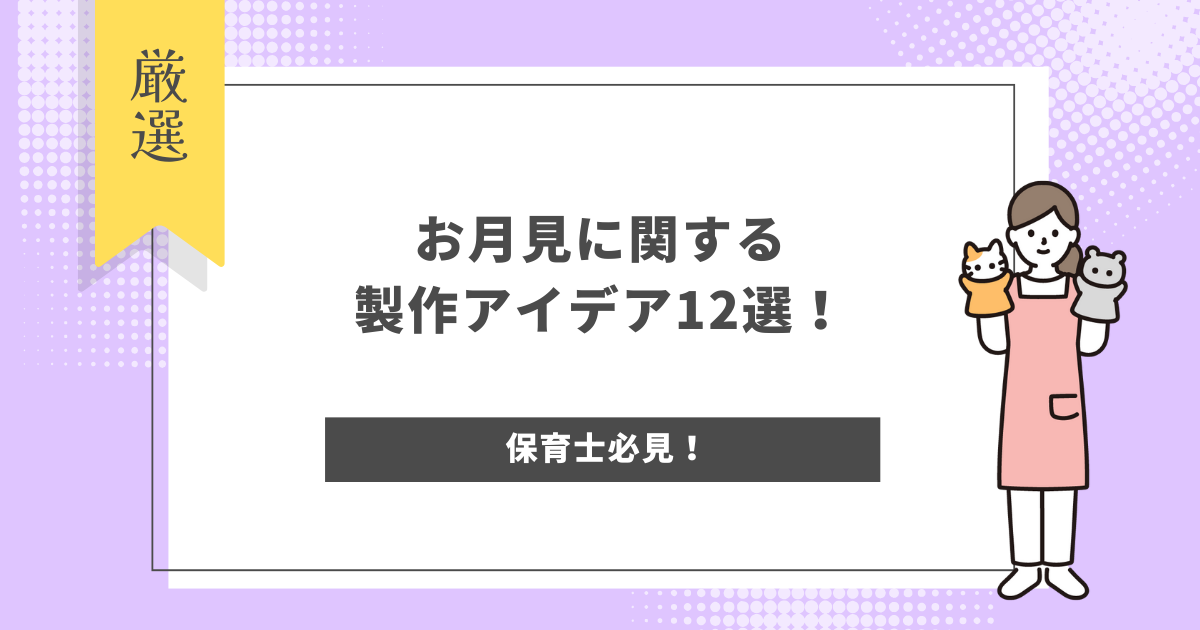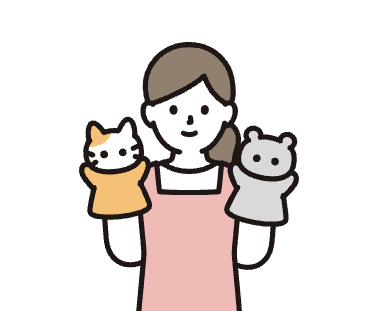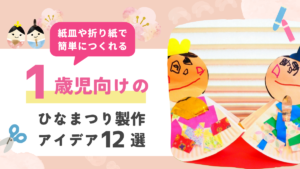お月見は秋を代表する行事の1つです。
自然を感じ、日本の文化に触れられるお月見はぜひ保育に取り入れて楽しみたいですね。
お月見を製作活動に取り入れたいと考える保育士さんは少なくありませんが、「お月見に関する製作って何をしたらいいの?」「年齢に合った製作ってどんなもの?」と悩んでしまうこともありますよね。
本記事では、おすすめのお月見製作を年齢別にご紹介します。
子どもたちと一緒にお月見にちなんだ製作を楽しみましょう!
- お月見は中国から伝わり、収穫祭としての意味が加わるなどして現在の形に受け継がれている。
- 保育園でお月見製作をすることは、季節を感じたり文化を知ったりするきっかけになる。
- 各年齢別のおすすめのお月見製作を紹介している。
 あん【元保育士ライター】
あん【元保育士ライター】暑さが和らぎ、ほっとする心地よい季節。
子どもたちと一緒に秋の訪れを味わい、楽しめる製作をご紹介します。


あん先生 元保育士ライター
保育士歴11年、現在は2児の母です。公・私立園それぞれで正規・非正規保育士として働いた経験を活かし、役立つ情報をわかりやすくお伝えします。
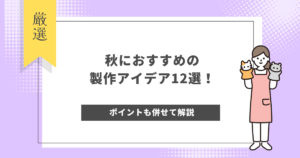
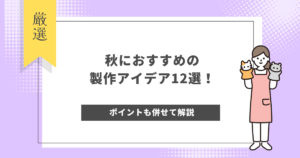
お月見(十五夜)とはどんな行事?
お月見は、すすきやお団子、果物などを月にお供えしたり月を観て楽しんだりする、風情のある行事ですよね。
そもそも、お月見(十五夜)にはどんな歴史があるのでしょうか。
お月見の由来やお月見製作のねらいについてお伝えします。
お月見の由来や歴史は?
旧暦の8月15日を「中秋」といい、この時期の月が特に美しいことから「中秋の名月」と呼ばれています。
中秋の名月を楽しむ十五夜は中国から伝わった貴族の行事でした。
のちに秋の収穫を祝う行事や芋類の収穫祭として行われるようになったことから「芋名月」とも呼ばれ庶民にも親しまれるようになり、今に受け継がれています。
保育園でお月見の製作を行うねらいとは?
子どもたちにとって行事に親しむことは、その土地の文化や風習を知ったり自然の移り変わりを感じたりできる意義深いものです。
製作活動をすることは行事について知るきっかけになりますし、より身近なものに感じることに繋がります。
製作を通して、楽しみながら月の美しさを感じたりお月見に興味を持てたりすると良いですね。
【0~1歳児におすすめ】お月見の製作4選
0~1歳児においては、製作活動を通して色々な感覚を楽しむことが大切です。
本章では、「つぶす」「破る」「丸める」など、0~1歳児の子どもたちがいろいろな感覚を感じ、楽しんで取り組める製作遊びをご紹介します。
「ペタペタするね」「びりびり~」など、子どもの行動や気持ちを代弁しながら楽しい雰囲気で取り組むと良いですね。
ポンポンスタンプの月見だんご
月見団子をスタンプ(たんぽ)で作る作品です。
ガーゼでスポンジを包む手順では、スポンジの代わりに綿を使っても作れます。
また、三方の上を狙ってスタンプするのが難しいと感じる場合は、別の黒い画用紙にスタンプしたものを切って貼り付けると良いですよ。
“ポン”と押すと白い丸が生まれる面白さを一緒に感じながら作ってくださいね。
- 画用紙(黒、茶、うす茶、黄色)
- スポンジ
- ガーゼ
- 輪ゴム
- 絵の具(白)
- 画用紙で三方を作り、台紙に貼っておく
- スポンジにガーゼを巻いて輪ゴムでしばり、スタンプを作る
- スタンプに絵の具をつける
- 三方の上の辺りにスタンプする
- 月を貼って完成
- アレンジ1…スタンプに持ち手をつけると、年齢が低くてもスタンプしやすいです
- アレンジ2…画用紙で作ったうさぎやすすきなどを貼るとお月見らしい雰囲気がアップします
立体だんごと足形うさぎ
丸めた紙粘土を台紙の上でつぶしたり握ったりして遊んで作る作品です。
動画では、きれいに作った団子を並べてからつぶすという手順を紹介していますが、一緒に紙粘土をこねたりちぎったりしたものを台紙に貼り付ける方法でも、感触を楽しめる活動になりますね。
足形うさぎは、乾いてから顔を描くとうさぎであることが分かりやすいですよ。
- 画用紙(黒・うす茶色・白・黄色)
- 筆
- 絵の具(白)
- 紙粘土
- 筆を使って子どもの足の裏に絵の具を塗る
- 台紙の黒い画用紙に足形をスタンプする
- 手の指に白い絵の具を塗ってスタンプし、うさぎの耳にする
- 紙粘土を丸めて団子を作る
- 三方の上に団子を置く
- 団子をつぶしたりつついたりして感触を楽しむ
- 画用紙を円く切った月を貼ってできあがり
絵の具とクシャクシャで2種類のお月様
2種類の製作を一度にご紹介しています。
絵の具をラップの上から指で広げる工程では、不思議な感触や色が混ざる面白さを一緒に感じ、気持ちを代弁しながら取り組むと良いですね。
また、くしゃくしゃにした月に子どもが色をつけるのが難しい場合は、子どもがなぐり書きした絵を円く切り抜いたものを丸めて楽しむというやり方もできます。
- 画用紙(白・黄色・黒・薄茶色)
- 絵の具(白・黄色)
- ラップ
- クレヨン
- デコレーションボール
- 丸シール(白)
- 型抜きした星または星のシール
- 白い画用紙を円く切り、黄色と白の絵の具を乗せる
- ラップをかぶせて、絵の具を指で広げたら1つ目の月が完成
- 黄色い画用紙を円く切ったものをくしゃくしゃに丸める
- オレンジ色のクレヨンで色をつけて2つ目の月が完成
- 大きめに円く切った黒の画用紙に作った月を貼る
- うさぎ(黒)や三方の形に切った黒の画用紙を重ねて貼り、白のデコレーションボールを貼って団子にする
- もうひとつの月を台紙に貼る
- うさぎ(白)と三方の形の画用紙を貼り、白の丸シールを貼って団子にする
- 周りに星のシール(又は型抜き)を貼って出来上がり
フラワーペーパーのお月見リース
円く貼ったフラワーペーパーを月に見立てたかわいいリースです。
フラワーペーパーを丸める作業は事前にしておくと、じっくり楽しんで取り組めますね。
できたものに穴あけパンチで穴を空け、リボンなどを通して吊り下げられるようにすると飾って楽しめますね。
のりは両面テープを代用すると、製作中に乾く心配がなくなりますよ。
- 紙皿
- カッター
- のり
- フラワーペーパー(白・黄)
- 画用紙
- クレヨン
- 画用紙(白)
- 紙皿の内側の円を、1部をつなげて切る
- フラワーペーパーを丸める
- ギザギザの円の部分にのりを塗って丸めたフラワーペーパーを貼り付ける
- 画用紙でうさぎの耳を作って貼る
- うさぎの顔を描いてできあがり
【2~3歳児におすすめ】お月見の製作4選
2~3歳児になると「お月様を作ろうか」等と伝えると、“月を作る”という目的を意識しながら製作を楽しめるようになってきます。
この年齢でも楽しめる「月」をテーマにした絵本を見たりすることで、興味を持ってお月見製作に取り組めますね。
動きや感触を楽しめる製作や、飾って楽しめる作品をご紹介しますので、参考にしてみてくださいね。
紙粘土で餅つきうさぎ
お餅の様に丸めた紙粘土を手でのばして遊んだら、うさぎがついているお餅になるという、楽しい製作です。
餅つきというものに馴染みがない子どもが多い事が予想されますので、餅つきが何なのかを事前に伝えておくと良いですね。
動画の様にきれいな形に紙粘土を伸ばさなくても良いので、それぞれが思うお餅の伸ばし方を楽しみましょう。
- 画用紙(紺・茶・白・黄)
- 紙粘土
- 星の型抜き
- 紺の画用紙の台紙に、うすの形に切った茶色の画用紙を貼る
- 紙粘土を丸めてうすに乗せる
- 手で紙粘土をのばす
- 画用紙で作ったうさぎときねと月を貼る
- 型抜きした星を貼ってできあがり
- アドバイス…星の型抜きをしたものを子どもが貼る場合は、小さすぎると難しいので少し大きめの星がおすすめです
こすると出てくるお月様
黒い画用紙に黄色い月が生まれる、楽しい製作です。
紙をめくる工程では、「どんな月ができるかな」等と期待を持てる言葉がけをすることで、ワクワク感を感じながら取り組めます。
お団子はシール貼りで作れますし、顔が描ける場合はうさぎの顔を描いても良いですね。
発達に合わせて取り組む内容を工夫しましょう。
- 画用紙(白・黒・茶)
- 絵の具(黄・白)
- 筆
- 星の型抜き
- 円く切った白の画用紙に、黄色と白の絵の具を塗る
- 黒の台紙の画用紙に、絵の具で塗った紙を重ねてこすってはがす
- うさぎや三方、団子の形に切った画用紙を貼る
- 最後に星の形に型抜きしたものを貼ってできあがり
- アレンジ…筆で隅々まで塗るのが難しい場合は、円い紙に黄色と白の絵の具を乗せ、ラップをかぶせた上から手で絵の具を塗ると簡単で楽しいですよ
お月見サンキャッチャー
紙をビリビリと破る感触や、ペタペタと貼り付ける工程を楽しめる製作です。
フラワーぺーパーは、黄色の割合を多めに準備すると月らしい色合いになりますよ。
貼り付けるときに紙の端までしっかりくっついていなくても、最後に上からのりで貼るのであまり気にしなくても大丈夫です。
出来上がった作品を一緒に眺めて楽しめるのも、素敵な時間になりますね。
- フラワーペーパー(黄・白)
- クッキングシート
- のり
- 画用紙(黒)
- 穴あけパンチ
- 糸
- フラワーペーパーを破る
- クッキングシートを半分に折る
- 折った片方にのりを塗り、破いたフラワーペーパーを貼る
- もう片方にものりを塗り、挟んでくっつける
- 円く切る
- うさぎ(黒)を貼る
- 穴を空けて糸を通したらできあがり
- アドバイス…サンキャッチャーなので、窓際などの光が当たる場所に吊るして飾ると光が透けてきれいですよ
塩でザラザラお月様
塩を使った面白い製作です。
動画ではスポンジをそのまま使っていますが、2~3歳児には少し難しいかもしれませんので、持ち手を付けると良いでしょう。
また、絵の具の色は黄色とオレンジ色に加えて白を使っても月らしいです。
塩を振りかけるときは、お料理気分で楽しめますね。
ぜひ一緒にザラザラの感触を楽しんでください。
- 画用紙(グレー・白・黄・薄茶)
- テープ
- 絵の具(黄・オレンジ)
- スポンジ
- 塩
- グレーの台紙の上に円くくりぬいた画用紙を乗せ、テープで固定する
- 黄色とオレンジ色の絵の具をスポンジを使ってスタンプする
- 上の画用紙を外し、絵の具の部分に塩を乗せる
- 絵の具が乾いたら余分な塩を落とす
- 画用紙で作った団子や三方、おばけを貼ってできあがり
- アドバイス…おばけをうさぎにするなど、下の部分は自由に変えましょう
【4~5歳児におすすめ】お月見の製作4選
4~5歳児になると、工程が多かったり少し難しかったりするものにも取り組めるようになってきます。
また、自分なりのやり方で工夫しようとする様子も見られるようになってきます。
アイデアや工夫を認め、のびのびと製作活動に取り組める雰囲気だと良いですね。
お月見という行事を、製作を通して身近に感じてみましょう。
じゃばらで!お月様
おりがみをじゃばらに折る作業は難しくはありませんが、同じものを4個作る必要があります。
同じ作業が続くので、集中が続かない場合は保育士と一緒に作ったり、1度に作ろうとせずに分けて作ろうとしたりするといった工夫をすると良いですね。
穴あけパンチで穴を空ける箇所にあらかじめセロハンテープを貼っておくと、補強されるのでおすすめです。
- おりがみ(黄)
- 穴あけパンチ
- リボン(青)
- 画用紙(白・黒)
- 両面テープ
- おりがみを2cm程度の幅でじゃばらに折る
- 折り終えたら半分に折り、のりで貼って扇形にする
- 同じものを4個作る
- 4個を貼り合わせて円にする
- 穴を空けてリボンを通す
- 雲の形に切った画用紙を両面テープで月に貼る
- うさぎの形に切った画用紙に顔などを描き、両面テープで月に貼って完成
- アドバイス…うさぎの顔を描く、雲を切る等子どもに合わせて取り入れましょう
スパッタリングの月とすすき
ブラシに絵の具をつけ、網をこすることでしぶきを飛ばすスパッタリングは、ステンシルにぴったりの技法です。
動画では黄色のみでの製作となっていますが、白の絵の具を重ねて作っても良いですね。
うさぎの形の画用紙は保育士が用意しても良いですが、子ども自身がうさぎなどの形を書いて切り取って作っても個性が現れて素敵です。
- 画用紙(黒・白)
- 絵の具(黄)
- スパッタリング用金網
- ブラシ(歯ブラシでもOK)
- おりがみ(薄茶)
- 黒の画用紙を円く切り、その上にうさぎの形に切った画用紙を重ねて置く
- ブラシに黄色の絵の具をつけてスパッタリングする
- おりがみを3分の1程度のところに折り筋をつけ、細かく切り込みを入れたら細く巻いてすすきを作る
- 絵の具が乾いたらうさぎの型を外す
- 雲の形に切った画用紙とすすきを貼り付けたらできあがり
走る紙コップうさぎ
とことこ動く様子がかわいい、作って楽しく遊んで楽しい製作です。
乾電池をセロテープでとめるときは、はがれないようにしっかり貼り付けましょう。
耳や足をのりで貼り付けるのが難しい場合は、両面テープを使っても良いですね。
十五夜とうさぎの関係を伝えた上で製作に取り組むと、製作への意欲や行事への理解につながります。
- 紙コップ
- 乾電池
- 輪ゴム
- セロハンテープ
- 画用紙(白)
- のり
- ペン
- 紙コップの縁の両端に2か所ずつ切り込みを入れる
- 切り込みを外側に折る
- 乾電池に輪ゴムを付けてセロハンテープでとめる
- 紙コップの切り込みに輪ゴムをかける
- 切り込みを外側に折ってセロハンテープでとめる
- 耳や足を貼り付ける
- ペンで顔を描いてできあがり
- アドバイス…たぬきやきつねを作っても、秋のお月見らしさが出ますね!
スクイーズ!?立体お月見アート
シェービングフォームとボンドを混ぜたものを使うと、乾いたときにスクイーズのように弾力のある月や団子ができる面白い製作です。
もこもこ泡が乾いた後、動画ではクレヨンでうさぎやすすきを描いていましたが、他にも折り紙で折ったうさぎを貼り付けるなど、アレンジ次第で色んな作品になります。
みんなで作品を触り合って楽しめますね。
- シェービングフォーム
- ボンド
- 食紅
- 容器
- スプーン
- 画用紙(紺・茶)
- 台紙の画用紙に、三方の形に切った画用紙を貼っておく
- 容器にボンドとシェービングフォーム、食紅を入れて混ぜる(黄色の食紅を入れるものと、食紅を入れないものの2書類作っておく)
- 台紙に三方の形を画用紙で作ったものを貼っておく
- スプーンを使って、②を台紙に乗せ、団子や月を作る
- 乾いたらうさぎやすすきの絵を描いてできあがり
まとめ
それぞれの年齢に合った製作をご紹介してきましたが、できる事には個人差があるので、まずは目の前の子どもたちに合っているかどうかを考えてみてください。
その上で、それぞれにとって良い製作の方法を見つけてくださいね。
製作活動でのびのびと表現することを通して、楽しみながらお月見に親しめるよう願っています。