お泊まり保育は一晩親元を離れ、普段とは違った場所に泊まる、年長児にとって特別な一大イベントです。
また、子どもたちの自立心や協調性を育み、卒園前の思い出作りをする大切な機会でもあります。
ここでは、お泊まり保育のねらいや指導案の書き方、注意すべきポイントなどについて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- お泊まり保育とは、子どもたちの成長と思い出作りにぴったりな年長児だけの特別なイベント
- 指導案は子どもたちの姿とねらいを十分に理解して作成することで、お泊まり保育を成功させる鍵になる
- お泊まり保育のねらいは、子どもたちの心の成長を促し、卒園前の大切な思い出作りをすること
- 子どもたちが安心・安全に過ごすためには保育者の細かな配慮と注意が必要不可欠
 Takako【元保育士】
Takako【元保育士】友達や先生とお泊まりできる体験は年長児ならではの行事で、普段とは違った特別な経験です。
お泊まり保育のねらいをしっかりと理解し、安全で楽しい体験を提供してくださいね。


Takako先生 元保育士ライター
保育士歴7年、現在は男女2児の母をしています。保育現場で培った経験や知識を活かし、悩んだり困ったりしている保育士の方、保育士を目指している方の力になれるような記事を心がけています。
お泊まり保育とは?
お泊まり保育とは、子どもたちが普段通っている幼稚園や保育園、近隣の施設などに一晩泊まり、友だちや先生と特別な時間を過ごす行事です。
子どもたちの自立心や協調性を育み、キャンプファイヤーや夕食作りなど、普段とは違う環境の中で貴重な体験ができます。
実施時期や宿泊場所、費用など詳しく見ていきましょう。
お泊まり保育の実施時期
年長児を対象に、7月〜8月ごろの夏に行われます。
夏は夜間でも寒さを感じず過ごしやすく、キャンプファイヤーや花火などの活動がしやすいうえに1年の中でも行事が少ない時期です。
そのため、この時期にお泊まり保育をするのが一般的です。
宿泊場所
宿泊場所は、子どもたちが通い慣れている保育園や、近隣の公共施設、自然豊かなキャンプ場などが一般的です。
安全性や衛生面を考慮し、園児が安心して過ごせる環境が選ばれます。
宿泊日数
多くの保育園では1泊2日で実施されますが、園によっては日帰りの形を取ることもあります。
園児の体力や生活リズムを考慮し、無理のない日程が組まれます。
お泊まり保育の費用
1人あたり数千円〜1万円程度が一般的です。
この金額には、宿泊施設代・食事代・交通費・保険料などが含まれており、保護者の負担方法は園によってさまざまです。
- 実費分を一括徴収
- 料金確定後に分割した金額を毎月の保育料に上乗せして支払う
- 事前に徴収した積立金の中からまかなう
お泊まり保育のねらい
お泊まり保育のねらいは、子どもたちの自立心や協調性を育み、仲間との絆を深めることです。
普段とは違う環境での特別な体験を通して、挑戦する気持ちや達成感、仲間と協力することを味わいながら、豊かな感性や社会性を育てることを目指します。
本章では、具体的なねらいについて詳しく解説します。
自立心と自己肯定感を育む
- 自分の身の回りのことを自分で行う習慣を身につける
- できた!という達成感を積み重ねる
- 仲間と助け合いながら行動する中で自信を深める
お泊まり保育では、最低限の身の回りのことを自分たちでする必要があります。
それにより自立心を育み、自分でできた喜びを経験することで自己肯定感が高まります。
また、仲間と協力して活動する中で、自分や他者の存在、役割の大切さを実感することでさらに自信が深まるでしょう。
協調性と仲間意識を養う
- 仲間と役割を分担し協力して活動する
- 相手の意見や気持ちを受け止める姿勢を養う
- 助け合いながら共通の目標を達成する
お泊まり保育では、少人数のグループに分かれて活動するため、夕食作りや後片付け、ゲームなどで役割分担をし助け合う場面が多くあります。
相手の意見や気持ちを聞く、受け止める、目標に向かって助け合うといった経験を通して協調性や仲間意識を養います。
仲間と達成感を共有することで信頼関係が深まり、仲間意識や集団の一員としての自覚が育まれるでしょう。
規則正しい生活習慣を身につける
- 早寝早起きのリズムを意識して過ごす
- 食事や就寝、起床などの時間を守る
- 集団生活の中で基本的なマナーを身につける
お泊まり保育では、食事・活動・就寝・起床といった一日の流れが時間で決まっており、子どもたちはその中で生活をします。
園外や特別な環境でも時間を守って行動することで、生活リズムの大切さを感じるでしょう。
また、あいさつや食事のマナーなど、基本的な習慣を身につけ、家庭でも継続できる力を養います。
人との絆を深める
- 友だちや保育者との交流を深める
- 共に過ごす時間を通して信頼関係を築く
- 思い出を共有し仲間意識を強める
日中だけでなく夜や翌朝まで一緒に過ごすことで、普段の保育時間では得られない深い交流が生まれます。
その中で仲間と協力しあい、楽しい時間を共有することで信頼関係が強まります。
また、一緒に作り上げた経験や思い出は仲間意識を高め、園生活の中での絆をより強固にします。
こうした経験は小学校進学後の人間関係にも良い影響を与えてくれるでしょう。
保育園での特別な思い出をつくる
- 日常では味わえない特別な活動を体験する
- 仲間と過ごす非日常の時間を楽しむ
- 思い出を通して園生活への愛着を深める
お泊まり保育は、仲間と一緒に夕食を作ったり、キャンプファイヤーをしたりと普段の保育とは違った、特別な経験をすることができます。
その非日常でかけがえのない体験は、園生活への愛着を深めるとともに、子どもたちにとって温かく鮮やかな思い出として残るでしょう。
お泊まり保育のスケジュール例
お泊まり保育では、1日をどう過ごすのか気になりますよね?
今回は、保育園に泊まるケースのお泊まり保育のスケジュール例をみてみましょう。
<1日目>
8:00〜9:00 通常通り登園・朝の会
9:00〜15:00 通常保育・遊びや制作、特別活動(スイカ割り、ゲーム、クッキングなど)
15:00〜17:00 おやつ・夕食準備・夕食
17:00〜19:00 夜のレクリエーション(キャンプファイヤー、花火など)
19:00〜20:00 入浴・就寝準備
20:00〜21:00 就寝
<2日目>
6:30〜7:30 起床・身支度
7:30〜8:30 朝食
8:30〜10:00 片付け・ふり返り活動
10:00〜11:30 解散・保護者お迎え
普段通りの登園なので子どもたちも安心しやすく、かつ特別な体験も新鮮で楽しめますね。
また、年長児のみ集合時間を設定(13時集合など)して、子どもたちの負担を軽減している園もあります。
お泊まり保育の事前準備
お泊まり保育を成功させるためには、しっかりとした事前準備は欠かせません。
持ち物の確認、安全対策、緊急時の対応方法、保護者との情報共有など細かな配慮が必要です。
ここでは、保育者が注意すべきポイントをわかりやすく説明しています。
ねらいに沿って計画を立てる
お泊まり保育の計画は「自立心を育てる」「挑戦する心と達成感を味わう」など、全体のねらいや目的をハッキリさせましょう。
子どもの年齢や体力、興味に合わせて無理のないスケジュールを組み、安全対策や緊急時の対応も計画に盛り込みます。
全体の流れや細かな部分を丁寧に見直しながら、ねらいをしっかり達成できる計画を心がけてくださいね。
また、計画したねらいや目的を子どもたちにもわかりやすく伝え、お泊まり保育への意欲や理解を高めることも大切です。
保護者への連絡
お泊まり保育を円滑に進めていく上で、保護者への十分な連絡は必要不可欠です。
事前説明会や案内文などで、持ち物や当日のスケジュールを詳しく伝えましょう。
また、迅速に連絡をとれるよう緊急連絡先を一覧にする、最寄りの病院や緊急時の避難場所などを明確にするなど、緊急時の対応方法をしっかり共有することで、保護者も安心して子どもを預けられます。
子どもたちの心の準備
子どもたちが安心してお泊まり保育に参加できるよう、事前に楽しみなことや不安なことなどを共有し、その気持ちを受け止めることで安心感が生まれます。
家庭での子どもたちの様子などを保護者から聞くなどして、さらに不安がある子には個別に寄り添い、安心グッズの持参の検討など安心して参加できるようにしっかりと心の準備をサポートをしましょう。
関連する絵本を読む
お泊まり保育の前に関連する絵本を読むことは、子どもたちの不安を和らげ、お泊まり保育の流れや楽しさをイメージしやすくなり、心の準備がしやすくなります。
以下におすすめの絵本を紹介しますので、参考にしてください。
- おとまりのひ
- 初めてのキャンプ
- ころちゃんのおとまり
- しまうまのズー はじめてのおとまり
これらの絵本は、初めてのお泊まりに対するドキドキや不安感、仲間と協力することの大切さをテーマにしています。
楽しい体験や達成感を味わうことで自己肯定感が育まれる内容になっています。
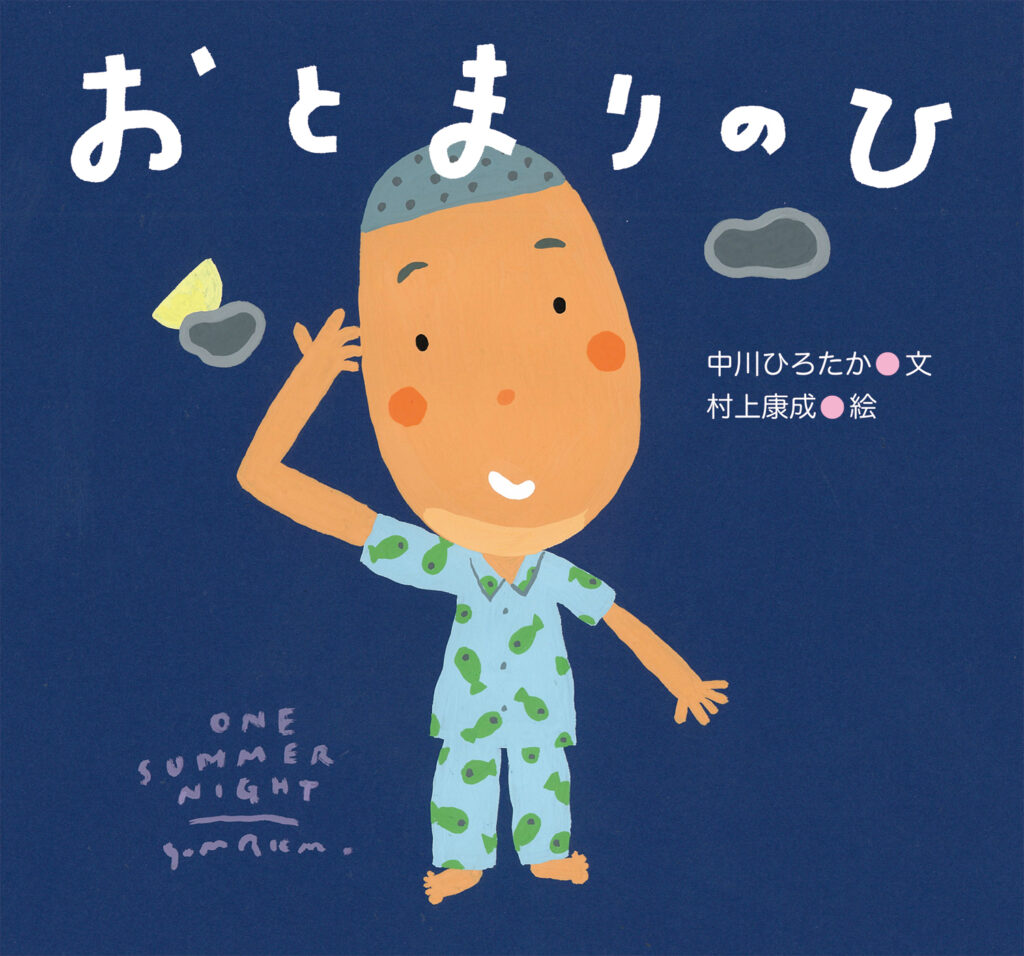
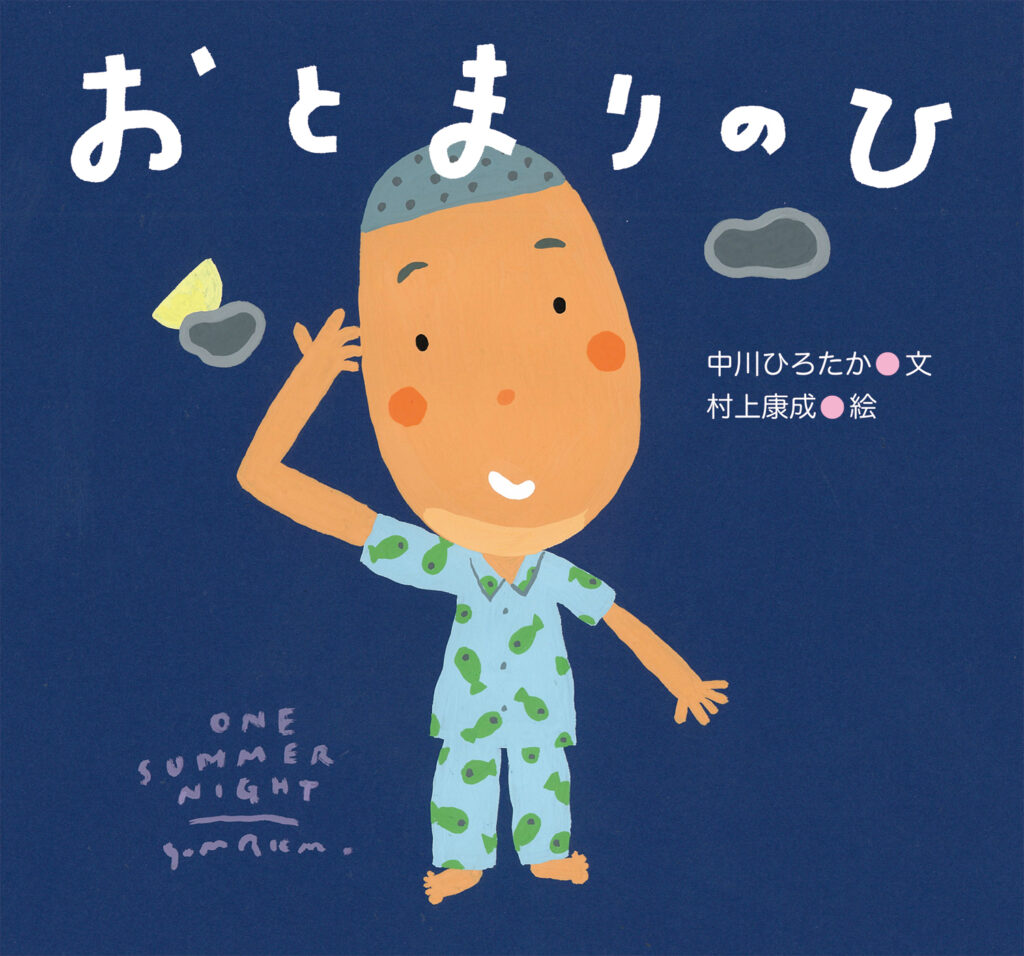
お泊まり保育のテーマに合わせた活動
お泊まり保育の活動は、事前に設定したテーマに合わせた活動を立てましょう。
たとえば、設定したねらいが「仲間意識を深める」なら、グループに分かれて宝探しゲームを取り入れるなど、目的を明確にし、それに沿った活動を選びます。
その際、子どもたちの発達段階や興味に合わせて、無理のないスケジュールにすることが大切です。
安全面のリスクを事前に想定し対策を計画に組み込むことで、子どもたちにとっても安心で楽しい経験ができる環境を整えることができます。
お泊まり保育に持っていくもの
お泊まり保育で必要な持ち物をしっかり準備することで、子どもたちが安心して楽しく過ごせます。
基本の持ち物や便利なアイテムを紹介しますので、状況に合わせて準備してくださいね。
- 着替え一式(下着・シャツ・ズボンなど)
- 寝巻き(パジャマなど)
- タオル・ハンドタオル
- 歯ブラシ・コップ
- おむつ・おしりふき(必要な場合)
- 室内履き(上履き)
- 保険証のコピー(園指定の場合)
お泊まり保育で必要な持ち物は、子どもが安心して快適に過ごすための基本的なものを中心に準備します。
また、クラスリーダーや主任と相談しながら、より安心感を与え、万が一に備えたアイテムなどを用意するのもおすすめです。
- お気に入りのタオルケット
- 軽い防寒着(夜や冷房対策に)
- 水筒やマイボトル
- 予備のビニール袋(汚れ物入れ)
各持ち物の目立つ場所に、はっきりと名前を書いてもらいましょう。
それにより、子どもたちも保育者も持ち物をすぐに見分けられ、紛失防止につながります。
お泊まり保育で注意したいことと配慮するポイント【元保育士が解説】
お泊まり保育は子どもたちにとって特別な体験ですが、安心・安全に過ごすためには細やかな配慮と注意が欠かせません。
体調管理はもちろん、アレルギー対応、環境整備など、子ども一人ひとりの状況に合わせた準備と見守りが重要です。
本章では、元保育士の視点から具体的な注意点と配慮ポイントを解説します。
アレルギーや持病への対応を徹底する
子ども一人ひとりのアレルギーや持病について正確に把握し、対応を徹底することが重要です。
事前に保護者から詳しい情報を聞き取り、食事や活動内容に配慮しましょう。
- アレルギー児や持病のある子の情報や投薬の有無を職員間で共有する
- アレルギー児には一対一で固定の保育者をつける
- アレルギー児の給食提供や持病のある子への投薬の際は、2名以上の保育者で確認を行い、固定の保育者が担当する
- 緊急時に備えた救急セットや薬(エピペンなど)の保管場所・使用方法の確認を徹底する
お泊まり保育は普段と違う特別な行事です。
イレギュラーな行事では、普段は気をつけられていることも見落としがちになるため、特に注意が必要です。
おねしょなども他の子には気づかれないように配慮
年長児でも、トイトレがどこまで進んでいるかは一人一人違います。
夜間のみオムツを着用している子もいれば、おねしょをしてしまう子、完全にトイレで排泄ができる子もいます。
5歳、6歳ごろの子どもたちはオムツをしていることや、おねしょをしてしまうことに恥ずかしさを覚えることもあるでしょう。
そういった子に対しては、保育者の近くや出入り口の近くで寝かせるなど配慮し、安心して過ごせる環境づくりが大切です。
保育者は子どもの様子に注意を払い、異変に気づいたらすぐに対応し、子どもの自尊心を大切に守ってあげてくださいね。
保護者も安心できるよう情報共有しながら進める
事前にスケジュールを伝えていても、何をして過ごしているのか、楽しめているのかなど保護者にとっても不安や心配はつきものです。
保護者からの質問や相談にも丁寧に対応することで、信頼が深まるでしょう。
また、連絡アプリや園のSNSなどがあればこまめに写真を載せるなど、子どもたちの様子が常にわかるようにするとより安心感が高まります。
情報共有を密にし、信頼関係を築きながら進めましょう。
グループのメンバー構成は性格や相性など配慮
グループのメンバー構成は、子どもたちの性格や相性を考慮して決めることが大切です。
仲良し同士で安心感を持てる場合もあれば、異なるタイプの子ども同士が刺激し合うこともあります。
また、明確にリーダーを決める必要はありませんが、グループを引っ張っていってくれる子、みんなの意見をまとめる子などがいると、活動が円滑に進みやすくなります。
保育者は子どもたちの普段の様子や関係性を把握し、バランスよくグループを編成しましょう。
【元保育士おすすめ】お泊まり保育でやってみて!おすすめイベント
お泊まり保育は、子どもたちにとって特別で楽しい思い出づくりの絶好の機会です。
本章では、子どもたちの笑顔があふれる人気のイベントを紹介します。
それぞれのイベントのおすすめの理由とねらいも紹介しています。
キャンプファイヤー
キャンプファイヤーはお泊まり保育におけるイベントの中でも、一大イベントといえます。
炎を囲む経験は、非日常感を感じることができ、子どもたちのワクワク感をさらに高めてくれます。
歌やゲームなどを全員で楽しむ時間は、一体感を高め、友達との絆を深めるきっかけにもなり、火のあたたかさや揺れる炎の美しさが心を落ち着かせ、思い出として長く心に残ります。
- 特別な雰囲気の中、仲間と過ごすことで繋がりや一体感、思い出を深める
- 炎のゆらめきやあたたかさ、薪が弾ける音など、自然の音や感覚を全身で味わう
- 歌やゲーム、劇などを通して表現力や協調性を育む



皆んなでキャンプファイヤーを囲んだ記憶は、炎のあたたかさや笑い声とともに、心に深く刻まれる宝物になりますね!
スイカ割り
スイカ割りは夏らしい季節感を楽しめるイベントで、子どもたちのワクワク感を高めます。
目隠しをしてスイカを探す過程では、友だちの声を頼りに進むため、協力や助け合いの気持ちが自然に育まれます。
また、割れた瞬間の達成感や歓声、みんなで分け合って食べる喜びは、お泊まり保育ならではの特別な思い出になります。
- 夏ならではの遊びを通して、季節感のある遊びを楽しむ
- 友だちの声やアドバイスを頼りに協力し合う力を育む
- 割る瞬間の達成感や喜びを共有し、仲間との絆を深める
季節感を感じながら協力して楽しめるスイカ割りは、思い出づくりにぴったりのイベントで、お泊まり保育におすすめです。
夜の自然観察
静かな夜の園庭で普段とは違う雰囲気の中、虫の声や風の音、星空を感じる特別な時間を楽しめます。
普段なかなか触れられない自然の不思議や美しさに目を向けることで、子どもたちの感性や観察力を育みます。
- 夏の夜の自然に触れ、感性を刺激する
- 仲間と一緒に静かな時間を過ごし、安心感や絆を深める
- 自然とのふれあいを通して心を落ち着ける
自然とふれあいながら感性を刺激する体験は、お泊まり保育にぴったりのおすすめイベントです。



夜空と虫の声に囲まれた特別な時間が、心を落ち着けるすてきな時間になりますね。
花火
暗闇に広がる鮮やかな色とりどりの光や音が、子どもたちの感性を刺激しワクワク感を高め、特別な体験として思い出に残ります。
また、みんなで共有する喜びは、仲間との絆を深める貴重な時間となるでしょう。
- 夏の風物詩を感じ、季節感や自然への関心を深める
- 花火の美しさや儚さを感じ、感受性や情緒を豊かにする
- 仲間と一緒に花火を楽しむ時間を通して、絆をさらに深める
花火は季節感、特別感を感じられる楽しいイベントなのでおすすめです。
【保育園のお泊まり保育】指導案の書き方
安全で楽しいお泊まり保育を成功させるためには、指導案は必要不可欠です。
本章では、指導案を書く際のポイントや配慮すべきことなど、具体的に紹介しますので参考にしてください。
指導案作成時のねらいに関しては、次の章で解説しています。
活動内容
- レクリエーション(スイカ割り・縁日ごっこ・宝さがし)
- 夕食づくり体験
- キャンプファイヤー
レクリエーションは、季節感や特別感があるものを選ぶと盛り上がり、特にスイカ割りや縁日ごっこは季節感もあるのでおすすめです。
夕食づくり体験では、子どもたちが協力して簡単な調理や準備をし、役割分担や協力することの大切さを学びます。
また、自分たちで作った食事を味わうことで、達成感や自立心、作り手への感謝の気持ちも育まれます。
キャンプファイヤーは火を囲み歌やゲームを楽しみ、仲間との絆を深める特別な時間です。
活動を通して、子どもたちの自主性や友情を育てる、季節感を感じられるもの、特別感を感じられるものなどを選ぶと良いでしょう。
環境構成
- 子どもが自由に動き回れる広さの確保
- 適切な照明と安心できる就寝環境の準備
- 緊急時の対策と避難経路の確認
お泊まり保育では、子どもたちが安心して活動できる環境を用意することがポイントです。
子どもが自由に動き回れる十分なスペースを確保し、活動中も快適に過ごせる環境を整えましょう。
就寝時の照明は、保育者が子どもの様子を確認できる最低限の明るさを確保します。
また、日中は平気でも就寝時に寂しさが込み上げてくる子もいます。
そのようなときは、保育者がそばに座り静かに背中をさするなどして、安心できるように配慮しましょう。
救急バックの中身・使い方など、万が一の緊急時に迅速に対応できる対策を整え、避難経路もしっかりと確認して書き出しておくと安心です。
予想される子どものすがた
- 仲間と協力し楽しむ姿が見られる子がいる
- 自分でできることに挑戦し自信がつく子がいる
- 初めての夜に緊張や不安を感じて、泣いてしまう子がいる
行事や活動の中で予想される子どものすがたを、具体的にイメージすることが重要です。
お泊まり保育を通して、子どもたちはさまざまな体験から自信や自主性を育むことができます。
活動の中でうまくいったことに対し、具体的に褒めるなどして次の意欲につながるよう声かけをしましょう。
その一方で、親元を離れることにより寂しさを感じる子などもいるかもしれません。
それぞれの姿に合わせた具体的な対応策を記入しておくことで、当日の保育者間の連携がスムーズになり、子ども一人ひとりに合った支援が行いやすくなります。
まとめ
お泊まり保育は、子どもたちの自立心や協調性を育み、仲間との絆を深める貴重な体験です。
準備や安全対策をしっかり行い、子どもたちが楽しく安心できる環境を整えることがなにより大切です。
保育者がねらいを理解し温かく見守りながら、子どもたちの成長と素敵な思い出づくりをサポートし、忘れられない最高のお泊まり保育を実現してくださいね。








