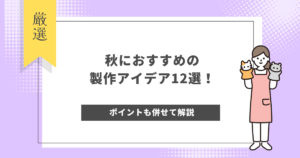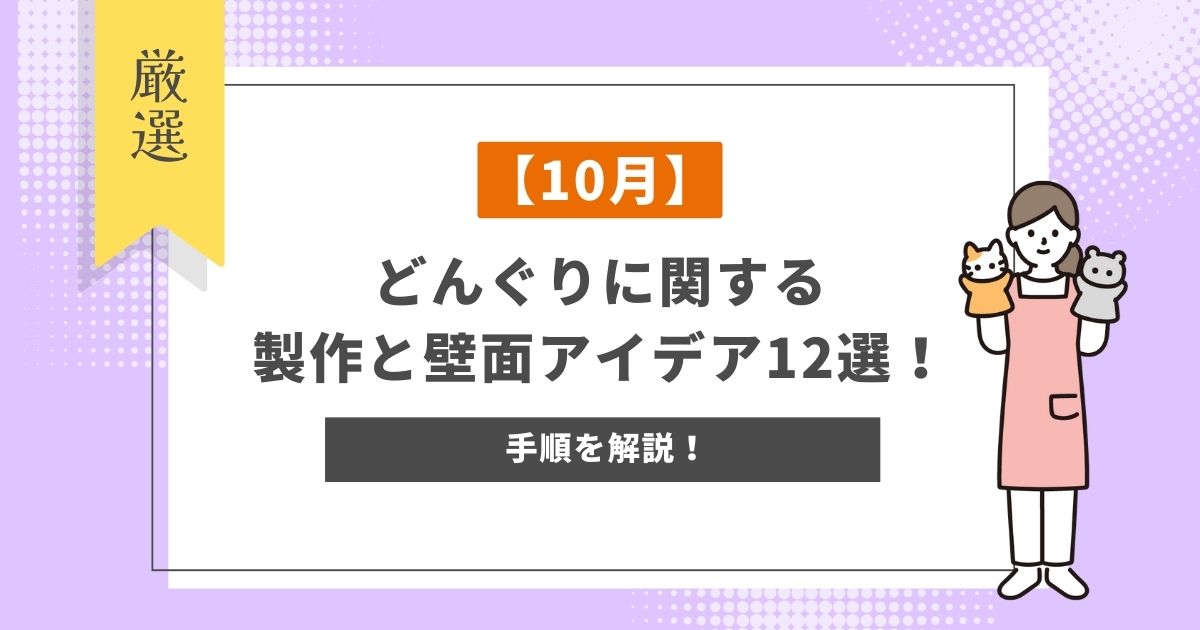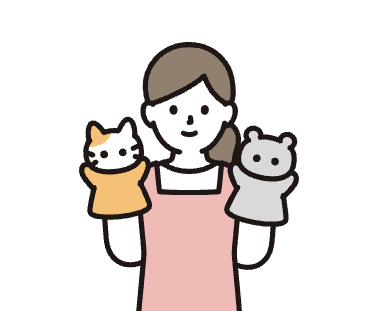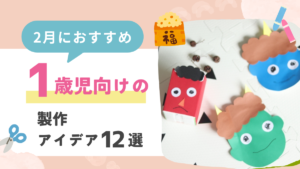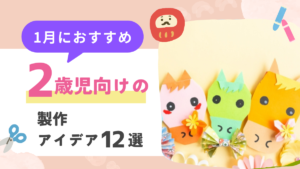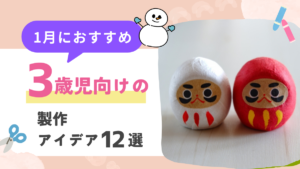10月になると園庭や公園を歩くと足元にはたくさんのどんぐりが落ちていて、子どもたちは夢中になって拾い集めます。
小さな両手いっぱいに集めたどんぐりは、子どもにとってまるで宝物のような存在でしょう。
そんな自然の恵みを活かした製作は、季節を感じながら楽しめる活動であり、指先を使う練習や表現力の広がりにもつながります。
この記事では、年齢ごとにおすすめのどんぐり製作を紹介し、保育や家庭での活動に役立つアイデアをまとめています。
この記事でわかること
- 10月らしい自然素材「どんぐり」を取り入れた製作アイデアを知ることができる
- 0~1歳・2~3歳・4~5歳と年齢別に楽しめる製作を確認できる
- どんぐり製作を通じて得られる発達面でのねらいや効果を理解できる
- 活動を行う際の注意点や、安全に楽しむための工夫を学べる
あわせて読みたい
秋におすすめの製作アイデア12選!ポイントも併せて詳しく解説
木々が色づき、どんぐりや落ち葉がたくさん見つかる秋は、自然を題材にした製作遊びがぴったりな季節です。 特に保育現場では、自然素材を活かした製作を通して、子ども…
目次
どんぐりを使った製作のねらい
- 季節感を味わいながら自然に親しむ
- 手先の器用さや集中力を育てる
- 想像力や表現力を広げる
- 友達との協力や関わりを深める
どんぐりを使った製作には、季節を感じる感性を育むだけでなく、指先の器用さや想像力を伸ばす効果があります。
自然素材に触れることで五感が刺激され、子どもたちは自分なりの表現を楽しめるでしょう。
また、共同で作品を作ることで友達との関わりも深まり、協調性や思いやりの心を育むきっかけにもなりますよ。
どんぐりを使った製作の注意点
- どんぐりを使う際には、口に入れてしまわないよう特に低年齢児には十分注意が必要
- 虫食いどんぐりは避け、煮沸や冷凍処理をしてから使用すると安心
【0~1歳児におすすめ】どんぐりの製作3選
0~1歳児はまだ素材を自由に扱うことが難しい時期ですが、どんぐりを「見る・触る・聞く」といった体験を通して十分に楽しめます。
どんぐりの固い手触りやコロコロ転がる動き、容器に入れたときの心地よい音など、五感を刺激する遊びは赤ちゃんにとって大きな発見の連続です。
特に、どんぐりを台紙に貼り付けた感触遊びや、透明なペットボトルに入れてマラカスのように振るおもちゃは人気があります。
自然と触れ合う喜びを安心して味わうことができるでしょう。
どんぐりマラカス