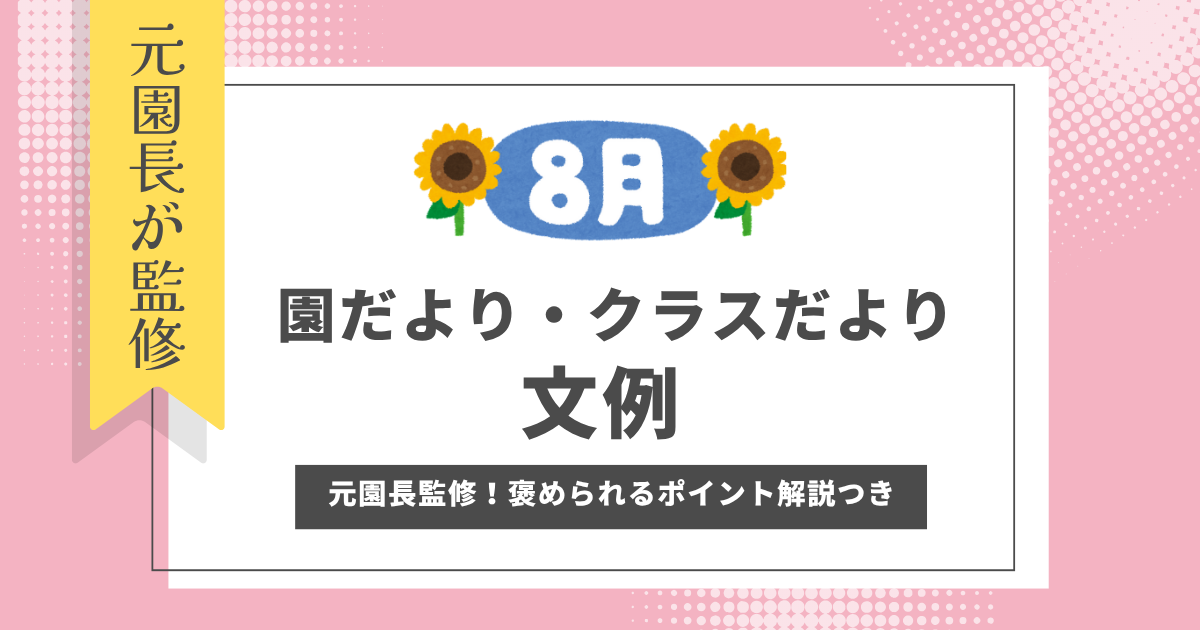夏真っ盛りの8月!保育園では水遊びが盛んに行われていることでしょう。子どもたちが水との触れ合いを楽しんでいる様子を伝え、真夏のいきいきとした姿を共有しましょう。また、暑い夏を過ごす上での注意点も伝え、健康に過ごせるようサポートしたいですね。

Aki 園長歴6年
保育士歴18年、園長歴6年。これまで多くのカリキュラム添削や、保育士さんたちの悩みに寄り添ってきました。この記事では園長として多くの月案・週案をチェックしてきた経験を活かし、 効率よく質が高い月案・週案を仕上げられるようサポートします。
ポイント解説を飛ばしいち早く文例をご確認したい方は「こちらのリンク」を押してください。
【全月共通】園だより/おたよりのポイント
園だよりはポイントを押さえておくことで、単なる「お知らせ」にならず、保護者に喜ばれる魅力的なおたよりを作成できます。
園長として数多くの園だよりを添削してきた経験から、保育士さんがつまずきやすいポイントをまとめました。
以下で解説する点を踏まえて、読み応えのある園だよりを作成していきましょう。
①専門用語や事務的な表現を使わない
・×「午睡」→ ○「お昼寝」
・×「発達段階に応じた遊び」→ ◯「子どもたちの成長に合わせた遊び」
・×「気温が低下するため」→ ○「寒くなるので」
園だよりは、全クラスの保護者に向けて発行するものです。
園を代表した文書のため、しっかりした文章を書かなきゃ…とプレッシャーに感じ、表現が事務的になってしまうことがあります。
しかし、事務的な表現は冷たい印象を与えてしまうことも。
子どもたちの魅力的な姿を十分に伝えられるよう、温かみのある柔らかい表現を心がけましょう。
また、文章を読むことに慣れていない保護者や、母国語が日本語以外の保護者のために、誰が読んでもわかるようなシンプルな言葉を使用するのも大切なポイントです。
②読む人がイメージしやすい文章を心がける
・×「いつものお散歩コース」→ ○「園近くの公園まで歩くお散歩コース」
・×「お外で遊びました」→ ○「砂場でお山を作ったり、追いかけっこをして遊びました」
・ ×「給食を食べました」→ ○「大好きなカレーを夢中で食べ、笑顔がいっぱいでした」
保護者は、園で子どもが何をして過ごしているのか、どんな小さなことでも知りたいと思っています。
しっかり伝わる文章を書くためには、読む人がその時々の情景を目の当たりにしているかのように感じられる表現を使用するのがポイントです。
具体的な描写を用いたり、場面ごとの感覚・匂い・味などの五感を活用したりすることで、より臨場感のある文章を作成することができます。
③誤字脱字や言葉の使い方を注意
<誤字脱字>
・×「食べれる」→ ○「食べられる」
×「見れる」→ ○「見られる」
・×「子供達」→ ○「子どもたち」
<言葉の使い方>
・×「してください」→ ○「しましょう」「していきましょう」
・×「安心感を感じる」→ ○「安心する」
<敬語>(二重敬語に気を付ける)
・×「お越しになられる」→ ○「お越しになる」
・×「お話しさせていただきます」→ ○「お話しします」
誤字・脱字や間違った言葉の使い方は、読み手にとって思った以上に気になるもの。
意図せず高圧的な物言いになっていたり、たびたび間違いがあるようでは、園への信頼を大きく失うことにも繋がります。
特に、パソコンで作られた文章は、思わぬ文字変換がされていることも少なくありません。
必ず複数名に確認してもらう、言葉使いや表現に自信がない場合には辞書で調べるなどを徹底し、正しい文章で作成できるよう十分に配慮しましょう。
【園長が体験】喜ばれたお便り/指摘されたお便り
 監修者
監修者ここでは園長として働く中で、実際に保護者の方に喜ばれた表現や、逆にご指摘いただいた表現について紹介します
・子どもたちの日常の様子が伝わってくる具体的な文章や写真の掲載
・日常の育児に活かせるコラム
・子どもたちに人気の遊びや給食のレシピ
・「お願い」ばかりの園だより
・高圧的、事務的な文章
・誰にでも当てはまるような文章や、丸々テンプレートの使用
日中、子どもと離れて過ごす保護者にとって、園の様子や子どもたちの成長を感じられるような園だよりは、楽しみにしていることの一つです。
子どもたちの日常が手に取るようにわかるものは、特に喜ばれます。
また、豊富なテーマのコラムや、子どもたちが喜ぶ給食メニューのレシピなど、日頃の育児に活かせる内容も園と家庭とをつなぐお守りのような存在になっているようです。
逆に、お願いばかりの内容や、圧を感じる文章では、読むのが嫌になってしまいます。喜んで読んでもらえるような内容を心がけて作成しましょう。
8月の園だより/おたよりのポイント
1年で一番暑い8月。
夏休み、プール、虫取り、すいか割り、お泊り保育など、楽しいイベントも目白押しの楽しい季節です。
同時に、ここ数年の日本の夏の暑さは異常で、危険を感じる気温の日も多くあります。
夏を健康に過ごせるような情報を盛り込んだ園だよりを作成していきましょう。
①夏季の健康管理について共有する
地域によっては、気温が40℃を超えることも珍しくない日本の夏。
湿度も高く、ほんの少しの戸外活動でも、小さな子どもたちにとっては命の危険を伴う可能性があります。
保育中はもちろんのこと、お休みの際の過ごし方や、登降園時の体調管理にも注意を払わなければなりません。
初めて子育てをする保護者の中には、何に気を付けたらいいのかわからずに不安に思っている場合も。
暑い夏を健康に過ごすために大切なポイントを詳しく伝え、園と家庭とで連携して子どもの安全を守りましょう。
②水遊びやプール活動の様子を伝える
子どもたちが大好きな水との触れ合い。
8月は、それぞれの園で毎日のように水遊びやプール活動が行われていることでしょう。
冷たい水の感触を楽しんだり、友だちと水を掛け合ったりする子どもたちの笑顔はとてもいきいきと輝いていますよね!
中には水を怖がり、活動を嫌がる子もいるかも知れませんが、どの表情も、その子どもの貴重な「今」の姿です。
その時々の姿を的確に捉え、保護者と共有しましょう。
季節の体験を通して我が子の「今」を感じられるのは、保護者にとっても大切な記録となります。
③夏休み中の過ごし方について伝える
8月に入ると、保護者の長期休暇に伴って保育園をお休みする子どもも出てきます。
1週間以上の長期休暇を取る家庭もあり、旅行に出かけたり親戚に会ったりと、それぞれ楽しいお休みを過ごすことでしょう。
家族とリラックスした時間を過ごせるのは喜ばしいですが、ただやはり、長い時間保育園の生活から離れると、生活リズムは崩れてしまうもの。
乱れたリズムのまま園生活に戻ると、体調を崩したり、ストレスが溜まったりしやすくなります。
再登園の際に子どもが辛くならないよう、なるべく通常の生活リズムを大切に過ごしてもらえるようお伝えしましょう。
それではここからは具体的な円だより/クラスだよりの文例を紹介していきます。
挨拶文・書き出しの文例
照りつける夏の日差しと響き渡るセミの鳴き声に、本格的な夏を感じます。子どもたちは、暑さにも負けず、汗を流しながら元気いっぱい毎日を過ごしています。
毎日うだるような暑い日が続きますが、子どもたちは変わらず元気いっぱい!水との触れ合いを喜び、プール活動を全身で楽しんでいます。
保育室の窓から入道雲を見つけ、「もうすぐ雨が降るかも知れないよ」と教えてくれた子どもたち。保育園にある図鑑を眺め、夏の天気の研究をしています。
先月は、夏祭りへのご協力いただきありがとうございました!思い出深い1日となったようで、夏祭りごっこが続いています。
水遊びを楽しむ子どもたち。「冷たーい!」「気持ちいいー!」と大喜びで、保育園のプールに笑顔の花が咲いています。
園庭の木で、セミの抜け殻を発見した子どもたち。保育室に持ち帰り、みんなが見える台の上に置いて順番に観察しています。
みんなで育てている夏野菜が豊かに実り、サイドメニューとして毎日の給食に並んでいます。とてもおいしく、元気の出る味です。
<長めの文例>
毎日厳しい暑さの中、安全な送迎をありがとうございます!登園するなり、麦茶をごくごく美味しそうに飲み、「生き返ったー!」と笑う子どもたち。「ママも冷たいお茶飲んだかな」と、出勤されるおうちの方を心配する優しい言葉も聞かれ、ほっこりしした気持ちになりました。
先月の夏祭りで、普段とは違う浴衣や甚平を身につけた子どもたち。とても喜んでくれていて、こちらも嬉しくなりました。ゲームやお買い物、盆踊りなど、どれもとても楽しかったようで、イベントが終わった今でも、保育園内では夏祭りごっこが続き、連日大盛り上がりです。
8月に入ってさらに暑さが厳しさを増し、猛暑日や酷暑日と呼ばれる日が続いていますね。園内では、室温・湿度管理はもちろんのこと、適切な水分補給、着替え、休息などを行い、子どもたちの健康管理を徹底しています。
保護者に伝えたいことに関する文例
朝早くから既に30℃を超える日が多くなってきましたね。熱中症予防のため、登園後、朝の会時、主活動の前後、給食時、お昼寝後、おやつ時、夕方など、決まった時間には必ず水分補給を行い、適度な休息を取るなどして、子どもたちの健康管理に努めています。体調を崩しやすい時期でもありますので、少しでもいつもと違う様子が見られた際には、登園時に職員にお知らせください。
朝プールに水を張っていると、「やったー!今日プールだ!」「早く入りたい!」と期待に胸を弾ませる子どもたち。初めのうちは水に顔を付けることを怖がる姿も見られましたが、毎日練習し、少し長く顔を付けられるようになってきましたよ。
夏休み中は、生活リズムが変わることで、体調を崩しやすくなります。お休みを満喫しながらも、朝はいつも通りに起きる、夜は早めに寝る、朝ごはんをしっかり食べるなどの基本的な生活リズムを守り、休み明けの登園も変わらず元気に過ごせるよう、サポートしていただけたらと思います。



1つ注意として、保護者の方からするとお願いされることが多いと疲れてしまいます。お願いの数はあまり多くならないようにしましょう。
また、「〜してください」「〜気をつけてください」など一方的な書き方は高圧的に感じてしまうので気をつけましょう。
子どもたちの姿に関する文例
乳児期・幼児期共通の文例
暑い日が続く中、子どもたちは水遊びに泥んこ遊び、色水遊びや寒天遊びなど、夏ならではの涼を感じられる遊びや活動を満喫中です。ダイナミックに遊ぶ子どもたちの笑顔は、夏の太陽に負けないくらい毎日きらきら輝いています。
夕方突然のゲリラ豪雨に見舞われた日。大きな雷が鳴り、怖がっている小さなクラスの子どもたちに、「大丈夫だよ」「お耳をふさぐと怖くないよ」と優しく声をかける大きなクラスのお兄さんお姉さんの姿が印象的でした。
夏の過ごし方が身に付いてきた子どもたち。保育者が声をかける前に、「お茶飲むね」「汗かいたから着替えよう」と、自ら行動する姿が見られます。お友だち同士声を掛け合う姿もあり、協力しながら生活をしている姿に感動します。
乳児期向けの文例
たらいに張った水に手を伸ばし、ちゃぷちゃぷと触ったりカップに汲んだり、高いところから流してみたりと、思い思いに水と触れ合いを楽しんでいます。保育士の顔を見上げて笑う姿は、「冷たくて気持ちいいよ!」と教えてくれているようです。
室内で風船遊びを楽しんでいる乳児組さん。エアコンの風の吸込みを利用して天井に風船をくっつけると、何が起こるんだろうと興味津々。エアコンを消すと、くっつけた風船が一気に降ってくるのですが、実演すると大喜び!「もう一回」と何度もリクエストをもらい、風船が降ってくるたびにけらけらと大笑いしていました。
いろいろな色を付けて固めた寒天を使って、感触遊びを楽しみました。最初はおそるおそる指先で触れていた子どもたちですが、ぷるぷるの感触の気持ちよさに気付くと、握ってみたり、色を混ぜたりして思い思いに遊びを楽しんでいましたよ。
幼児期向けの文例
毎日、弾けるような笑顔と一緒にプールを楽しむ子どもたち。バタ足やワニ歩き、宝探しや流れるプール作りなど、どれも夢中になって取り組んでいます。顔に水がかかるのが苦手だった子も、連日の水との触れ合いの中で苦手意識を克服し、今では得意気に取り組むようになりました。
まだまだ続く夏祭りブーム。先月行った夏祭りがとても楽しかったようで、年長さんを中心に夏祭りごっこを楽しむ姿があります。画用紙でお面や焼きそばやかき氷を作ったり、輪投げ大会を開催したりと、イメージを共有し合いながら毎日楽しんでいます。
先日、スイカ割り大会を行いました。一人ずつ目隠しをしてスイカ割りに挑戦!「もっと前!」「もう少し右!」と教え合いながら、みんなで協力して、大きなスイカを割りました。割れたスイカは、給食の先生にフルーツポンチにしてもらい大喜び!にこにこしながら頬張っていましたよ。
食育に関する文例
食欲増進メニュー
栄養のある食事をしっかりと摂り、夏バテを予防したいこの時期。子どもたちが大好きなカレー風味で食欲増進を図り、スタミナを付けましょう!適度なスパイスは、食欲をそそり消化も助けてくれるなど、様々な効果があります。
暑さで食欲が落ちるこの時期は、つるっと食べられる麺料理がおすすめ。野菜やチーズをかわいく型抜きして盛り付ければ、見た目にもかわいく、子どもたちも喜びます。冷たい麺料理なら、調理するお母さんも涼しく助かりますね!
旬の食材を使ったメニュー
夏野菜キーマカレー…子どもたちに大人気のカレーに、夏の太陽の恵みをたっぷりもらった夏野菜を加えて、キーマカレーはいかがですか?にんじん、玉ねぎ、ピーマン、ナス、ズッキーニなど、どんな野菜でもOK。みじん切りにすれば、野菜苦手な子どもでも喜んでぱくぱく食べてくれますよ。
スイカのフルーツポンチ…丸々とした大きなスイカを器にして、フルーツポンチを作ってみませんか?丸く繰り抜いたスイカ、桃やみかんの缶詰、寒天などをスイカの器に入れ、ジュースやシロップを入れて完成!かわいい見た目とカラフルなフルーツに、子どもたちも大喜びすること間違いなしです。
こまめに水分補給をしましょう
喉が渇いている時には、既に体内の水分が不足している状態と言われています。特に子どもは、自分から喉の渇きを訴えられなかったり、遊びに夢中になって忘れてしまったりすることも。大人の声掛けで、適切な水分補給を行いたいですね。
冷たいジュース類は飲みやすく、ついつい与えてしまいがちですが、糖分の多いジュースやスポーツドリンクは、水分補給には適していません。あくまで嗜好品として少量を飲用し、通常の水分補給はお茶や水で行ってください。保育園にお持ちの水筒の中身も、お茶か水のみでお願いいたします。
保健に関する文例
紫外線トラブルに注意
日光を浴びるのは大切ですが、夏の日差しはとても厳しく、肌の弱い子どもたちが長時間浴びるのは様々なリスクが伴います。外出する際は、帽子をかぶる、日焼け止めを塗る、ラッシュガードを着用する、日陰で休憩するなどを心がけ、日光の浴びすぎに注意しましょう。
真夏の心地良い睡眠について
熱帯夜が続き、寝つきが悪くなるこの時期。設定温度の下げすぎから、睡眠時に寝冷えして風邪をひく子どもが増えてきています。室温の下げすぎに注意し、扇風機やタイマー設定などをうまく活用しながら、冷やしすぎないようにしましょう。寝具やパジャマなどは、汗を吸収してくれる綿素材のものがおすすめです。
虫刺されについて
体温の高い子どもたちは、大人よりも虫刺されのリスクが高く、患部を掻きむしったり腫れあがったりと、肌トラブルを起こしがちです。虫よけスプレーの使用や、薄手の長袖・長ズボンを着用するなどして、虫刺され予防をしましょう。腫れてしまった場合には、患部を水で洗い、冷たいタオルなどで冷やすと症状が和らぎます。
行事に関する文例
スイカ割り大会
〇日は、園庭でスイカ割り大会を行います!幼児組さんを中心に、大きな丸いスイカを協力して割り、割ったスイカは、給食の先生にフルーツポンチにしていただき、おやつで食べる予定です。当日の様子は写真でお伝えしますので、楽しみにしていてくださいね。
プールじまい
〇日でプールじまいとなり、水遊び・プール期間は終了となります。最終日には、年長さんを中心に、今年も安全に楽しく遊べたことへの感謝の気持ちを込めて、プールや玩具をきれいに洗う予定です。最終日には、プール・水遊びグッズはお持ち帰りしますので、ご家庭で保管をお願いいたします。
終戦記念日
8月15日は終戦記念日。終戦から80年目を迎える今でも、世界中で戦争や紛争が行われ、何が起こってもおかしくない時代を生きています。暗く、辛い話題ではありますが、絵本を通して、子どもたちと一緒に平和の素晴らしさを伝え、一緒に考える機会としたいと思います。
雑学に関する文例
山の日
8月11日は「山の日」。山に親しみの気持ちをもち、山の恩恵に感謝する日として、2016年に新たに制定されました。夏の身近な自然に触れ、ハイキングや虫取りなどを行うなどして、ご家族で自然への興味関心を育む日として、ぜひ楽しんでください。
立秋
暦の上では秋を迎えるとされる「立秋」。8月7日に立秋を迎えますが、実際は夏真っ盛りの時期であり、秋はまだまだはるか遠いような気がしますよね。とは言え、立秋を境に、ふとした時の涼しい風が吹き、朝夕の空気が変わってきたことを感じられるようになってきます。慌ただしく過ぎる毎日ですが、季節の移ろいも楽しんでいきたいですね。
締め・まとめの文例
まだまだ暑い日が続きますが、体調に気をつけながら、子どもたちと一緒に残りの精一杯夏を楽しんでいきたいと思います。
今月末でプールも終了となりますが、最後まで水との触れ合いを思いっきり楽しみ、夏ならではの遊びを満喫したいと思います。
装飾で使える!8月用のフリーイラスト素材
すいかのイラスト
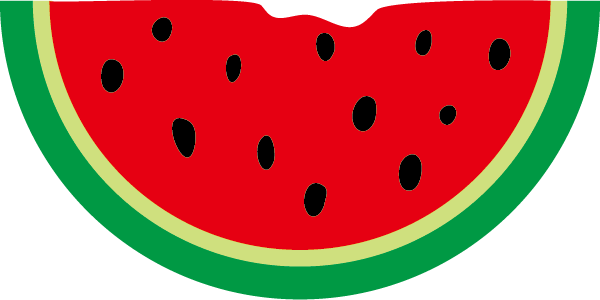
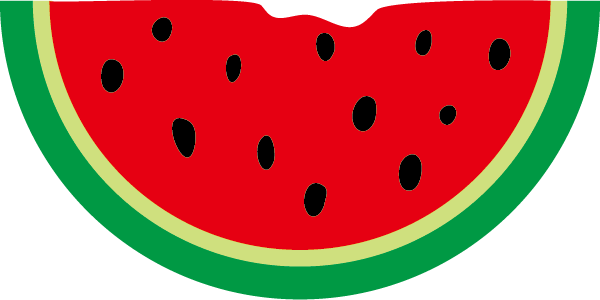
ダウンロードページURL:https://illust-dayori.com/2023/07/4454/
やしの木のフレームのイラスト


ダウンロードページURL:https://illust-dayori.com/2023/07/4430/
今回のまとめ
今回は、8月の園だよりを作成する際のポイントについて解説しました。
8月は、夏休みを取る家庭が多いこともあって行事が少なく、日常の活動がメインになります。
新しい情報が少ない分、普段の様子を伝えるチャンスでもありますので、子どもたちの「今」の姿をたくさん伝えてあげましょう。
そして、保育士の皆さんも、体を休めながら、暑い夏を元気に乗り切ってくださいね。
そのほかの月の園だより/おたより文例
-


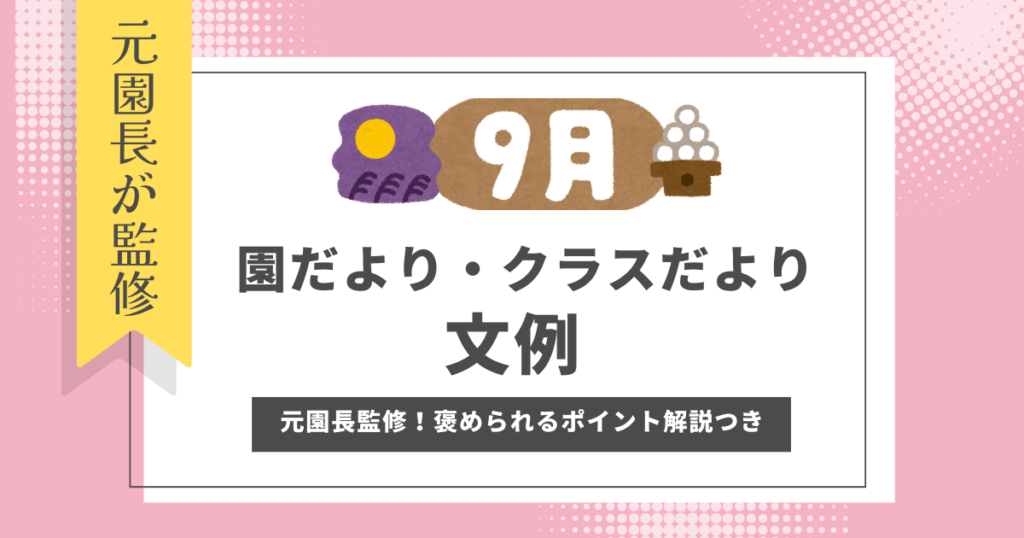
元園長監修【9月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


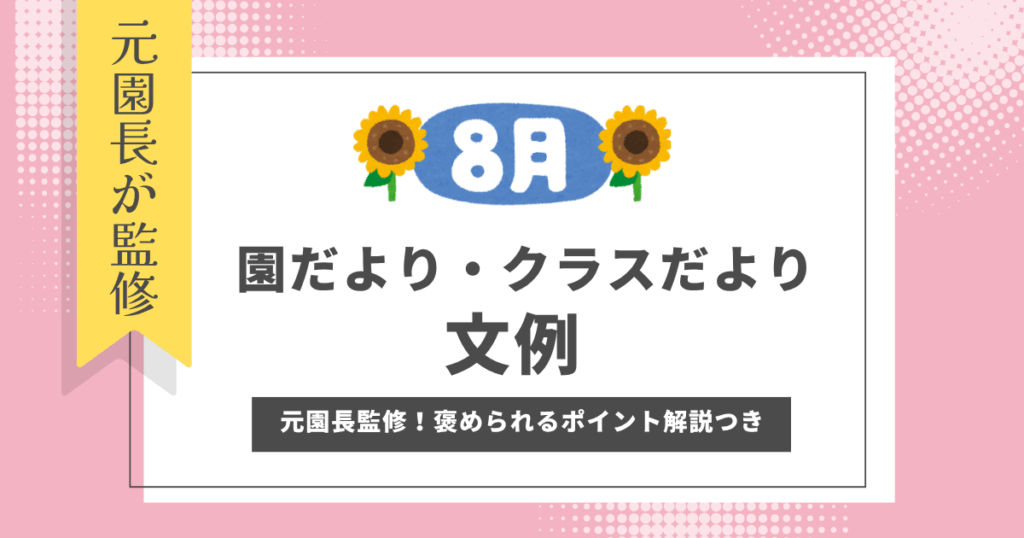
元園長監修【8月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


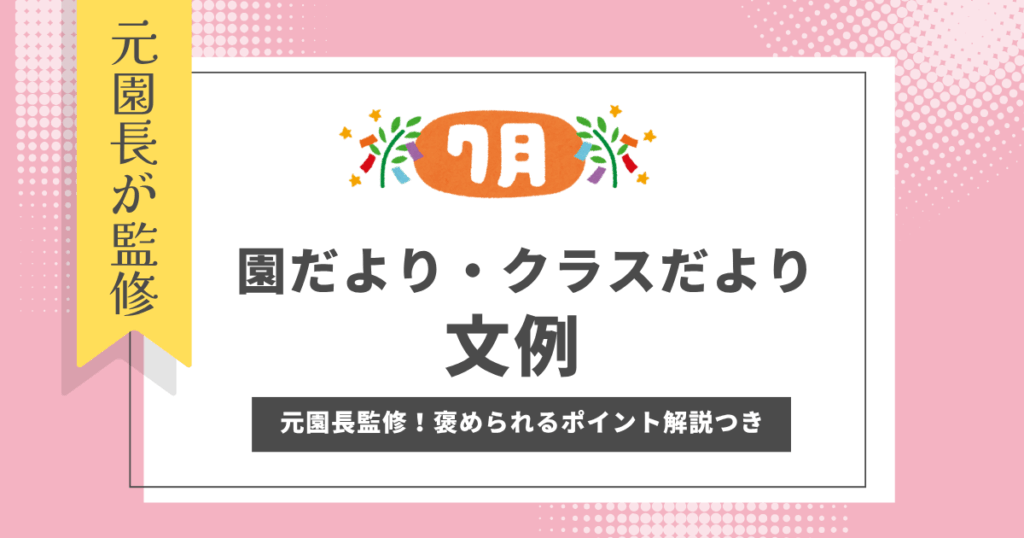
元園長監修【7月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


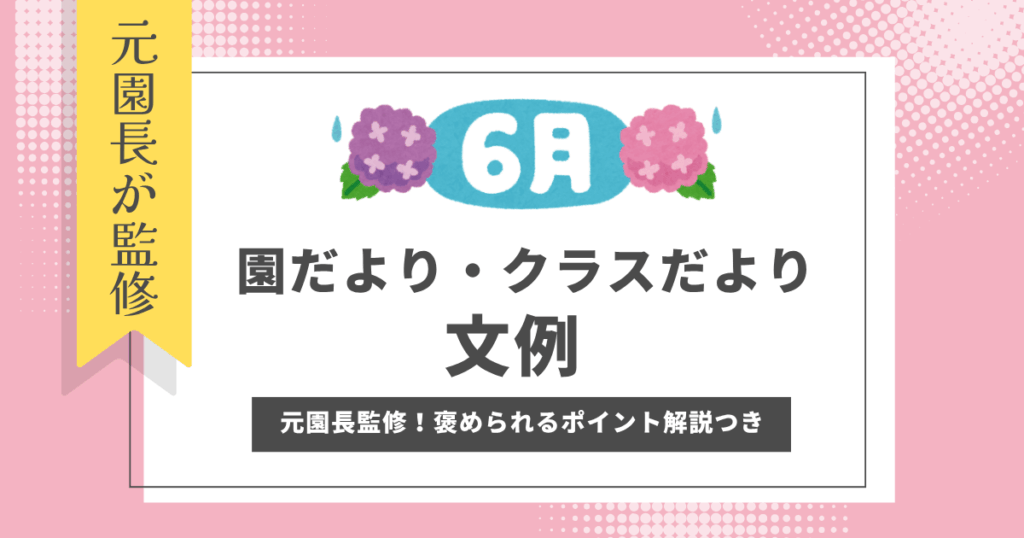
元園長監修【6月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


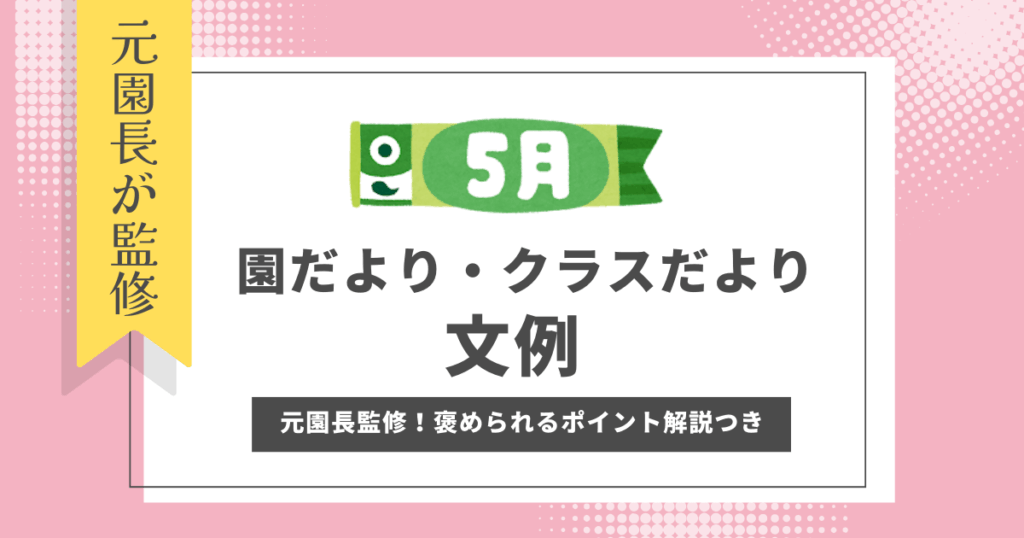
元園長監修【5月おたより】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア文例
-


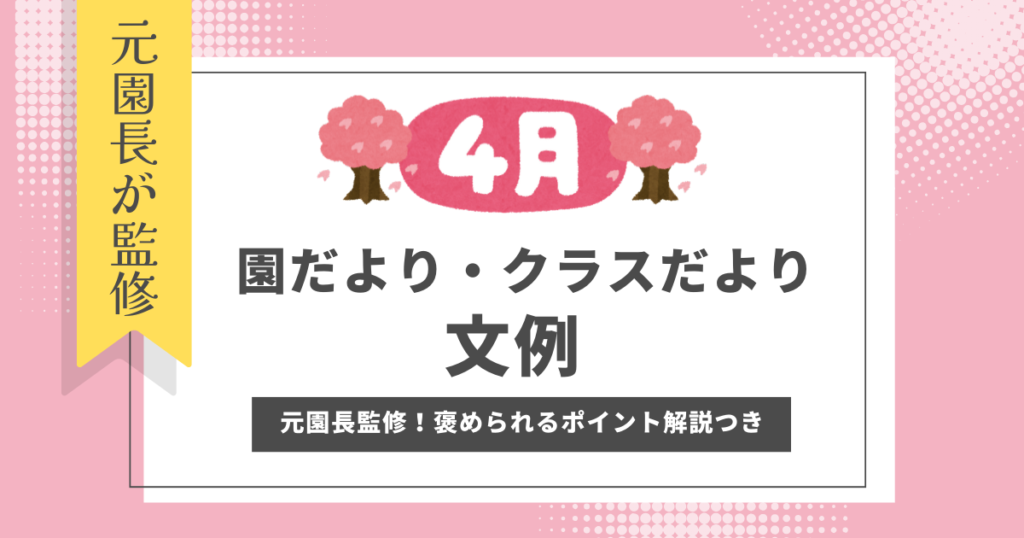
元園長監修【4月・おたより】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア文例