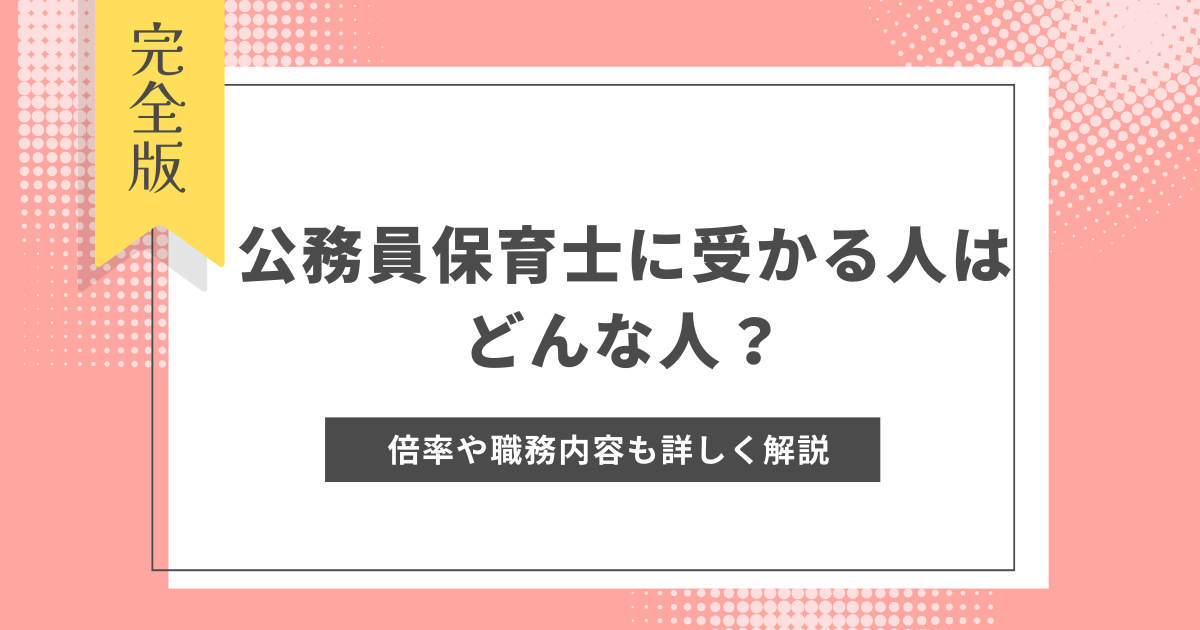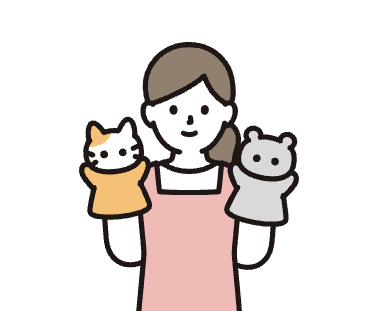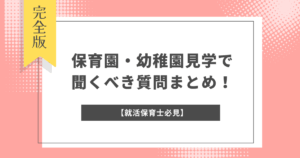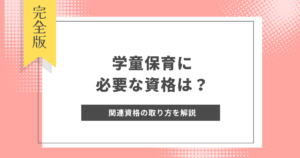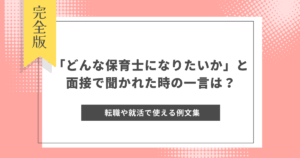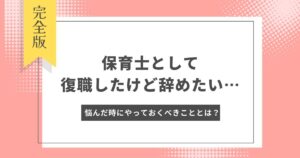安定した定期昇給・賞与が見込めたり、育休や有休・手当などの福利厚生が充実している職種はとても魅力的ですよね。
公務員保育士は地方自治体が運営している保育園・保育施設で働く保育士のことで、上記の理由のため人気な職種です。
本記事では、公務員保育士についての解説をはじめ、私立保育士との違い・公務員保育士になるまでの流れ・公務員試験についてまで具体的にご紹介します。
また、公務員保育士のメリット・デメリット・注意点も合わせてご紹介するため、ぜひ参考にしてください。
- 公務員保育士とは?
- 公務員保育士と私立保育士の違いは何?
- 公務員保育士になるには?
- 公務員試験の倍率は?
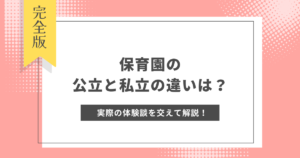
公務員保育士とは?
公務員保育士とは、地方自治体が運営している保育園・保育施設で働く保育士のことです。
そのため、公務員の中でも地方公務員に該当し、公立保育士とも呼ばれます。
公務員保育士として働くためには、保育士資格を取得する以外に、自治体が行っている公務員試験に応募をして合格する必要があります。
公務員保育士は、自治体が運営する公立保育園に勤務することが多いですが、その他に公立の認定こども園・児童養護施設・支援センターなどで勤務する場合もあるため、事前に確認をすると良いでしょう。
公務員保育士の雇用形態は主に4つに分けられ、職務内容は以下の通りです。
| 種類 | 職務内容 |
|---|---|
| 正規職員 | ・常勤の職員が該当 ・フルタイム勤務 ・クラス担任を受け持つ ・勤続年数を重ねていくと、主任や園長を務めることもある |
| 臨時職員 | ・非正規雇用の職員 ・正規職員に比べて勤務日数・勤務時間が少ない ・更新期間は3ヶ月間から1年間が多い ・正規職員に比べて賞与・手当などの待遇が異なる |
| 嘱託職員 | ・非正規雇用の職員 ・定年退職した職員が再雇用される ・1年~3年の契約 |
| 派遣保育士 | ・派遣会社での雇用 ・主に保育補助を担当する ・派遣期間が決められている |
参照:公務員保育士に受かる人の特徴は?試験難易度や倍率も徹底解説!
公務員保育士は人気?みんなの声を紹介
保育士としての働き方はたくさんありますが、その中でも公務員保育士は人気のようです。
特に公務員保育士の正規職員は、給料が臨時保育士に比べて高めに貰えたり、手当や有休・交通費も充実しているという声もありました。
保育士として働く際には、公務員保育士以外に私立保育士という働き方があります。
公務員保育士になるには、公務員試験を受ける必要がありますが、私立保育士の場合は必要ありません。
試験を受ける必要があったとしても、公務員保育士は人気で、試験の倍率が高いようです。
公務員保育士と私立保育士の違いを解説
| 項目 | 公務員保育士 | 私立保育士 |
|---|---|---|
| 勤務先 | ・自治体が運営する公立の保育施設 | ・社会福祉法人や株式会社、NPO法人が運営する保育施設 |
| 勤務時間 | ・7時~19時までのシフト制(自治体・保育施設によって異なる) | ・保育施設によって、保育時間が異なる ・延長・休日保育に対応している園もある |
| 平均年収 | ・344万9172円(施設長・主任を除いた常勤職員) | ・306万4,980円(施設長・主任を除いた常勤職員) |
| 賞与 | ・経験年数によって高くなる | ・保育施設によって異なる ・勤務先によってはない場合もある |
| 退職金 | ・地方公務員と同額 | ・保育施設の運営母体によって異なる |
| 福利厚生 | ・地方公務員と同様 | ・保育施設によって異なる |
| 有給・育休 | ・有休や育休を比較的取りやすい | ・人手不足で取りにくい園もある ・育休取得率が高いなど、実績を出している園もある |
| 副業 | できない | 園の方針による |
公務員保育士は、自治体が運営する公立の保育施設に勤務し、地方公務員に該当します。
私立保育士は、社会福祉法人や株式会社、NPO法人が運営する保育施設に勤務する保育士です。
給与面としては、公務員保育士は経験年数に応じて年収や賞与が見込めることがメリットで、私立保育士と比べて勤続年数もやや長い傾向にあります。
私立保育士の場合は、保育施設の運営元によって、給与面・福利厚生などが大きく異なります。
私立保育士の方が待遇が良い場合もあるため、いろいろな求人を見ながら比較すると良いでしょう。
公務員保育士になるまでの流れ
公務員保育士として働くためには、希望する自治体の公務員試験を受ける必要があります。
保育士資格を取得してから、勤務先の保育施設が決まって公務員保育士になるまでの流れを、5つのステップに分けてご説明します。
公務員試験を受けるうえでの注意点などもご紹介するため、ぜひ参考にしてください。
公務員保育士になるためには、まず保育士の資格を取得する必要があります。
保育士資格を取得するには、厚生労働省が指定する保育士養成施設を卒業する方法と、年に2回実施する保育士試験に合格する方法があります。
保育士養成施設は、4年制大学・短大・専門学校などがあるため、比較をして検討しましょう。
保育士資格を取得後、希望する自治体の公務員試験に申し込みをします。
自治体のWebサイトで、募集を行っているかどうか、募集期間・申し込み方法などを必ず確認しましょう。
公務員試験の募集時期は、自治体ごとに異なることが多いのですが、試験日が同じだったということがあります。
例えば、○○市と△△市の公務員保育士が気になっていたとしても、試験日が同じであれば同時に受けることが難しいため、気をつけましょう。
公務員試験の申し込み後は、受験案内書を確認し、公務員試験を受験しましょう。
筆記試験を行う一次試験に合格した後は、面接や実技試験の二次試験を受けます。
試験内容は自治体によって異なり、ピアノの実技試験で曲などが指定されている場合もあります。
必ず事前に試験内容を確認をし、試験対策を行いましょう。
公務員試験に合格した場合、その自治体の採用候補者名簿に1年間登録されます。
その後、自治体の保育施設からの採用の申し出が来るまで待機をしましょう。
自治体の保育施設から連絡がないまま、登録有効期限の1年を過ぎた場合には、公務員試験を再度受験する必要があります。
公務員試験に合格した後も、配属先が決まるかどうかは分からないため、気をつけましょう。
採用候補者名簿に登録された後、配属する保育施設・自治体からの連絡、採用通知書が届きます。
配属先の保育施設が決定することで、公務員保育士として勤務できます。
採用通知書では、担当者の連絡先や必要な書類についてを確認しましょう。
勤務する前に、何か質問や疑問点があれば、担当者の連絡先から聞いてください。
参照:公務員保育士に受かる人の特徴を解説!試験の難易度や対策方法も紹介
参照:公務員保育士とは?特徴や私立保育士との違いについて解説
公務員保育士の試験内容
公務員保育士の試験内容は、自治体によってさまざまで、過去の試験内容とも異なる場合があります。
希望をする自治体の募集案内を確認する必要がありますが、公務員試験では筆記試験を行う一次試験と、面接や実技試験の二次試験を受けます。
具体的にどのような試験なのか、何が出題されやすいかをまとめたので、ぜひ参考にしてください。
一次試験
一次試験では筆記試験を行う自治体が多く、主に教養試験と専門試験を行います。
教養試験は、高校卒業程度の一般的な知識及び知能を問われる試験です。
教養試験の内容は自治体によって異なりますが、出題されやすい分野は以下の通りです。
- 文章理解力(現代文・英文・古文)
- 判断推理力
- 数的推理力
- 資料解釈力
専門試験は、保育士になるうえで必要な保育の専門的な知識を問われます。
教養試験の内容は自治体によって異なりますが、出題されやすい分野は以下の通りです。
- 社会福祉
- 子ども家庭福祉(社会的養護を含む)
- 保育の心理学
- 保育原理・保育内容
- 子どもの保健など
教養試験や専門試験以外に、論文や適性検査を行う自治体もあるため、必ず募集案内を確認しましょう。
参照:公務員保育士の試験内容とは?年齢制限や難易度、おすすめの勉強方法は?
参照:令和6年度夏実施試験名古屋市職員採用試験案内
参照:令和6年度横浜市職員(高校卒程度、免許資格職など)採用試験受験案内
二次試験
二次試験の内容は自治体によって異なりますが、実施されやすい内容は以下の通りです。
- 個別面接
- 実技試験
- 論文試験
二次試験の中で、特に配点が高く重要視されやすいのは個別面接です。
志望動機やなぜ公務員保育士になりたいのかなどを問われることが多いため、質問内容を想定し、どう答えるかを考えておきましょう。
実技試験では、テーマに沿って保育の場面を想定して行う実技や、ピアノ実技を行うことが多いです。
ピアノ実技で弾く曲の楽譜を持参するよう、受験案内に書かれている場合もあるため、必ず事前に確認をしましょう。
論文試験では与えられた課題について、記述式で回答する試験です。
受験案内に制限時間や文字数が書かれている場合もあるため、論文対策を行っておくとよいでしょう。
参照:【2023年最新版】保育士の公務員試験を徹底解説!試験内容や合格に向けた対策法
参照:令和6年度夏実施試験名古屋市職員採用試験案内
参照:令和6年度横浜市職員(高校卒程度、免許資格職など)採用試験受験案内
公務員保育士の倍率【都道府県別】
公務員保育士は私立保育士に比べてメリットが多く、勤続年数が長い傾向にあるなど、長期的に働きやすい環境です。
これらの理由から、公務員保育士は募集の人数に対して、応募する人数が多く倍率が高い傾向にあります。
実際に公務員試験の合格率がどのくらいか、それぞれの自治体の職員採用試験実施状況を基にまとめました。
参考にした市は7つで、高崎市・千葉市・横浜市・名古屋市・大阪市・浜松市・新潟市です。
自治体によって合格率は大きく異なり、特に高崎市・新潟市は公務員試験に合格することがかなり難しいことが分かると思います。
| 市町村 | 合格率(%) |
| 高崎市 | 12.5% |
| 千葉市 | 26.5% |
| 横浜市 | 42.1% |
| 名古屋市 | 19.5% |
| 大阪市 | 27.0% |
| 浜松市 | 33.3% |
| 新潟市 | 13.3% |
公務員保育士に受かりやすい人の特徴
公務員保育士は安定した給料・待遇が見込めることから人気の職種です。
自治体によって大きな差はありますが、公務員試験の合格率が12.5%の市町村もあるなど、募集の人数に対して応募する人数が多く倍率が高い傾向にあります。
ここでは、どのような人が公務員保育士に受かりやすいのかを3つにまとめました。
- 試験対策がしっかりできる人
- 自治体ごとの募集情報をリサーチできる人
- 志望動機が明確な人
試験対策がしっかりできる人
1つ目は試験対策がしっかりできる人です。
公務員試験では一次試験と二次試験を行い、筆記試験や実技試験・面接・論文などあらゆる試験に取り組む必要があります。
筆記試験で出題されやすい分野はとても幅広いため、それぞれの分野に対応できるよう前もって勉強する必要があります。
また、二次試験では保育の場面を想定して実技試験を行ったり、ピアノ試験を行うことが多いです。
実技試験に対応できるよう、過去にどのような内容を行ったのか情報を集めたり、ピアノの練習を行う必要があります。
自治体ごとの募集情報をリサーチできる人
2つ目は、自治体ごとの募集情報をリサーチできる人です。
公務員試験での試験内容は、自治体によって異なります。
そのため、自治体ごとの募集案内を事前に確認し、それぞれの試験内容に合った試験対策を行う必要があります。
公務員試験に応募する自治体が決まったら、過去の試験内容・募集人数・倍率を確認したり、今年度はどのような試験内容を行うのかなどを、早めに情報を収集することでしっかりと試験対策を行いましょう。
志望動機が明確な人
3つ目は、志望動機が明確な人です。
自治体によって試験内容は異なりますが、二次試験の中で、特に配点が高く重要視されやすいのは個別面接です。
個別面接では志望動機やなぜ公務員保育士になりたいのか・なぜその自治体を選んだのかをよく問われます。
なぜその自治体で公務員保育士になりたいのかを、抽象的に答えるのではなく、自分の経験・体験も入れながらなるべく具体的に話せるよう考えておきましょう。
参照:公務員保育士に受かる人の特徴は?試験難易度や倍率も徹底解説!
公務員保育士試験に受かるための対策
試験科目が多く、倍率も高い公務員保育士試験に合格するためには、本格的に対策しなければなりません。
本章では、対策方法を詳しく解説するので、試験に受かるために自分に合った方法で対策を始めましょう。
対策①参考書や過去問を繰り返し解く
独学で試験勉強を進める場合には、参考書や過去問を繰り返し解いていきましょう。
過去問題集を使うときのポイントは、1冊のテキストを使って何度も同じ問題を解くことです。
なかには3〜4冊ものテキストを使う人もいますが、一度にたくさんの問題を解いてしまうと逆に勉強が非効率になってしまいます。
1冊の問題集を繰り返し解けば過去の問題傾向がつかめ、効率良く対策できますよ。
公務員保育士試験の場合、受験する自治体によって出題傾向が異なるので、過去問を何度も繰り返し解くことで傾向や特徴を把握しやすくなるでしょう。
対策②予備校や通信講座を活用する
プロのサポートを受けながら勉強したい人は、予備校や通信講座の活用がおすすめです。
直接質問や添削をしてもらえるので、独学よりも理解が深まりやすいメリットがあります。
また、一人では対策しづらい面接や実技試験の対策をしてくれる場合もあるため、公務員保育士を目指す人にぴったりでしょう。
独学より費用がかかるのが難点ですが、それ以上にしっかりと対策できるので検討してみてください。
対策③面接・実技試験の準備をする
公務員試験の対策には、面接・実技試験の準備が欠かせません。
1次試験から2次試験までの日数は1〜2ヶ月程度なので、1次試験を終えてからでは十分な対策ができないでしょう。
筆記試験対策と同時に、面接や実技試験の準備も始めてみてください。
面接試験対策をする際は、家族や友人に協力してもらうと本番の雰囲気と緊張感を味わえるのでおすすめです。
実技試験は自治体によって内容が異なるので、事前に確認して対策を進めましょう。
公務員保育士のメリット
公務員保育士は、福利厚生や退職金などが地方公務員の基準で定められているため、待遇が良いことが公務員保育士のメリットです。
ここでは、公務員保育士のメリットを3つにまとめました。
具体的にどのようなメリットがあるのか、私立保育士と比べながら具体的にご紹介します。
- 私立保育士と比べて給与が高い
- 福利厚生が充実している
- ローンの審査などが通りやすい
私立保育士と比べて給与が高い
1つ目のメリットは、私立保育士と比べて給与が高いことです。
公務員保育士の平均年収は、344万9,172円で、私立保育士の平均年収は306万4,980円(施設長・主任を除いた常勤職員)です。
経験年数やそれぞれの保育施設によって給与は異なりますが、公務員保育士は私立保育士に比べて平均年収が約40万円高い結果になります。
公務員保育士は長期的に働きやすく、高めの給与を安定してもらえます。
福利厚生が充実している
2つ目のメリットは、福利厚生が充実していることです。
公務員保育士は福利厚生も地方公務員と同様のため、充実しています。
具体的に公務員の福利厚生とは、職務関連手当や生活関連手当・有給休暇・産前産後休暇・育児休暇・公的医療保険・年金などに該当します。
公務員は福利厚生が法律で定められているため、私立保育士と比べて有給休暇や育児休暇が比較的取りやすいこともメリットの一つです。
参照:公務員の主な福利厚生一覧!手当・休暇・割引などで私生活が充実
ローンの審査などが通りやすい
3つ目のメリットは、ローンの審査などが通りやすいことです。
ローンの審査に通りやすい人の特徴・傾向の1つとして、職種が安定している・勤続年数が長いことがあります。
公務員は安定している職種だと見なされやすく、給与が安定していて福利厚生も充実していることから、勤続年数も長い傾向があります。
そのため、公務員保育士はローンの審査などが通りやすいです。
参照:住宅ローン審査で通りやすい人の傾向を解説!審査を厳しくしている要因は意外な点
公務員保育士のデメリット
公務員保育士には、安定した給与・賞与が見込めたり、福利厚生が充実しているなど、たくさんのメリットがあり、志望する方が多い職種です。
しかし、私立保育士にはない、公務員保育士ならではのデメリットもあります。
ここでは、公務員保育士のデメリットを3つにまとめました。
具体的にどのようなデメリットがあるのか、具体的にご紹介します。
- 異動がある
- 副業が普通の公務員同様に禁止
- 倍率が高い
異動がある
1つ目のデメリットは、異動があることです。
公務員保育士は2~4年で定期的に異動をすることが一般的です。
移動は同じ市町村内で行いますが、勤務先によっては住宅から距離が遠くなって、通勤時間が長くなる可能性もあります。
また、保育者同士の人間関係や保護者・子どもとの関わりも新しくなるため、関係を始めから築いていく必要もあります。
1つの保育施設で働き続けたいという方や、新しく人間関係を築いていくことが苦手という方にとって、人事異動はデメリットです。
参照:公務員保育士に受かる人の特徴を解説!試験の難易度や対策方法も紹介
副業が普通の公務員同様に禁止
2つ目のデメリットは、副業が普通の公務員同様に禁止であることです。
近頃、副業という言葉が一般的になり、副業に興味がある方もいるかもしれません。
しかし、公務員保育士は国家公務員法と地方公務員法で禁止となっています。
国家公務員法と地方公務員法の内容としては、「副業を禁止する」と明記されていませんが、「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」とされています。
倍率が高い
3つ目のデメリットは、公務員保育士の倍率が高いことです。
それぞれの自治体や、公務員試験を受ける年度によって倍率は異なりますが、一般的に合格率が低く、倍率が高いです。
具体的に、新潟市の合格率は13.3%で、横浜市の合格率は42.1%という結果から、公務員試験の合格は非常に難しい状況であると言えます。
希望する自治体の試験内容をこまめに調べたり、筆記試験の勉強を早めに行っておくなど、試験対策を十分に行えるよう準備・計画をしておくとよいでしょう。
公務員保育士の注意点
公務員保育士になるためには、希望をする自治体の募集案内で、試験内容や日程を必ず確認する必要があります。
また、試験内容や日程以外にも、事前に募集案内などで確認が必要だったり、最低限知っていかなければならない項目があります。
それは、公務員試験の募集があるかや年齢制限・採用候補者名簿についてです。
ここでは、公務員保育士になる過程で気をつけていただきたい注意点を3つにまとめ、具体的に説明をしています。
- 毎年募集されるわけではない
- 年齢制限が設けられていることがある
- 採用候補者名簿への登録は1年間
毎年募集されるわけではない
1つ目の注意点は、毎年公務員保育士が募集されるわけではないことです。
自治体が公務員保育士を募集するのは、保育士の人出が不足し、欠員が出た時などに行うことが基本です。
そのため、応募しようと思っていたときに募集がない年・自治体もあります。
そのため、希望する自治体が今年度は募集を行うのか、ホームページなどでこまめにチェックしたり、募集がない場合にはどういう選択をするのかを考えておく必要があります。
参照:公務員保育士に受かる人の特徴は?試験難易度や倍率も徹底解説!
年齢制限が設けられていることがある
2つ目の注意点は、年齢制限が設けられていることです。
自治体によって異なりますが、年齢によって公務員試験に応募できない場合があります。
募集案内に「大学卒業程度・○○歳~○○歳」や「○○ 年(平成○年)4月2日以降に出生した人」などの年齢要件が記載されています。
多くの自治体は30歳程度までの募集が多いため、年齢によって公務員試験に応募できるかどうか、必ず募集案内の年齢要件の欄を確認しましょう。
参照:令和6年度夏実施試験名古屋市職員採用試験案内
参照:令和6年度横浜市職員(高校卒程度、免許資格職など)採用試験受験案内
採用候補者名簿への登録は1年間
3つ目の注意点は、採用候補者名簿への登録は1年間であることです。
公務員試験に合格した場合、その自治体の採用候補者名簿に1年間登録されます。
その後、自治体の保育施設からの採用の申し出が来るまで待機をしましょう。
自治体の保育施設から連絡がないまま、登録有効期限の1年を過ぎた場合には、公務員試験を再度受験する必要があります。
公務員試験に合格した後も、配属先が決まるかどうかは分からないため、気をつけましょう。
まとめ
- 公務員保育士は、地方自治体が運営している保育園・保育施設で働く保育士
- 公務員保育士は、自治体が実施している公務員試験に合格する必要がある
- 公務員保育士は、募集の人数に対して、応募する人数が多く倍率が高い傾向にある
- 公務員保育士に応募する際に、必ず募集案内を確認をする
公務員保育士は、安定した定期昇給・賞与が見込めたり、育休や有休・手当などの福利厚生が充実しているため希望する方が多い職種です。
公務員保育士として働く際には私立保育士と比べてみたり、本記事を参考にしながらメリットとデメリットを踏まえて、職種の選択をしてみてください。