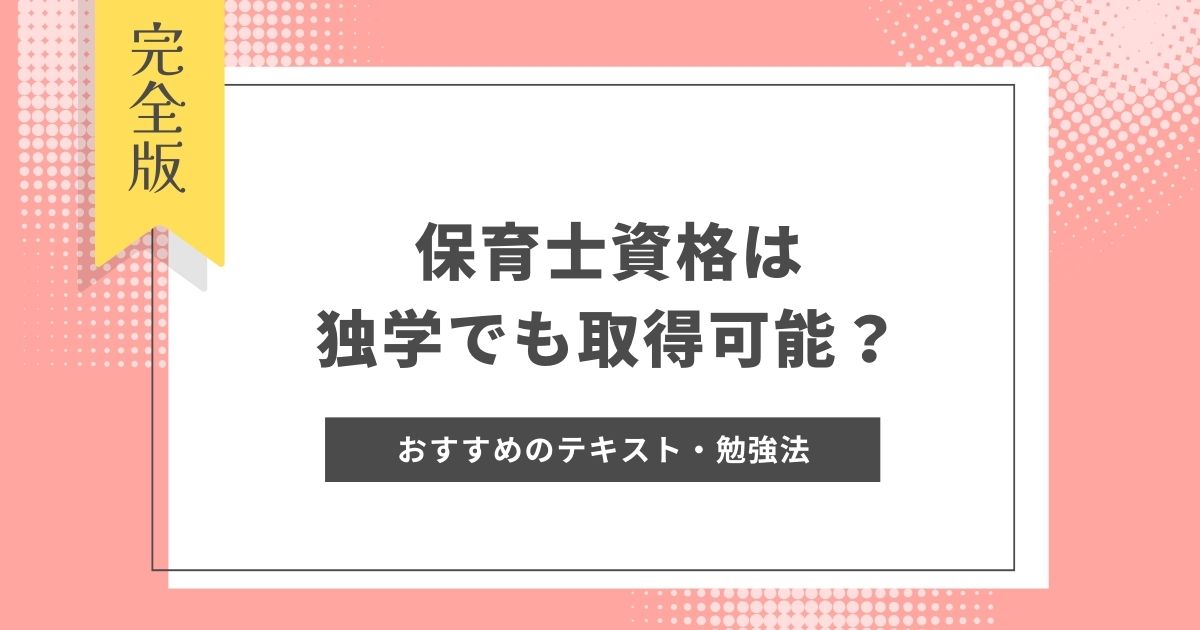保育士資格を取る際によく知られているのは、大学や短大または専門学校で単位を取って卒業と同時に資格を取得するという方法です。
しかし学校に通う以外にも、独学で試験を受けて保育士資格を取るという方法もあります。
本章では、資格試験を受けて保育士資格を取得する際のメリット・デメリットや試験に向けたアドバイスをお伝えします。
独学で保育士の資格を取りたいと思っている方はぜひ参考にしてくださいね。
- 保育士資格を独学で取得するには、メリットとデメリットがある
- 保育士資格試験は筆記試験と実技試験があり、筆記試験の合格科目は一定期間免除される
- 試験の受験資格は学歴や経験年数等によって与えられる
- 最新版のテキストやスマホ学習で勉強するのがおすすめ
- 通信教育も検討すると良い
 あん【元保育士ライター】
あん【元保育士ライター】需要が多い国家資格である保育士資格を取得したいと思っても、学校に通うのは時間やお金の面などを考えるとハードルが高いですよね。
独学で保育士資格を取る方法を知って、目標を実現させるための選択肢を増やしましょう!


あん先生 元保育士ライター
保育士歴11年、現在は2児の母です。公・私立園それぞれで正規・非正規保育士として働いた経験を活かし、役立つ情報をわかりやすくお伝えします。


保育士資格を独学で取得する難易度は?
保育士資格を独学で取得する難易度はどの程度なのでしょうか。
令和5年度と令和4年度の保育士資格試験の受験者数と合格者数をみると、それぞれ26.9%と29.9%となっており、合格率はいずれも30%弱です。
国家資格には他にも多くありますが、その中でも保育士の資格の難易度は普通~やや高めと言えるでしょう。
3~4人に1人は合格できるということでさほど難しくないという見方もできますが、過去には合格率が10%台だったこともあるので油断は禁物です。
また筆記試験では9科目ある全ての科目で6割以上得点する必要があるため、出題範囲が広い科目や専門性の高い科目は特にしっかり勉強する必要があります。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 66,625人 | 17,955人 | 26.9% |
| 令和4年度 | 79,378人 | 23,758人 | 29.9% |
保育士資格を独学で目指す人の特徴
- 子育てや仕事と両立しながら勉強したい
- 費用をなるべく抑えたい
- 自分のペースで学びたい
- 通信講座や通学で学ぶことが難しい
簡単とは言えない保育士資格試験を独学で目指す人には、上記のような特徴があります。
子育てや仕事をしていると通学は難しいので、資格取得を目指す場合は時間の調整をしやすい独学が適しています。
また短大や専門学校に通うには少なくとも200万円ほどのお金がかかりますが、独学だと教材費や受験料程度で済み、費用があまりかかりません。
自分のペースで勉強できることも魅力です。
少しずつ時間をかけて勉強をし、できるときにはまとめてしっかり取り組むなど、無理のないペースで勉強ができます。
通信講座や通学が難しい場合でも、テキストを購入して自分なりに勉強できる独学は自由度が高い勉強方法と言えます。
保育士資格を独学で取得するメリット
保育士資格の取得については保育系の養成校を卒業するのが一般的です。
資格試験を受けるよりも難易度が低いですし、カリキュラムが組まれているのでそれに従って勉強すればよいという気楽さもあります。
しかし独学での資格取得には、通学にはないメリットがあります。
どういった点で優れているのか、具体的にお伝えします。
費用が安く済む
保育士資格を取得するための学校にかかる学費は年間でおおよそ100万円程度とされており、短大の2年間では200万円、4年制大学では400万円程度かかる計算になります。
また、すでに保育以外の短大や4年制大学を卒業している人にとっては、重ねての学費の支払いとなってしまいます。
しかし独学で資格試験を受験する場合に必要な費用は教材費(数千円~2万円程度)と受験料(12,700円)のみで、だいぶ安くなります。
自分のペースで勉強ができる
学校に通うとなると決められた授業に出席する必要がありますし、期日までに課題を仕上げて提出することが求められたりもします。
また、決められた日までにピアノの練習をする必要があるなど、しなければならないことに追われてしまいがちです。
独学なら自分のペースに合わせて勉強ができるので、無理なく勉強に取り組めます。



仕事をしている方や予定を立てづらい方にとっては、自分のペースで勉強して資格取得を目指せるのは嬉しいですね。
勉強スタイルを自由に選択できる
独学での勉強は、以下のように自分の好きなスタイルで勉強できるのもメリットのひとつです。
- スケジュールをしっかり立てて計画的に勉強する。
- 通勤中や家事の合間にアプリ等を使って勉強する。
- YouTubeや音声教材を活用する。
- テキストで学んですぐに問題集を解く、過去問中心に解いてテキストで復習する等、自分に合ったアプローチをする。
自分に合った勉強の仕方は人それぞれですので、取り組みやすい方法を見つけてくださいね。
保育士資格を独学で取得するデメリット
独学での資格取得におけるメリットを考えると断然独学が良いように思えますが、メリットがある反面デメリットもあります。
資格の勉強をする上で、なるべく不安材料は取り除いて合格に近付きたいですよね。
いったいどんなデメリットがあるのでしょうか。
それぞれご紹介・ご説明しますので、参考にしてくださいね。
モチベーションの維持が難しい
保育士の資格取得のための勉強は出題範囲が広く、長期に及びます。
そのためモチベーションの維持がだんだんと難しくなるのが、独学のデメリットのひとつです。
目標を明確にして繰り返し意識したり、勉強をした日はカレンダーにチェックを入れたりして頑張りを可視化することは、モチベーションを保つために有効です。



SNSなどで同じ目標を持つ人とつながるだけでも励みになりますし、時々カフェなどで勉強して気分転換しても良いですね。
情報収集・教材選びが自己責任
試験勉強をするにあたり傾向と対策を知ったり質の良い教材を使用したりすることは、効率よく合格するために大切です。
しかし独学では、最新の情報の取得や教材選びはすべて自分でしなくてはならない点がデメリットと言えるでしょう。
先ずは、全国保育士養成協議会の公式サイトで試験に関する正しい情報を手に入れましょう。
また、過去問をざっと見て、どんな形式でどんな内容が出題されているのかを掴むと教材選びがしやすいですよ。
実技対策に不安がある
実技試験は筆記試験と違い、知識を付けるだけでは対策は不十分です。
独学では実際に練習を見てもらってアドバイスしてもらうことが難しいのが難点です。
市販の教材で過去の傾向を知ることができますしYouTubeでも対策動画が多数あるので、具体的なイメージを掴むのにはおすすめです。



録音や録画で自分の姿を客観的に知ることができますし、家族や友人の前で練習することで本番をイメージしやすいですよ。
保育士資格試験の概要と科目数
保育士資格試験に合格するためには、試験について知ることが大切です。
本項では試験の概要と筆記試験・実技試験の大まかな内容をお伝えしますので、まずはどういう勉強をする必要があるのかということをイメージしてくださいね。
また一発で合格できなかった場合に1度合格した科目を免除してもらえる制度や、受験資格についても解説します。
保育士資格試験の概要
そもそも保育士資格試験とはどんなものなのでしょうか。
以下がその概要です。
- 保育士とは国家資格であり、子どもの保育や保護者への指導を行う者である。
- 保育士資格を取得するには保育士養成校を卒業するか、保育士試験に合格する必要がある。
- 受験資格を満たしていれば保育士試験が受けられる。
- 試験では筆記試験8科目、実技試験2科目(3科目から選択)に合格する必要がある。
さらに試験の詳しい内容は次項でご紹介しますのでご確認くださいね。
筆記試験は全部で9科目、実技試験は2科目の選択式
- 保育の心理学
- 保育原理
- 教育原理及び社会的養護
- 子ども家庭福祉
- 社会福祉
- 子どもの保健
- 子どもの食と栄養
- 保育実習理論
- 音楽に関する技術
- 造形に関する技術
- 言語に関する技術
筆記試験に合格すると実技試験を受けられます。
筆記試験は出題範囲が広いうえに、各科目において6割以上得点することが必要です。
特に「教育原理」と「社会的養護」は、2科目で1セットと見なされ、それぞれで6割以上得点する必要があるので、バランスよく勉強を進めておきましょう。
一発合格じゃなくても大丈夫!?合格科目免除期間延長制度
残念ながら保育士資格試験が不合格だった場合でも、合格した筆記試験科目は合格した年を含めて3年間有効です。(ただし、教育原理と社会的養護は同一試験で両科目合格する必要あり。)
また、合格科目免除期間延長制度を使うと、筆記試験の有効期限を最長5年間まで延長することができます。
免除申請するためには必要な勤務期間と総勤務時間数が決められていますので、制度の詳しい内容については一般社団法人全国保育士養成協議会の公式サイトでご確認ください。
参照:筆記試験合格科目における 合格科目免除期間延長制度について|一般社団法人全国保育士養成協議会
保育士資格試験の受験資格
保育士資格試験の受験資格があるかどうかは、学歴や実務経験の有無などで決まります。
- 四大・短大卒…受験資格あり(学部・学科は問わない)
- 専門学校卒…基準を満たした学校であれば受験資格あり
- 高卒…卒業年月日や保育科かどうか、実務経験によって受験資格の有無が決まる
- 中卒…実務経験があれば受験資格あり
受験をお考えの方は、学歴による受験資格を確認しておいてください。
参照:受験資格|一般社団法人全国保育士養成協議会
独学におすすめのテキスト・勉強方法
保育士資格試験に向けて勉強をする時にはどんなことに気を付けると良いのでしょうか。
間違ったやり方ではせっかくの勉強が無駄になりかねません。
貴重な時間を使って勉強をするのですから、少しでも効率よく取り組みたいですよね。
本項では独学で試験勉強をするときにおすすめのテキストや勉強方法についてお伝えします。
市販のテキストは最新版を選ぼう
先ず、市販のテキストを購入する際は最新版を選ぶことが大切です。
令和7年の筆記試験(前期)の概要には以下のように記載されています。
筆記試験における法令・保育所保育指針等については、令和6年4月1日以前に施行されたものに基づいて出題します。
引用元:全国保育士養成協議会
保育所保育指針は大体10年で改訂されますし、法令や制度はその都度変更や新設がありますので、最新の情報を得る必要があるのです。
また、最新のテキストは出題傾向や過去問の分析がされているので、効率良く対策することができます。
スキマ時間にスマホ学習もおすすめ
スキマ時間の活用にはスマホ学習が便利ですね。
おすすめのYouTube動画とスマホアプリをご紹介します。
- 保育士試験合格ch
- ほいくんの保育士チャンネル
保育士試験合格chは1問1答のクイズを基本に、試験の内容をわかりやすく解説している動画です。
ほいくんの保育士チャンネルはテンポの良い解説で飽きずに視聴できる動画です。
クイズ形式の動画や語呂合わせの暗記動画もありますよ。
- 保育士過去問(解説投稿型)
- 保育士 資格試験対策問題集
いずれも問題を解いて解説を読むというスタイルのアプリです。
ちょっとした時間に手軽に勉強できますよ。
実技試験対策は早めに準備しよう
実技試験は音楽・造形・言語の3分野から2分野を選んで受験します。
先ずは難関の筆記試験に合格する必要があるので本格的な実技試験の準備は筆記試験が終わってからで良いのですが、余裕があれば実技試験の課題が公表された頃から少しずつ準備をするのが望ましいです。
特に音楽や言語では誰かに見てもらうことで本番の緊張感に近付けるので、ぜひやってみてくださいね。



どの分野も繰り返し練習することで慣れて上達し、余裕を持って試験に臨むことができますよ。
独学が不安な人は通信講座も検討しよう
独学での勉強だと費用はおさえられますが、学習計画や情報のリサーチ等すべて自分でしなければならず、不安に感じる方も少なくないでしょう。
通信講座を活用することで必要な勉強を効率的にすることができますので、検討してみても良いですね。
- ヒューマンアカデミー保育士講座
- キャリカレ保育士講座
- ユーキャン保育士講座
ヒューマンアカデミー保育士講座はプランが充実しており、自分に合った勉強方法を選択できますし、eラーニングでスキマ時間を活用できます。
キャリカレ保育士講座は、不合格になった際には受講料が全額返金されます。
またイラストや写真が豊富でわかりやすい教材というのも特徴です。
ユーキャンは過去に多くの合格者を輩出している実績がありますし、実技試験の対策もできる点も安心です。
先輩保育士の私が「独学で保育士を目指す人に伝えたいこと」
独学で保育士資格を取って就職したときには、養成校で実施される保育実習が無い分、現場で戸惑う方が少なくないかもしれません。
子ども同士のケンカの時の対応や保育に対する姿勢、保育士同士の連携、指導計画や記録の書き方等、現場で学ぶことはたくさんあります。
しかも実習生ではなく職員として保育に携わるので、手厚い指導はしてもらいにくいかもしれません。
その際は周りをよく観察し、自分から質問していきましょう。
先輩保育士たちは新人保育士が何を知りたいか、何がわからないのかがわからないので、質問してもらえる方が助かると感じることが多いです。
保育士になるのはゴールではなくスタートです。
自己研鑽を積んで素敵な保育士を目指しましょう!
まとめ
保育士資格を取得するための試験は出題範囲が広く勉強には時間がかかるので、自分に合ったテキストや動画、アプリ等を利用して効率よく勉強し、合格につなげたいですね。
試験勉強は大変ですが、資格を取得したら保育士としての活躍の場が待っています。
保育士不足が問題となり保育のニーズは多様化し、保育士に求められていることは増えています。
大変ですが、子どもたちの将来につながるとても重要な仕事です。
そんな保育士を目指す皆さんを応援しています!