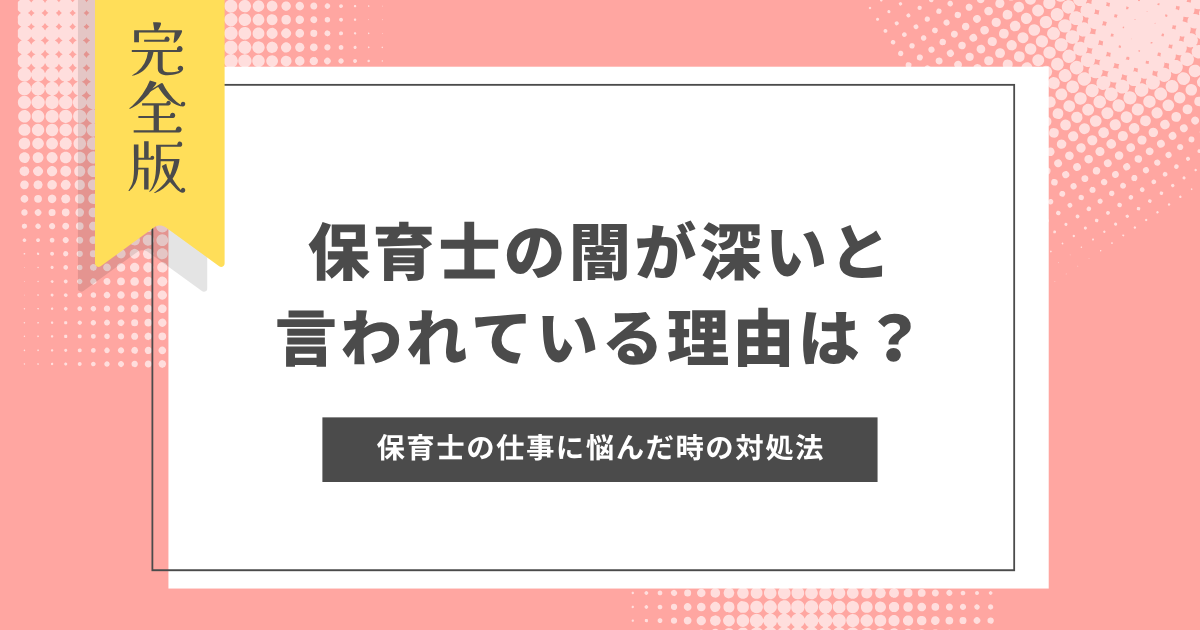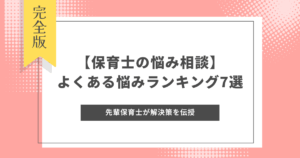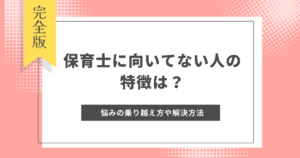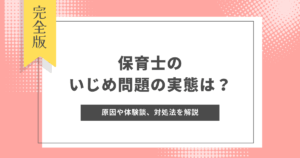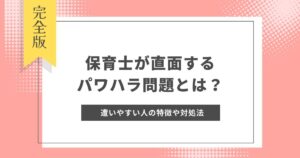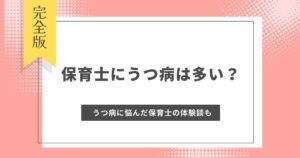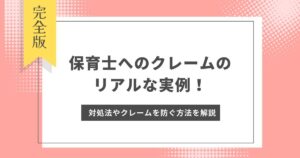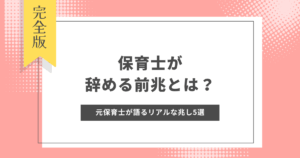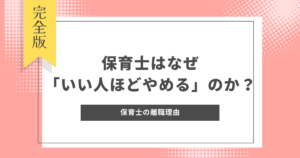「保育士の闇が深い」という言葉を耳にしたことはありませんか?
保育の仕事は、子どもの命と成長を預かる重要な仕事でやりがいのあると有名ですが、その裏では長時間労働や人間関係、保護者対応など、多くの負担が積み重なっています。
本記事では、実際に現場で働いた経験をもとに、保育士たちが抱える悩みの実態や、「闇が深い」と言われる保育園の特徴、さらには子どもへの影響や向き合い方まで、リアルな声をもとに解説します。
- 保育士の仕事は多岐にわたり、大きなストレスをかかえている人も少なくない
- 闇が深い保育園の特徴には、年度途中で退職者が出るなどが挙げられる
- 闇が深い保育園の子どもたちは、健やかに育つ機会が失われることもある
- 悩みと向き合うには、相談したり転職を検討する
 ちあき【元保育士ライター】
ちあき【元保育士ライター】私も保育士として約6年間現場に立ち、何度も「続けていけるのか」「ずっと保育士の仕事だけをしていくのか」と悩みました。
本記事が、同じように悩むあなたの力になれたら嬉しいです。


ちあき先生
認可保育園で勤務後退職して留学。その後は英語の幼稚園で働く。結婚を機に派遣保育士に転身し、さまざまな園で経験を積む。保育士歴は通算7年ほど。
子どもが重度アレルギー児になったことでライターに転身した2児の母。
保育士の「闇が深い」ってどういうこと?よくある悩みとその理由
「保育士はかわいい子どもと関われて楽しそう」と言われることがよくあります。
しかし、裏側では、想像以上の負担とプレッシャーがのしかかっています。
日々の業務は大忙しで、感情労働の連続です。
加えて、理不尽なクレームや組織内の上下関係などに悩む保育士も少なくありません。
本章では、多くの保育士が感じている闇と理由を解説します。
長時間労働と持ち帰り仕事の実態
保育士の1日は、子どもの登園前からすでに始まっています。
開園準備、環境整備、子どもたちを受け入れた日中は常に気を張り、休憩すらままならない日もあります。
保育時間が終わっても、書類作成や行事準備などの仕事が待っており、自宅に持ち帰って作業するケースも少なくありません。
「子どもが帰ったら仕事は終わり」という幻想とは裏腹に、保育士の業務は多岐にわたり、労働時間の長さが深刻な課題の1つです。
職場内の人間関係のストレス
保育園は女性が多い職場であることから、人間関係に悩むケースが多いのも現実です。
新卒や若手保育士にとっては、先輩との距離感や、園内の暗黙のルールに戸惑うこともあるでしょう。
よくあるストレス要因として、派閥やグループ内の対立や園長や主任による一方的な指導などが挙げられます。
精神的に追い詰められ、体調を崩す保育士も決して少なくありません。
「子どもと関わる仕事が好きなはずなのに…」という葛藤を抱えながら働き続ける日々に、限界を感じる人もいます。
保護者との間でのトラブル
保護者とのコミュニケーションは保育の質にも直結しますが、近年ではモンスターペアレントと呼ばれるような理不尽な要求も増加しています。
「うちの子がケガをしたのは先生のせい」「他の子におもちゃを取られたのに先生は何もしてくれなかった」など、保育現場の事情を理解せず一方的に責められるケースもゼロではありません。
その結果、保育士が常に「クレームを恐れて行動する」ような萎縮した保育になり、子どもとの自然な関わりが難しくなることもあります。
給与の低さと待遇のギャップ
保育士は国家資格が必要な専門職であるにもかかわらず、給与水準は依然として低いままです。
厚生労働省のデータによると、保育士の平均年収は約330万円で、全職業平均の約490万円よりもかなり下回っています。
「責任の重さ」「心身への負担」に対して、対価が見合っていないと感じる保育士は多く、退職理由としては常に上位です。
保育士の給与アップに向けて国が動いていますが、まだまだ他の業種と比較したときに差があり、現場で働く保育士は不満を募らせています。
参考:保育士の平均賃金
「理想」と「現実」のズレに苦しむ瞬間
保育士を目指したきっかけが「子どもが好き」「一人ひとりに寄り添いたい」だった人も多いでしょう。
しかし現実は、時間と人手が足りない中で流れ作業のように保育を進めることが求められる日々であることも少なくありません。
特に乳児クラスでは、泣いている子に声をかけられないままおんぶして別の子をあやすなど、「全員に向き合う」のが難しい状況に陥ることもあるでしょう。
「やりたい保育が実現できない」と夢と現実のギャップに苦しむうちに、「このままでいいのか」と悩みながら働く保育士が多く存在します。
「闇が深い保育園」の特徴
すべての保育園が悪いわけではありませんが、中には「これはもう限界…」と職員が感じてしまうほど、組織的な問題を抱えている園も存在します。
そんな園では、人の入れ替わりが激しかったり、保育の質よりも利益を重視していたりと、いくつかの共通した特徴があります。
本章では、闇が深い保育園の典型的な特徴を具体的に見ていきましょう。
職員の入れ替わりが異常に激しい
職員の出入りが異常に激しい保育園は、内部に大きな問題を抱えている可能性が高いです。
新卒が定着しない、ベテランが次々と辞めていく、年度途中での退職者が多いなどの現象が慢性的に起こっている園は、働きやすい環境とは言えません。
- 年度途中の退職者が多い
- 常に求人広告を出している
- その保育園で長く勤めている職員がいない
人間関係や業務過多、上層部の対応など、原因はさまざまですが、「長く働きたい」と思える雰囲気がないことは確かです。
保育の質より「利益」を優先する運営方針
営利目的で運営されている保育園に多く見られるのが、保育の質を犠牲にしてでも利益を出そうとする姿勢です。
たとえば、法定ギリギリの人員で運営しようとしたり、保育士の意見を無視して経費削減を進めたりするケースです。
利益優先の保育園では、必要な備品の購入を拒否されたり、安全面に不安がある環境でも改善されなかったり、子どもの対応が効率重視で子どもの利益を考えていないなどの特徴があります。
こうした環境では、保育の質は保てず、子どもたちへのケアも十分に行き届かなくなります。
経営陣のワンマン体制
園長や理事長が「絶対権力者」として君臨しているような保育園もあります。
意見を言う職員は排除され、改善提案は無視され、現場の声が届かない一方通行の組織は、働き手のモチベーションを下げます。
ワンマン経営の特徴は、園長の方針が頻繁に変わったり、職員の意見は無視されたり、管理職が経営者のイエスマンばかりなっていることがあります。
このような職場では、自然と「黙って従う」雰囲気が蔓延し、本来のチームワークや保育の創意工夫が失われ、質の高い保育は提供できません。
「闇が深い」保育園や保育士が子どもに与える影響
大人の職場環境は、実は子どもにも少なからず影響を与えています。
保育士の表情や声かけのトーン、日々の余裕のなさは、実は、子どもたちは感じ取っているのをご存知でしょうか。
本章では、保育士が心身ともに疲弊している現場で、子どもたちがどのような影響を受けやすいのか、保育経験に基づき解説します。
保育園に行きたがらなくなる
「毎朝泣きながら登園する」「休日明けに体調を崩す」といった子どもの様子が続く場合、園内の雰囲気に何らかの問題があるケースもあります。
もちろん、子どもの性格や発達段階、家庭の事情によるものもありますが、保育士の関わり方が一因となっているケースもゼロではありません。
- 「先生が怖い」と言う
- 夜泣きやおねしょが増える
- 朝のぐずりが激しくなる
保育士が余裕をなくしていると、子どもの気持ちに応えることが難しくなり、登園拒否という形でSOSを出す子もいます。
安心感が育たず自己肯定感が低下する
子どもの心の土台を育てるためには、「自分は大切にされている」と感じる経験が欠かせません。
しかし、保育士が忙しさやストレスで十分な保育が行えていない場合、子どもは「どうせ見てもらえない」と感じてしまうことがあります。
関係性の希薄さは、表情の乏しさ、積極性の低下、周囲の反応を極端に気にするなどの行動から現れます。
こうした様子が見られた場合は、子どもが寂しさや不信感を感じていて、必死でアピールしているのかもしれません。
他の子どもに対して攻撃的になる
心に不安やモヤモヤを抱えた子どもは、言葉で表現できず、行動で示すことがあります。
例えば、友達を叩く、物を投げる、大声で泣くなど、攻撃的な行動が目立ってきたときには、背景に保育環境の不安定さがある可能性も考えられます。
子ども自身が保育園の闇を感じ取っていて、対抗するために攻撃的になっているケースもあるでしょう。
これらの行動は心のサインであり、決してわがままではありません。
私が保育士を辞めようと思った理由
保育士として働き始めた頃は、子どもたちの笑顔に囲まれて天職と思っていた人も多いのではないでしょうか。
でも、現実は日々の疲労やストレスに加えて、自分の保育観が否定されるような場面に出会うこともあります。
本章では、実際に保育士を辞めたいと思った理由や、同じように悩んだ人たちの声をご紹介します
「休めない職場」に心が折れた
どんなに体調が悪くても、どんなに気持ちが限界でも、「人手が足りないから休めない」となりがちなのが保育現場の実情です。
シフトに穴を開けることへの罪悪感や、周囲からのプレッシャーが、保育士を追い込んでしまう原因になっています。
仕事行きたくない行きたくない行きたくない。保育士辞めたい無理。でも休めないから気合いで頑張るしかないのがつらい頭痛い。6連勤が続くと病む。明日も来週も土曜遅番だから余計にしんどい。急に休むと上司に嫌味言われるしお菓子配りながらみんなに謝らなきゃだし休みづらいけど行きたくないよ
引用元:X
「頑張りたい」という気持ちがあっても、このような現状では心と体がついていけなくなります。
人間らしく休むことが許されない職場に、希望を持ち続けることはできないですよね。
気が付けば保護者のための仕事をしている
保育士の原動力は「子どもが好き」「成長を支えたい」という気持ちだったとしても、現実には、保護者対応や上司の顔色、行事や書類などの事務作業に振り回され、本来向き合いたい子どもとの時間が削られていくこともあります。
保護者にごまするために保育士になったんじゃない。疲れた
引用元:X
保護者対応が悪いわけではありませんが、子どもの保育をする時間よりも優先されることが多すぎるのは問題です。
目的と手段が逆転したような日々に、「何のためにこの仕事をしているんだろう」と迷子になる保育士も少なくありません。
業務範囲が広すぎて耐えられない
「保育が嫌いなわけじゃない」「むしろ子どもは好き」と思っていても辞めることを考えてしまうのは、やることが増える一方で、心身のゆとりも、経済的な安定も得られないからです。
さらに、職員間で価値観が合わなかったり、保護者の姿勢に疑問を感じたりすることで、孤独感も募っていきます。
保育士の仕事嫌いじゃないよ…でも手取り上がらずやることだけ増える、シフト細か過ぎるのが嫌でずっと辞めたい
引用元:X
好きだからこそ、頑張れていても、ふとした瞬間に「もう頑張れない」と感じる人も少なくないです。
保育士としての経験が増えれば、それだけ仕事が増え、でも給与が変わらないときに退職を考え始めるのも不思議ではありません。
保育士の悩みとの向き合い方
保育士として働く中で、悩みを感じない人はいないといっても過言ではありません。
子どもの命を預かる責任、保護者や職場との関係、理想と現実のギャップなどさまざまな悩みがありますが、保育が好きという気持ちで我慢してしまう人も多いのが現状です。
本章では、保育士として抱える悩みとどのように向き合い、心と体を守っていくべきかを考えていきます。
信頼できる人に相談する
悩みを一人で抱え込むと、視野が狭くなり、冷静な判断ができなくなることがあります。
職場の仲間や信頼できる先輩、家族、あるいは元保育士の友人など、自分の気持ちを安心して話せる相手に相談してみましょう。
「話すだけでスッキリした」「他の人も同じことで悩んでいた」と気づくこともあります。
声に出すことで、自分の感情を客観視できるようになり、「じゃあ次にどうするか?」が見えてくることもあります。
メンタルケアを大切にする
保育士の仕事は、体力だけでなく心のエネルギーも消耗します。
子どもや保護者に常に笑顔で接するには、自分の心が元気であることが前提です。
そのためには、しっかり休む・眠る・話す・笑うといった当たり前のことを、まずは丁寧に行うことが大切です。
- 好きな音楽を聴く
- 適度な運動を取り入れてみる
- 気持ちをノートに書き出す
「無理しない」が何よりのセルフケアです。
自分を後回しにしない習慣を、少しずつ身につけましょう。
転職も検討してみる
どうしても環境が改善されない場合、転職を検討するのは決して逃げではありません。
むしろ、自分と子どもたちのために「よりよい保育ができる場所」を探す前向きな一歩です。
最近では保育士専門の転職サイトも充実しており、非公開求人や働きやすさを重視した園の紹介もあります。
- 理想の保育、理想の保育園を明確にする
- 相談してみる
- 保育士以外の選択肢を知る
環境が変わることで、自分らしい保育ができるようになり、「やっぱり保育が好き」と再確認できることもあります。
闇が深い保育園を辞めたくなったら-保育士の転職サイト3選
保育士が転職を考えるとき、最も大きな不安は「今より悪くなるかもしれない」という恐れではないでしょうか。
自力で求人を探すのではなく、保育業界に特化した転職サイトを利用して上手に口コミをチェックするのが安心です。
本章では、信頼できるサポートが受けられる保育士向け転職サイトを厳選して3つご紹介します。
保育士ワーカー


| 運営会社名 | 株式会社トライトキャリア |
|---|---|
| 求人数 | 29,560件(2025年7月20日時点) |
| エリア | 全国 |
| 公式サイト | https://hoikushi-worker.com/ |
保育士ワーカーは、求人数が非常に豊富で、全国各地の求人情報があります。
また、求人は保育園だけでなく、幼稚園・学童・企業内・病院内保育など多様な施設の求人を取り扱っているところも魅力的です。
登録後は、専任スタッフが希望条件に合った職場を丁寧に紹介してくれる上に、求人情報には一般には出回らない内部の雰囲気や働き方など、詳細な情報も教えてくれます。
転職後に「想像していた園と違う」というミスマッチを防ぐためにサポート体制も整っています。
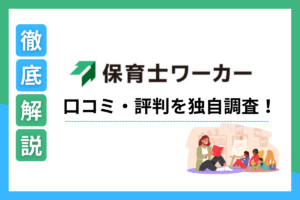
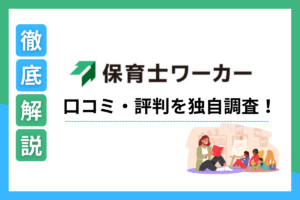
保育エイド


| 運営会社名 | 株式会社サクシード |
|---|---|
| 求人数 | 会員のみに公開 |
| エリア | 全国 |
| 公式サイト | https://www.hoiku-aid.jp/ |
保育Aidは、非公開求人がメインの保育士専門の転職サイトです。
求人情報は登録者限定で公開されており、自分に合う職場があるかどうかは、まず登録してみないとわからないところはデメリットです。
しかし、登録後は元保育士である担当スタッフが希望や理想の保育、今抱えている悩みに寄り添いながら、ぴったりの求人を丁寧に紹介してくれます。
特に「人間関係を重視したい」という方には心強い味方です。


ジョブメドレー


| 運営会社名 | 株式会社メドレー |
|---|---|
| 求人数 | 34,458件(2025年7月20日時点) |
| エリア | 全国 |
| 公式サイト | https://job-medley.com/cw/ |
ジョブメドレーは、全国の保育園・幼稚園・療育施設・病院内保育所など、幅広い施設の求人を多数取り扱う転職サイトです。
求人数がかなり豊富で全国に展開しているので、希望する勤務地の求人が見つけやすいでしょう。
サイト内には保育に関するコラムも充実しており、働き方や業界の情報が手に入るのもポイントです。
LINEでの問い合わせも可能なので、忙しい合間にも手軽に転職活動を進められます。
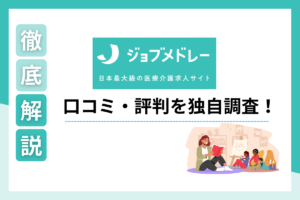
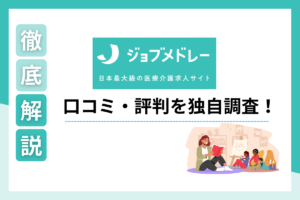
まとめ
保育士はやりがいのある仕事ですが、裏側には長時間労働や人間関係、待遇の不満など多くの悩みが潜んでいます。
無理を続ける前に、自分に合った環境を探すことも大切な選択肢です。
保育士向けの転職サイトを活用すれば、より良い職場に出会える可能性が広がります。
自分の心と体を守りながら、理想の保育ができる施設や環境を探してみてください。