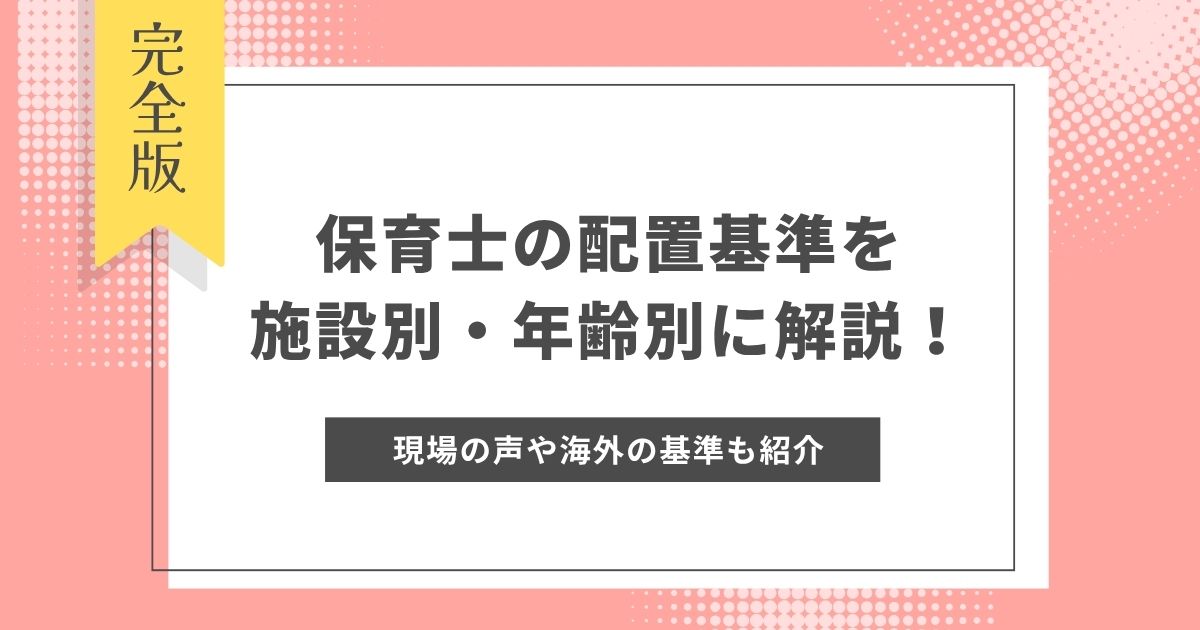保育施設に必要な保育士の人数を定めたものを「保育士の配置基準」と呼びます。
本記事では各施設の具体的な保育士の配置基準や、配置基準の見直し等、様々な角度から解説します。
- 認可保育園など、保育施設ごとに保育士の配置基準が決められている。
- 年齢別に配慮する内容が違い、それぞれの基準が設定されている。
- 配置基準は時間帯や自治体によって違いがある。
- 施設を運営する上で配置基準を守る事は絶対である。
 あん【元保育士ライター】
あん【元保育士ライター】必要な保育士の数が決まっている事は知っていても、詳しく知る機会はなかなかないですよね。
保育士の配置基準について知ることは保育環境を考える際に重要です。
ぜひ保育に対する理解に役立ててくださいね。


あん先生 元保育士ライター
保育士歴11年、現在は2児の母です。公・私立園それぞれで正規・非正規保育士として働いた経験を活かし、役立つ情報をわかりやすくお伝えします。
こども家庭庁が定めた保育士の配置基準
保育士の配置基準はこども家庭庁により定められています。
こども家庭庁とは2023年4月に発足した組織で、各機関が縦割りで担っていた子どもに関する行政業務を一元化し、課題に取り組むために作られました。
2024年には早速配置基準の改善がなされ、今後も見直しが検討されています。
一体何が変わったのか、解説します!
2024年に配置基準が見直された背景
- 保育の質の向上
- 子どもの安全性の確保
- 保育士の負担軽減
- 出生率の向上
保育士の配置基準は1948年に制定されて以来、大きな見直しはほとんど行われていませんでした。
2024年度に基準が見直され、4・5歳児は30対1から25対1になり、3歳児は20対1から15対1になるという改善がなされました。
上記が主な見直しの理由ですが、具体的な背景として保育施設での重大事故の増加、保育士の離職の多さ、出生率の低さなどがあります。
今後の配置基準の見直しはどうなる?
2025年度から、1歳児に対する保育士の配置基準が現行の「子ども6人に保育士1人」から「子ども5人に保育士1人」へと見直される予定です。
ちなみに、3歳以上の子どもに対する保育士の配置は「最低基準」が見直されて改善されましたが、1歳児については少し違って、「加算措置」という形での対応になります。
「最低基準」:「必ずこの人数の保育士がいなければいけない」という決まりのこと
「加算措置」:「その人数を配置すれば、国からの補助金が上乗せされます」という仕組み
全国どこの園でも守らねばならない「最低基準」に比べ、「加算措置」はあくまで努力した園への支援という位置づけです。
つまり、1歳児の配置改善は決して義務ではなく、園ごとの判断に委ねられていることに注意が必要です。
今後の動向に注目していきたいですね。
参考:こども家庭庁ホームページ 令和7年度保育関係予算案関連資料
施設別の保育士の配置基準
保育を担う施設は保育園だけではありません。
幼保一体化の動きの中でこども園が生まれ、待機児童が話題になり社会的な問題として注目される中で、乳児の保育の受け入れ先は拡充されました。
中には施設内での保育が難しい事例に対応するための事業もあります。
それぞれの施設で異なる、保育士の配置基準についてご紹介します。
認可保育園における保育士配置基準
- 0歳児 ・・・・3人
- 1・2歳児・・・6人
- 3歳児 ・・・・15人
- 4・5歳児・・・25人
上記の数は、国が認可保育園定に対して定めている保育士配置の最低基準です。
また、国が定めた法律とは別に地方自治体が独自で配置ルールを定め、保育の質を高める取り組みをしているケースもあります。



2024年度に最低基準の改定がされる前は、3歳児は20人、4・5歳児は30人となっており、それぞれ改善されています。
幼保連携型認定こども園における保育士配置基準
- 0歳児 ・・・・3人
- 1・2歳児・・・6人
- 3歳児 ・・・・15人
- 4・5歳児・・・25人
幼保連携型認定こども園では、子どもの年齢ごとの職員配置基準は、認可保育園と同じ基準が使われています。
ただし、配置される職員については違いがあり、認定こども園では「保育士」ではなく「保育教諭(=保育士+幼稚園教諭の資格)」を配置する必要があります。



「保育教諭」とは保育士資格と幼稚園教諭の免許を併せ持っている人を指します。
保育士資格のみを持っている場合は、通常より少ない単位で幼稚園教諭の資格を取れる特例措置がありますよ。
地域型保育事業 小規模保育事業 A・B型における保育士配置基準
- 0歳児 ・・・・3人
- 1・2歳児・・・6人 (保育士の数は配置基準+1人)
小規模保育事業は待機児童解消の目的で作られ、定員は6~19人です。
A型もB型も、保育者の人数に関しては認可保育園と同じ基準が適用されます。
特に注目すべき違いとして、A型では保育にあたる全ての職員が「保育士の資格を持っていること」が条件であるのに対し、B型では「保育士の割合が全体の50%以上」であればOKとされています。
また、どちらの型でも、配置が必要とされている数にプラス1人を加えた人数を確保することが義務づけられています。
地域型保育事業 小規模保育事業 C型における保育士配置基準
園児3人に対し家庭的保育者1人 (補助者を置く場合は園児5人に対し保育者2人)
小規模保育事業C型はA・B型より更に規模が小さく、定員は6人~10人です。
C型では年齢ごとに職員が配置されるのではなく、全体の人数に応じて職員の数が決まっています。
また、職員には保育士資格は必要ありません。
市町村が行う研修を受けた保育士や、保育士と同等以上の知識や経験があると認められた人が家庭的保育者として保育に携わります。
家庭的保育事業における保育士配置基準
園児3人に対して家庭的保育者1人 (家庭的保育補助者を置く場合は園児5人に対して2人)
家庭的保育事業は0~2歳を対象にしており、定員は5人です。
全体の子どもの人数に応じて保育者の人数が決められており、年齢は関係ありません。
保育者は市区町村に認定された家庭的保育者であり、必ずしも保育士資格は必要ではありません。
保育者が自宅などを保育室として提供し、より家庭的な雰囲気の中で保育ができるのが特徴です。
事業所内保育事業における保育士配置基準
- 0歳児 ・・・・3人
- 1・2歳児・・・6人
- 0歳児 ・・・・3人
- 1・2歳児・・・6人 (保育士の数は配置基準+1人)
事業所内保育事業とは、企業などの事業所内で、そこで働く保護者の子どもや地域の0~2歳児を預かる保育サービスのことです。
この保育施設の定員が20人以上となる場合は、保育士の数や施設の基準などが「認可保育園」と同じルールで運営されます。
一方で、定員が19人以下だと職員配置や施設設備について「小規模保育事業(A型・B型)」に準ずることになっています。
居宅訪問型保育事業における保育士配置基準
保育者1人につき乳幼児1人
居宅訪問型事業とは、保育を必要とする乳幼児の家で家庭的保育者が保育を行う事業の事で、1対1のマンツーマンで行われます。
保育時間は1日8時間が原則で、保育園と同じく保育所保育指針に準じて保育を提供します。
3歳未満の子どもを対象としており、条件に当てはまっていると市町村が判断すれば利用できます。
保育者は市町村に認められれば、保育士でなくても可能です。
年齢別の保育士配置基準
年齢ごとに必要となる保育士の数を考慮して設定されている基準ですが、「実際その数で保育をするのってどうなの?」「どんな配慮が必要なの?」といった疑問もありますよね。
本章では、例として認可保育園のルールについて具体的にお伝えします。
各年齢に必要な子どもへの配慮をふまえて解説しますので、参考にしてください。
0歳児における保育士配置基準
0歳児の保育においては、子ども3人に対し保育士1人の配置が求められる基準が設けられています。
愛着形成の観点からも、0歳児は特に丁寧な関わりが求められます。
また睡眠や授乳等、生活リズムがそれぞれ違うので、個々に応じた対応が必要です。
誤飲や転倒防止、SIDS防止の為の睡眠時の頻回なチェック等配慮すべき点が多く、1歳児の2倍の配置になっています。
1歳児・2歳児における保育士配置基準
1歳児および2歳児の保育においては、6人の子どもに対し保育士1人を配置することを目安としています。
歩行が発達することで行動範囲が増え、好奇心旺盛になりイヤイヤ期とも重なるこの時期は、危険の無いように見守りつつ「やりたい」気持ちを尊重する必要があります。
気持ちの代弁やルールを伝えることも大切で、個々への丁寧な関わりが求められます。
3歳児における保育士配置基準
2024年の制度見直しにより、3歳児の保育士配置基準が引き下げられ、従来の「保育士1人につき20人」から「15人」に緩和されました。
より手厚い保育を行うための改善として、現場では安心材料となっています。
3歳児は友達との関わりが増え、生活習慣の自立や言葉の発達など成長が著しい時期であり、丁寧な関わりによる支援が大切です。
2歳児から進級すると保育士の数が一気に減るので、子どもや保護者が不安に感じないような配慮も必要です。
4歳児・5歳児における保育士配置基準
4・5歳児の保育士の配置基準も、改訂により保育士1人あたりの子どもの数がこれまでの30人から25人となりました。
4歳児は子ども同士のやりとりが増えて集団遊びが盛んになる時期で、子ども同士の関わりを大切にしつつ適切な仲裁が重要です。
また5歳児は自主性や責任感が高まる時期であるとともに就学に向けた準備が必要で、それぞれの状況を把握した上で望ましい対応が求められます。
その他の保育士の配置基準
保育士の配置基準は国によって定められたルールがありますが、すべての場面で一律に適用されるとは限りません。
例外的に時間帯によって違ったり、自治体がそれぞれに目安を設けたりしている場合があります。
どうしてそれぞれで違いがあるのでしょうか。
理由についても併せてご説明します。
時間帯などによって変わる保育士の配置基準
1日を通して必要な職員の数は変わりませんが、待機児童解消に向けて緩和されている内容があります。
子どもの人数に関わらず、保育園では常に2人以上の保育士が必要だとされています。たとえ1人しか預かっていない日でも、この基準は変わりません。
ただし、朝や夕方などで子どもの数が少ない時間帯は、2人のうち1人を、自治体の研修を受けて認定された「子育て支援員」が担当することも可能とされています。
また、開所時間が8時間を超えることにより、最低基準以上の保育士が必要になった際は、その分を子育て支援員が代替できることになりました。
このように、一定の条件下では人員配置のルールが柔軟に運用される仕組みになっていて、保育士不足がなかなか解消されない中での対策となっています。
自治体によって変わる保育士の配置基準
保育士の配置に関する基準は、国が示した「最低限守るべきルール」として決められています。
しかし、自治体によってはこのルールよりもさらに手厚い配置を目指し、独自に上乗せした基準を設けて、より質の高い保育の実現に力を入れているところもあります。
朝日新聞の調べでは、全国の政令指定都市や東京23区においては6割が独自の基準を設けていることがわかりました。
また、3歳児に対して保育士1人が12人の子どもを担当するという、より手厚い配置を実施している自治体も存在しています。
こうした取り組みからも、保育の質を大切にする姿勢が感じられます。
しかし独自の基準が無い自治体もあり、自治体によって保育の質にばらつきがあるのが現状です。
自治体間格差を無くすためにも、配置基準の更なる改善が求められています。
朝日新聞 保育士配置、6割の自治体が独自基準 人材確保、待遇改善も課題
配置基準を算出する方法
①保育施設の年齢ごとの定員を確認する
②年齢ごとの定員数を配置基準で割る
③小数点以下は繰り上げる
たとえば、以下の場合何人の保育士が必要になるか、認可保育園の配置基準に基づいて計算してみましょう。
| 年齢 | 子どもの人数 | 保育士の人数 |
|---|---|---|
| 0歳児 | 3人 | 3÷3=1人 |
| 1歳児 | 6人 | 6÷6=1人 |
| 2歳児 | 12人 | 12÷6=2人 |
| 3歳児 | 30人 | 30÷15=2人 |
| 4歳児 | 25人 | 25÷25=1人 |
| 5歳児 | 30人 | 30÷25=1.2人 |
小数点以下は繰り上げとなりますので、5歳児は2人となり、合計9人の計算になります。
改定前の基準に当てはめると5歳児は1人の扱いになるので、この差は大きいですね。
配置基準の見直しで保育業界に期待される変化とは?
- 保育の質の向上
- 子どもの安全性の向上
- 保育士の負担軽減
- 保育士不足の改善
配置基準が見直されることにより、1人ひとりに関わる時間が多く確保できることから保育の質の向上が予想され、見守りの人数を増やせるので子どもの安全性が向上することも期待されています。
職員が増えることで負担の軽減につながりますし、負担が減ることで労働環境が改善され離職率が下がることで保育士不足の改善につながります。
今後更なる改定や見直しがなされることが求められていますので、配置基準の動きに注目したいですね。
保育士の配置基準を守っていないとどうなる?
- 改善勧告や命令が出される
- 業務の停止命令
- 認可・確認の取り消し
- 施設の閉鎖
保育園では、決まりが正しく守られているかを確認するために監査が行われます。
その際に配置基準についてもチェックされ、違反が確認された場合は基準を守るように勧告がなされます。
勧告に従わない場合には改善命令が出され、それでも改善されない場合は業務の停止命令や認可の取り消し、または確認取り消しとなるので速やかな対応が必要です。
最終的に施設の閉鎖という可能性もありますので、基準を守る事は保育施設を運営する上で絶対条件です。
海外の保育士配置基準はどうなっているの?
日本の保育士の配置基準に対して、海外ではどのような基準になっているのでしょうか。
本章では、経済協力開発機構(OECD)によって2018年に実施された、幼児教育・保育の環境に焦点を当てた国際調査の結果をもとに、海外の保育士配置基準や日本の保育士の満足度などについてご紹介します。
世界と比較して客観視することで、日本の保育士が置かれている状況への理解を深めましょう。
各国と日本の職員配置基準の比較
OECD加盟国における保育者の配置基準をまとめてみました。
| 3歳未満 | 3歳以上 | |
|---|---|---|
| 日本 | 0歳児)保育士1人:子ども3人 1〜2歳児)保育士1人:子ども6人 | 3〜4歳児)保育士1人:子ども20人 4〜5歳児)保育士1人:子ども30人 |
| チリ | 2歳未満)アシスタント1人:子ども7人 教員1人:子ども42人、子ども40人につき食事担当職員1人 2歳)アシスタント1人:子ども25人、教員1人:子ども32人 | 3歳)アシスタント1人と教員1人:子ども32人 4歳)アシスタント1人と教員1人:子ども35人 (ただし、グループ規模が10人以下であれば、 教員1人で可) 5〜6歳)アシスタント1人と教員人 多分1人: 子ども35人(ただし、グループ規模が15人以下 であれば、教員1人で可) |
| デンマーク | 家庭的保育に対してのみ設けている 保育者1人:子ども5人 他施設にはグループ規模、及び子ども/教職員の人数比の規制なし | |
| ドイツ(ベルリン) | 3歳未満)保育者1人当たり子ども4.8人 | 3〜5歳)保育者1人当たり子ども8.7人 |
| イスラエル | 保育施設 15ヶ月未満児)保育者1人:子ども6人 2歳未満児)保育者1人:子ども9人 2〜3歳児)保育者1人:子ども9人 家庭的保育施設 保育者1人:子ども5人 | 30人未満のグループ規模の場合: 教員1人、アシスタント1人 30人〜35人のグループ規模の場合: 教員1人、アシスタント2人 |
| 韓国 | 0歳児)保育教師1人:子ども3人 1歳児)保育教師1人:子ども5人 2歳児)保育教師1人:子ども5人 | 3歳児)保育教師1人:子ども15人 4〜5歳児)保育教師1人:子ども20人 |
| ノルウェー | 3歳未満児)少なくとも保育者1人:子ども3人 3歳未満児)少なくとも教員1人:子ども7人 | 3歳以上児)少なくとも保育者1人:子ども6人 3歳以上児)少なくとも教員1人:子ども14人 |
| トルコ | データなし | 教員1人:子ども18人 |
参照:「OECD国際幼児教育・保育従事者調査2018年報告書」に関する研究ノート
(日本は認可保育園の基準を参考にしていますが、配置基準改定前の2019年のデータとなっています。)
データからは日本は他の国と比べて、3歳以上児の場合保育者1人当たりの人数が多い事がわかります。
また、日本は多くの子どもを1人で保育できる基準になっています。
他国では1グループの数が多い場合は複数が保育することになっており、20人を超える人数を1人で保育が可能なのは日本のみです。
3歳未満児においては保育士の数は先進国の中では平均よりもやや高い数字となっています。
各国と日本の保育士の満足度は?
- 給与に満足している日本の保育者の割合・・・・・・・・・・2番目に低い(22.6%)
- 全体としてみれば、この仕事に満足していると答えた割合・・2番目に低い(80.7%)
OECD加盟国の中で日本の保育士の満足度は、給与面でも総合的に見た場合でもかなり低い数字になっています。
特に給与面で29歳以下の若い年齢層の保育士の満足度が30~40代より低いのは、日本のみに見られる傾向です。
また、「子供たちは私を保育者として高く評価している」「保護者は私を保育者として高く評価している」「保育者は社会的に高く評価されていると思う」と答えた割合は日本が最も低い事からも満足度の低さがうかがえます。
参照:OECD国際幼児教育・保育従事者調査2018報告書 第2巻-働く魅力と専門性の向上に向けて-結果のポイント
参照:OECD国際幼児教育・保育従事者調査2018 報告書-質の高い幼児教育・保育に向けて-結果のポイント
各国と日本の保育者の職務上のストレス
各国の保育について調べると、全ての調査参加国において、財政的支援、物的資源、保育者等の資源の不足が保育者のストレスの要因の上位に入っています。
保育士の配置人数が少ない日本では、他国よりもストレスを強く感じることが予想できます。
また、「子どもの育ちや学び、生活の充実に責任を負っていること」も日本の保育士がストレスを感じると回答した上位の理由です。
1人で担当する子どもの数が多いと保育における責任が大きくなることから、保育士の少なさが複数のストレスの要因になっている事が読み解けます。
参照:OECD国際幼児教育・保育従事者調査2018 報告書-質の高い幼児教育・保育に向けて-結果のポイント
現場の保育士は配置基準をどう思っている?SNSの声から分析
実に76年ぶりに改訂になった保育士の配置基準。
実際現場で働いている保育士は、改訂になった基準についてどう思っているのでしょうか。
SNSの投稿には、改訂しても保育環境の改善を実感できていないという思いが多く見られました。
保育士はどんな風に感じているのか、Xに寄せられたコメントの一部をご紹介します。
やっと25人に1人って
幼児18人に保育士1人ですら無理があると感じるのに、法定の配置基準では今年の改訂でやっと4,5歳児25人に保育士1人ってどういうことなの…?
引用元:X(旧Twitter)
子ども18人を保育士1人で担当というのは、仕事量も責任も多い上に安全を守るプレッシャーもあり、簡単ではありません。
そんな経験があるから、改訂されてもなお4・5歳児の「保育士1人:子ども25人」の基準は厳しいというのが素直な気持ちでしょう。
改定はされましたが、まだまだ現場が納得できる基準とは言えなさそうです。
あんまり変わらないけど
保育士の配置基準に改訂があって4歳さん30人に対して保育士1人→25人に1人になったみたいです
配置基準下げてくれてありがとう。
5人だとあんまり変わらないけど
あと私のみている0歳児さんは3人に対して保育士ひとり。1人おんぶ、1人抱っことして災害があった時どうやって避難するんだろうね。ね?
引用元:X(旧Twitter)
改訂したことはありがたく思っているけど、まだ不十分だというのは多くの保育士の正直な気持ちではないでしょうか。
また0歳児の「保育士1人:子ども3人」は世界的に見れば手厚い方ですが、それでも不安に感じる気持ちが見て取れます。
保育士が働きやすい環境を作る為には、保育士の人数以外にも改善すべき点が多そうです。
日本に生まれて良かったと思える保育
日本に生まれた赤ちゃん達に 『日本に生まれて良かったー!』 と思って貰える 保育士配置基準にしてくれー 日本の保育園で 子ども達の安全と幸せを満たす事が出来る 保育士配置基準にしてくれー!
保育士は皆それを望んでいるんだ。 主語がデカい? 構うもんかー!!
本当やー!!
引用元:X(旧Twitter)
目指す保育ができる職員配置を望む声です。
日本では保育先進国と呼ばれる北欧諸国と同じく、子どもの興味・関心に合わせた柔軟な保育が基本的な考え方となっています。
こういった柔軟な保育には設定型の保育よりも多くの保育者の数が必要ですが、日本は設定型の保育を行っている他国よりも少ない配置条件になっています。
保育士経験者が感じる現在の配置基準の問題点
保育士の配置基準が改善されたことは望ましいですが、まだ不十分だと感じます。
常に安全を確認しながら環境設定や個々への対応等が求められるので、忙しくてトイレに行くこともままならず膀胱炎が職業病になるほどです。
昼休みが1時間あることになっていても十分に取得するのは困難です。
子どもの命と安全と成長を保障する立場の保育士が心身共にゆとりを持って働き、更なる意欲を持てるように、職員配置の更なる充実が必要だと感じます。
まとめ
保育士の配置基準は、保育の質を確保し、保育士の労働環境を守るうえでも非常に重要であり、施設はこの基準を遵守して運営する必要があります。
また、保育に関する課題は様々ありますが、配置基準の改善は保育士不足や保育の安全性向上など、多くの課題に関わります。
今後の基準の見直しで、日本の保育がより豊かなものになると良いですね。