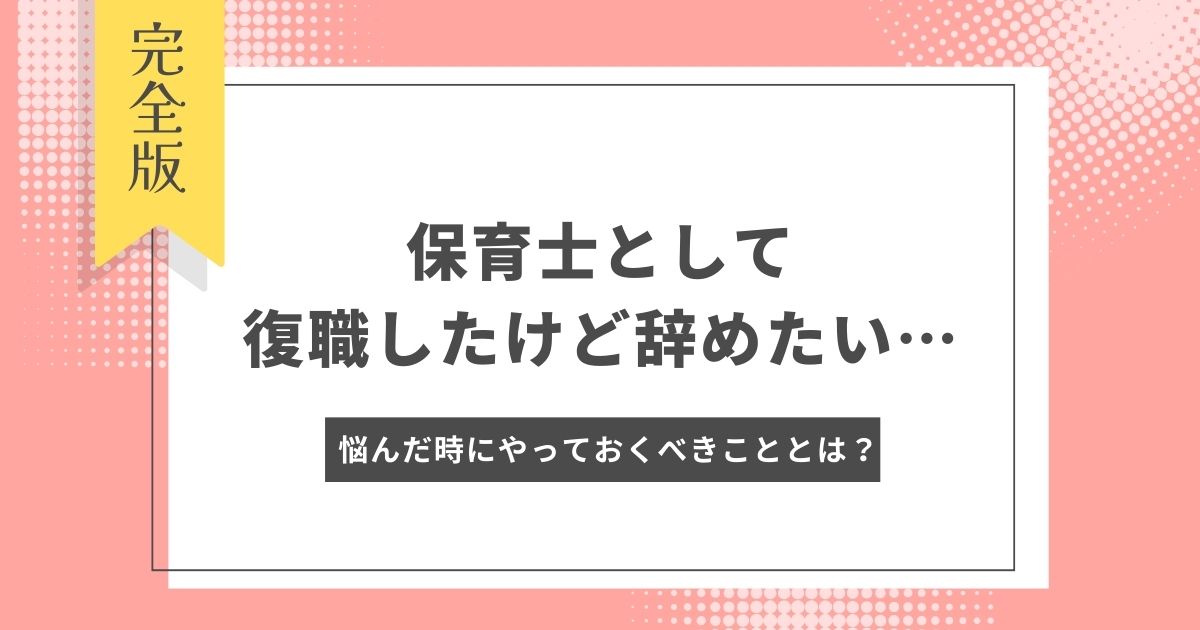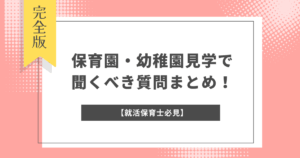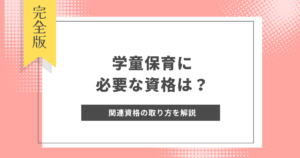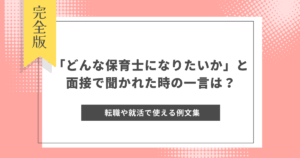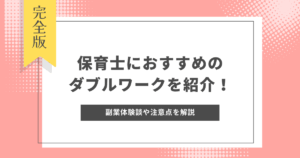保育士として復職したけどやっぱり辞めたいと思うこともありますよね。
本記事ではどうして辞めたいと感じてしまうのか、辞めたいと思った時にどうすると良いのかなどを解説します。
- 育休明けに育児との両立が負担になるなどの理由で「辞めたい」と感じる事がある
- 育休明けに仕事を辞めると収入減少などのリスクがある
- 保育士の復職を支援する制度の活用が可能
- 復職する前に準備しておくと失敗を防げる
- 職場を辞めたいときにおすすめの転職サイトを紹介
 あん【元保育士ライター】
あん【元保育士ライター】久しぶりに職場に復帰するというだけでも、ハードルを感じるものですが、子育てをしながらの復職は更に大変ですよね。
「辞めたい」と思った時にどうするのが最善なのか、どういった事に気をつければいいのかを一緒に考えてみましょう。


あん先生 元保育士ライター
保育士歴11年、現在は2児の母です。公・私立園それぞれで正規・非正規保育士として働いた経験を活かし、役立つ情報をわかりやすくお伝えします。
育休明けに退職しても大丈夫?
育休を取った後辞めることはできるのでしょうか。
結論から言うと、育休明けに退職することは法律的には問題ありません。
ですが、育休とは育児が原因で退職しなければならないという事態を防ぐことで雇用が継続できるようにするための制度です。
復帰を前提とした制度であるので、育休明けもなるべく続けるのが望ましいです。
また、法律的には問題が無いとはいえ、職場にとっても自分にとってもリスクがありますので、よく考えて決めましょう。
「保育士に復職したけど辞めたい」と思ってしまう理由
「復帰したらまた頑張って仕事をしよう」と思って産休に入ったにも関わらず、いざ復帰してみると「辞めたい」と感じてしまう人は少なくありません。
育休前は問題なく仕事ができていたのに、「辞めたい」と思ってしまうのはどうしてでしょうか。
育休明けに辞めたいと感じる5つの理由をご紹介しますので、詳しく見ていきましょう。
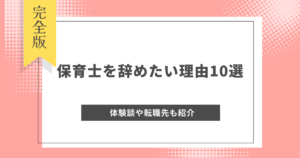
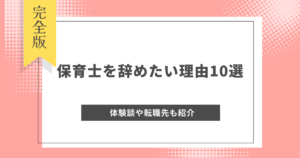
子どもとの時間を大切にしたい
育休をとる人は基本的に正職員で勤務時間が長いので、幼い子どもを預けて長時間働く事は思っていたよりもつらく感じてしまう事があります。
自分の子どもとの時間を大切にしたいと思っていたのに、ゆっくり関わる時間が少ない事が、仕事を辞めたいと思うきっかけになります。
保育園で「子どものため」を思って保育しているのに、自分の「子どものため」に時間を使えない矛盾を感じ、復職した後に辞めたいと感じる原因になります。
育児と仕事の両立が予想以上に負担
育児と仕事の両立は、出産前に思っていたよりも負担が大きいです。
復職後の慣れない環境の中1日仕事をした後に子どもを迎えに行き、まだ目が離せない子どもを見守りながら食事の用意や洗濯、掃除をするのは時間的にも体力的にも大変です。
育休前は比較的時間があったため、ある程度の家事ができていたとしても、復職後にだんだんと家事が雑になってしまう事に「もっとちゃんとしなきゃ」と焦りを感じてしまう事もあります。
子どもの預け先が確保できなかった
復職したいという気持ちがあっても、子どもを保育園等に預けられないことが理由で復職をあきらめるというケースもあります。
待機児童はずいぶん減ってきてはいますが、未だ解消には至っていません。
子どもを保育園等に預けられなった場合は育休を延長できますので、検討しても良いですね。



小規模保育園など、乳児の預け先は拡大しているので、子どもの預け先の門戸を広げて探してみると入園先が見つかりやすいかもしれませんね。
育休中に業務内容や雰囲気が変化していた
育休は多くの場合1年間ですが、保育園に入れなかった場合などは最長で2年間まで延長できますし、公立の保育士は3年間取得できます。
また、続けて妊娠・出産した場合はそれ以上に何年も続けて育休を取得することになります。
しばらく現場を離れている間に、業務内容や人間関係、園の雰囲気が大きく変わっていることは珍しい事ではありません。
以前は働きやすかった環境が変わっていて、復職はしたけど「辞めたい」と思ってしまうこともあります。
時短勤務のはずが業務量が変わらず両立が困難
子どもが小さいうちは時短勤務を希望する場合もあるでしょう。
時短勤務が認められても、担任しているクラスがあったり業務が振り分けられていなかったりすると、結局作成する書類や記録、保育準備などの業務量は変わりません。
勤務時間が短いのに業務量が多ければ、残業ができない分は持ち帰って仕事をすることになりかねません。
家事や育児をしながら持ち帰りの仕事までする余裕はなく、両立は難しいと感じてしまいます。
保育士が育休明けてすぐに辞めるリスク
保育士が育休明けすぐに辞めることはできますが、仕事を続けた時と比べて不利になる点もあります。
育休明けてすぐに辞めるとどんなリスクがあるのでしょうか。
本章では主なリスクを5つご紹介します。
どんなことが予想されるかを事前に把握しておくことで「こんなはずじゃなかった」と後悔しないようにしておきましょう。
職場の人の目が気になる
職場の人は育休後にあなたが帰って来ることを前提に仕事をしています。
新しく職員を雇わずにフリーの保育士に手伝ってもらったり、代わりに他の職員が中心になって仕事をしたりするなど、育休を取ることで少なからず他の保育士にしわ寄せがいってしまいます。
そんな中、育休後すぐに辞めてしまうとそれまで育休の穴埋めを頑張ってきた職員の頑張りを無駄にしてしまう様で罪悪感を持ってしまいますし、「どう思われているのだろう」と気になってしまいます。
世帯収入が減ってしまう
仕事を辞めると単純に収入が減ります。
パートナーなどの収入はあったとしても、それまでの想定していたよりも収入は減少します。
特に子どもが生まれると先々の教育費などを考える必要もあるので、辞めた後の金銭面についても考えなければなりません。
一旦辞めて再就職する道もありますが、職場によっては年齢制限がある等の理由で再就職が難しい事もあります。



経済的な面も考慮して仕事を辞めるかどうかを考える必要がありますね。
子どもが保育園に通えなくなる
保育園は就労などで家庭で保育ができない子どもを預かる施設ですので、仕事を辞めたら保育園に子どもを預けられなくなります。
また、もし希望していた保育園への入園が決まっていたのだとしても内定は取り消されることになりますし、次回申し込んだときにその保育園に入れる保証はありません。
就労中でなくても“求職中”という事で預けることはできますが、期間が限られていますし、仕事が決まっている人が優先的に入所できるので希望の園に入るには不利になってしまいます。
次の転職先が見つからない可能性がある
育休明けにすぐに辞めたことは履歴書から読み取れてしまいます。
次に転職を希望する職場の採用担当者からは、「また育休を取って辞められたら困る」と思われてしまいかねません。
また、復職すると約束していたのにしなかった人という、誠実さに欠けるイメージを持たれる可能性もあります。
止むを得ない理由がある場合は別ですが、単に「育休後に辞めようかな」と思っている場合は、後々にも影響する事を考えてから決めるのが良いでしょう。
給付金支給額に差が出る可能性がある
育休中にもらえる手当である育児休業給付金(育休手当)は、職場復帰を前提としているため退職した時点で給付金が支給されなくなります。
更に、育休中は健康保険料や厚生年金保険料の免除を受けることが可能ですが、育休中に退職すると、これらの免除が受けられなくなります。
失業保険は申請してもすぐには受給できないので、育休期間中に退職を考える場合は収入が減ってしまうリスクがあることを考慮する必要があります。
保育士に復職したけど辞めてしまった人の体験談
保育士に復職したけど辞めてしまった人は、実際どんな気持ちだったのでしょうか。
本章では、復職して間もなく退職した2名の方の体験談をご紹介します。
それぞれ理由は違いますが、当時の本人にとってベストな選択を考えて退職の決断をしています。
ご自分のケースと照らし合わせることで、自分らしい選択の後押しになればと思います。
子どもの体調を最優先に



育休後、子どもの保育園入園をきっかけに春から幼児クラスの副担任として復職しました。
預け始めたわが子はもともとアレルギー体質があったのですが、保育園入園をきっかけに急激に悪化してしまい、復職してすぐ「このまま働き続けるかどうか」迷う日々を過ごすことに。
最終的には子どもの体調を最優先にし、復帰からわずか二ヶ月で退職する決断をしました。
短い復職期間でしたが、親としての選択に後悔はなく、家庭の状況に応じた働き方の難しさを強く感じた経験です。
担任のクラスを持つ保育士として責任をもって仕事に取り組みたいという思いと、子どものために仕事を辞めたいという思いの間で葛藤し、とても悩んだ事が読み取れます。
「こうするのが正解」というものはありませんが、体験談の中に“親としての選択に後悔はない”とあるように、本人が納得できる選択をできることが大切であると感じます。
突然の異動に不信感



2人目の育休を終えて復帰してからわずか4か月で退職を決断しました。
理由は、私に事前の相談もなく姉妹園への異動を一方的に命じられたことです。
これまで慣れ親しんだ園で子どもや保護者、職場の仲間との関係を築いてきた中で、突然の異動は非常に戸惑うものでした。
相談もなく決められたことに強い不信感を抱き、このまま働き続けることに不安を感じました。
職員としての信頼関係や意思疎通が軽視されているように思え、退職という選択に至りました。
仕事をする上で職員間の信頼関係は重要ですよね。
施設の職員である以上、人事異動は仕方ないですが、意向を聞かず一方的に命じられることで自分がないがしろにされている感覚になってもおかしくありません。
また、不信感を持ったままでは連携もとりにくく、良い保育はできません。
我慢せず、別の職場を考えた方が前向きでいられる場合もありますね。
復職したけど辞めたい…その前にできることは?
復職したけど辞めたいと思った時、問題を整理してみることで解決の方法が見つかるかもしれません。
- パートや時短勤務に切り替えられないか相談する
- 業務量や仕事の種類を調整してもらう
- ベビーシッターを活用する
- 失業保険が受給できるか確認しておく
- 退職の意向は1~2か月前までに伝える
勤務時間の短縮や仕事量を減らすことができないかを職場に相談したり、ベビーシッターなどを活用したりすることで仕事を続けられるかもしれません。
また、もし辞めると決めたら、失業保険についての確認や退職の意向を早めに伝えるといった事が必要になってきます。
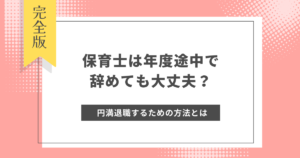
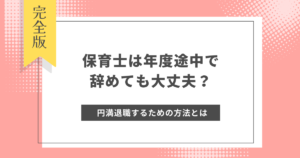
保育士に復職することのメリット
「育児と仕事の両立が難しい」「子どもとの時間が取れない」等のネガティブな印象もある復職ですが、反対に良い面もあります。
復職する事にはどんなメリットがあるのでしょうか。
復職する事のメリットを知ることで、仕事に対して前向きな見方ができるかもしれませんので、迷っているときの参考にして頂けたらと思います。
以前よりいい待遇で復職できる可能性がある
保育士は全国的に不足しており、「給与を上げてでも保育士を確保したい」という園もあります。
きっかけが無いのに急に待遇の話はしにくいですが、復職のタイミングは「時短勤務」「配置転換」「給与条件」などを話し合えるチャンスです。
特に勤続年数が長く、園にとって重要な人材であれば、条件改善の余地があります。



園の経営の状況や方針次第では待遇の改善は難しい場合もあることを理解したうえで、園とはなるべく早めに話し合いを持ちましょう。
復職補助制度を活用できる可能性がある
保育士不足を緩和するため、保育士が復職しやすいように作られた制度がいくつかあります。
「就職準備金貸付」や「保育所復帰支援貸付」等の貸付金は各都道府県が受け付けており、返還の免除もありますので確認してみても良いですね。
また「保育士・保育所支援センター」は復職相談、就職マッチング、職場見学、研修案内などを無料提供しており、復職までのサポート体制が整えられているので、復職を考えているけど不安があるといった場合に相談できますよ。
保育士の復職支援制度をチェックしよう!
保育士が不足している現状を受けて、保育士の復職には支援制度が用意されています。
公的なものから転職サイトが運営するものまでありますのでどんなものがあるのかを確認して、自分に合った制度を活用しましょう。
就職準備金貸付
保育士が就職の準備に必要なものを揃えるための資金を貸し付ける制度です。
各都道府県が窓口になっており、保育士として就職する人に、転居費用や仕事で着用する服、通勤の車などの購入に使う費用を貸し付けます。
対象者の要件などの詳細は自治体ごとに違いますし、返還の免除もありますので、詳しくは対象の都道府県にお問い合わせください。
保育所復帰支援資金
「未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業」等、自治体によって呼び方は異なりますが、保育士が新たに保育園等に就職するまたは産休育休から復帰する際に未就学の子どもの保育料が半額貸し付けられるというものです。
2年間従事すると返還が免除になるメリットもあるので、詳しくは対象の都道府県にお問い合わせください。
未就学児をもつ保育士の子供の預かり支援資金
未就学児をもつ保育士が保育園などに勤務する場合に、ファミリーサポートセンターやベビーシッター派遣事業を利用した際、利用料金の半額を無利子で借りられる制度です。
年間の貸付上限額は123,000円で、2年間継続して勤務した場合は返還が免除となります。
貸付対象者の詳しい要件は自治体によって異なりますので、対象となる都道府県にご確認ください。



保育園だけでなく、ファミリーサポートセンターなどに使える貸付があると、時差出勤等にも対応できますね。
就職相談会や就職支援セミナー
就職相談会や就職セミナーは多種多様で、国や自治体、ハローワーク、転職サイトなど様々な機関が主体となって開催しています。
オンラインで開催しているものもあり、地方での就職活動にも活用できる仕組みになっています。
また、「保育施設限定」など特定の職業に特化したものもあるので、自分に合ったものを効率よく活用すると良いでしょう。
保育士の復職で失敗しないためには?
久しぶりの保育士としての仕事復帰を前にして、どんな準備をすればよいのか悩んでしまうこともあるかと思います。
焦ったり失敗したりしないように、また納得できる復職となるように事前に準備をしておきましょう。
本章では、保育士の復職で失敗しないためのポイントをまとめていますので参考にしてみてくださいね。
保育士証の確認
保育士として働く場合は保育士証が交付されていることが必要ですが、子育ての忙しさで管理が行き届かず紛失していては大変です。
また、結婚などにより名前や本籍地が変更されている場合は、登録内容を変更する必要があります。



再発行や登録内容の変更は、届出てもすぐにはできませんので、時間に余裕を持って準備しておきましょう。
希望条件を明確にしておく
復職するにあたって、希望する勤務の条件を明確にすることで自分の希望する働き方が見えてきます。
- 時短勤務
- 担任を持つかどうか
- 業務量・内容
- 時差出勤
- 休日
- 残業の有無
子育てをしながら無理のない範囲で仕事を続ける為に、どのような働き方を希望しているかを縁側に提示し、どうしても譲れない部分があればそれも伝えましょう。
就職相談会や就職支援セミナーに参加する
今までとは違う職場に復帰したいときには、就職相談会や就職支援セミナーに参加するのが有効です。
多くの求人を知ることで子育てと両立しやすい求人を見つけやすいですし、園の担当者と直接話せるので、面接前に「残業の有無」「子育て中の勤務シフト」などリアルな質問ができるのも魅力です。



セミナーでは保育現場の最新情報なども学べるので心強いですね。
子どもの預け先を決めておく
復職にあたっては、家庭で保育する人がいる場合を除いて、子どもの預け先を確保しておく必要があります。
保育園等の入園申し込みの時期や方法は各自治体によって少しずつ違いますので、早めに問い合わせることをおすすめします。
入所予定の園を見学したい場合も、園側の都合がありますので早めに連絡するのが良いでしょう。
復職したけど辞めたいときにおすすめの保育士転職サイト
復職したけどやっぱり辞めたいと思った時、転職先を探すのにおすすめの保育士転職サイトをご紹介します。
「保育士の転職サイトってたくさんあるけど、どれを選べばいいのかわからない」「登録ってハードルが高い」と思ってしまいがちですよね。
本章では、実績のある保育士転職サイトをご紹介しますので参考にしてみてください。
保育士ワーカー
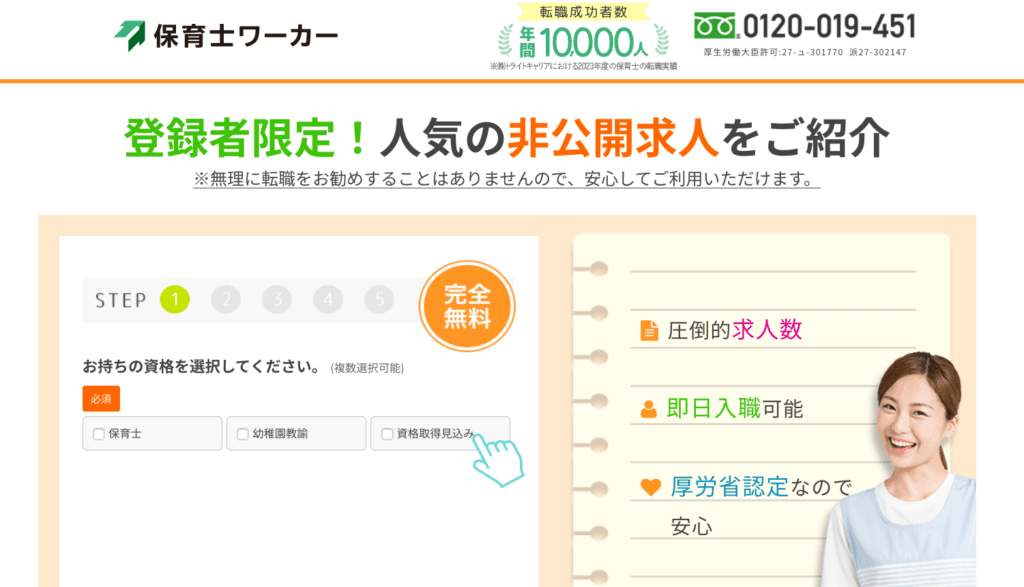
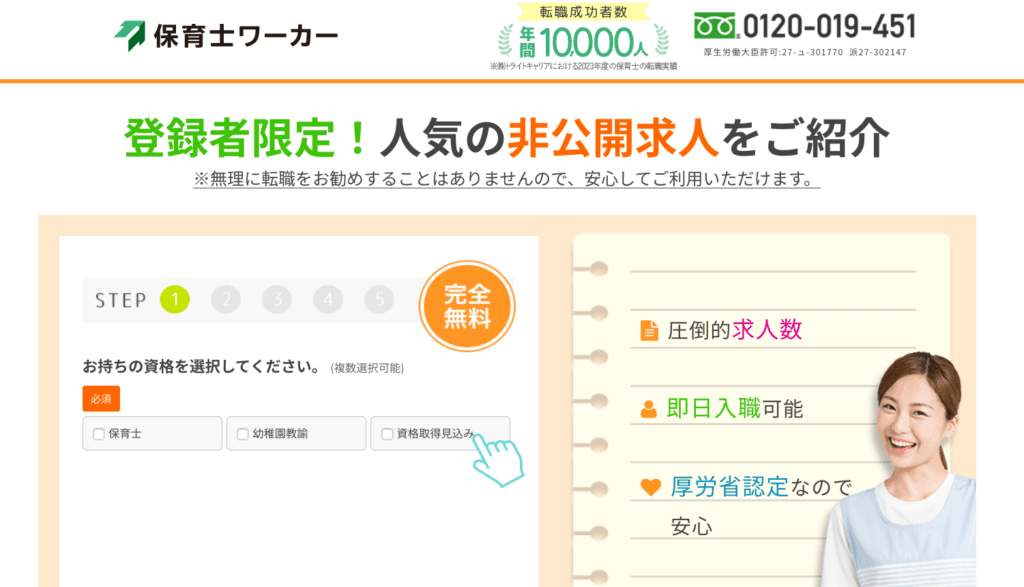
| 運営会社 | 株式会社トライトキャリア |
|---|---|
| 求人数 | 24,000件以上 |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト |
| 公式サイト | 保育士ワーカー |
保育士ワーカーは求人数も転職の成功者も多く、実績のある転職サイトです。
サイトでは検索項目が多く、希望の求人を見つけやすくなっています。
また、アドバイザーが職場の雰囲気などの施設の情報を詳細に教えてくれ、面接の日程調整や条件調整を行ってくれるなど、手厚いサポートが受けられます。
入職希望が半年以内の保育士は優先的に対応してもらえるので、早期での転職も可能です。
非公開求人も多数ありますので、とりあえず登録しておくのも良いでしょう。
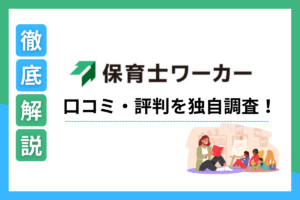
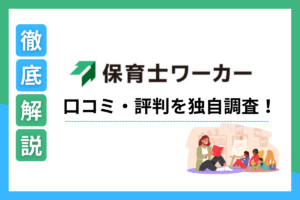
マイナビ保育士


| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
|---|---|
| 求人数 | 20,000件以上 |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員、派遣社員、パート・アルバイト |
| 公式サイト | ここに記述 |
マイナビ保育士は大手人材派遣会社のマイナビが運営しています。
求人は特に一都三県のものが多いので、首都圏での転職を希望している方にはおすすめの転職サイトです。
履歴書の添削や職場環境の事前確認、給与などの条件の交渉を代わりにしてくれるなど、手厚いサポート体制があるのは安心できる点ですね。
入職後のアフターフォローもしてもらえるので、新しい職場で何かあった時にも相談できるという安心感がありますね。
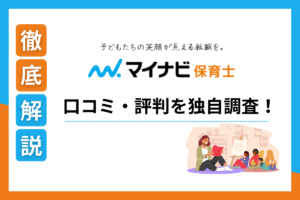
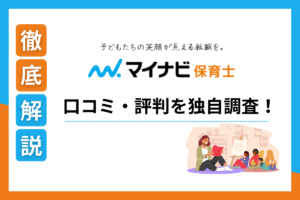
保育士人材バンク


| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス |
|---|---|
| 求人数 | 20,000件以上 |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、派遣、パート・アルバイト |
| 公式サイト | 保育士人材バンク |
保育士人材バンクは上場企業が運営しており、厚生労働省の優良事業認定を受けていることもあり安心して利用できる転職サイトとなっています。
求人エリアは全国ですが、一都三県の求人が豊富です。
専門のキャリアアドバイザーが求人票ではわからない施設の詳細を教えてくれるという点でも高評価を得ています。
また保育環境や勤務条件を、サイト独自の細かい条件で絞って検索できるので、希望に合った求人を探しやすいのも魅力です。
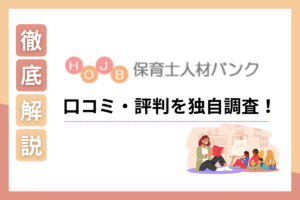
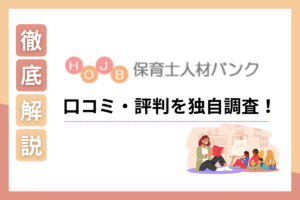
まとめ
復職後には様々な理由で「辞めたい」と思うことがありますよね。
周りに迷惑をかけないことは大切ですが、無理をしていては続けられませんし、自分の子どもに大きなしわ寄せがいく事にもなりかねません。
勤務の条件を交渉したり、場合によっては辞める決断も必要でしょう。
何が大切かをよく考え、納得できる道を選びましょう。