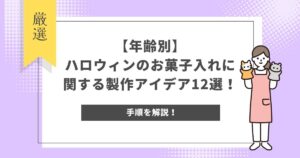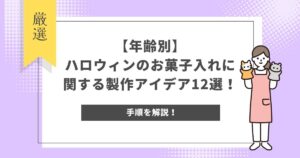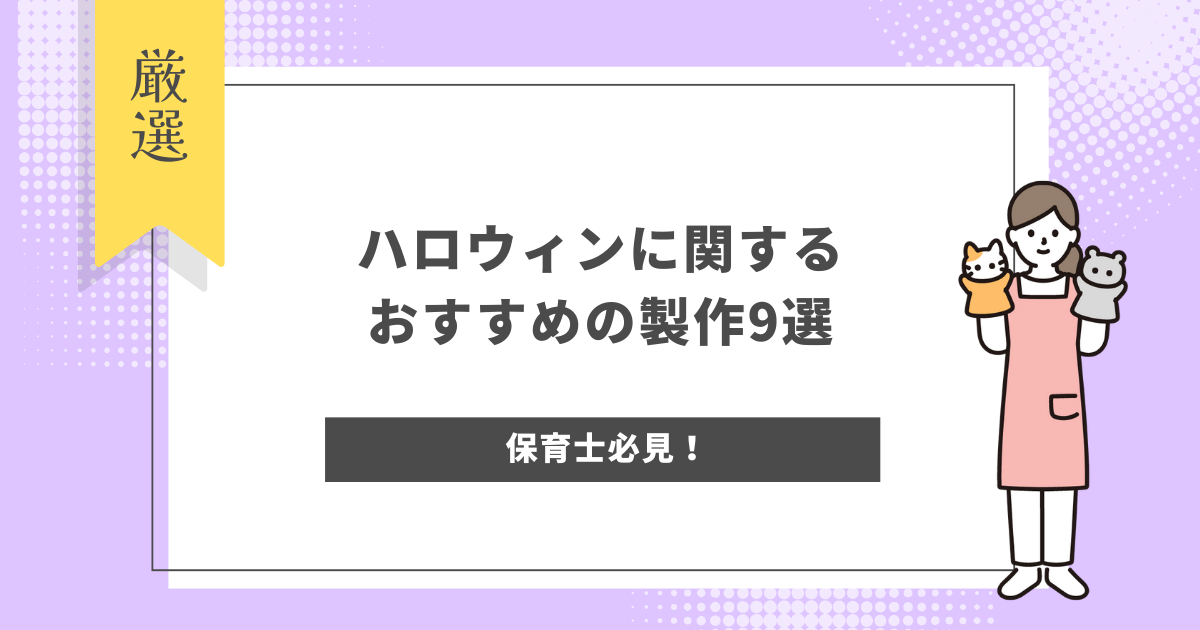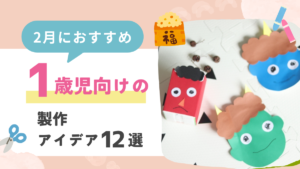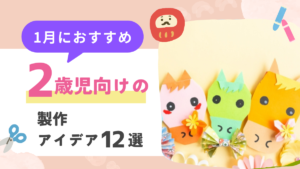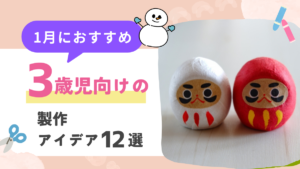ハロウィンは秋の一大イベントですね。
季節を味わうことを大切にする保育の現場では、ハロウィンに関連した保育が展開されたり、ハロウィンに関する製作活動を取り入れたりすることが多いです。
忙しい毎日の中で、「ハロウィンに関する製作って何がある?」「年齢に合わせた製作内容を考えるのが大変」と思うこともありますよね。
本記事では、年齢別のおすすめのハロウィン製作を動画付きでご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください!
- ハロウィンの起源は古代ケルト人の魔よけの風習である
- 製作にハロウィンを取り入れることで、季節の行事に親しみイメージを膨らませて取り組める
- 年齢別の動画付きの製作について解説している
 あん【元保育士ライター】
あん【元保育士ライター】何かと忙しい秋、製作について考えるのが大変…と思った時にお役に立てたら嬉しいです!


あん先生 元保育士ライター
保育士歴11年、現在は2児の母です。公・私立園それぞれで正規・非正規保育士として働いた経験を活かし、役立つ情報をわかりやすくお伝えします。
ハロウィンについて


ハロウィンの起源
ハロウィンは、ヨーロッパに住んでいた古代ケルト人の風習が起源とされています。
古代ケルト人の風習では、10/31は死者の霊が親族の家を訪れる日であると同時に、悪霊や魔物もこの世に現れて悪さをするということで、自ら魔物の格好をすることにより身を守りました。
また11/2の死者の日には、ソウルケーキと呼ばれるお菓子を食べて死者の霊の成仏を祈りました。
後にアメリカに移住したケルト人の文化が広まり、今のハロウィンの形になったと言われています。
ハロウィン製作のねらい
様々な素材や道具に触れたり表現する楽しさを味わったり、時に友達と協力し合いながら取り組める製作活動は子どもの育ちにおいて大きな役割を果たします。
加えて、ハロウィンを製作に取り入れることで、季節の行事に親しみ、想像を膨らませて表現する楽しさを味わえます。
また、作ったものを飾ることでハロウィンの雰囲気を感じられますし、作ったものを使ってハロウィンごっこをすると、より行事に関心が持てますね。
【0~1歳児におすすめ】ハロウィンに関する製作3選
0~1歳児の製作活動では、感触や音、色、動きなどを楽しむことが大切です。
年齢が低いと、製作で何をすればいいのか困ってしまうこともあるかと思います。
下記の製作以外にも、フラワーペーパーを子どもたちがちぎったものをポリ袋に入れ、おばけの顔を付けるだけで、おばけのボールができますよ。
また、なぐり書きした絵を紙コップに貼り目玉を付けてマラカスにするなど、子どもが楽しめることを考えるとアイデアが生まれますね。
ハロウィンの手形足形アート
0~1歳児の手形・足形スタンプの製作は定番ですね。
この動画ではハロウィンらしく、かぼちゃのおばけ、コウモリ、おばけにアレンジしています。
もちろん動画で紹介されている以外にも、カラフルな色で手形を押してモンスターにするなどのアレンジをしてもかわいいです。
動画でも説明がある通り、顔を子どもが描くか保育士が描くか、またシールを貼るか等は子どもに合わせて、楽しめたり意欲を持てたりする方法で取り組むと良いですね。
- 画用紙(白・黒)
- 絵の具
- 筆(スポンジ)
- 鉛筆
- はさみ
- シールやクレヨン
- のり
- 子どもの手足に絵の具を付け、手形や足形をとる
- 乾いたら手形や足形を切り取る
- 台紙となる画用紙に、切り取った手形や足形を貼る(それぞれの形になるように配置する)
- 画用紙で作った顔などのパーツを貼る(なぐり書きしたものを使うのも良い)
- 場合に応じてシールを貼る
- 台紙にお菓子やおばけをつけて飾り付けてもかわいい
感触遊びモンスター
色んな形のモンスターがかわいい作品ですね。
袋の上から絵の具を触る感触や、触った絵の具が広がる面白さを味わえる製作遊びです。
動画の3色以外にも、どんな色の絵の具でも素敵な作品になりますよ。
黒い画用紙に、白や白を混ぜて作ったパステルカラーの絵の具を乗せても夜のイメージになって面白いですね。
感触を味わいながらも指が汚れないので取り組みやすいです。
もちろん、袋を使わずにフィンガーペインティングにしてもOKですよ。
- 画用紙
- ジッパー袋
- 絵の具
- 丸シール(白)
- ペン
- 画用紙をジッパー袋に入る大きさに切る
- ジッパー袋に画用紙を入れ、絵の具を点々と乗せる
- 子どもが袋の上から絵の具をのばす(触ったりおさえたりのばしたりして遊ぶ)
- 袋から取り出す
- 絵の具を乾かす
- 丸シールの目を貼る
- 丸シールに目を書く
- 【アレンジ】画用紙で作ったコウモリやキャンディを貼ると、ハロウィンっぽい雰囲気になる
新聞スタンプでジャック・オ・ランタン
年齢の低い子ども向けのスタンプ遊びには“たんぽ”を取り入れる事が多いですが、こちらは新聞紙を使ったスタンプです。
新聞紙のスタンプの良いところは、まず掴みやすい事です。
新聞紙の大きさを調整することで、子どもの手にちょうど良い大きさのスタンプを作れますし、しっかり握れるので力を入れやすいところも良いですね。
新聞紙をくしゃくしゃに丸める工程も楽しめますよ。
また子どもが自由に貼った顔は、個性的な配置になって素敵ですね。
- 画用紙(黄・黒・黄緑・紺)
- 絵の具
- 新聞紙
- リボン
- のりまたは両面テープ
- 画用紙を切って、かぼちゃを作る(黄色のかぼちゃに黄緑色のヘタをつける)
- ジャック・オ・ランタンの顔のパーツや服も画用紙を切って作っておく
- 新聞紙をくしゃくしゃに丸める
- 新聞紙に絵の具を付けてスタンプする
- 顔のパーツを貼る(のりや両面テープなどを使う)
- 切っておいた服を貼り合わせる
- 服にリボンをつけて完成
【2~3歳児におすすめ】ハロウィンに関する製作3選
2~3歳児の製作遊びでは、「自分でやってみたい」「作るって楽しい」という気持ちを育むことが重要です。
ちぎったり塗ったりと手を動かす中で、「何を描こう」「どんな色にしようかな」等と考える面白さを感じられます。
作品の「完成度」ではなく、子どもが意欲や楽しさを感じて主体的に取り組むことを大切にしたいものです。
大人の真似をして行事を楽しめるようになってくる時期ですので、子どもの興味をうまく製作遊びにつなげたいですね。
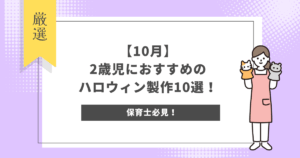
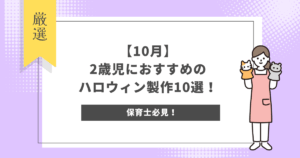
おばけが浮き出るはじき絵
クレパスで描いた絵が絵の具を塗ることで浮き出てくるはじき絵は、驚きや楽しさを感じられる製作遊びです。
暗闇に現れるおばけを描いて楽しむのには、ぴったりの技法とも言えますね。
クレパスの色を薄めにして絵の具の色を暗めにすると、“見えないおばけが現れる面白さ”を感じやすいです。
また、筆は太めのものが使いやすいです。
薄くといた絵の具はコップの様な容器に多めに作っておき、紺や黒等、選んで使えるようにしておくと良いですよ。
- 画用紙
- クレパスまたはクレヨン(薄い色)
- 薄くといた絵の具(暗い色)
- 筆
- 画用紙にクレパスで、おばけなどの好きな絵を描く
- 薄くといた絵の具をクレパスの絵の上から塗る
- 乾かしたら出来上がり
- 【アレンジ1】画用紙等で作ったコウモリやお菓子などを貼るとハロウィンの雰囲気が増す
- 【アレンジ2】はじき絵で描いた絵を保育士が切り抜いて、ハロウィンの衣装の帽子やバッグ等に貼って飾り付ける
ひも通しでくものす
ひも通しは、指先の微細運動を促し、手と目の連携や手指の細かい動きの発達が促されます。
また、繰り返しの運動なので、集中して取り組める活動です。
動画の様にきれいな形にならず、輪っかの外側を毛糸が通る事なども予想されますが、それも含めて個性的な作品になりますね。
星の型抜きで飾り付けする部分は、子どもがシールを貼っても良いですし、事前に子どもがスタンプしたりなぐり書きしたりしたものを切り取って使っても良いですね。
- 画用紙
- 毛糸
- モール
- セロテープ
- 型抜きした星
- のり
- 画用紙で輪っかを作り、穴あけパンチで穴を数か所空ける。
- 毛糸の端をテープでとめて、反対側の端を穴に通していく(毛糸の端はセロテープを巻いておくと通しやすい)
- 通し終えたら、毛糸の端をテープでとめる
- 同じ長さに切った4本のモールを真ん中でねじる
- モールをクモの足の様に広げて体と目をボンドで貼る
- 星の形の型抜きをのりで輪っかに貼る
マーブルおばけ
色が混ざって思いがけない模様になるマーブリングはきれいですね。
通常のやり方では水の上に絵の具を流し入れて竹串などで模様を作り、紙をそっと浮かせて作りますが、加減が必要であったりして2~3歳児には少し難しいです。
この動画で紹介されているやり方は簡単なので無理なく取り組めますよ。
色を混ぜすぎると汚くなってしまうので、3色までがおすすめです。
紙をめくるときにどんな模様になっているか、ワクワクする製作です。
- 白い画用紙
- アルミホイル
- 水性ペン
- 水を入れた霧吹き
- ペン
- (目玉)
- 画用紙をおばけなどの形に切っておく
- アルミホイルに水性ペンで色を付ける
- 水性ペンで塗った部分に霧吹きする
- 画用紙を乗せてはがす
- ペンや目玉シールをつかって顔を描く
- 【アレンジ1】黒や紺色の画用紙に貼ると、夜の雰囲気が出て作品が際立つ
- 【アレンジ2】輪っかに作ったおばけなどを貼り付けて、ハロウィンリースにしても良い
【4~5歳児におすすめ】ハロウィンに関する製作3選
4~5歳児になると、はさみやのりなどの道具を自由に使えるようになってきます。
また、手先の器用さや構成力が発達してきて、“自分で工夫して作る”、“イメージを膨らませて作る”といった取り組み方ができるようになってきます。
少し難しい事や根気が必要な活動にも挑戦することで、達成感を感じられる活動を取り入れても良いでしょう。
作った作品を通して、ハロウィンの雰囲気を友達と一緒に楽しめると良いですね。
ステンシルで作るハロウィンハウス
不思議な雰囲気で、はっと目を引く作品ですね。
たんぽは低年齢児の製作で使う事が多いですが、このステンシルは4~5歳児でも十分に楽しめます。
家や木は自分で描いて切り抜くと、個性豊かな作品になりますよ。
また、スタンプする絵の具は、動画の様に2色ほど使用すると良い雰囲気になります。
絵の具をとく水は少なめにしましょう。
仕上げに貼るおばけや窓は、子どもたちがイメージを膨らませて、思い思いに作れると良いですね。
- 画用紙(白・黒・黄色など)
- 割りばし
- 綿
- 輪ゴム
- ガーゼ
- 絵の具
- 綿の周りにガーゼを巻いたものを割りばしの先端に輪ゴムで付ける(たんぽの棒)
- 白の画用紙に家や木の絵を描き、切り取る
- ②の画用紙の裏にマスキングテープを貼り、黒の画用紙に付けて固定する
- たんぽの棒に水で溶いた絵の具を付けてスタンプする(白画用紙のフチはしっかりスタンプする)
- 白の画用紙をはがす
- コウモリやおばけ、窓などを付けて完成
折り紙で作るクモのす
ハロウィンの飾りつけに欠かせないクモのすは、折り紙で簡単に作れます。
工程自体はシンプルですが、間違わずに線を引いたりはさみで細かい部分を切り取ったり破らずに開いたりと、理解力や技術力が必要な製作です。
線を引くところを間違えてしまうとクモのすにならずにバラバラになってしまうこともありますが失敗することで成長します。
アレンジも色々できますので、何度も挑戦していろんなクモのすを作ってみましょう!
- 折り紙
- 太めのペン
- はさみ
- 折り紙の色の面が上になるように机に置く
- 三角に4回折る
- 1回開き、真ん中の折り筋をなぞるように太めのペンで線を書く
- 真ん中の線を軸にし、左右対称に端に向かって線を引く(少し曲がった線の方がクモのすっぽくなる)
- ペンで書いた部分以外を切り取る
- 折り紙を開いて完成(破れないようにそうっと開くのがポイント)
張り子のハロウィン飾り
張り子で作るハロウィン飾りは、バッグにしたりちょうちんの様に飾ったりしても良いですし、明かりを入れてランタンにしてもきれいですね。
4~5歳児になると、画用紙の色を選んだり顔のパーツを作ったり、2本のモールをねじったりと、できる工程が多いです。
子どもの様子を見て取り組み方を考えると良いですね。
また、工程が多い製作である上に張り子は乾燥させる時間が必要ですので、製作にかける期間は余裕を持つことをおすすめします。
- 画用紙の切れ端
- 黒画用紙
- モール 2本
- 厚紙
- 風船
- 液体のり(または薄めたボンド)
- 両面テープ
- 2本のモールはねじって1本にし、切れ端の画用紙はくしゃくしゃにして破る
- 破った紙にのりを付けて、膨らませた風船全体に貼る
- ②を乾かす
- 風船に穴を空け、紙からはがす
- 入口の部分を切って形を整える
- 黒画用紙で作った顔を、両面テープで貼る
- 持ち手を取り付ける部分に厚紙を貼り、穴を空ける
- モールを穴に通して持ち手にする