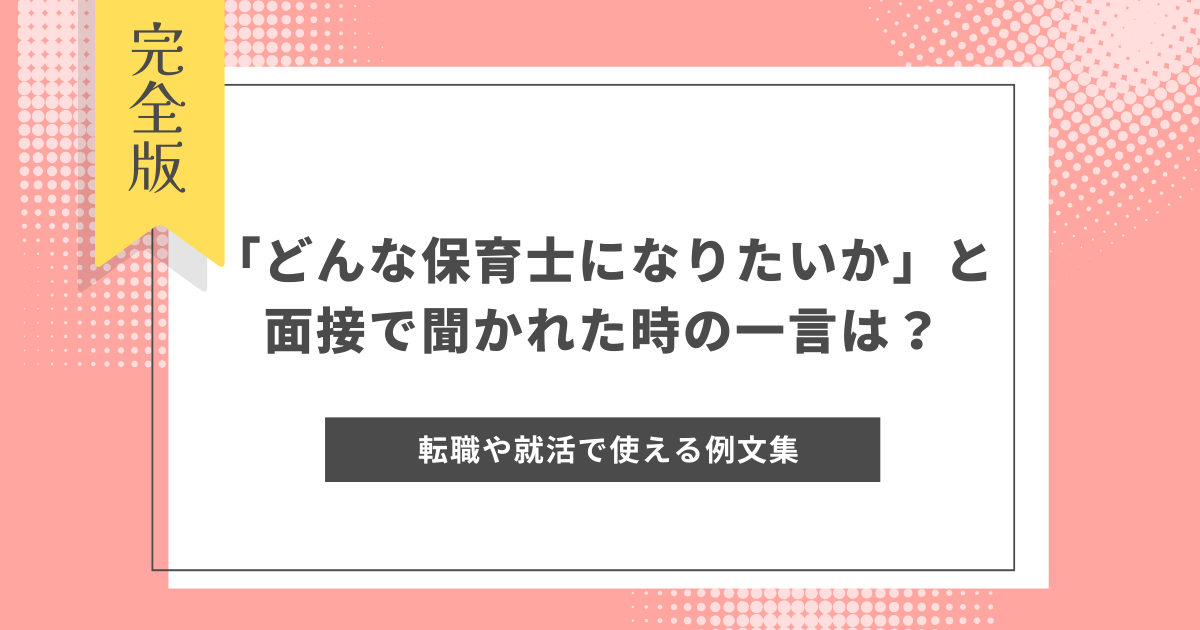就職活動や転職活動の面接でよく聞かれる定番の質問として「どんな保育士になりたいですか?」があり、実際に聞かれた経験のある人も多いのではないでしょうか。
採用担当者は、あなたの保育観や人柄、園との相性を知るため、この質問を非常に重視しています。
自分の思いをうまくまとめるのは難しいですが、事前に整理しておけば安心ですよ。
本記事では、回答の意図や例文を紹介し、面接や作文で役立つヒントをお届けします。
- 「どんな保育士になりたいか」聞かれるのは、保育観や園との相性などを知るため
- ただ理想を語るだけでなく、実現するために行っている具体的な行動を伝えられるとなお良し
- 面接では、緊張していたとしても誠実に伝えるように意識する
- どんな保育士になりたいか、思いつかない場合は過去を振り返るとヒントになる
 ちあき【元保育士ライター】
ちあき【元保育士ライター】私は何回か転職経験がありますが、必ずと言っていいほど聞かれている質問です!就職活動中や転職活動中の保育士は要チェックですよ。備えあれば憂いなし、です!


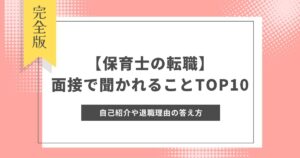
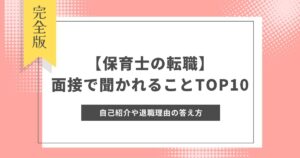


ちあき先生
認可保育園で勤務後退職して留学。その後は英語の幼稚園で働く。結婚を機に派遣保育士に転身し、さまざまな園で経験を積む。保育士歴は通算7年ほど。
子どもが重度アレルギー児になったことでライターに転身した2児の母。
「どんな保育士になりたいか」を面接で聞かれる理由は?
採用担当者が知りたいのは、保育士としての経験やスキルだけではなく、あなたの保育に対する考え方や人柄、園の方針とのマッチ度です。
どんな保育観を持ち、どのような人柄で園の雰囲気や保育方針と合うかどうかを判断するために「どんな保育士になりたいか」という質問が投げかけられます。
代表的な理由を挙げて詳しく解説しましたので、参考にしてください。
子どもへの向き合い方(保育観)を知るため
園によって保育士に求める保育観は異なるため、採用面接で応募者の子どもへの向き合い方を知る必要があります。
例えば「子どもの主体性を尊重する園」では、子どもの自由な遊びを尊重して見守れる姿勢が大切なポイントです。
一方「カリキュラムを通してたくさんの経験をして子どもの可能性を広げる園」では、多様な活動で子どもの興味関心を引き出すことにやりがいを感じている保育士を求めています。
自分なりの目標や方向性があるかを確認するため
応募者が入職後にどのような目標や方向性を持っているかを知るために、「どんな保育士になりたいか」質問することもあります。
なんとなく仕事をするよりも、自分なりの理想像を持ち、保育を通して成長しようとする姿勢がある人は、現場で経験を通してより学びを深めて専門性を高めていけます。
応募者に主体性や学ぶ姿勢があるか、保育現場での成長可能性はあるかを確認するための質問です。
園の方針やチームとの相性を見極めるため
採用担当者は、応募者の保育観を知るだけでなく園の保育士と一緒に働ける人材かどうかも重視しています。
- 質問の回答が園の方針と合っているか
- チームで協力できる姿勢があるか
- 園の保育に興味関心をもっているか
就業スタートしてから前向きな気持ちで関われるかどうかを見極めるために、「どんな保育士になりたいか」という質問がされます。
自己理解・自己表現力があるかを見るため
「どんな保育士になりたいか」という質問の背景には、どれだけ自分のことを理解しているか、自分を言葉で表現できるかを確認する意図があります。
自分の強みや課題を理解しているか、そしてそれを簡潔に言葉で伝えられるかが重要です。
採用担当者は、自己理解の深さと表現力を通して、今後の成長可能性や保育士としての姿勢を見極めています。
「どんな保育士になりたいか」と聞かれた時の例文集
「どんな保育士になりたいか」は、いざ聞かれると答えに悩みがちな質問ですが、事前に参考となる例文を読んでおくことで自分に近い考えが見つかります。
本章ではシーン別に使いやすい例文を紹介します。
下記の例文をヒントにして、自分だけの回答を考えてみてくださいね。
短く簡潔にまとめ、園の方針や自分の強みとリンクさせることがポイントですよ。
常に笑顔で親しみやすい保育士
「私は、いつでも笑顔で子どもたちに接する保育士になりたいです。子どもにとって保育園は家庭の次に安心できる場所であるべきだと思います。笑顔で寄り添うことで、子どもが『ここに来ると楽しい』と感じられるような雰囲気をつくりたいです。」
上記の例文には、子どもにとって保育士が安心の存在であることの大切さが込められています。
笑顔は子どもだけでなく保護者や同僚にも安心感を与え、園全体を明るい雰囲気にする力があります。
日々の小さな関わりの積み重ねが信頼につながり、子どもの成長を支える土台となるのです。
子どもの可能性を引き出す保育士
「子どもたちが自分らしく表現できる環境をつくり、一人ひとりの可能性を引き出せる保育士になりたいです。小さな『できた!』を否定せずに丁寧に受け止めて、積み重ねることで、自信を持ち、挑戦する意欲を育んでいけるようサポートしていきたいと思います。」
上記の例文からは、保育士が子どもたちに対して肯定的なまなざしを持っていることが分かります。
子どもたちが安心して成長でき、前向きに挑戦を重ねていき、すくすくと育つイメージが湧きますね。
失敗も成長の一部として受け止め、次へのステップへと導く姿勢は採用担当者へも好印象でしょう。
子どもの心に寄り添える思いやりのある保育士
「子どもたちの気持ちに寄り添い、安心して過ごせる環境を整える保育士を目指しています。子どもが発する小さなサインに気づき、受け止めることで信頼関係を築きたいです。そして『先生がいるから安心』と思える存在になりたいです。」
子どもが育つ上で、情緒的な安定は欠かせません。
上記の例文は、子どもの表情やしぐさから不安や喜びを感じ取り、それに応じて声をかけることで、安心できる環境を整えてくれそうな保育士像が見えてきますね。
採用担当者は、応募者の理想の保育士像から、今後どのような保育士になるのかを見極めています。
子どもと全力で遊び、共に楽しめる保育士
「子どもたちと目線を合わせて一緒に全力で遊び、喜びや楽しさを共有できる保育士になりたいです。追いかけっこや製作なども遊びと同じように、常に子どもと同じ目線を意識していきます。その中で、遊びの中で自然と学びや成長につながる経験を大切にしていきたいと思います。」
保育士が子どもの世界に入り込み一緒に楽しむことで信頼関係が深まり、子どもも積極的に挑戦するようになります。
上記のような理想の保育士像を持っている先生には、遊びを主体とした保育園と相性が良さそうですね。
自然の中で学びを育む感性豊かな保育士
「自然に触れることで得られる学びを大切にし、子どもと一緒に発見や感動を共有できる保育士になりたいです。草花や季節の変化を感じる活動を通じて、子どもが感性を育み、心豊かに成長できるような保育を実践したいです。」
自然は、子どもの感性や探究心を伸ばすうえで大きな役割を持ちます。
自然体験は予測外の発見が多く、驚きや疑問を子どもと一緒に分かち合える場です。
上記のような理想の保育士像を持つ保育士のまなざしや関わりは、子どもにとって学びを広げるきっかけになりそうですね。
保護者に安心と信頼を届ける保育士
「子どもだけでなく、保護者にとっても安心できる存在でありたいと思っています。日々の出来事を丁寧に伝え、子育ての悩みを一緒に考えられる保育士を目指しています。保護者と信頼関係を築くことで、子どもの成長を共に支えていきたいです。」
上記の例文は、保育士は家庭と密につながって共に子育てをサポートする役割を意識していることが感じられます。
保護者に寄り添い安心感を届けることで、子どもはより安定して園生活を送れますし、強い信頼関係を築けることでしょう。
理想の保育士像が現実になったら、保護者と共に子どもの発達を支える連携が可能になります。
チームワークを大事にできる保育士
「同僚や先輩後輩と協力し合い、チームとして子どもを支える保育士になりたいです。困ったときには助け合い、それぞれの強みを生かすことで、子どもたちにとってよりよい環境を作りたいと思います。協調性を大切に働きたいです。」
上記の例文からは、現場でのチームワークを重要視していることが分かります。
保育は一人では完結せず、仲間と協力することで子どもへの関わりがより豊かになります。
互いの強みを尊重し合う姿勢は、採用担当者にとっても印象が良く、高い評価を得られそうです。
「どんな保育士になりたいか」を聞かれた時の注意点
「どんな保育士になりたいか」という質問は、面接で必ずといってよいほど出てきます。
しかし、ただ理想を語るだけでは不十分です。
採用担当者が知りたいと感じている点が過不足なく伝わるよう、気を付けましょう。
場面ごとに気をつけるポイントを理解しておけば、自分の思いをきちんと伝えられ、面接官にも誠実さや成長意欲が伝わりますよ。
面接の場合
面接で「どんな保育士になりたいか」と聞かれた際は、誠実さが大切です。
短い言葉で自分の思いをまとめ、園の方針と重なる部分を意識して伝えると好印象ですよ。
- 園の保育方針とリンクさせる
- 明るく前向きな言葉を選ぶ
- 実現可能な内容にする
例えば「子ども一人ひとりに寄り添える保育士になりたいです。そのために日々の小さなサインを見逃さず、安心できる環境をつくりたいと考えています。」といった回答なら、具体性と現実性があり評価されやすいです。
面接では、緊張していても誠実に伝えようとする姿勢が面接官に好印象を与えます。
作文の場合
作文で問われる場合は、具体性と構成力が評価のポイントになります。
抽象的すぎる内容では伝わりにくいため、自分の体験やエピソードを交えて書くことが大切です。
- 導入・本文・結論の流れを意識する
- 自分の体験や学びを盛り込む
- 理想だけでなく努力していることも書く
- 誤字脱字や表現の丁寧さに注意する
経験と目標や具体的なエピソードなどを盛り込むことで、説得力のある文章になります。
「どんな保育士になりたいか」が浮かばない時に役立つポイント5つ
「正直、どんな保育士になりたいのか自分でもよくわからない…」と悩む人も少なくありません。
理想像がすぐに思いつかなくても大丈夫です。
自分の中にある思いや経験を丁寧に振り返ることで、自然と答えが見えてきます。
本章では5つの視点を紹介します。
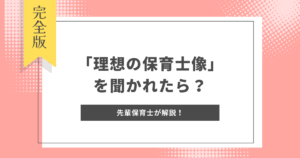
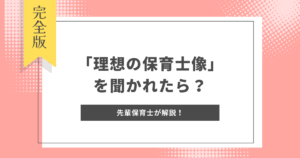
なぜ保育士を目指そうと思ったのか振り返ってみる
保育士になろうと思った最初の原点に、ヒントが隠されているケースがあります。
- 子どもが好きだから
- 幼い頃に憧れた先生がいたから
- 妹や弟のお世話が好きだった
- 身近な経験がきっかけになった
初心を丁寧に言葉にすることで、自分の理想とする保育士像が自然と見えてきます。
これまでに会った保育士や先生を思い出してみる
これまでに出会ってきた保育士や先生から、自分の印象に残った人を思い浮かべてみるのも理想の保育士像を見つける方法のひとつです。
- 優しく声をかけてくれた先生
- 遊びに全力で付き合ってくれた先生
- 保護者にも丁寧に対応していた先生
過去に出会った先生の姿を「自分ならどう活かしたいか」と考えると、自分の目指す方向が定まりやすくなります。
子どもや保護者からの目線で考えてみる
「子どもや保護者にとって、どんな保育士であってほしいか」を想像しながら、自分の理想の保育士像を探す方法もあります。
- 子どもにとって安心できる存在
- 話を聞いてくれる存在
- 保護者にとって信頼できる相談相手
子どもたちや保護者に今求められていることを考えると、自ずとどんな保育士でありたいかも見えてきますね!
自分の長所や特技から考えてみる
自分の強みをこれから保育にどんなふうに活かすか考えると、具体性のある自分ならではの理想像が見えてきます。
- 音楽や運動などの特定の分野に得意なものがある
- 製作や絵本の読み聞かせが好き
- 明るさや傾聴力といった性格面
自分の持ち味を存分に活かせるようになれば、それだけで園に唯一無二の存在になれるかもしれませんね!
身近な人の意見を参考にする
自分のことは自分が一番知っているようで、実は自分が一番よくわかっていないこともあります。
そんな時は、身近な同僚や家族、友人からの言葉をヒントに考えてみましょう。
- 友人や家族から「あなたらしい」と言われたこと
- 同僚に褒められた経験
- 学生時代の先生の評価
自分では当たり前と思っていることが、実は強みであることも多く、そこから理想の保育士像が見つかることもあります。
人の意見も参考にしながら理想像を描いてみましょう。
まとめ
「どんな保育士になりたいか」は、自己理解や園との相性を見極める大切な質問です。
面接では、簡潔に具体的なエピソードを交えて伝えることが求められます。
もし理想像が今思い浮かばなくても、なりたいと思ったきっかけやこれまでの経験を振り返ることでヒントは見えてきます。
自分の思いを整理し、自分らしい言葉で伝えることが、信頼される第一歩になります。