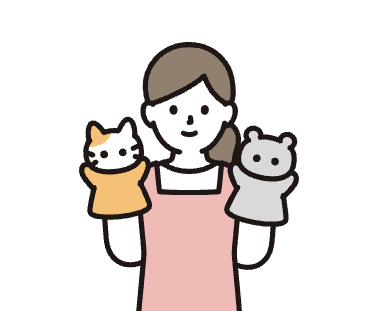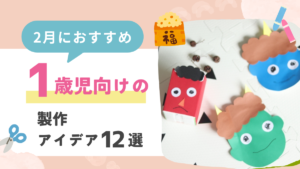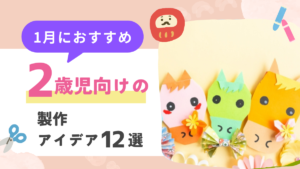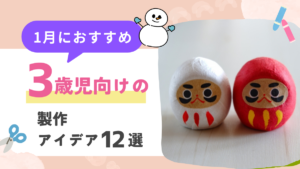12月といえばクリスマスをテーマにした製作が定番ですが、実はクリスマス以外にも子どもたちと一緒に楽しめる題材がたくさんあります。
雪や冬の動物、年末年始の風習などを取り入れれば、季節を感じられる活動が広がるでしょう。
この記事では、スノードームや雪だるま、年賀状、お正月にちなんだ製作、さらに子どもたちが大好きなペンギンのアイデアまで紹介します。
クリスマス一色になりがちな12月に、幅広いテーマを取り入れてみませんか?
- 12月のクリスマス以外に注目したい行事や季節のイベントを知ることができる
- スノードームや雪だるまなど、冬を感じられる製作アイデアを学べる
- 年末の活動に役立つ年賀状やお正月製作のヒントを得られる
- 子どもたちが喜ぶ冬の動物「ペンギン」を題材にした製作例を参考にできる
 ほいぽけ編集部
ほいぽけ編集部クリスマスの製作ばかりになりがちな12月。別の製作アイデアがあればいいなと思い、今回まとめてみました。12月の製作のバリエーションを増やしていきましょう♪
12月のクリスマス以外のイベントや行事は?
12月はクリスマスが目立ちますが、他にも子どもたちと関われる大切な行事が数多くあります。
冬至や大晦日など、日本ならではの伝統行事は子どもたちに季節の移り変わりを伝える良い機会になります。
保育の中で取り入れることで、行事の意味を知りながら製作へとつなげられるでしょう。
- 冬至(ゆず湯・かぼちゃを食べる習慣)
- 大晦日(年越し行事、除夜の鐘)
- 新年を迎える準備(年賀状作りや正月飾り)
- 雪遊びや冬の自然を楽しむ活動


スノードーム・雪だるまに関する製作アイデア3選
雪の降る季節にぴったりなのが、スノードームや雪だるまの製作です。
丸い形や白を基調にしたデザインは子どもたちにも分かりやすく、手軽にアレンジできます。
飾って楽しめる作品に仕上がるのも魅力ですね。
冬の製作に!プラ板でお手軽 スノードーム
12月といえばクリスマスが中心になりがちですが、あえて「クリスマス以外」をテーマにすると子どもたちに新鮮な体験を提供できます。
今回ご紹介するのは、空きびんとスポンジ、プラ板を使った手作りスノードームです。
ラメやスパンコールを入れれば、雪がキラキラと舞い降りるような幻想的な風景が楽しめます。
- 空きびん
- スポンジ
- プラバン(完成済みのもの)
- 瞬間接着剤
- カッター
- 筆記用具
- 水:洗濯ノリ=「7:3」の量
- ラメやスパンコール
- びんの口をスポンジの上に置き、ふたと同じ大きさの円を描きます。
- 描いた線に沿ってカッターでスポンジを切り抜きます。
- スポンジにプラ板が差し込める程度の切り込みを入れ、プラ板のキャラクターやモチーフを差し込み固定します。
- スポンジごとふたの内側に接着剤でしっかり貼り付けます。
- びんの中に水と洗濯のりを7:3の割合で入れ、さらにラメやスパンコールを加えます。
- ふたをしっかり閉め、振ってみて雪の落ち方を確認します。速すぎる場合は洗濯のりを少し足しましょう。
ペットボトルのスノードーム
ペットボトルを使ったスノードームは、ガラスを使わないので安心で、手軽に雪景色を表現できます。
中には雪だるまのパーツを入れて、子どもたちが思い思いに飾り付けると個性豊かな作品が仕上がります。
紙コップや画用紙を組み合わせることで、冬の世界を身近に感じられる製作になり、保育室の装飾としても映えますよ。
- 紙コップ
- ペットボトル
- 色画用紙
- 丸シール
- 梵天(ぼんてん)
- コピー用紙
- セロハンテープ
- カラーペン
- 穴開けパンチ
- ハサミ
- のり
- 白の画用紙を雪だるまの形に切り抜き、帽子や蝶ネクタイも画用紙で作っておきます。
- 雪だるまの顔をカラーペンで描き、紙コップに貼り付けます。
- 白い丸シールや、穴開けパンチで抜いた紙を使って雪を表現します。
- ふわふわ感を出すために、梵天(ポンポン)も用意しましょう。
- 空のペットボトルに雪だるまや紙の雪、梵天を入れます。
- ペットボトルいっぱいに水を入れ、しっかりふたを閉めます。
- 紙コップを台にして立てると、かわいいスノードームの完成です。
ビニール袋で簡単につくれる雪だるまの製作
材料はシンプルで、ポリ袋と綿があれば完成!
丸く膨らんだ形が、自然に雪だるまらしさを引き出してくれます。
綿がない場合は、フラワーペーパーを丸めて代用できるので準備も簡単です。
さらに帽子やマフラーを自由に選べば、オリジナル感たっぷりの雪だるまに仕上がります。
個性が出やすいので、作品を並べると保育室全体が楽しい冬の雰囲気に包まれますよ。
- ポリ袋
- 紙コップ
- 毛糸(15cm×4~5本)
- 綿やフラワーペーパー
- 綿棒
- コットンボール
- 画用紙
- 接着剤
- ビニール袋に綿を詰め、丸い形になるように整えたら口を結びます。
- カットした毛糸をまとめて、袋の口を結ぶように巻き付けて固定します。これがマフラーになります。
- 画用紙で作った目・鼻・口をのりで貼り付け、綿棒で手を作って取り付けます。
- 帽子代わりに紙コップを逆さにして頭に乗せると、雪だるまらしさがぐっと増します。
- 顔の表情やマフラーの色を変えると、一人ひとり違うかわいい雪だるまが完成します。


年賀状に関する製作アイデア3選
12月の終わりには、新しい年を迎える準備も始まります。
年賀状作りは、子どもたちに日本の伝統文化を伝える良いきっかけです。
手形やスタンプを使ったアイデアで、個性あふれる年賀状を楽しく制作できます。
タンポでお絵かきをして年賀状を作ろう
タンポは脱脂綿をガーゼで包み、割りばしを差し込むだけで簡単に作れる製作です。
スタンプのように絵の具をつけてポンポンと押せば、雪や動物などの模様を描くことができます。
さらに仕上げに文字や絵を描き足すと、オリジナルの年賀状が完成します。
保護者へのプレゼントにもぴったりで、喜ばれること間違いなしです。
- ガーゼ 1枚
- 脱脂綿 適量
- 割りばし 1本
- 輪ゴム 1本
- 年賀状 1枚
- 絵の具
- 色鉛筆やペン
- 脱脂綿を割りばしの先端にのせ、ガーゼで包んで輪ゴムでしっかり止めます。
- 出来上がったタンポに絵の具をつけ、年賀状用のはがきにポンポンとスタンプして色をのせます。
- 色が乾いたら、色鉛筆やマーカーで干支や飾りの絵を描き加えます。
- 「あけましておめでとう」などの新年のあいさつ文を入れると完成度が高まります。
- 子どもたちの個性が出るデザインになるので、一人ひとり違った年賀状が楽しめます。
スタンピングで描く年賀状
今回は、プチプチ緩衝材を活用して模様を作る年賀状作成を紹介します。
絵の具をつけてスタンプすると、細かい丸模様が出て独特の風合いを楽しめますよ。
はさみで切った動物の形や干支のモチーフを台紙に貼ると、より年賀状らしいデザインになるでしょう。
シンプルながらも工夫次第で華やかな仕上がりになり、親子で一緒に作っても楽しめそうですね。
- トイレットペーパーの芯
- プチプチシート
- 輪ゴム
- 絵の具
- 色画用紙
- 台紙(ポストカードや年賀状など)
- 両面テープ
- クレヨン
- ペン
- のり
- ハサミ
- 好きな色の絵の具を用意し、プチプチに塗ります。
- プチプチをはがきにスタンプして模様を作ります。
- トイレットペーパーの芯にプチプチを巻き付けると持ちやすくなります。
- 干支や動物を台紙に描いて切り抜きます。
- 切り抜いたパーツをスタンプしたはがきに貼り付けます。
- さらに模様を重ねると華やかさがアップします。
- 世界に一つだけのオリジナル年賀状の完成です。
砂で立体的な年賀状を作ろう!
接着剤で好きな絵を描き、その上から色砂をふりかけると、カラフルでざらっとした質感の作品に仕上がります。
砂を落とすまでどんな模様になっているか分からないため、わくわくした気持ちで完成を待つのも楽しいですね。
接着剤は先の細いものを使うと描きやすく、筆で塗る方法もおすすめです。
保育室に飾ってもきれいなので、特別な活動になります。
- 砂 適量
- パステル(好きな色)
- カッター
- 画用紙 1枚
- ボンド
- 入れ物にパステルを削り入れて色砂を作ります。
- 軽く振って混ぜ合わせ、複数の色を準備しましょう。
- 画用紙やはがきに、ボンドや接着剤で好きな絵を描きます。
- 描いた部分の上から色砂をふりかけます。
- 軽くトントンと紙をはじいて余分な砂を落とします。
- 完全に乾いたら、鮮やかで立体感のある年賀状の完成です。
【先取り】お正月に関する製作アイデア3選
お正月は、子どもたちにとって特別感のある行事です。
12月のうちから正月飾りや遊び道具を作っておくと、新しい年を迎えるワクワク感を高められます。
鏡餅や門松、凧やコマなどを題材にすることで、日本の伝統を自然に伝えられますよ。
トイレットペーパーの芯で作る門松
日本のお正月飾りの代表「門松」を、トイレットペーパーの芯を使って簡単に作りましょう。
完成した門松を保育園の玄関や部屋に飾れば、手作りならではのあたたかさが感じられますよ。
お正月の伝統に触れるきっかけにもなる活動です。
飾ることで保育室全体が華やかになり、子どもたちも日本のお正月文化に自然と親しめます。
- トイレットペーパーの芯 3個
- 緑の画用紙 3枚
- 画用紙 1枚
- 和柄の折り紙 2枚
- はさみ
- 緑の画用紙をのりでトイレットペーパーの芯に巻き付けます。
- 乾いたら芯の端を斜めに切って竹の形にします。
- 同じものを3本作り、両面テープでまとめます。
- 大きめの画用紙に和柄の折り紙を貼り、土台を作ります。
- 上下にはみ出した部分に切り込みを入れ、外側に折り返します。
- 竹を土台に巻き付けて固定します。
- バランスを整えて、華やかな門松の完成です。
牛乳パックdeぶんぶんゴマ~お正月の手作りおもちゃ
お正月の遊びにぴったりな、「ぶんぶんごま」を牛乳パックで作りましょう。
糸を引っ張ると勢いよく回転し、「ブーン」という音を立てて回るのが特徴です。
だるまやコマなど、お正月らしい絵を描くとさらに雰囲気が出ます。
遊びながら力加減や手先の動きが身につき、運動要素もある製作です。
- 牛乳パック
- タコ糸
- クレヨン
- 油性ペン
- 両面テープ
- ハサミ
- 牛乳パックを開いてよく洗い、乾かします。
- 底面と飲み口を切り取り、内側を表にして2つ折りにします。
- 楕円形を下書きして切り抜きます。
- だるまの絵を描き、クレヨンで色を塗ります。
- 2枚を両面テープで貼り合わせ、厚みを出します。
- 真ん中に穴を開け、タコ糸を通します。
- 糸の端を結んで輪にし、引っ張れば完成です。
お正月に♪紙紐を使って簡単しめ縄作り
しめ縄には「神様を迎える家に邪気が入らないようにする」という意味があり、伝統を学ぶきっかけにもなります。
紙ひもをねじったり結んだりする工程は幼児にとって難しい部分もありますが、保育士さんがサポートすれば安心です。
飾りには折り紙で作ったみかんや扇をつけると華やかになり、子どもたちも達成感を味わえます。
- 紙ひも
- テープ
- 折り紙(オレンジ)
- 折り紙(金)
- 丸めた新聞紙
- ペン
- 赤いひも
- 白い紙
- 紙ひもをテープで固定し、ねじって縄を作ります。
- 2本を合わせてさらにねじり、しっかりとした形にします。
- 輪にして結び、しめ縄の形を整えます。
- 折り紙を丸めてみかんを作り、ペンでヘタを描きます。
- 金の折り紙を蛇腹折りにして扇を作ります。
- 扇・みかん・赤いひも・紙垂をしめ縄に飾り付けます。
- 固定できたら本格的なしめ縄の完成です。


ペンギンに関する製作アイデア2選
冬を連想させる動物といえば、ペンギンですよね。
ペンギンの可愛らしい姿は、子どもたちに大人気です。
丸みのある形で作りやすく、紙皿や折り紙を使って簡単に製作できます。
遊びながら、冬を感じられる題材としてぴったりです。
紙コップでつくるペンギン
紙コップを使えば、かわいい立体ペンギンを簡単に作成できますよ。
紙コップの側面を切り込み、外側に折り曲げることで羽の形を表現できます。
お腹部分を白く塗ると、ペンギンらしい姿に近づきます。
完成したペンギンを並べれば「ペンギンパレード」にもなり、積み重ねて遊ぶと「ペンギンタワー遊び」としても楽しめるのも魅力です。
- 紙コップ
- マジック
- ハサミ
- 紙コップを逆さに置き、側面に羽用の切り込みを入れます。
- 切った部分を外に折り曲げて羽の形を作ります。
- 反対側も同じように切り込みを入れ、左右の羽を完成させます。
- 正面にお腹の半円を描き、白く塗ります。
- くちばしや目を描き入れます。丸シールで表現してもOK。
- 好きな色でデコレーションしても楽しいです。
- 完成したら、並べたり積んだりして遊びましょう。
紙を2枚使って作るペンギンの折り方
折り紙2枚で作るペンギンは、頭と体を別々に折るので立体感があり、かわいらしい作品に仕上がります。
子どもと一緒に作れば「大きな目にしようかな」「くちばしはとがらせてみよう」など、工夫する楽しさも味わえます。
簡単な折り方から少し複雑なアレンジまでできるので、年齢に合わせて調整可能です。
動物好きな子にも大人気の製作ですよ。
- 折り紙2枚
- セロハンテープ
- サインペン
- 1枚目の折り紙を三角に折り、さらに折って頭部分を作ります。
- 折り目を戻し、角を内側に折り込んで形を整えます。
- 上の角を折り返してペンギンの頭を完成させます。
- 2枚目を三角に折り、体のベースを作ります。
- 両端を中央に折り、体の幅を整えます。
- 下の角を折り返して足を作ります。
- 頭と体をテープで貼り合わせます。
- 最後にサインペンで目や模様を描いて完成です。


まとめ
12月は、どうしてもクリスマスに注目が集まりますよね。
でも冬ならではの自然や日本の伝統行事をテーマにした製作を取り入れることで、子どもたちに幅広い学びを届けられます。
スノードームや雪だるまは季節感を楽しむ製作、年賀状やお正月の飾りは文化を体験できる製作です。
そしてペンギンは、子どもたちが喜ぶ動物テーマとして活用できますよ。