保育士の仕事は「やりがいはあるけれど、続けていくには給与や待遇が厳しい」と言われることが多い職種です。
そんなときに注目したいのが、園や企業が用意している福利厚生です。
健康保険や年金といった国が定めるものに加え、住宅手当や社宅制度、研修費補助など園独自の制度もあります。
本記事では、保育士の福利厚生の種類と内容、チェックすべきポイントをわかりやすく解説します。
- 福利厚生には法定福利厚生と法定外福利厚生がある
- 法定外福利厚生は園によってさまざまな内容がある
- 求人を選ぶときは、自分が大事にしたい軸を意識して福利厚生をチェックする
- 自治体で取り組んでいる制度もある
 ちあき【元保育士ライター】
ちあき【元保育士ライター】求人をチェックするときに、給与は確認するけど福利厚生はよく見ていない人も多いのでは?
福利厚生の有無で保育士としての暮らしやすさが変わることもあるんですよ。本記事で一緒に理解を深めましょう。


ちあき先生
認可保育園で勤務後退職して留学。その後は英語の幼稚園で働く。結婚を機に派遣保育士に転身し、さまざまな園で経験を積む。保育士歴は通算7年ほど。
子どもが重度アレルギー児になったことでライターに転身した2児の母。
福利厚生についておさらい
福利厚生とは、職員やその家族が安心して働けるように設けられた給与以外の支援制度のことです。
対象は正規職員を中心に、勤務条件を満たすパート・契約職員も含まれる場合があります。
福利厚生には、2種類あります。
- 国が義務づけている法定福利厚生
- 園や企業が独自に設ける法定外福利厚生
前者は社会保険・年金など、すべての労働者に共通する基本制度で、後者は、住宅補助・手当・研修制度・休暇など園によって差が出るのが特徴です。
保育士の法定福利厚生
まずは、保育士として安心して働くために法定福利厚生を知っていきましょう。
法定福利厚生は、すべての働く人が安心して働けるように法律で定められている制度です。
普段はあまり意識することがないかもしれませんが、もしも病気やけが、出産、失業といったいざという時に、私たちをしっかり支えてくれる大切な仕組みです。
保険・年金など
| 健康保険 | 病気やけが、出産などのときに医療費の一部を補助してくれる制度。 自己負担は基本3割で済み、出産手当金などが支給される。 保険料は園と保育士で折半して給料から天引き。 |
|---|---|
| 厚生年金 | 老後の生活を支える公的年金制度。 園と保育士本人が保険料を折半して納め、給与から天引き。 |
| 介護保険 | 40歳以上の人に加入義務があり、将来的に介護が必要になったときに介護サービスの費用の一部を保証してもらえる制度。 給与から天引きされる形で保険料を支払う。 |
| 雇用保険 | 退職や育児休業などで働けなくなったときに給付金が支給される社会保険制度。 保険料は園と保育士で決められた割合を給与から天引きして支払う。 |
| 労災保険 | 仕事中や通勤中に事故でけがをしたときなどに、治療費や休業補償が受けられる制度。 原則として保険料は事業主である園が負担。 |
| 子ども・子育て拠出金 | 事業主が負担する社会保険料で、児童手当や保育所や幼児教育の充実など、社会全体の子育て支援に使われる制度。 |
上記の制度は、フルタイム勤務の正規職員だけでなく、週の労働時間が基準を満たしていればパート保育士でも加入対象になるケースもあります。
特に健康保険や厚生年金は、長く働くほど将来に大きく影響する部分とも言えるので、入職時には加入の有無をしっかり確認しておくことが大切です。
また、近年では多くの園で社会保険完備が一般的になり、福利厚生の格差は少しずつ改善されています。
「保育士=生活が不安定」というイメージを変えるためにも、制度を正しく理解し活用していきましょう。
休暇制度
保育士の働き方を支えるもうひとつの柱が休暇制度です。
仕事に集中するためには、しっかり休んでリフレッシュする時間も欠かせません。
法律で定められている休暇を下記で確認しましょう。
産前産後休暇
産前6週間、産後8週間(双子の場合は産前14週間)まで休むことができる制度です。
産前休業は希望制・産後休業は原則取得必須です。
休暇中は健康保険から「出産手当金」が支給され、給与の約3分の2程度が補償されます。
育児休業
原則、子どもが1歳(条件により最大2歳)になるまでの連続した期間で取得できる休暇です。
育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給され、収入が一定割合保障されます。
介護休暇
要介護状態の家族の介護やお世話をするために取得できる休暇です。
年間で最大5日(2人以上なら10日)まで取得可能で、1日単位・半日単位でも利用できる柔軟な制度です。
申請方法等は就業規則・事業所の定めに従ってください。
有給休暇
勤続6か月以上で、全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇です。
初年度は10日間、その後は勤続年数に応じて増加していきます。
保育士の法定外福利厚生
法定外福利厚生とは、国が義務づけている制度以外に、園や企業が独自に設けているサポートのことです。
例えば、交通費や給食費の補助、社宅制度など、園によって内容はさまざまです。
職員の暮らしを少しでも楽にしたい、長く安心して働いてほしいなどの思いから整備されています。
本章では、保育士が実際によく利用している支給制度について紹介します。
支給される費用や物品
保育士が働くうえで必要な経費や備品を園がサポートしてくれる制度です。
日々の出費を減らし、安心して働ける環境づくりにつながっています。
交通費支給
通勤にかかる交通費を園が負担してくれる制度です。
上限額を設けているところが多いですが、全額支給している園もあります。
電車やバスだけでなく、車・自転車通勤の場合のガソリン代や駐車場代が含まれる場合もあります。



私が勤めていた園では、1駅離れた場所に住んでいて自転車で通勤していた私に、電車を利用していないのに1駅分の電車の交通費を支給してくれました。
給食費支給または補助
職員も園児と同じ給食を食べられる園では、無料または一部補助されるケースがあります。
毎日のお弁当作りが不要になり、家計にもやさしい人気の制度です。
エプロン支給
制服やエプロンを園が支給してくれる制度です。
洗い替えや季節ごとの支給がある園もあり、自己負担が減るだけでなく園の統一感にもつながります。



一見ありがたいサポートですが、入職時の3枚の支給だけでは、胃腸炎が流行ったときに洗替がなくなるハプニングが多発しました。
社宅制度
遠方からの入職者をサポートするために、借上げ社宅制度や住宅補助を用意している園もあります。
家賃の一部または全額を園が負担してくれることもあり、都市部で働く保育士にとって大きな魅力となっています。
各種手当
保育士の働き方を支えてくれるのが、園が独自に設けている手当です。
本章では、代表的な手当の内容を紹介していきます。
住宅手当や家賃の補助
家賃の一部を園が補助してくれる制度で、特に都市部では人気の手当です。
自治体によっては保育士宿舎借上げ支援事業を活用し、家賃を抑えられるケースもあります。
引越手当
遠方からの転職や新卒採用時に引越費用の一部の補助として支給されます。
地方から上京して働くときに、初期費用を軽減できる嬉しいサポートです。
資格手当
国家資格である保育士資格を持つ場合に支給される手当です。
最近では、無資格でも保育補助として働けるので、有資格者を評価する意味で多くの園で取り入れられています。
役職手当
主任・副主任・リーダーなどの役職に就くと支給される手当です。
責任の重さに見合った手当であり、キャリアアップを目指す保育士のモチベーションにもつながります。
家族手当、扶養手当
配偶者や子どもなど扶養家族がいる職員に支給される手当です。
しかし、保育士は世帯主でない場合が多いので、取り入れている園は少ない傾向です。
特殊業務手当
行事やイベントの際に増えた業務に対して支給されます。
すでに基本給に含まれている園もあります。
特別手当(賞与・ボーナス)
年2〜3回支給される手当です。
園によって支給月数や金額は異なりますが、基本給の2〜4ヶ月分が一般的です。
法人の経営状況によって変動する場合もあります。
お祝い金など
保育士の頑張りや人生の節目を応援するために、お祝い金や見舞金の制度を設けている園もあります。
結婚お祝い金
職員の結婚をお祝いして支給される制度です。
金額は園によって異なりますが、1〜3万円程度が一般的です。
出産お祝い金
出産を迎える職員に対して支給されるお祝い金です。
赤ちゃん誕生のお祝いと、育児を応援する気持ちを込めた制度で、1万円〜数万円程度支給されることが多いです。
お見舞い金
病気やケガなど園が規定する条件に当てはまる場合、お見舞い金が支給される園もあります。
永年勤続表彰
長年勤務した職員に対して、表彰や金一封を贈る制度です。
5年・10年・20年など節目の年数ごとに表彰されることが多く、園への貢献をねぎらう大切な機会になっています。
特別休暇
特別休暇は、通常の有給休暇とは別に特定の目的や状況に応じて取得できる休暇制度です。
園によって名称や内容は異なりますが、職員のライフイベントや体調に寄り添った柔軟な仕組みが増えています。
本章では、実際に多くの園で導入されている主な特別休暇を紹介します。
| 休暇の種類 | 内容 |
|---|---|
| 生理休暇 | 女性職員が体調不良の際に取得できる休暇。 |
| 年末年始休暇 | 12月末から1月初旬にかけて設定される休暇で、園によるが12月29日~1月3日までを一斉休園とするケースが多い。 |
| 行事後振替休日 | 運動会や発表会などの行事後に、振替休日を設けて休息できる制度。 |
| 誕生日休暇 | 誕生日月に1日特別休暇を取得できる制度。 |
| 結婚休暇 | 結婚の際に取得できる休暇で、3〜5日程度設けられることが一般的。 |
| 忌引き休暇 | 親族の弔事の際に取得できる休暇で、間柄により日数は異なる場合が多い。 |
| ボランティア休暇 | 社会貢献活動や自己研鑽のために休みを取れる休暇。 |
| 夏季休暇 | 夏季に数日取得できる休暇。 |
| リフレッシュ休暇 | 5年、10年などの節目で長期勤務者向けの数日間の休暇を取れる制度。 |
「休みにくい」と感じやすい保育業界だからこそ、上記のような柔軟な休暇制度を用意している園も少なくないです。



結婚休暇を結婚式の準備や新婚旅行に使っている保育士は多かったです!
各種サービス
園によっては、保育士が安心して長く働けるように、入社時の有休や研修制度、健康サポートなど、さまざまな制度を設けています。
入社時の有休
通常、有給休暇は入職後6か月経過してから付与されますが、最近では入社時から数日間の有休を付与する園も増えています。
体調不良や家庭の用事など、いざという時に安心できる制度です。
研修・資格取得支援
保育士としてのスキルアップを応援する園では、研修費や資格取得費を園が一部負担してくれるケースもあります。
退職金
長く働いた保育士の努力をねぎらうために、退職金制度を設けている園も多くあります。
勤続年数に応じて金額が決まる仕組みで、将来の安心にもつながります。
系列園で子どもの保育園利用の優遇
自分の子どもを系列園に優先的に入園できたり、保育料の割引が受けられる制度もあります。
子育てと仕事を両立したい保育士にとって、嬉しい福利厚生です。
健康診断・メンタルサポート
年1回の健康診断を実施するほか、ストレスチェックやカウンセリング制度を設けている園もあります。
忙しい現場だからこそ、心身の健康を守る仕組みが整えています。
公立保育士(公務員保育士)と私立保育士の福利厚生の違い
公立保育士(公務員保育士)は、地方自治体に所属する公務員として働くため、福利厚生が非常に安定しているのが特徴です。
- 共済組合による医療保険制度、退職金制度
- 産前産後休暇や育児休業の取得の保障
- 公務員専用の職員宿舎を安い値段で利用できるケース
定期的な昇給も明確に規定されており、長く働くほど安心感が増す職場環境といえるでしょう。
パート保育士・派遣保育士の福利厚生は?
パートや派遣の保育士にも、一定の条件を満たせば福利厚生が適用されます。
たとえば、週の勤務時間や契約日数が基準を超える場合は社会保険に加入が可能、勤務先によっては交通費支給・給食補助・エプロン貸与といったサポートなどがあります。
派遣保育士の場合は、派遣会社の福利厚生を利用でき、有給休暇・産休育休制度・健康診断・研修サポートなどが利用できるでしょう。
正社員と比べて制度の差はありますが、働き方に合わせた柔軟なサポートが受けられるケースも多いです。
【先輩保育士に聞いた】保育士にとって嬉しい福利厚生は?
今回は「保育士にとって嬉しい福利厚生は?」というテーマで、現場経験のある先輩保育士にお話を伺いました。
福利厚生の充実は、働きやすさや定着率にも大きく関わるポイント。
先輩たちのリアルな声を参考に、就職・転職時の園選びに役立ててください。



夏休み休暇があったことです。有給休暇にプラスして、7月~9月までの間に使える3日間の有休がもらえました。新人の頃から必ず取るように言われていたので、取りにくさを感じたことはありません。ただ、全正社員が取得するので、ときには譲り合うことも必要でした。
夏の時期は行事も多くて忙しい分、こうした特別休暇があると本当に助かります。
全員が取得する分シフト調整は必要ですが、譲り合いながら休める環境があればライフスタイルが変わっても長く働き続けられますね。



私が以前勤めていたところでは「リフレッシュ休暇」がありました。
1年のうち好きなところで5日間のまとまったお休みをもらえるものです。
多くの人は、友達との旅行や実家に帰省するために利用していました。
まとまった休みが取りにくい新人にも、先輩が積極的に取るように促して
くれるのでありがたかったです。
子どもたちと向き合う毎日はやりがいがある反面、体力的にも精神的にもハード。
だからこそ、リフレッシュ休暇のような制度は本当にありがたいですよね。
旅行に行ったり家でゆっくり過ごしたり、心と体をリセットできる時間があることで、また笑顔で子どもたちと向き合える余裕が生まれます。
【園選びで失敗しない求人票の見方】福利厚生はここをチェック!
求人票を見るとき、つい給与額だけに目が行きがちですが、実際の働きやすさを左右するのは福利厚生の充実度です。
同じ月給でも、家賃補助・賞与・休暇制度などによって、手取りや生活のゆとりは大きく変わります。
本章では、求人票で見落としがちなポイントをわかりやすく整理し、自分に合った職場を見極めるために、確認しておきたい項目を紹介します。
福利厚生は自分が重視する軸で選ぶ
福利厚生といっても内容は園によってさまざまです。
家賃補助がある園で一人暮らしをしやすい環境を選ぶ人もいれば、子育て中で時短制度や保育料の補助を重視する人もいます。
全部が完璧な職場は少ないため、まずは自分にとって譲れない条件は何かを整理しましょう。
たとえば、退職金制度の有無、給食費補助、休日数など、自分が重視する軸を意識して選ぶと失敗が少なくなりますよ。
賞与は支給割合と基本給をセットで確認
求人票の「賞与〇ヶ月分」という表記だけで判断するのは危険です。
賞与の計算基準が基本給ベースなのか、総支給額ベースなのかによって、実際の支給額は大きく異なります。
たとえば、基本給が15万円で賞与4ヶ月分なら60万円ですが、総支給が20万円で同じ4ヶ月分なら80万円になり、年収単位で考えると大きな差になるのです。
求人票に賞与〇ヶ月分の数字が大きいものの、基本給が少なかったというケースもあるので注意しましょう。
固定残業代や残業時間なども忘れず確認
求人票に「月給○万円(固定残業代含む)」と書かれている場合は、実際に何時間分の残業が含まれているのかを必ずチェックしましょう。
たとえば「固定残業20時間分を含む」とあれば、それを超える分は別途支給されるかどうかを確認する必要があります。
また、持ち帰り仕事の有無や行事準備の繁忙期の残業状況も重要なので忘れずにチェックしましょう。
給与だけでなく、労働時間とのバランスも見ることが大切です。
保育士が利用できる支援や補助金制度のチェックも忘れずに!
保育士は、国や自治体の支援制度を活用することで、より安心して働き続けられます。
「ふなばし手当」は、船橋市内の私立保育園などで働く保育士に支給される独自の上乗せ手当です。
月額4万5,100円に加え、賞与にも年間約9万7,000円が加算され、年額約63万円が支給されます。
正職員だけでなく、フルタイムパートも対象です。
参照:船橋市公式サイト「ふなっしーも応援!船橋市内の保育園で働きませんか?~保育士さん向け支援をご紹介~」
「とだ保育士応援手当」は、戸田市内の私立保育園で働く保育士の給与に月額3万4,000円を上乗せ支給する制度です。
申請は不要ですが、実施の有無は園によって異なります。
参照:戸田市公式サイト「私立保育所等の保育士支援[戸田市独自]を実施します!」
※ 自治体制度は改定があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。
福利厚生が充実した保育園への転職にはエージェントを活用しよう!
「福利厚生がしっかりしている園に転職したい」と思っても、求人票だけでは制度の中身は分かりにくい場合があります。
そんなとき頼れるのが、保育士専門の転職エージェントです。
非公開求人の紹介はもちろん、園の雰囲気・残業実態・賞与支給実績など、実際に働く人の声をもとにした情報を提供してくれます。
本章では、利用者満足度の高い代表的な3社を紹介します。
保育士ワーカー
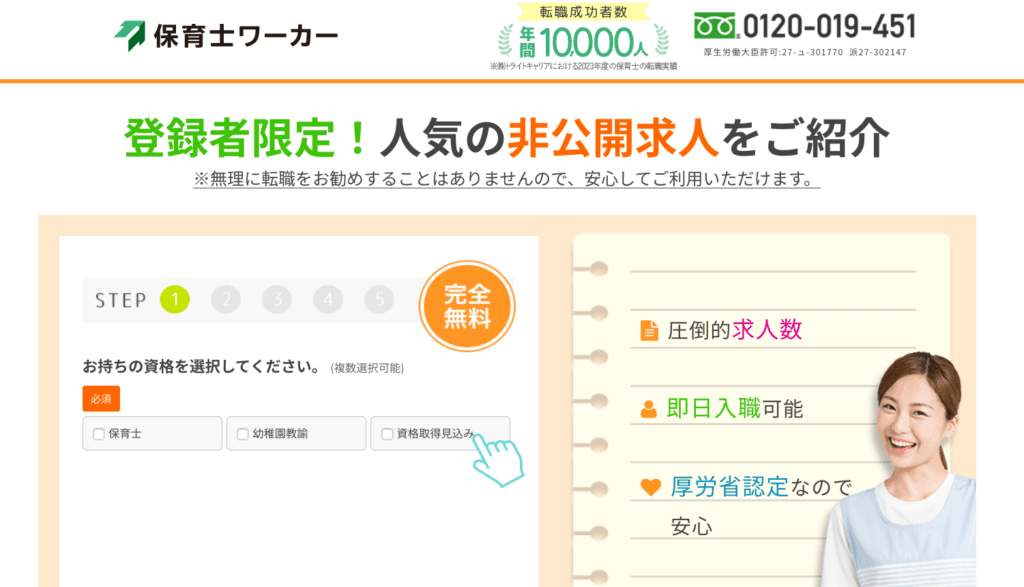
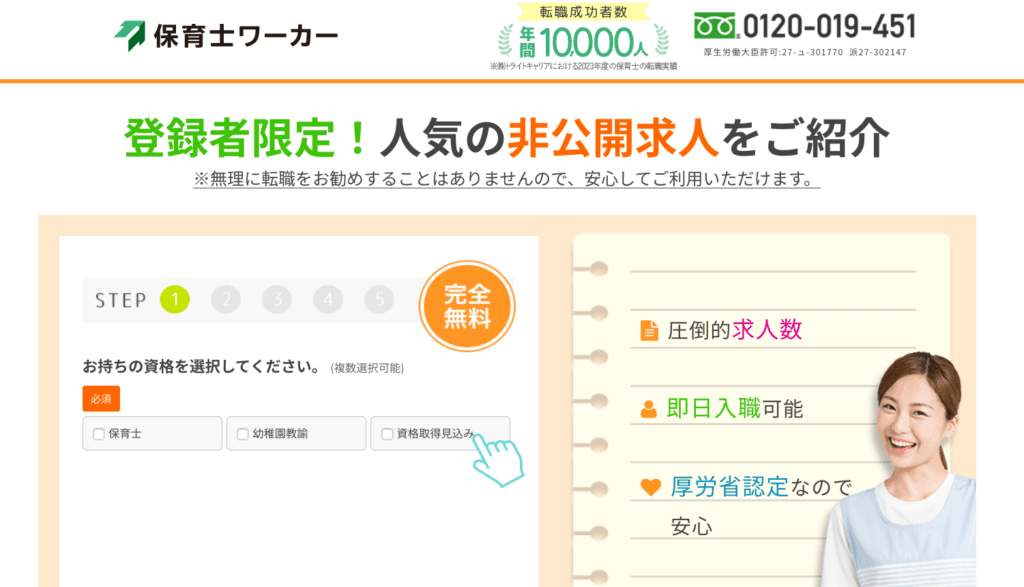
| 運営会社 | 株式会社トライトキャリア |
|---|---|
| 求人数 | 約20,365件(2025年10月時点) |
| 対応エリア | 全国対応 |
| 雇用形態 | 正社員・パート・契約社員 |
| 公式サイト | https://hoikushi-worker.com/ |
全国規模で圧倒的な求人数を誇るエージェントです。
担当者が園の雰囲気や人間関係など現場のリアルを丁寧に教えてくれるのが特徴です。
また、「残業少なめ」「託児所あり」「住宅補助あり」など、さまざまなこだわりの条件に対応していて、自分の希望条件が明確であればあるほど、マッチした求人を紹介してもらえます。
面談の調整や面接のサポートなどの対応もスピーディーで、転職初心者でも安心して利用できる点も高評価です。
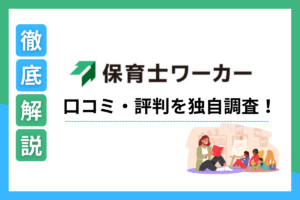
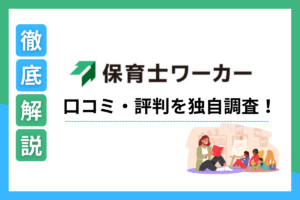
マイナビ保育士


| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
|---|---|
| 求人数 | 約20,706件(2025年10月時点) |
| 対応エリア | 全国対応 |
| 雇用形態 | 正社員・パート・契約社員 |
| 公式サイト | https://hoiku.mynavi.jp/ |
大手人材会社が運営する信頼性の高い転職サービスです。
保育園の取り扱いが、私立、企業主導型、認定こども園など幅広いだけでなく、保育園以外にも保育士の資格を活かしたさまざまな施設の選択肢があります。
転職までのサポートが充実している上に、入職後のアフターフォローまでしてくれるのでとても心強いです。
大手ならではの、保育士から異業種への転職サポートも行っていて、保育業界に限らず福利厚生が整った仕事先を探すことが可能ですよ。
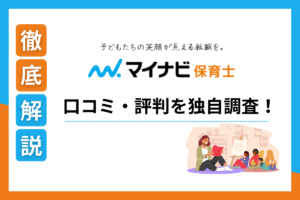
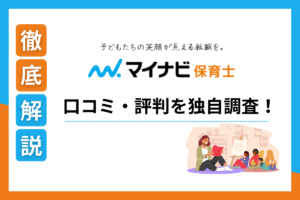
保育士人材バンク


| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス |
|---|---|
| 求人数 | 約38,706件(2025年10月時点) |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・パート・契約社員 |
| 公式サイト | https://hoiku.jinzaibank.com/ |
保育分野に特化した転職支援サービスエージェントです。
LINEでのやり取りにも対応しており、忙しい保育士さんでもスキマ時間に転職活動ができると好評です。
ヒアリングから、どのような保育方針や職場環境が合うのかを丁寧に提案してくれ、転職活動をする上で出てくる疑問や気になる園への質問を代理で確認。
見学や面接の日程調整や書類準備、面接対策など幅広いサポートをしてくれます。
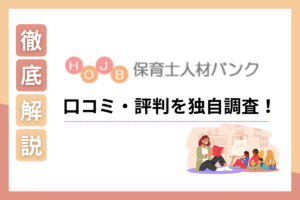
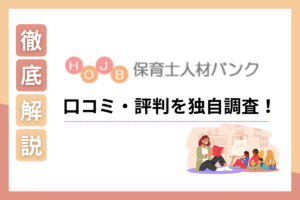
まとめ
保育士の働きやすさは、給与額だけでなく福利厚生の充実度にも大きく左右されます。
法定福利に加え、社宅制度や家賃補助、研修制度などが整っている園は、安心して長く働ける環境です。
また、自治体の支援制度や転職エージェントを上手に活用すれば、より自分に合った働き方や待遇改善も可能です。
園選びの際は、自分が重視しているポイントに合っているかで判断すると、より自分にぴったりな園を見つけられるでしょう。








