児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がいや発達に特性のある子どもとその家族を支える専門職です。
本記事では、児童発達支援管理責任者になるためのステップや給与水準、勤務体制をわかりやすく解説します。
- 児童発達支援管理責任者は、障がいや特性のある子ども一人ひとりに合わせた支援を行う専門職
- 児童発達支援管理責任者を目指すには、最低でも7年の期間が必要
- 個別支援計画の作成から関係者との連携、職員支援、送迎まで幅広く業務を担う役割
 Takako【元保育士】
Takako【元保育士】本記事では、児発管になるためのステップの他に、1日のスケジュールなども紹介しています。
この記事を読んで、理解を深めてくださいね。


Takako先生 元保育士ライター
保育士歴7年、現在は男女2児の母をしています。保育現場で培った経験や知識を活かし、悩んだり困ったりしている保育士の方、保育士を目指している方の力になれるような記事を心がけています。
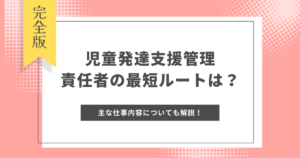
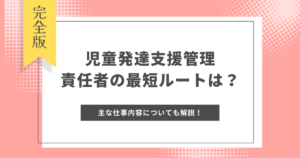
児童発達支援管理責任者(児発管)とは?
児童発達支援管理責任者(児発管)とは、作成した支援計画をもとに支援を実施し、保護者や関係機関と連携しながら日々の成長や生活をサポートする専門職です。
子ども一人ひとりに寄り添った支援を提供します。
日々の観察や評価・振り返りを通して、より効果的な支援の提供をするとてもやりがいのある仕事です。
児童発達支援管理責任者の役割
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスや児童発達支援施設などで働き、障がいや発達の遅れがある子どもとその家庭に対して支援計画を立て、実施を行います。
子ども一人ひとりの特性、発達段階に合わせた支援計画書を作成し、「挨拶」「順番を待つ」「ボタンを留める」「靴を履く」など、一人ひとりの日常生活に必要な力を育む支援を行います。
関係機関や保護者と連携し、子どもの発達を多方面から支える重要な存在です。
サービス管理責任者・相談支援専門員との違い
サービス管理責任者・相談支援専門員との違いを下記の表にまとめました。
| サービス管理責任者 | 相談支援専門員 | |
|---|---|---|
| 役割 | 障がいをもつ18歳以上を対象とした生活支援、就労支援、日常生活の自立をサポート | 障がいをもつ人やその家族が、必要な福祉サービスを適切に利用できるよう支援する |
| 所属先 | ・就労継続支援A型・B型事業所 ・自立訓練(生活訓練・機能訓練)事業所 ・短期入所事業所 | ・指定特定相談支援事業所 ・指定障害児相談支援事業所 ・社会福祉協議会 ・地域包括支援センター |
| 主な業務内容 | ・自立訓練 ・就労訓練 ・療養介護 ・生活介護 | ・課題分析と最適なサービスの提案 ・サービス等利用計画の作成 ・関連機関との連携 |
発達に遅れや障がいのある子どもへの支援を行う児童発達支援管理責任者は、成長や自立を支える役割を担っており、サービス管理責任者とは担当範囲や内容が異なります。
児童発達支援管理責任者になるには何年かかる?
児童発達支援管理責任者を目指すための実務経験年数は、ルートによって異なります。
- 相談支援ルート:5年
- 直接支援ルート:資格の有無で5年または8年
- 国家資格等ルート:3~5年
研修(基礎→OJT→実践)要件もあり、近年はOJT短縮・みなし配置などの緩和措置も設けられています。
また、保育士・医師・看護師などの国家資格を持つ方は、資格に応じて3〜5年程度と、通常よりも短い実務経験で要件を満たせる場合があります。
参照:埼玉県庁公式サイト「児童発達支援管理者の実務経験」
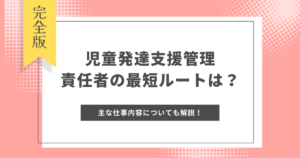
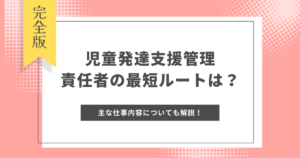
児童発達支援管理責任者になるための資格要件
児童発達支援管理責任者になるには、障害児支援などの実務経験に加え、所定の研修(基礎・OJT・実践)の修了が必要です。
保育士や看護師などの国家資格を持つ場合、要件が一部緩和されることもあります。
ルートや経験年数により条件が異なるため、事前に確認しておきましょう。
児発管になるには?必要な資格
児発管になるために必ず取得しなければならない資格はありません。
無資格でも「直接支援業務ルート」で条件を満たすことは可能です。
ですが、保育士を含む特定の国家資格があると実務経験の期間が短縮されるケースがあるので事前に確認しておきましょう。
必要な実務経験の種類
児発管になるルートとして、「相談支援業務」「直接支援業務」「国家資格業務」の3種類があります。
どのルートでも、必要な実務経験のうち、児童福祉または障がい福祉の分野での現場経験を1年以上含むことが必要です。
障害児相談支援事業、発達障害者支援センターなどで5年以上(保育士、社会福祉士、介護福祉士など特定の国家資格を所有している場合は3〜5年以上)の実務経験が必要です。
障害児入所施設などの直接的な支援を行う業務を8年以上(保育士、社会福祉士、介護福祉士など特定の国家資格を所有している場合、5年以上)の勤務経験が必要です。
特定の国家資格を有する人は、資格を活かした実務経験を3〜5年以上積む必要があります。
老人福祉施設や介護保険事業所での勤務期間は、障害児支援に該当しないため、実務経験としてカウントされません。要件を満たすには障害児支援に関わる業務が必要です。
国家資格等ルートでの取得方法
指定の国家資格等を所有している場合、資格に基づく業務の通算5年以上に加え、相談支援業務または直接支援業務から除外期間(例:高齢者等支援)を除いた期間が3年以上必要です。
その上で、基礎研修・OJT(実務)・実践研修を順に修了すると資格要件を満たします。
該当する国家資格の一例を以下にまとめました。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師・准看護師、PT、OT、ST、視能訓練士、義肢装具士、社会福祉士、介護福祉士、栄養士、精神保健福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師 など。取扱いは自治体要綱で確認してください。
国家資格ルートの方が、要件を満たすまでの実務年数が短くなるケースがあるということです。
児童発達支援管理責任者になるには?流れを5つのSTEPで解説
児童発達支援管理責任者を目指すためには、実務経験や研修を順序立てて行うことが必要です。
ここでは、初心者の方でも分かりやすいよう、実務経験の積み方や基礎研修の内容、研修後に児発管として働くまでの流れとポイントを解説します。
STEP1 実務経験を積む
現場で実務経験を積むことが、児童発達支援管理責任者を目指す第一歩といえます。
対象となるのは、児童発達支援事業所、放課後等デイサービスなど、子どもに関わる施設です。
高齢者施設などで働いた期間は、実務経験に該当しないので注意しましょう。
国家資格を保有している場合、実務経験の期間が短縮される場合があるため、事前にしっかり確認しておくと安心です。
STEP2 基礎研修を受ける
実務経験を積んだ後は、基礎研修を受講します。
基礎研修は、各自治体や厚生労働省の委託団体が実施しており、児発管として必要な知識、支援計画作成の基礎などを学びます。
STEP3 現場で実践を積む
基礎研修を修了したら、学んだ知識をもとに現場で実践し、経験を積む段階です。
対象となる施設は、放課後等デイサービスや障がい児入所施設、児童発達支援事業などです。
ここでは、子どもへの直接支援、保護者との連絡調整などを行い、研修で学んだ内容を実務に落とし込みます。
STEP4 実践研修を受ける
現場での実践経験を積んだ後は、実践研修の受講が必要です。
実践研修では、個別支援計画の作成や状況の確認・観察、関係機関との連携の方法など、実務で直面する課題に沿った学びを深めます。
ケーススタディやグループワークを通して、現場での対応力や判断力を養い、児発管として必要なスキルを確実に身につけましょう。
STEP5 児発管として働く
実務経験と研修を終えたら、いよいよ児童発達支援管理責任者として勤務できます。
個別支援計画の作成・面談、保護者や関係機関との連携、スタッフの指導などを行い、施設全体の支援の質を管理します。
子ども一人ひとりの成長や生活の質を高める、重要な役割を担う大切な存在です。
児童発達支援管理責任者の仕事内容
児童発達支援管理責任者の主な業務は以下の通りです。
- 個別支援計画の作成
- 保護者・関係機関との連携
- 職員への技術指導
- 記録・評価業務
- 送迎・現場支援
- 管理者業務(兼任の場合)
このように、児童発達支援管理責任者の主な業務は、個別支援計画の作成、保護者や関係機関との連携、職員への指導などがあげられます。
今回は3つに絞って詳しく解説していきます。
個別支援計画の作成
個別支援計画の作成には、利用者・その保護者と面談を行います。
障がいを持つ子どもの特性や、生活状況、発達段階に応じて、短期・中期・長期の具体的な目標を設定します。
また、保護者の要望もしっかりヒアリングし、支援計画に落とし込むことで、家庭と連携した実践的な支援計画を作成できるでしょう。
保護者・関係機関との連携
関連機関と連携することで、子どもに一貫した支援を提供できます。
そのため、児童発達支援管理責任者は、保護者や学校、医療機関、福祉サービス事業者と連携し、子どもの支援を一体的に進めることが求められます。
子どもの成長や生活状況を共有し、支援内容の調整や情報交換を行いながら、家庭と施設、関係機関が一体となった質の高い支援を実現しましょう。
管理者業務(兼任の場合)
児童発達支援管理責任者が施設管理者を兼任する場合、職員への指導・シフト管理・安全管理・予算管理など、施設の運営全般に関わります。
また、関係機関との調整や保護者対応も行い、施設運営と支援の両立を図ります。
日々の支援業務と並行しながら、施設全体の運営を見渡し、支援の質を維持・向上させる責任ある仕事です。
児童発達支援管理責任者の1日のスケジュール
児童発達支援管理責任者の1日は多忙です。
児発管の1日のスケジュール(一例)を以下にまとめました。
9:00 勤務開始
・朝礼
・1日のスケジュールの確認・共有
・伝達事項の確認・共有
9:30〜12:00
・個別支援計画を作成
・関係機関への連絡
13:00〜
・療育を行う職員のフォロー
・保護者へ連絡
・事務作業
・面談
・子どもの様子を確認
17:30~18:00
・送迎
18:00〜
・清掃
・会議(社内ミーティング)
・伝達事項の確認・共有
・1日のまとめ
・翌日の準備
19:00 勤務終了
このように、午前中は事務所での作業や、関連機関への連絡業務がメインです。
午後は、子どもたちの様子を観察したり、職員の支援をサポートしたりする時間が中心です。
また、保護者との面談や連絡、記録・事務作業も並行して行います。
児童発達支援管理責任者が働ける施設一覧
児発管が働ける主な施設は下記の通りです。
| 施設区分 | 主な施設名・サービス内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 発達に遅れや障がいのある未就学児を対象に、日常生活や学習・運動・社会性を支援する |
| 放課後等デイサービス | 学校終了後や長期休暇中に、障がいのある児童に学習・運動・社会性を育む支援を提供する |
| 幼保連携型認定こども園 | 保育・教育・療育を組み合わせ、障がいのある子どもにも対応する幼稚園・保育園の複合施設 |
| 病児保育事業 | 病気や体調不良の子どもを一時的に預かり、必要に応じたケアや支援を提供する |
これらの施設で児童発達支援管理責任者として働くことで、多様な環境で子ども一人ひとりに合わせた支援を提供でき、専門性を活かしながらキャリアを広げることができます。
児童発達支援管理責任者の給料や待遇
児童発達支援管理責任者の給与や待遇は、勤務する施設や地域、経験年数によって差があります。
都心部では給与が高めですが、地方では生活費が抑えられるため、手取りの差は必ずしも大きくありません。
賞与や各種手当、勤務時間なども含め、働きやすさやキャリア形成の観点からも確認しておくことが重要です。
児童発達支援管理責任者の平均年収
児発管の平均年収は、常勤で約430万です。
ただし、勤務する施設の形態や規模、勤続年数、地域によっても大きく変わります。
放課後等デイサービスや障がい児入所施設などでの経験や、管理者業務との兼任の有無によっても変動するため、あくまで目安として考えるとよいでしょう。
児発管は責任ある仕事でありながら、子どもの成長に直接関わるやりがいも大きく、安定した収入と充実したキャリア形成の両方を目指せる職種です。
参照:令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要
エリア別の給与相場
エリアによって児童発達支援管理責任者の給与相場は大きく異なります。
東京都の場合、給与が30万円を超える求人が多く、都心部では生活費が高い分、給与水準も高めです。
また、通勤手当や住宅手当などの福利厚生が充実している求人も多く、総支給額は地方より高くなる傾向があります。
一方、地方では給与は23万円前後と東京都に比べるとやや低めですが、家賃や生活費が抑えられるため、手取りの差は思ったほど大きくないケースもあります。
参照:求人ボックス
児童発達支援管理責任者の勤務体制
施設によっては、開所時間に合わせてシフト勤務となる場合もありますが、基本的には平日の日中勤務です。
勤務時間は施設や事業所によって異なりますが、一般的には9時〜18時前後が多く、休憩時間や送迎対応、会議・研修参加なども含まれます。
また、施設によっては兼任で管理者業務を行うこともあり、柔軟な対応力や複数の仕事を効率よく行う力が求められます。
児童発達支援管理責任者に向いている人は?
児発管は、視野を広く持ち、多忙な業務をこなしていく必要があります。
ここでは、児童発達管理責任者に向いている人と向いていない人の特徴をわかりやすく解説します。
働き方や適性を考えるヒントとして、参考にしてくださいね。
児童発達支援管理責任者に向いている人・向いていない人
児童発達支援管理責任者は、子ども一人ひとりの特性や成長に寄り添いながら、保護者や関係機関と連携して支援を進める役割を担っています。
そのため、子ども一人ひとりに丁寧に関わり、複数の業務をこなせる柔軟性や責任感のある人が向いています。
一方、多様な業務に負担を感じてしまう人・責任ある判断に不安を抱きやすい人は、児童発達支援管理責任者に向いていないかもしれません。
自分の性格や働き方を把握することも、児童発達支援管理責任者として活躍するうえで大切です。
児童発達支援管理責任者のやりがいとは?
児童発達支援管理責任者のやりがいは、子どもの成長や発達を間近で見られることです。
一人ひとりの発達に応じて個別支援計画を作成し、保護者や関係者と一緒に支援を形にしていくことは大きな達成感を感じられるのではないでしょうか。
児発管は責任ある大変な仕事ですが、自分の関わりが子どもの成長や生活に直接つながる喜びを得られる大切な仕事です。
児童発達支援管理責任者の将来性
児童発達支援管理責任者は、障がい児支援や発達支援のニーズが高まる中で、今後ますます求められる職種です。
特に、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所の増加に伴い、経験豊富な児発管の需要は更に高まっています。
また、専門知識とマネジメント能力を兼ね備えていることから、将来的には施設長や管理職としてキャリアアップする道も開けます。
独自アンケート「児童発達支援管理責任者になって良かったことは?」
実際に児童発達管理責任者の経験がある方々にアンケートを実施しました。
児発管のリアルな声を見ていきましょう。
児発管はチームで支える発達支援(ゆみさん/女性/39歳/児発管歴:3年)
【児童発達支援管理責任者になって良かったことは?】
お子さんができることを一つずつ増やしていく姿を間近で見られることに、何よりのやりがいを感じます。
ご家族から「通うようになって笑顔が増えました」と言っていただけると、本当に嬉しくなります。
【児童発達支援管理責任者の大変な部分・日頃の悩みなどありますか?】
関係機関やご家庭との調整に時間がかかり、想いをうまく伝える難しさを感じることがあります。
書類作成や加算要件の確認など事務面も多く、支援との両立に悩む日もあります。
【これから児童発達支援管理責任者を目指す人に一言お願いします!】
児発管の仕事は責任も大きく、最初は覚えることの多さに戸惑うかもしれません。
でも、子どもたちの成長を支え、ご家族と喜びを共有できる貴重な仕事です。
チームで協力しながら一人ひとりに合った支援を考える日々は、決して楽ではないですが、とても充実しています。
子どもの「できた!」という笑顔が何よりの原動力になります。焦らず一歩ずつ、仲間と学びながら前に進めば、きっとやりがいを感じられると思います。



子ども一人ひとりに真剣に向き合う姿勢と、「できた!」という成長の瞬間を大切にしている想いが伝わってきますね。忙しさの中でも、その笑顔がやりがいにつながっているのだと感じます。
経験を重ねるほどに実感する、支援のやりがい(ひろさん/男性/35歳/児発管歴:3年)
【児童発達支援管理責任者になって良かったことは?】
子どもが少しずつできることを増やしていく瞬間を近くで見られるのが何よりの喜びです。
保護者の方が笑顔で「ここに通ってよかった」と言ってくださる時、この仕事を選んで本当に良かったと思います。
【児童発達支援管理責任者の大変な部分・日頃の悩みなどありますか?】
支援計画の作成やモニタリング、書類作業が多く、子どもと関わる時間をどう確保するかが常に課題です。
スタッフ間で支援方針を共有するのも簡単ではなく、個々の意見をまとめる難しさを感じています。
【これから児童発達支援管理責任者を目指す人に一言お願いします!】
最初は責任の重さに戸惑うかもしれませんが、経験を重ねるうちに「自分の関わりが誰かの未来を変えている」と実感できます。子どもや保護者、職員の笑顔を支えるやりがいの大きな仕事です。焦らず、自分のペースで学びながら進んでください。



児発管は、保護者や職員、関連機関をつなぐ重要な役割も担っており、とても責任の多い仕事ですよね。
自分たちの支援が、子どもや家族の「喜び」や「笑顔」、そして「未来」につながることは、何よりのやりがいですね。
子どもたちの「できた!」を支える喜び(つくねさん/男性/36歳/児発管歴:6年)
【児童発達支援管理責任者になって良かったことは?】
自分が作成した個別支援計画を通じて、子どもたちが「できた!」と笑顔になる瞬間に立ち会えることです。
保護者の方から「ここに通うようになって子どもが明るくなった」「相談して良かった」と感謝の言葉をいただいた時や、支援チーム一丸となって子どもの成長を支えられた時に、大きな喜びとやりがいを感じます。
【児童発達支援管理責任者の大変な部分・日頃の悩みなどありますか?】
個別支援計画の作成やモニタリング報告書の作成など、書類業務が非常に多く、時間に追われがちな点です。
また、保護者の方の多様なニーズや思いを受け止め、関係機関との調整を行う中で、それぞれの立場の板挟みになり、精神的な負担を感じることも少なくありません。
【これから児童発達支援管理責任者を目指す人に一言お願いします!】
広い視野とコミュニケーション能力、そして何より子どもたちへの愛情が求められる仕事ですが、「子どもたちの未来を支えたい」という強い気持ちがあれば、きっと素晴らしい児童発達支援管理責任者になれるはずです。
応援しています!



一人ひとりに丁寧に関わることが求められる分、葛藤やもどかしい思いを感じることもありますよね。それでも、子どもたちの成長を感じた時の感動は、児発管にとって大きな喜びですね。
児童発達支援管理責任者への転職活動
児童発達支援管理責任者への転職を考える際は、必要な実務経験を整理し、研修スケジュールや施設の特徴を把握することが重要です。
ここでは、転職活動のポイントや効率的に実務経験を積む方法をわかりやすく解説します。
キャリアチェンジの参考にしてください。
保育士から児発管へのキャリアチェンジは可能?
保育士の資格を持っていれば、児発管へのキャリアチェンジは十分に可能です。
ですが、国家資格ルートでの対象資格には含まれないため、相談支援業務で3年以上または、直接支援業務で5年以上の実務経験は必要です。
保育士から児発管を目指す場合は、経験を積みながら研修を受け、ステップを踏んで取得する形になります。
児童発達支援管理責任者になるための転職活動のポイント
転職活動を行う際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 実務経験(相談支援・直接支援・国家資格業務)を整理して棚卸しする
- 基礎研修・実践研修の開催時期を事前に確認する
- 履歴書・職務経歴書に児発管志望と実務経験を明記する
また、資格をまだ取得していない場合でも、一定条件を満たせば児発管として配置されているとみなされる「みなし配置制度」が利用できる事業所があります。
みなし配置可能な施設を選ぶことで、必要な実務経験を効率よく積み、転職成功につなげることができます。
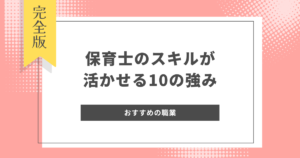
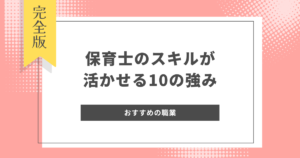
まとめ
児発管は、適切なステップを踏めば目指せる専門職です。
子ども一人ひとりの成長に寄り添い、保護者や関係機関と連携しながら支援を実践することで、大きなやりがいや達成感を得られます。
さらに、資格や実務経験を活かしてキャリアアップや専門性の向上も可能で、長期的なキャリア形成にもつながります。
児童発達支援管理責任者になって、自分らしい支援で子どもたちの成長を間近で感じてみてください。








