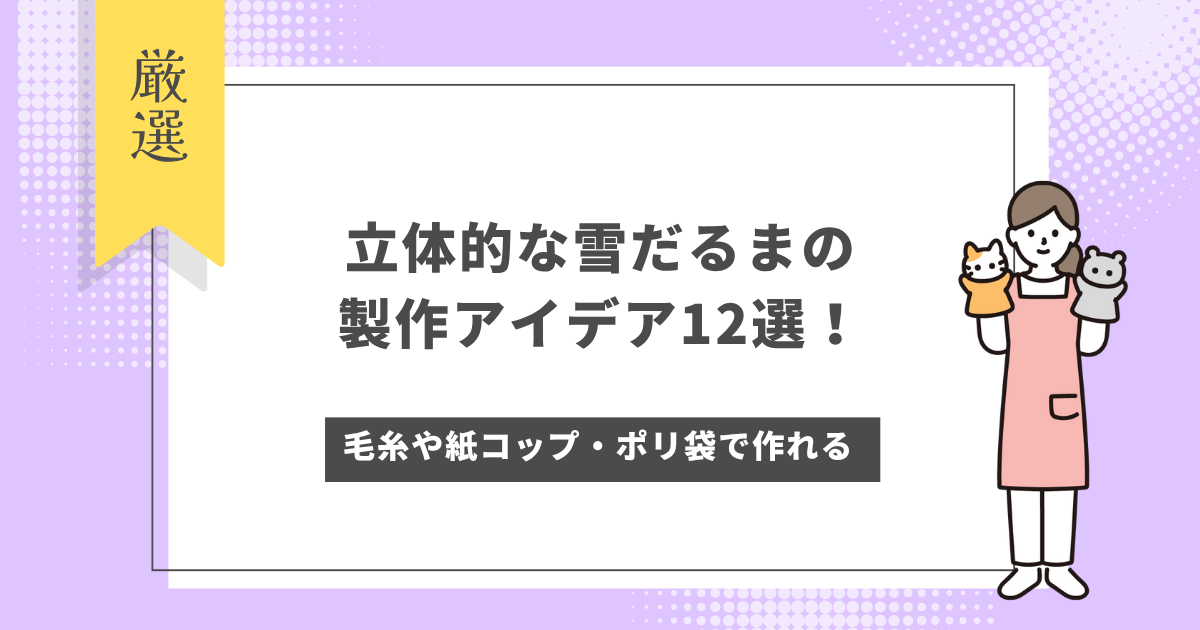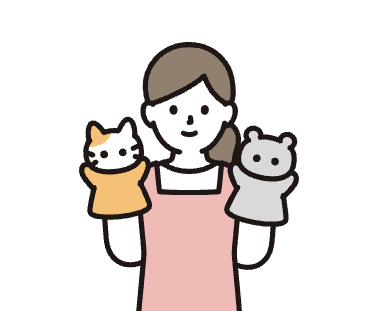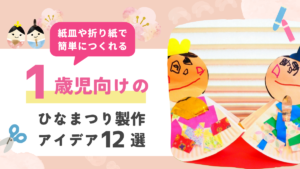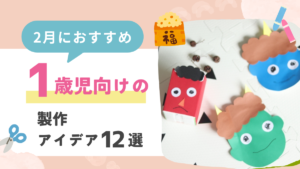冬といえば、子どもたちが大好きな“雪だるま”の季節。
園庭に雪がなくても、室内で立体的な雪だるまを作ることで、冬の雰囲気を存分に味わえます。
毛糸や紙コップ、ポリ袋、風船など、身近な素材を使えば、どの年齢の子どもでも楽しみながら製作できるでしょう。
手先を動かして形を作ったり、表情を描いたりすることで、想像力や創造力を育むことにもつながります。
今回は、1歳から5歳までの年齢別に楽しめる立体的な雪だるまを紹介するので最後までお見逃しなく!
※誤飲防止・工具管理・素材確認を徹底し、保育者の見守りで安全に製作しましょう。
この記事でわかること
- 毛糸・紙コップ・ポリ袋など、身近な素材を使った“立体的な雪だるま”の作り方を知ることができる
- 年齢ごとの発達に合わせた、1歳~5歳児向けの製作ポイントを学べる
- 季節感を楽しみながら、造形力・色彩感覚を育む冬の製作活動のヒントが得られる
- 完成後に飾って楽しめる、冬の壁面装飾や季節行事にもぴったりなアイデアを紹介している
あわせて読みたい
雪だるまの製作アイデア10選!0〜5歳まで年齢に合わせた製作を解説
冬の時期にぴったりな「雪だるま製作」は、季節感を感じながら子どもたちの創造力を育むのに最適な活動です。 年齢に応じた工夫を加えることで、それぞれの成長段階に適…
目次
大きいサイズの立体的な雪だるま製作4選【壁面製作にも】
大きめの雪だるま製作は、存在感があり、クラス全体で楽しめる冬の製作です。
ポリ袋や風船を使えば軽くて安全に作ることができ、子どもたちが協力して形を整える過程も楽しい時間になります。
完成後は帽子やマフラーをつけて飾れば、保育室が一気に冬の雰囲気に包まれます。
写真撮影の背景としてもおすすめです。
ポリ袋雪だるま