おたよりの書き出しを考える際、「なにを書いたらいいの?」と悩んだことはありませんか?
書き出しは、保護者が最後まで読みたくなる流れを作ることが大切です。
本記事では、11月のおたよりにそのまま使える文例や、年齢別で使えるアイデア、書き出しを考える際のポイントなどを紹介しています。
- 11月のおたよりの書き出しは、秋を連想させる言葉を使う
- 年齢別のおたよりでは、クラスの子どもたちの様子をイメージしやすい言葉で伝える
- 冬の準備や行事を載せると、保護者が事前に必要なものなどの準備がしやすくなる
 Takako【元保育士】
Takako【元保育士】「おたよりの書き出し、どう書こう」と悩むこと、ありますよね。
子どもたちの園での様子や季節の活動を、保護者にわかりやすく伝えるのは意外と難しいものです。
そんなときは、子どもたちの笑顔や楽しんでいる姿、季節の変化を取り入れるだけで印象がぐっと良くなりますよ。


Takako先生 元保育士ライター
保育士歴7年、現在は男女2児の母をしています。保育現場で培った経験や知識を活かし、悩んだり困ったりしている保育士の方、保育士を目指している方の力になれるような記事を心がけています。
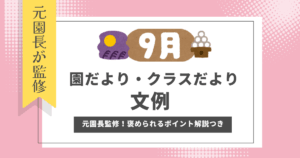
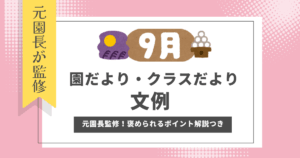
【先輩保育士直伝】11月のおたよりの書き出し文例アイデア集
11月は秋の深まりを感じる季節です。
園庭の落ち葉や秋の味覚を通して、子どもたちの感性や表現力が育まれる時期でもあります。
この章では季節を感じられる書き出しや、子どもの姿がイメージしやすい文例、食育や健康に関する文例、作成時のポイントなどを紹介しています。
短めの書き出しの文例
木々の色が赤や黄色に色づき、園庭もすっかり秋の装いとなりました。
園庭や散歩先で落ち葉を集めたり、枯葉を踏みしめて音を楽しむ子どもたちの姿に、秋の深まりを感じます。
秋晴れの日には、園庭で元気に体を動かしながら、友だちと笑顔いっぱいで過ごしています。
保護者の興味・関心を引き、文章を読み進めてもらうきっかけを作るため、書き出しに季節感や子どもの様子を入れましょう。
短めの書き出しにする場合、短くても、季節感または子どもの園での様子がパッと想像できる文章にすることがポイントです。
長めの書き出しの文例
朝夕の空気が一段と冷たくなり、園庭の木々も少しずつ冬の装いへと変わってきました。落ち葉を集めたり、どんぐりを見つけたりと、子どもたちは秋ならではの遊びを楽しんでいます。
澄んだ空気に冬の気配を感じるようになりました。子どもたちは夢中になって、落ち葉や木の実などの小さな秋を集めています。
長めの書き出しでは、子どもたちが遊ぶ様子や表情を丁寧に伝えることで、園での姿がよりイメージしやすくなります。
そうすることで、書き出しの文章に温かみが増しますよ。
季節に合わせた書き出しの文例
園庭に落ち葉が舞い、子どもたちは枯葉を踏みしめながら元気いっぱい遊んでいます。
サツマイモやリンゴなど、秋の味覚を取り入れた給食を、子どもたちも楽しみにしています。
冷たい木枯らしが吹くようになり、冬の足音が少しずつ近づいてきました。
落ち葉や紅葉、木枯らし、立冬、七五三、秋の味覚(サツマイモ・リンゴ)などの言葉を入れると、11月らしい季節感を表現できます。
秋をイメージできる言葉を意識して取り入れることで、より季節感を感じることができるおたよりになります。
子どもの姿についての書き出し文例
紅葉した葉っぱを使って貼り絵をしたり、色とりどりの作品を作ったりと、子どもたちは季節を感じる活動に夢中です。
給食のさつまいもご飯をほおばりながら「おいしい!」と笑顔を見せ、秋の味覚を楽しんでいます。
ポイントは、「踏みしめる」「集める」「笑顔を見せる」といった、子どもたちの動作や表情を入れることです。
また、「見て!」「おいしい!」といった、子どもの一言を添えることで、保護者が園での姿を具体的にイメージしやすくなります。
11月の食育についての書き出し文例
寒さが増してくるこの時期、体を温める食べ物が子どもたちの元気の源になります。旬の野菜を使った温かい汁物は、心も体もぽかぽかにしてくれます。
園庭で元気に遊んだ後、子どもたちは「今日の給食はなにかな?」と楽しみにしています。サツマイモやキノコなど、旬の食材を取り入れることで、食への興味もますます広がっていきます。
「寒さ」「温かい汁物」「サツマイモ」「キノコ」など、季節感のある言葉を入れましょう。
11月らしい季節感をだしながら、食育のねらいに繋がるよう意識することがポイントです。
健康に関する書き出し文例
朝晩の冷え込みが強まり、体調を崩しやすい季節になりました。園でも手洗いやうがいを大切にしながら、元気に過ごせるよう心がけています。
元気に遊ぶ子どもたちですが、朝夕の寒暖差で体調を崩しやすい時期です。衣服の調節や十分な休息を心がけ、毎日を快適に過ごせるようにしています。
季節感に、手洗い・うがいといった健康管理の基本を合わせたり、衣服の調整・休息などの具体的な健康管理方法を伝えましょう。
子どもの姿や保護者と共有したい視点を盛り込むと親しみがでやすい文章になります。
行事に関する書き出し文例
11月◯日は、サツマイモほりがあります。「どんなかたちのおいもがでてくるかな?」「おおきいおいもとりたい!」と子どもたちも期待でいっぱいです。
11月◯日は待ちに待った秋の遠足です。子どもたちは「おやつはなににしようかな」と待ちきれない様子です。当日も元気いっぱいに出発できるよう、ご家庭でも体調を整えていただければと思います。
冒頭で日付を入れると、パッと見て行事の日程が分かりやすくなります。
また、子どもの言葉や様子を具体的に入れることで、子どもたちのワクワク感や、成長を実感しやすい文章になります。
記念日に関する書き出し文例
11月15日は七五三です。子どもたちの健やかな成長を祝う日本の大切な行事です。園でも「大きくなったね」「おめでとう」と声をかけながら、一人ひとりの育ちを温かく見守っています。
11月23日は勤労感謝の日です。いつもお仕事をしてくれている方々にありがとうの気持ちを伝える機会として、子どもたちと一緒に「感謝のことば」を考えています。
冒頭に日付を入れ、短くどのような日かを説明しましょう。
そうすることで、保護者は行事の予定や意味を理解しやすくなり、読みやすくなります。
結びの文例
これからも一人ひとりの成長を温かく見守っていきます。
引き続き、ご家庭でもご協力をよろしくお願いいたします。
元気いっぱいの子どもたちと、楽しい日々を過ごしていきたいと思います。
結びの文章は、文章全体の締めくくりです。
長くなりすぎず、簡潔で前向き、温かい表現を意識しましょう。
このようにすると、文面からも安心感や前向きな印象を与えられます。
【年齢別】おたよりの書き出し文例アイデア集
年齢別のおたよりの書き出しでは、各歳児の子どもたちの成長の様子や季節の活動がイメージしやすい文章を書くことが大切です。
保護者に伝わる表現を意識することで、園での様子をより身近に感じてもらえます。
ここでは、年齢別の書き出し文例を掲載していますので、クラスだよりの参考にしてください。
0歳児クラスの書き出しの文例
朝晩の冷え込みが感じられる季節となりました。0歳児クラスの子どもたちは、あたたかく、安心できる環境の中で笑顔いっぱいに過ごしています。
日ごとに表情が豊かになってきた◯◯ぐみさん。保育者の声かけやおもちゃ、スプーンなどに興味を示す姿から、少しずつ好奇心や安心感が育っています。
1歳児クラスの書き出しの文例
自分で靴を履いたり、おもちゃを片付けたりする姿が増えてきた◯◯ぐみさん。子どもたちの中で、少しずつ自立心が育っていることを感じます。
落ち葉を踏みしめながら、園庭で元気いっぱい遊ぶ姿が増えています。初めて触れる自然の感触に驚いたり、落ち葉や花を友だちと一緒に観察したりして、笑顔があふれています。
2歳児クラスの書き出しの文例
落ち葉を手に取り、友だちと見せ合いながら遊ぶ〇〇ぐみさん。秋の自然に触れ、色や形の違いを感じながら楽しみ、感性を育んでいます。
自分の気持ちを言葉で伝えたり、友だちの気持ちを受け止めたりする姿が増えてきました。お友達や保育者とのやり取りを楽しみながら、少しずつコミュニケーション力や思いやりの気持ちが育っています。
3歳児クラスの書き出しの文例
自分の考えを言葉で伝えて、友だちの話を聞く姿が増えました。少しずつ表現力や思いやりの気持ちが育ち、友だちとの関わりを通して協調性や順番を守る姿勢も身についてきています。
お散歩が大好きな◯◯ぐみさん。散歩先では、木の実や落ち葉の色づきに気づき、季節を感じています。落ち葉やどんぐりなどを使った遊びや制作活動に興味津々です。
4歳児クラスの書き出しの文例
秋の園庭で友だちと落ち葉を拾ったり、木の実を観察したりして遊ぶ〇〇ぐみさん。友だちと協力したり、自分のアイデアを出して遊んだりしながら、表現力や考える力が育っています。
秋晴れの園庭でかけっこや鬼ごっこを楽しむ〇〇ぐみさん。体をいっぱい動かしながら、友だちとルールを守って遊ぶ楽しさを感じています。
5歳児クラスの書き出しの文例
◯◯ぐみさんは、お絵描きや制作活動を通して、自分の考えやアイデアを形にする楽しさを感じています。友だちと協力して作品を作る中で社会性や達成感も育っています。
活動の中で役割分担やリーダーシップを意識する姿が増え、主体性や責任感が育っています。友だちと意見を出し合うことで、思いやりや協力の気持ちが育ち、自分の考えを伝える力もぐんぐんと伸びています。
11月のおたよりで伝えたいこと
11月のおたよりでは、寒さ対策や服装の準備を促すことが大切です。
また、園行事や七五三、勤労感謝の日なども丁寧に伝えてください。
冬の準備や園での活動、行事の内容、記念日の意味がわかると、家庭での体調管理や子どもたちの成長を支える声かけがしやすくなります。
寒さ対策
11月は肌寒い日が増え、朝晩の気温差も大きくなります。園で快適に過ごせるよう、薄手の長袖や脱ぎ着しやすい上着の準備をお願いします。外遊びで汗をかくこともあるため、体温調整のしやすい服装の用意があると安心です。
季節の変わり目で体調を崩しやすくなるため、体温調節のしやすい服の準備をお願いしましょう。
また、本格的な冬に備えて、冬用の長袖や上着の準備も保護者に伝えておくと安心です。
行事や記念日の紹介
11月30日は「絵本の日」です。絵本の日は、子どもたちに読書の楽しさを伝え、絵本を通して想像力や言語力を育むことを目的としています。園では、子どもたちが絵本の楽しさを感じられるよう、積極的に読み聞かせを行なっています。
11月に行われる園行事や記念日を紹介をするときは、保護者が予定を把握しやすいように書くことがポイントです。
行事の意味やねらいが保護者に伝わるよう、簡潔に書きましょう。
- 11月3日 文化の日・みかんの日
- 11月7日 立冬・鍋の日
- 11月15日 七五三
おたより作りに悩んだときのヒント
おたより作りに悩んだときは、まず伝えたい内容を整理することが大切です。
そうすることでわかりやすく、読んでいて安心感のあるおたよりになります。
季節の行事や子どもの様子、園での活動など、保護者に知ってほしい情報を軸にすると書きやすくなります。
ここでは、おたより作りに悩んだときのヒントやポイントを紹介しています。
11月の保育で取り入れる予定の歌や遊びを紹介する
子どもたちが楽しむ予定の歌や遊びを紹介すると、保護者が園での様子をイメージしやすくなります。
歌や遊びの名前を具体的に記載し、季節感や活動のねらいも添えることがポイントです。
落ち葉や木の実を使った遊び、季節にちなんだ歌、友だちと協力する活動など、体験の楽しさや学びにつながる内容を簡潔に伝えます。
そうすることで、家庭での声かけや遊びのヒントに繋がります。
11月にぴったりな絵本の紹介をする
- 乳児クラス:きのこのこ・どんぐりずもう・おつきさまこんばんは
- 幼児クラス:やきいもたいかい・きのみのケーキ・もりのふゆじたく
秋の自然や食べ物をテーマにした絵本を紹介しましょう。
乳児は、色や形に触れ、木の実や落ち葉など季節の変化を感じ、五感を刺激しながら楽しめる絵本がおすすめです。
絵本の読み聞かせを通して、ゆったりとした時間を楽しみながら、季節や自然への興味を育みます。
幼児は、秋の味覚や行事、冬への準備を題材にした絵本を選ぶと、想像力をより育んでくれます。
絵本を読むことで、季節の変化や文化を学ぶきっかけにもなります。
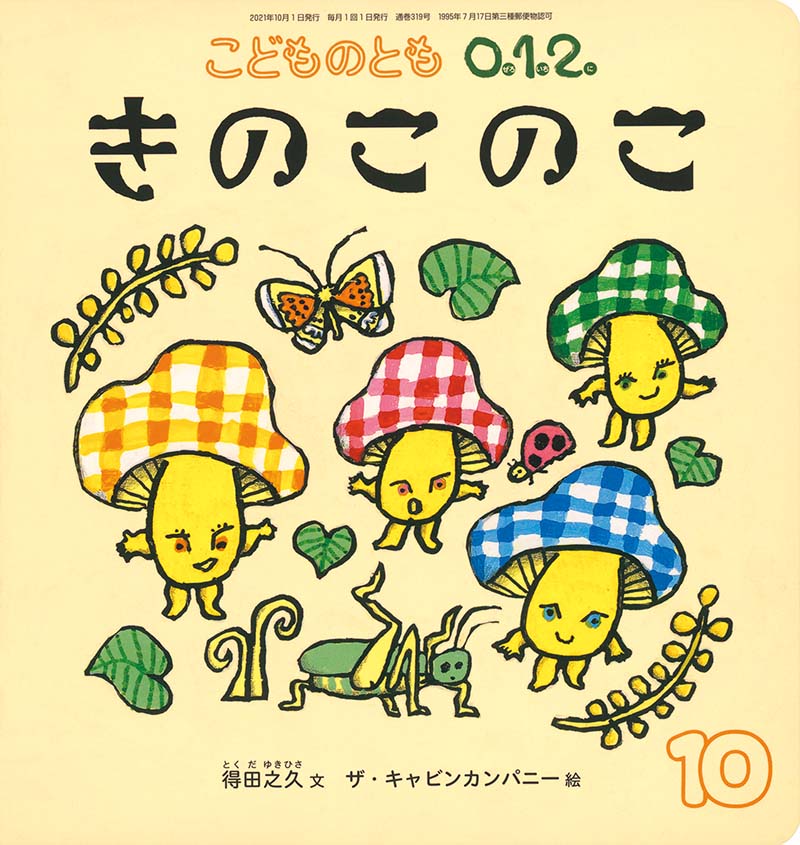
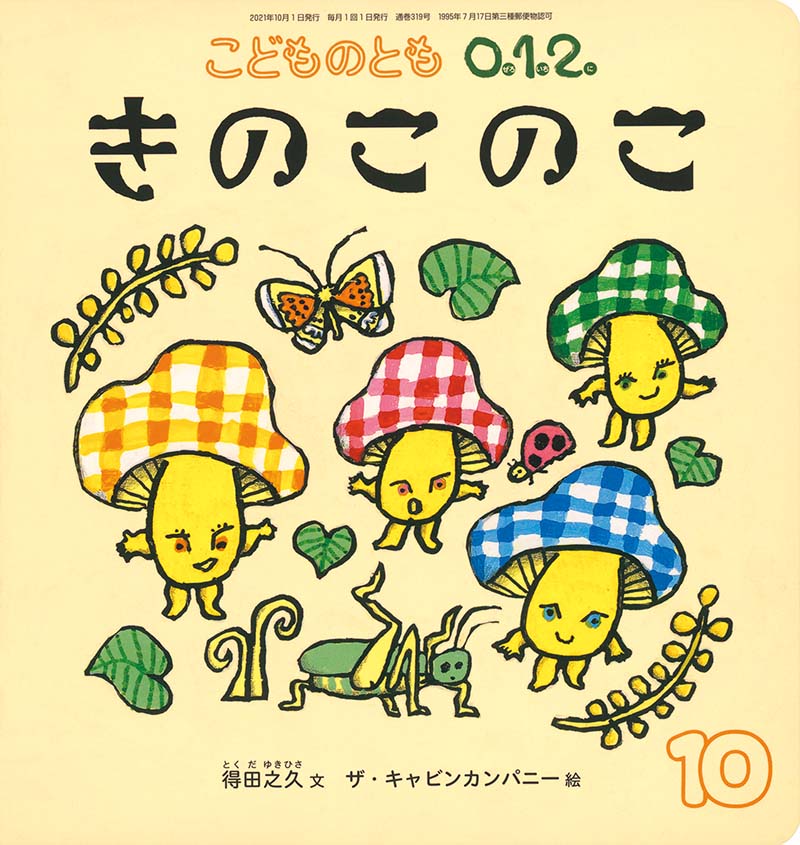
保護者へのお願いごとや周知しておきたいことを書く
保護者に安心感を与え、保育園と家庭の連携をスムーズにするためにも、保護者へのお願いごとや周知しておきたいことを書きましょう。
例えば、服や持ち物の記名、体調管理の協力、行事への参加や持ち物の確認などを今一度伝えておくと安心です。
また、園での活動や子どもの成長の様子も共有します。
そうすることで、家庭でも生活習慣の声かけがしやすくなり、園と家庭が一体となって子どもを見守る環境作りにつながります。
まとめ
11月のおたより作りでは、季節感や子どもの成長を感じられる書き出しを意識することが大切です。
行事や健康面の注意点、服装や持ち物の準備なども添えると、保護者にとってわかりやすく安心感のある内容になります。
紹介した文例やポイントを参考に、保護者が最後まで読みたくなるようなおたよりを作ってみてくださいね。








