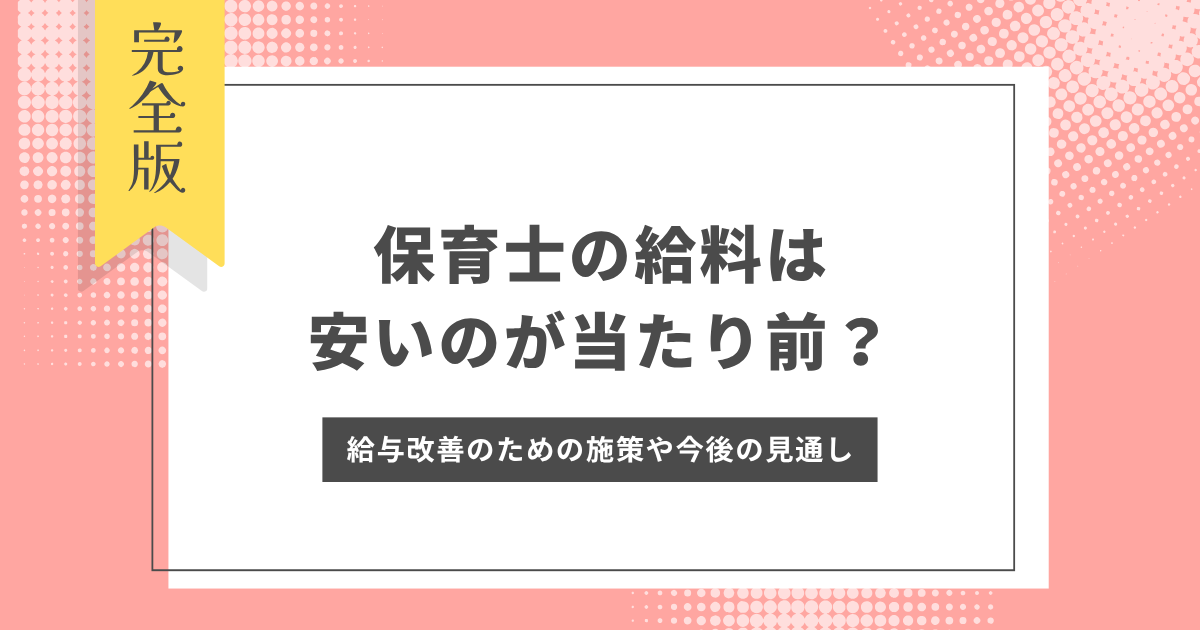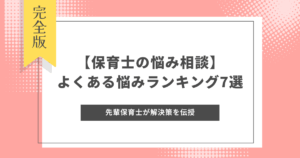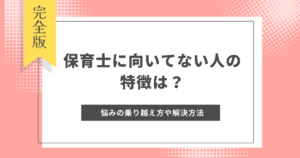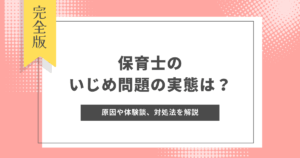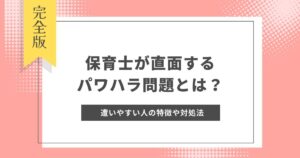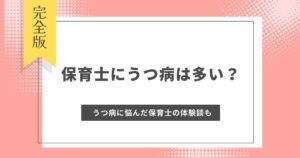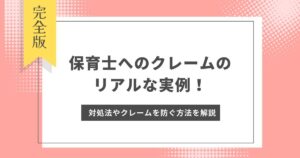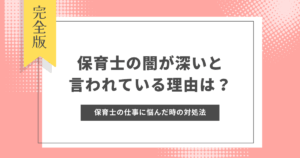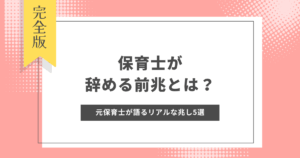「保育士の給料が低いのは当たり前?」と言われる背景には、保育士の給料は他職業に比べて低く、長年にわたり給与改善が進められていなかったためです。
ですが、近年では国や自治体などが保育士の給与改善のためのさまざまな施策を積極的に進めていて、2025年からは制度の一本化など、給与改善のための施策が強化されつつあります。
本記事では、保育士の給与改善のための施策と、今後の見通しについて分かりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
- 保育士の給料は低いが、様々な施策により上昇傾向にある
- 国は、保育士の給料を上げるため処遇改善等加算の導入や、施策の一本化などを行なってきた
- 積極的な施策により、働きやすさの向上とより良い保育の提供が期待される
- スキルや経験を活かしたり、支援制度などを活用することで給料アップが期待できる
 Takako【元保育士】
Takako【元保育士】保育士の仕事は責任のある、とても重要な仕事です。
業務はたくさんあり、責任も重いのに、給与も低いとなるとこのままでいいのか不安になってしまいますよね。
この記事では、具体的にどのような施策が進められているのか、給料アップの方法など解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。


Takako先生 元保育士ライター
保育士歴7年、現在は男女2児の母をしています。保育現場で培った経験や知識を活かし、悩んだり困ったりしている保育士の方、保育士を目指している方の力になれるような記事を心がけています。


「保育士の給料は安いのが当たり前」と言われる背景は?
「保育士の給料は安いのが当たり前」と言われる背景には、保育士の給料が他職種と比べて低い水準だったことが原因の1つではないかと考えられます。
保育士の仕事は、子どもの命や成長に大きく関わる責任の重い仕事ですが、その重要度に見合った処遇改善が行われてきませんでした。
ですが、近年では国も保育士の給料をあげようと積極的に様々な施策を行い、保育士の給料は以前よりもあがっています。
保育園の運営資金には限りがある
保育園の主な収入は、国や自治体から入る公費と、保護者から支払われる保育料です。
公費や保育料は、国や自治体が定めた「公定価格」によって決められているため、保育園側が自由に調整できません。
以下に保育園の運営資金から支払うものをまとめました。
- 職員の給料・ボーナス・社会保険料
- 事務管理費・教材費
- 給食費
- 施設維持費光熱費
- 備品購入費・災害対策費
- 研修費など
このように、保育園の運営資金は多岐にわたる支出項目に充てられており、国からの補助と保護者からの保育料で賄われているため、保育士を雇うための人件費にも限りがあります。
利益を生み出しにくい仕組み
保育園の収入源の、補助金である公費と保護者から支払われる保育料は、国や自治体で細かく決められています。
また、保護者が支払う保育料にも所得に応じた制限があり、園側が独自に増額したり、自由に利益に回すことも認められていません。
保育園は、営利目的の運営ではないため、保育園の収入は厳しい基準と制限の中で決まっていて、支出は人件費などの固定費が多く、利益を生み出しにくい仕組みとなっています。
社会的な評価の低さ
厚生労働省が行なった「保育士資格を持っているが保育士としての就業を希望しない人」を対象とした意識調査では、アンケート回答者のうち約22%の人が保育業務における社会的評価の低さを感じていると答えました。
これはおよそ5人に1人が保育士の社会的評価を「低い」と感じていることを意味しています。
この結果により、依然として保育士という職業への理解や評価が十分とは言えない現状があることがわかります。
参照:厚生労働省
保育士の給与の現状
保育士の給与の低さは、就業意欲の低下や、離職率の高さなど深刻な人材不足の一因となっています。
国は処遇改善や、借り上げ制度、補助金の拡充などさまざまな取り組みを行っていますが、生活の安定には課題が残っています。
2024年度の平均年収は約406万円と徐々に上昇傾向にあるものの、他職種と比べると依然低く、さらなる待遇改善が求められるでしょう。
現在の保育士の平均給与は?
令和6年賃金構造基本統計調査によると最新の保育士の平均給与(年収換算)は406.8万円で、平成28年の326.8万円に比べると大きく上昇しています。
これを月収に換算すると約27万となり、過去5年間でおよそ2.7万円上昇していることになります。
この結果から、国が行っている処遇改善の施策が大きく影響していると言えるでしょう。
年齢、経験年数、地域、役職、公立・私立などによって給与には差がありますが、全体としては改善が続いていることがわかります。
参照:令和6年賃金構造基本統計調査
参照:統計で見る日本
保育士の給与に関する現場の声は?保育士のリアルな悩みを紹介
保育士の給料の低さに関する不満は多くみられます。
業務の多忙さに見合わない給料で、将来の不安を感じる人も少なくありません。
ここでは、保育士のリアルな悩みを紹介します。
保育士は国家資格なのに低賃金、リアルな給料と生活のジレンマ
てかほんと、保育士の給料じゃ諸々我慢しないと生きていけなさすぎて悩みどころ
大卒国家資格なんだけどな
引用元:X(旧Twitter)
保育士は国家資格で専門的な知識や技術が必要なのに、給料が低いと指摘されることもおおくあります。
Xの口コミの中には、5年勤めても手取りが20万との声もありました。
借上制度を利用したとしても、生活に必要な金額を引くと手元にはいくらも残りません。
そうなると、趣味や娯楽など自分のために使えるお金も大幅に制限する必要があり、もどかしい思いになりますよね。
子どものためにがんばる保育士の葛藤
保育士していて辛いのは給料は低い事は100も承知でこの世界に飛び込んでみたものの自分の子どもがいじめとかむしゃくしゃしていた時に元気付けようとファミレスとかに行って『今日は好きな物食べていいよ!』って言ってあげたいけど『まだ給料日前だしなぁ…』と考え躊躇してしまう時。😢
引用元:X(旧Twitter)
保育士の給料は一般的な職業と比較すると、依然として低い傾向にあります。
子どもがいる家庭なら、子どものための貯金や、子どもにかかる支出も多くなりますよね。
ですが、給料の低さから給料日前の外食はなかなか思い切れないものです。
必要以上に自分を責めず、「今できること」を大切にしてくださいね。
手取り30万なら続けたい、保育士の本音と業務の重さ
保育士まじ給料見合わないわ手取り30万とか普通に貰えれば保育士不足少しは改善するとおもうしまだ頑張るかってなるけどね
引用元:X(旧Twitter)
保育士の業務は、ただ単に子どもと遊んでいるだけではありません。
一緒に遊びながらも、危険がないか視界は常に全体を見渡し、1人1人の特性に応じた対応を行なっています。
また、保育が円滑に進むように事前準備を行なったり、一人ひとりに合わせた生活習慣の獲得ができるよう、きめ細かい指導計画の作成、サポート、健康管理、保護者との信頼関係の構築など、保育者の仕事は多岐に渡ります。
実際に業務量と給料が見合わないと感じる保育士も多くいて、とても難しい問題でもありますよね。
国が実施してきた保育士の給与改善の施策
国は保育士の人材確保と処遇改善を目的に、「処遇改善等加算」制度の導入や、公定価格の引き上げなど、保育士の給与アップのための施策をおこなってきました。
2025年からは複雑だった処遇改善等加算制度が一本化されシンプルに、わかりやすくなります。
これらの施策により、保育士の月収や年収は上昇傾向にあります。
処遇改善加算制度
保育園で働く職員の待遇を良くするため、国や自治体から追加で補助金を受け取ることができる「処遇改善加算制度」というものがあります。
この処遇改善加算制度は、保育士の給料アップや専門性の評価、長く働きやすい環境づくりを目指しています。
保育士の給料が低い、大変なのに評価されにくい、といった問題を改善するためにも役立つでしょう。
処遇改善加算制度には3種類あり、それぞれで目的・対象などが異なってきます。
処遇改善加算Ⅰ
まず、処遇改善加算Iです。
これは、平均勤続年数に応じた加算がされます。
職員が長く働いているほど、園に入る補助金が多くなります。
| 目的 | 人材や、質の高い保育の確保をしていくために、長く働ける職場を構築すること |
|---|---|
| 内容 | 平均経験年数・キャリアパスの構築等に応じ加算率(最大19%)を設定し処遇改善を実施 |
| 対象 | 認可保育園の全職員(非常勤を含む) |
参照:社会福祉人材サポートセンター
参照:こども家庭庁
参照:こども家庭庁
処遇改善加算Ⅱ
次に、処遇改善加算IIです。
これは、経験や専門性を高めた職員(副主任保育士・専門リーダー等)に、役割や研修実績に応じて追加加算をするものです。
| 目的 | 職員の技能・経験の向上(キャリアアップ)が目的 |
|---|---|
| 内容 | 基本給や役職手当など、決まって毎月支払われる手当、または基本給により賃金改善を行う |
| 対象 | ・園長、主任を除く3年以上の保育士 (副園長を除く場合もあり、役職や自治体によっては7年以上の保育士) ・キャリアアップ研修を修了している保育士 |
参照:社会福祉人材サポートセンター
参照:こども家庭庁
参照:こども家庭庁
処遇改善加算Ⅲ
次に、処遇改善加算Ⅲです。
これは、全職員のベースアップ(基本給の底上げ)などを目的とした加算です。
賃上げ効果が「継続されること」を前提として加算されます。
経験や役職によらず、全員の給与がアップします。
| 目的 | 全職員の賃金のベースアップ(基本給の底上げ) |
|---|---|
| 内容 | 多様なサービスを提供しやすくなり、必要な場合は追加の補助金を受けることが可能。 |
| 対象 | 認可保育園の全職員(非常勤を含む) |
参照:社会福祉人材サポートセンター
参照:こども家庭庁
参照:こども家庭庁
公定価格の引き上げ
公定価格とは、国や自治体が「子ども一人あたり、1か月いくらまで補助金を出すか」を定めた基準のことです。
子どもの年齢、地域区分、夜間保育園、障がい児加算など一つ一つ細かく設定されています。
公定価格は、施設運営のための人件費や管理費、事業費などがまかなわれ、職員の給与や処遇改善加算にも充てられます。
これにより、給与や待遇が良くなり、保育士などの離職を防ぎ、新たな人材の確保にもつながるのではないでしょうか。
参照:子ども家庭庁
参照:全国民間保育園経営研究懇談会
補助金の拡充
保育園に関する補助金の拡充について、施設整備・運営支援から保育士の処遇改善、保護者への直接補助まで多岐にわたる施策が進められています。
主な施策を下記にまとめました。
- 施設整備・運営支援の拡充
- 新設・改修・整備費用の補助率が引き上げ
- 医療的ケア児の受け入れ体制強化や、園外活動時の移動経費も新たに支援対象に追加
- 保育士の処遇改善
- 「キャリアアップ補助金Ⅱ」により、園長・主任保育士を除く保育士等の賃金改善が可能となった
- 保護者への補助金の拡充
- 認可外保育施設利用支援事業補助金が拡充され、利用者負担の軽減が図られている
園の運営費の「見える化」
ここdeサーチとは、主に教育や保育施設の情報を誰でもインターネット上から検索・閲覧が可能になるプラットフォームです。
2025年から新たに、人員配置・職員給与・収支状況などが年度終了後5か月以内に報告・公表されるよう義務付けられるなど、機能や運用方法が拡充されました。
これにより、保護者や保育士が、園の経営状況や職場環境に関する情報を手軽に得られるようになりました。
必要な情報を「見える化」することにより、業務効率の向上、課題の早期発見、利用者への情報提供、継続的な経営改善の実現が期待されています。
今後の保育士給与改善の見通しは?
保育士の給料は、依然として低いものの少しずつ上がっています。
国としては、制度の見直しや導入、補助金の拡充、公定価格の引き上げ、費用の使途や処遇改善の成果の見える化など、さまざまな施策を行なっています。
こうした様々な取り組みにより、保育士の働きやすさや保育の質がさらに良くなることが期待されているのではないでしょうか。
また、今後も保育士の給料の改善は継続されていき、経験や頑張りに応じた給与体系も整えられていくと考えられます。
「こども誰でも通園制度」で保育業界はどう変わる?
「こども誰でも通園制度」は、生後6か月から満3歳未満の未就園児を対象とした新しい制度で、2025年度から段階的に制度化が進められています。
保護者の就労状況や理由を問わず、誰でも利用可能です。
この制度により、多様な家庭のニーズに柔軟に対応し、子育てと仕事の両立をさらに支援することが可能になり、保育園運営の安定化に繋がる可能性があります。
一方で、保育者の負担が増える、人材確保、安全・質の維持など、新たな課題にも直面することが考えられます。
保育士自身ができる給料アップの方法
保育士自身が給料アップを目指す方法は、キャリアアップ研修の受講や役職取得、新たな資格の取得など様々あります。
また、手当や福利厚生が充実した園への転職も有効です。
給料アップを目指すなら、自身のスキルや経験を活かし、積極的に給与改善の機会を探ることが重要です。
主任や園長へのキャリアアップ
主任や園長へのキャリアアップは、保育士としての経験やスキルを積み重ねることが必要です。
主任になるために、特別必要な資格や試験、研修はありません。
公立の園長になるためには、「昇格試験」を行いますが、私立保育園では昇進試験などは必要ありません。
ですが、実際には保育の知識や経験、リーダーシップが求められます。
そのため、マネジメント研修、リーダーシップ研修、主任保育士研修、園長向けの研修、キャリアアップ研修などを受講しておくと、運営力向上に大きく役立ちます。




副業やスキル活用
- ベビーシッター
- 単発バイト
- イベント託児スタッフ
- ハンドメイド販売
保育士の資格や経験を活かした副業は多岐に渡り、副業やスキルを活用することでも給料アップが期待できます。
また、研修や勉強会の参加、新しい資格やスキルの習得などスキルを活かしたキャリアアップも給料をあげるためには効果的です。
保育士のスキルや経験を活かした副業は、収入アップだけでなく、スキルアップやキャリアアップにもつながります。
ですが、副業禁止の園などもあるため就業規則の確認や、本業に支障がないよう時間管理や健康管理なども重要です。


自治体ごとの支援制度を活用
自治体ごとに保育士の待遇を改善したり、働きやすさをサポートしてくれる支援制度は数多くあります。
家賃の一部または全額を自治体や園が負担してくれる借上制度や、給料上乗せ補助、キャリアアップ研修などの費用を負担してくれるキャリアアップ補助、資格取得支援など様々あります。
これらの制度を活用することで、経済的負担の軽減や、スキルアップ、キャリアアップに大きく役立ってくるでしょう。
参照:東京都福祉局
給料の高い職場への転職
給料アップを目指すなら、給料の高い職場へ転職することはとても有効な手段です。
転職を考える際は、キャリアアップ研修や専門資格の習得をしておくと、転職活動が有利に進む可能性が高くなります。
また、公立保育園は給料や賞与、福利厚生が安定しており、公務員としての待遇を受けられるため、年収も高い傾向にあります。
資格や研修の修了は、給料交渉や待遇面でのアピール材料となり、昇給や役職アップのチャンスも広がるため、積極的にスキルアップを目指しましょう。


おすすめ保育士転職サイトの紹介
保育士の転職活動を効率よく進めていくためには、転職サイトの活用も効果的です。
転職サイトは豊富な求人数や非公開求人の取り扱い、専任アドバイザーによる徹底的なサポートなど、転職活動をしたことがない人でも安心して取り組めるのが特徴です。
転職サイトはさまざまあり、特徴もちがいます。
自身にあった転職サイトを使用し、転職活動を有利に進めていってくださいね。
ミラクス保育


| 運営会社 | 株式会社ミラクス |
|---|---|
| 求人数 | 公開求人37,701件 非公開求人29,875件 |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員・派遣・パート・アルバイト |
| 公式サイト | https://hoiku.miraxs.co.jp/ |
ミラクス保育は、全国に約37,000件以上の求人を抱え、非公開求人も非常に多く、業界最大級の求人数が強みです。
多様な雇用形態に対応し、勤務地や勤務時間など細かく条件を指定して検索できるので、自身の希望条件に沿った転職先が見つかるでしょう。
元保育士の経験豊富なコンサルタントが、面接対策や給与交渉も含めて転職活動を徹底サポートしてくれるので、転職活動に不安がある人にはおすすめです。
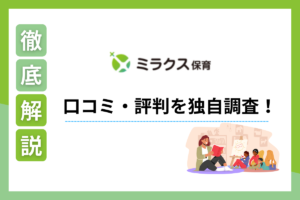
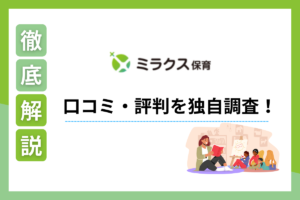
マイナビ保育士


| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
|---|---|
| 求人数 | 15,000件以上 |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員・パート・アルバイト |
| 公式サイト | https://hoiku.mynavi.jp/ |
マイナビ保育士では、全国47都道府県の求人に対応し、特に首都圏の求人が非常に豊富なのが特徴です。
また、保育園以外にも障がい児施設、放課後デイサービス、病後児保育など様々な形態の求人も取り扱っているため、キャリアチェンジを考えている人にもおすすめです。
マイナビ保育士は全国対応で、キャリアアドバイザーが希望条件や悩みに沿ったサポートを行なってくれるため、安心して転職活動を行うことができるでしょう。
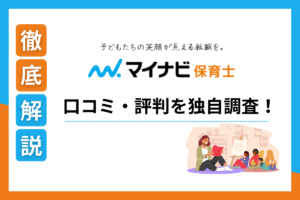
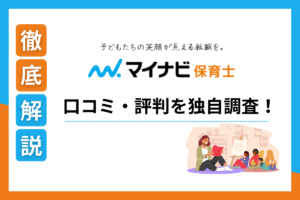
保育のお仕事


| 運営会社 | 株式会社トライトキャリア |
|---|---|
| 求人数 | 48,770件 |
| 対応エリア | 全国 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員・派遣・パート |
| 公式サイト | https://hoiku-shigoto.com/ |
保育のお仕事は、認可・認定こども園、企業内保育、病院内保育などの幅広い施設形態に対応しています。
雇用形態も多様なので、自身にあった就職先を見つけることができるでしょう。
全国対応で地方の求人も多く、地方での転職を考えている人や多様な働き方や施設を探したい人におすすめの転職サイトです。
また、履歴書の書き方や面接のアドバイスなど手厚いサポート体制が整っています。
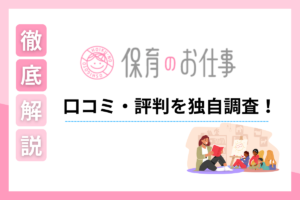
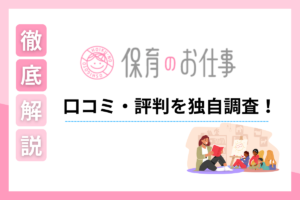
まとめ
保育士の給与は長年、低いままでした。
ですが近年では、保育士の給与の低さが見直され国や自治体による処遇改善や制度の一本化で改善の兆しが見えています。
今後は、現場で働く保育士の声を反映した柔軟な制度の運用と、更なる待遇の改善が期待されます。
保育士の給与や待遇が改善することで、潜在保育士が復職をしたり、保育士の意欲向上につながったり、より質のいい保育の提供が実現するのではないでしょうか。