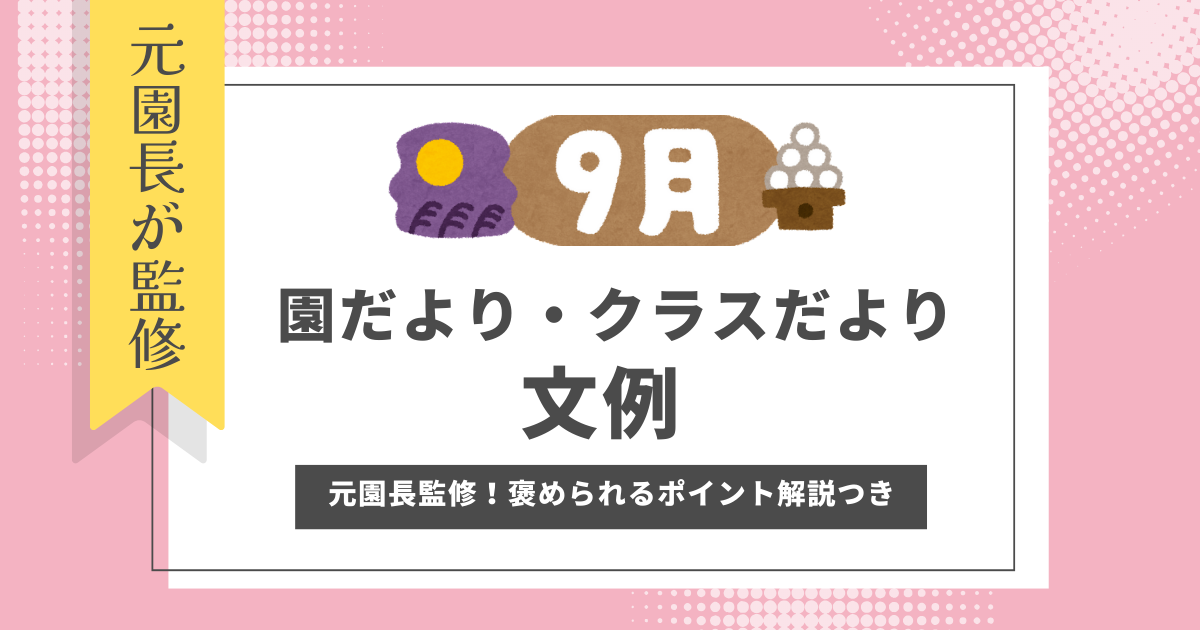楽しかった水遊びや、各家庭ごとの夏休みも終了し、徐々に日常が戻ってくる9月。季節の移り変わりを感じられる季節には、その時期ならではの自然事象や出来事を盛り込み、園だよりからも季節感を感じられるように作成したいですね。
いち早く文例をご確認したい方は「こちらのリンク」を押してください。

Aki 園長歴6年
保育士歴18年、園長歴6年。これまで多くのカリキュラム添削や、保育士さんたちの悩みに寄り添ってきました。この記事では園長として多くの月案・週案をチェックしてきた経験を活かし、 効率よく質が高い月案・週案を仕上げられるようサポートします。
ポイント解説を飛ばしいち早く文例をご確認したい方は「こちらのリンク」を押してください。¥
挨拶文・書き出しの文例
<短めの文例>
日中はまだまだ暑い日が続きますが、朝夕の風が心地良く、いつの間にか秋の訪れを感じるようになってきました。
夏の間、毎日大活躍だった水遊びグッズたちの片付けも終え、園内では、秋を迎える準備が整いつつあります。
十五夜を迎える9月。園の絵本コーナーでは、今月のおすすめ絵本である「パパ、お月さまとって」が大人気です。
セミの鳴き声が響き渡っていた8月を超え、いつの間にか、鈴虫の涼し気な鳴き声が聞こえるようになりました。
夕方気温が下がってきた時間を見計らい、お散歩に出かける子どもたち。身近に転がっている小さな秋探しを楽しんでいます。
9月15日は敬老の日。各クラスごとに、大好きなおじいちゃん・おばあちゃんに宛てたプレゼント作りが始まりました。
10月の運動会に向け、いよいよ準備が始まりました。各クラスごとに、かけっこや玉入れ、ダンスなどの練習に励んでいます。
<長めの文例>
朝夕の空気が入れ替わり、心地良い風が吹くようになりましたね。あっという間に夏が終わり、季節は秋へと歩みを進めました。暑すぎて戸外遊びを控えていた子どもたちも、涼しい時間を見計らい、園庭や公園で元気いっぱい走り回っています。
少しずつ進めてきた運動会の準備が、本格的にスタートしました!各クラスとも、担任が工夫を凝らし、子どもたちが楽しめる競技やダンスを考えています。体を動かすことを喜ぶ子どもたちは、「待ってました!」とばかりに、張り切って練習に参加しています。
9月1日は防災の日です。園では毎月1回、地震や火事を想定した避難訓練を行っています。園内放送と共に訓練がスタートすると、遊んでいた手を止め、担任の元にすぐ集まる子どもたち。訓練の成果が出ており、日々の積み重ねの大切さを改めて実感しました。
保護者に伝えたいことに関する文例
日中ぼーっとしていたり、お昼寝時になかなか目覚められなかったりと、夏の疲れが見られる子どもたちが多くなってきました。園では、子どもたちの様子を見ながら活動を調整し、無理のないように過ごしています。ご家庭でも引き続き、様子を見ていただけるようお願いいたします。
年間予定表等で事前にお知らせしています通り、〇日に引取り訓練を実施いたします。大規模な災害が発生したことを想定し、園から一斉メールを送信します。メールに書かれた内容に沿って各自ご対応をいただき、安全な方法でお迎えをお願いいたします。
運動会の練習が始まり、毎日張り切って練習に励んでいる子どもたち。かけっこ、跳び箱、鉄棒などなど…。少し難しいものや苦手意識のあるものにも積極的に挑戦する姿がたくさん見られます。当日、大好きなおうちの方々にかっこいい姿を見せられるよう頑張っていますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね!
 監修者
監修者1つ注意として、保護者の方からするとお願いされることが多いと疲れてしまいます。お願いの数はあまり多くならないようにしましょう。
また、「〜してください」「〜気をつけてください」など一方的な書き方は高圧的に感じてしまうので気をつけましょう。
子どもたちの姿に関する文例
乳児期・幼児期共通の文例
散歩先でどんぐりを発見した子どもたち。保育者が渡したビニール袋いっぱいに詰め込み、その後砂場でケーキ屋さんごっこに発展!友だちと一緒に見立て遊びを楽しんでいました。今月は一人ひとりお散歩バッグを作り、秋探しのお散歩を楽しみたいと思います。
園の絵本コーナーを、夏から秋に模様替えしました。秋をテーマにした絵本や図鑑がメインの棚に並び、毎日の読み聞かせを楽しむ子どもたち。どんぐり、松ぼっくり、きのこ、鈴虫、お月様など、秋を感じられる絵本から、季節を楽しんでほしいなと思います。
行事に向けた活動がそれぞれ始まり、子どもたちは毎日の園生活を張り切って過ごしています。その年齢ならではの取り組みを通して、「できた!」や「やってみたい!」という心を育てられるよう、職員一同関わっています。
乳児期向けの文例
「自分でやりたい!」の気持ちが育ってきている〇〇組さん。保育者の見守りの中、身の回りのことを自分でしようと奮闘中です。一人でできずに悔し泣きする姿もありますが、それでも頑張ってやり遂げた時の笑顔は格別!園生活を通して、自信が育つ関わりをしていきたいと思っています。
涼しい時間を見計らい、お散歩に出かけ秋探しを楽しんでいます。落ちている葉っぱの色や音の変化に気付いた子どもたち。「緑じゃないね」「カサカサするね」と教えてくれ、身近な自然から、季節の移り変わりを感じられたようでした。
運動会に向け、室内に巧技台やマットを出し、サーキットを行っています。巧技台を使って山登りやジャンプ、マットで前転、フープのトンネルくぐりなど、4月からは比べ物にならないほど、いろんな動きができるようになりました!
幼児期向けの文例
防災の日にちなんで、災害時に安全を確保するためのクイズ大会を行いました。日頃から保育者の話をよく聞いている幼児組のお兄さん・お姉さんたちは、なんと全問正解!避難する時にすること、してはいけないことをしっかりと理解できていました。
園に飾るお月見団子を粘土で作った〇〇組さん。粘土の扱いには慣れているものの、小さくてきれいな丸型にするのは意外とコツがいるようで、「ここの形が変」「もう少しきれいな丸にしたい!」と、自分の納得がいくまでこだわって製作していました。
ルールのある遊びや集団遊びを通して、友だちと協力して活動する楽しさや、やり遂げる難しさなどを経験している子どもたち。以前であれば、ささいなことで言い合いになっていた場面でも、お互いの意見を尊重し合おうとする姿が見られるようになってきました。
食育に関する文例
さつまいもを使ったメニュー
さつまいもスティック…甘くておいしい、子どもたちが大好きなさつまいもを使っておやつを作りませんか?よく洗ったさつまいもを皮ごとスティック状に切り、熱したフライパンに少量の油を入れカリッと焼いたら出来上がり!自然の甘さが魅力の安心おやつです。
さつまいもボール…皮をむいたさつまいもを蒸して柔らかくし、牛乳やミルクと混ぜ合わせて潰します。冷めたら丸く成形し、お好みできなこや粉糖をふりかけたら完成!離乳食にもおすすめの、甘くておいしいさつまいもメニューです。
旬の食べ物
きのこ類…秋に旬を迎える、栄養価の高いきのこ。ビタミンDや食物繊維が多く含まれており、骨や免疫力の強化、腸内環境の正常化などに効果を発揮してくれます。風邪予防にもおすすめ!しいたけ、えのき、しめじ、まいたけなど種類も豊富で、炒め物やスープなど様々なメニューに変身する優秀食材です。
ぶどう…ポリフェノール、ビタミンC、カリウムを多く含み、免疫力を高め、細胞の老化を防いでくれるぶどうは、子どもたちにも人気のフルーツです。おやつやデザートとしてそのまま食べるのはもちろん、ゼリーやジュースにしたり、ケーキに乗せたりと、様々なアレンジが楽しめます。
食で夏の疲れを癒す
夏の暑さで食欲が落ち気味だった子どもたち。気温の変化と共に、徐々に回復してくるこの時期は、胃腸にやさしい消化のよい食材や、ビタミン・ミネラルを含む野菜を取り入れることが大切です。旬のきのこをふんだんに使ったスープや煮物、リゾットなどで、疲れた体を内側から元気にしていきましょう。
夏の疲れを癒すには、栄養バランスのとれた食事と十分な休息が大切です。特にビタミンB群やたんぱく質を含む食材は、体力回復に効果的。園では、食事の中でしっかり栄養を摂れるよう心がけると共に、見た目にも楽しい、子どもたちが食を楽しめるメニューを提供しています。
保健に関する文例
季節の変わり目の体調管理
夏から秋へ、季節が移り変わる9月。夏の間の疲れが一気に出るこの時期は、気温差も相まって子どもたちの体調も揺らぎがちです。体力の落ちている時は、鼻水、咳などの初期症状を見逃さず、早めに対応をすることが、重症化させないための鍵。園でも日々の健康観察をしっかりと行っていきますので、ご家庭でも気になる症状が見られた際には、早めの受診をお願いいたします。
救急の日
9月9日は救急の日。子どもは急に病気をしたり、思わぬ怪我をしたりすることがあるため、もしもの時の備えが肝心です。ご家庭の救急箱の中身を再度確認し、必要な物を揃えておきましょう。
<救急箱の中にあると良いもの>絆創膏(大・小)、滅菌ガーゼ、サージカルテープ、はさみ、包帯、綿棒、ピンセット、毛抜き、体温計、ワセリン、使い捨ての冷却材、ハンドタオル、ビニール袋
足に合った靴を選びましょう
運動会が近づき、練習も活発に行われるようになりました。足に合わない靴は、活動を妨げると共に、足や体全体に負担をかけてしまいます。この機会に、靴がお子さんの足に合っているか、確認をしましょう。
<ポイント>つま先に、0.5cm~1cmほどの余裕がある、横幅が合っている、高の高さが合っている、かかとが固定されていて安定感がある
行事に関する文例
敬老の日
9月の第3月曜日は敬老の日。大好きなおじいちゃん・おばあちゃんへ、日頃の感謝の気持ちを込めて、子どもたちがプレゼントを用意しています。喜んでくれる顔を思い浮かべながら、張り切って製作に励む子どもたちです。また、〇日には、年長さんが老人ホームを訪問し、歌を披露したり、一緒にゲームをして遊ぶ予定です。
十五夜
日本では、平安時代から月を鑑賞する行事として親しまれてきた十五夜。農作物の収穫に感謝し、豊作を祈る意味を込め、すすきや団子、秋の収穫物を飾る風習が生まれました。保育園でも、子どもたちが粘土で作ったお団子を飾り、お月様にちなんだ絵本を読んで、行事に親しむ予定です。
防災の日
9月1日は防災の日。大正12年に発生した関東大震災を教訓とし制定されました。保育園では毎月必ず、様々な災害を想定した避難訓練を実施しています。〇日には、保護者の皆様の協力もいただきながら、引取り訓練も実施する予定です。いつ発生してもおかしくない大災害に備え、園と家庭とで連携し、大切なお子さんの命を守る機会となればと思っております。ぜひご参加ください。
雑学に関する文例
秋の空が高く見える理由
秋の空がなぜ高く見えるのかご存知ですか?それは、湿気が少なく、空気が澄んでいるためです。湿度が高くジメジメした夏よりも鮮明に映り、遠くまで見渡せるようになるのです。乾燥した空気が青を際立たせ、空が高く見える錯覚を生み出しています。ぜひ親子で、秋の空の下のお散歩を楽しんでくださいね。
月の模様は何に見える?
日本では、月の模様が「うさぎが餅つきをしている」と言われていますよね。中国では、仙人に使える賢いうさぎ、西洋では女性年老いた男性の横顔、南米ではワニに例えられています。それぞれの文化で、月の模様の解釈も変わってくるんですね。ぜひご家族で月を眺め、どんな模様に見えるか話し合ってみてくださいね。
締め・まとめの文例
これから日ごとに秋の深まりを感じられるようになりますね。心地良い陽気の中、たくさん体を動かし、元気いっぱい過ごしていきたいと思います。
季節の変わり目の体調不良に配慮しながら、心地良い風を体いっぱいに感じ、秋を楽しんでいきたいと思います。
装飾で使える!9月用のフリーイラスト素材
お月見のイラスト
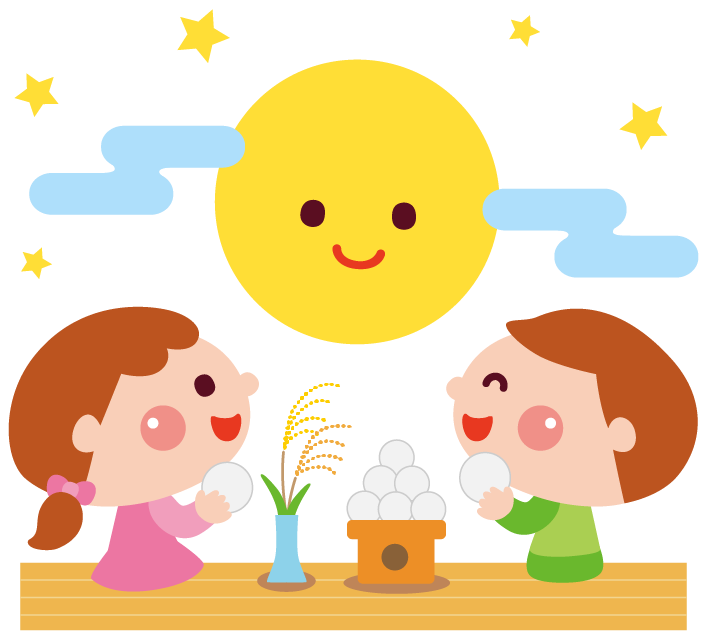
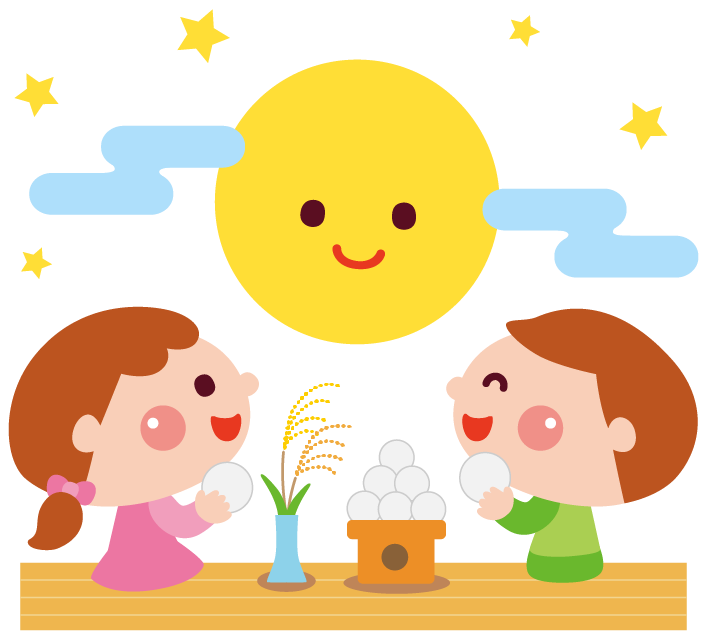
ダウンロードページURL:https://puchikawaii-illust.com/%e3%81%8a%e6%9c%88%e8%a6%8b/
秋の味覚のイラスト


ダウンロードページURL:https://puchikawaii-illust.com/%e7%a7%8b%e3%81%ae%e5%91%b3%e8%a6%9a/
今回のまとめ
今回は、9月の園だよりを作成する際のポイントについて解説しました。
9月は行事が多くあると共に、季節の移り変わりに伴う体調管理や防災について、保護者へのお願いや伝えたいことがたくさん出てきます。
園と家庭との連携がより大切になってきますので、わかりやすく丁寧な文章を心がけ、家庭の協力を仰ぎましょう。
そのほかの月の園だより/おたより文例
-


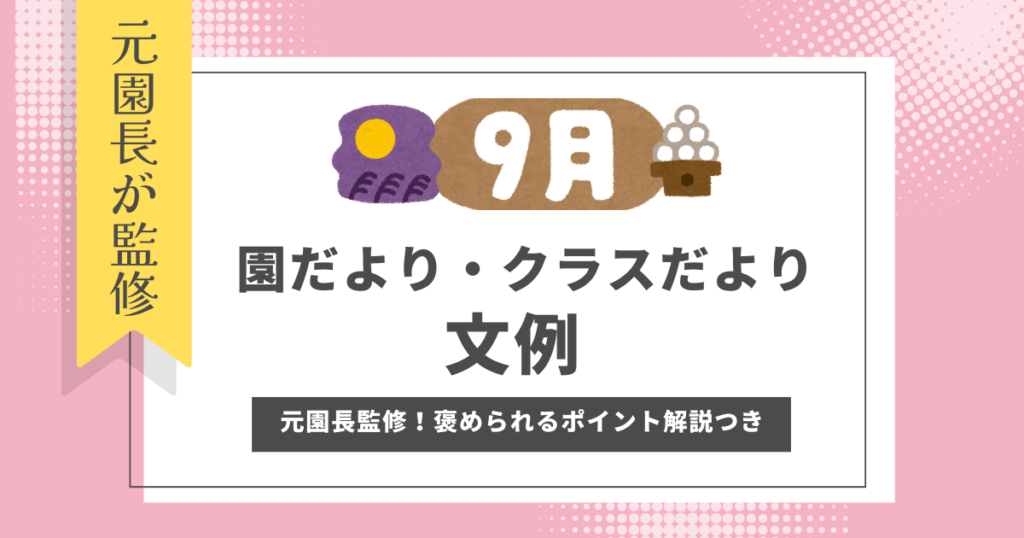
元園長監修【9月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


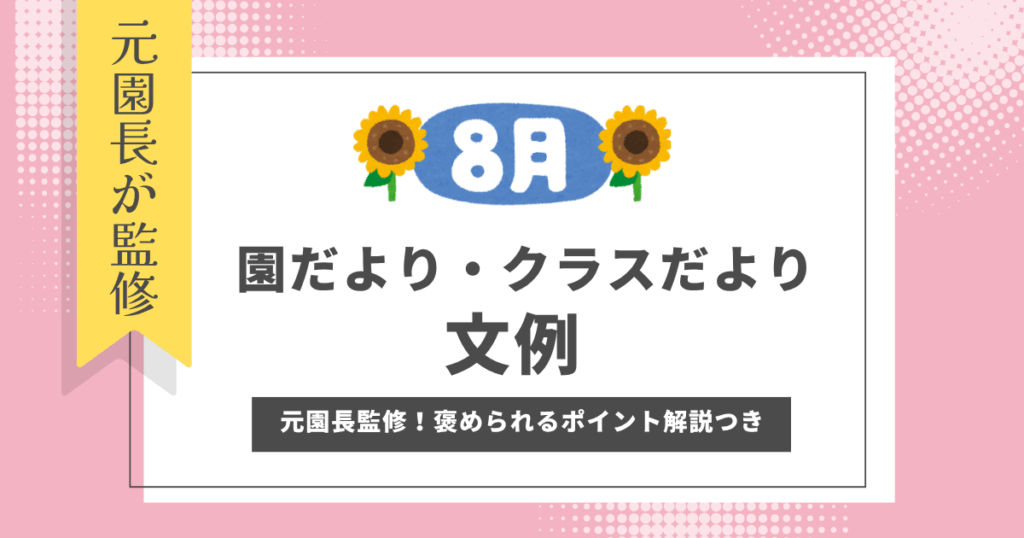
元園長監修【8月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


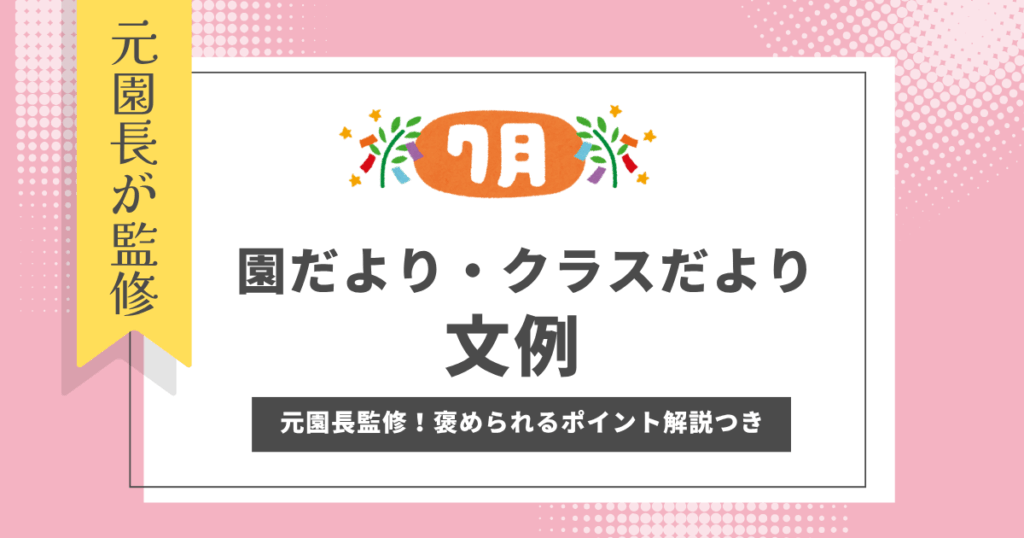
元園長監修【7月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


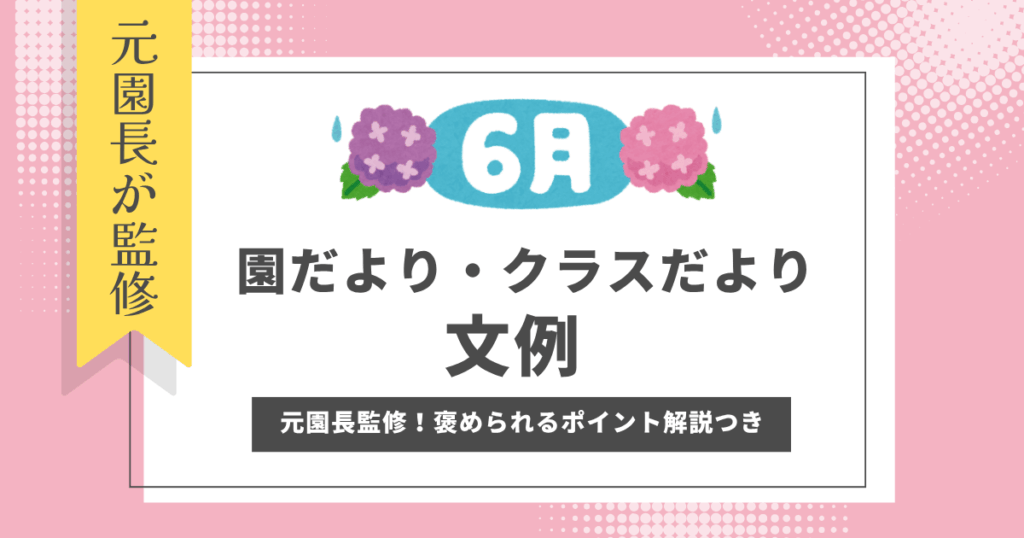
元園長監修【6月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


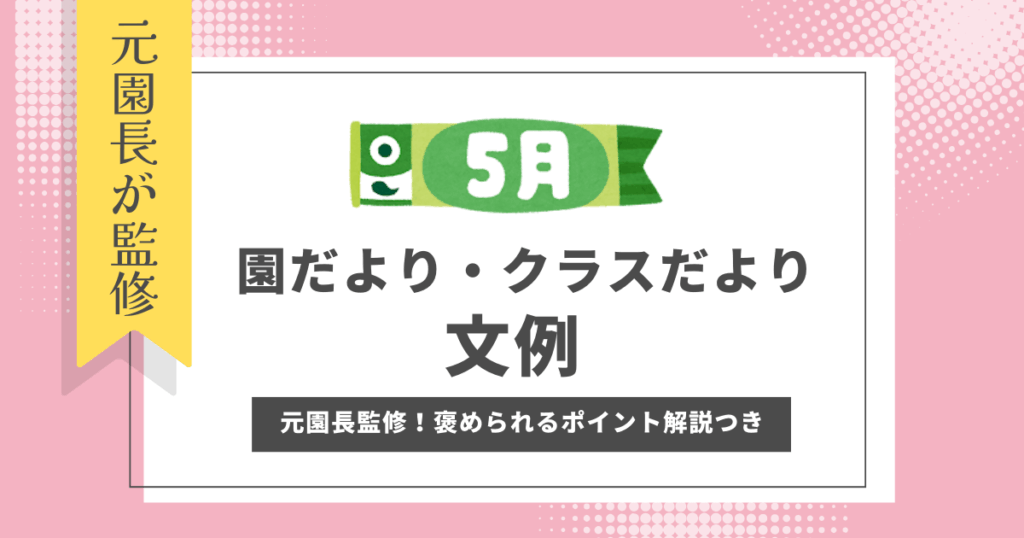
元園長監修【5月おたより】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア文例
-


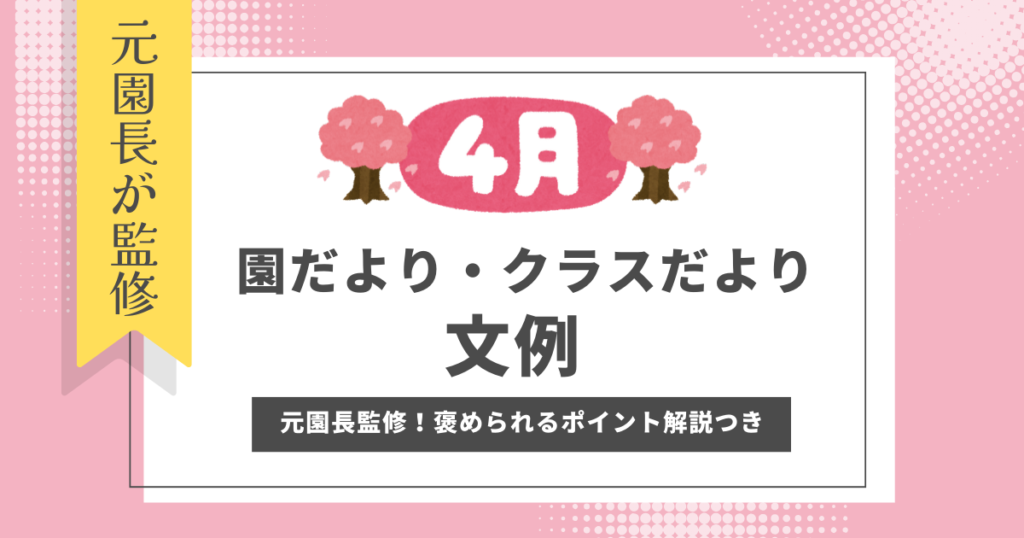
元園長監修【4月・おたより】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア文例