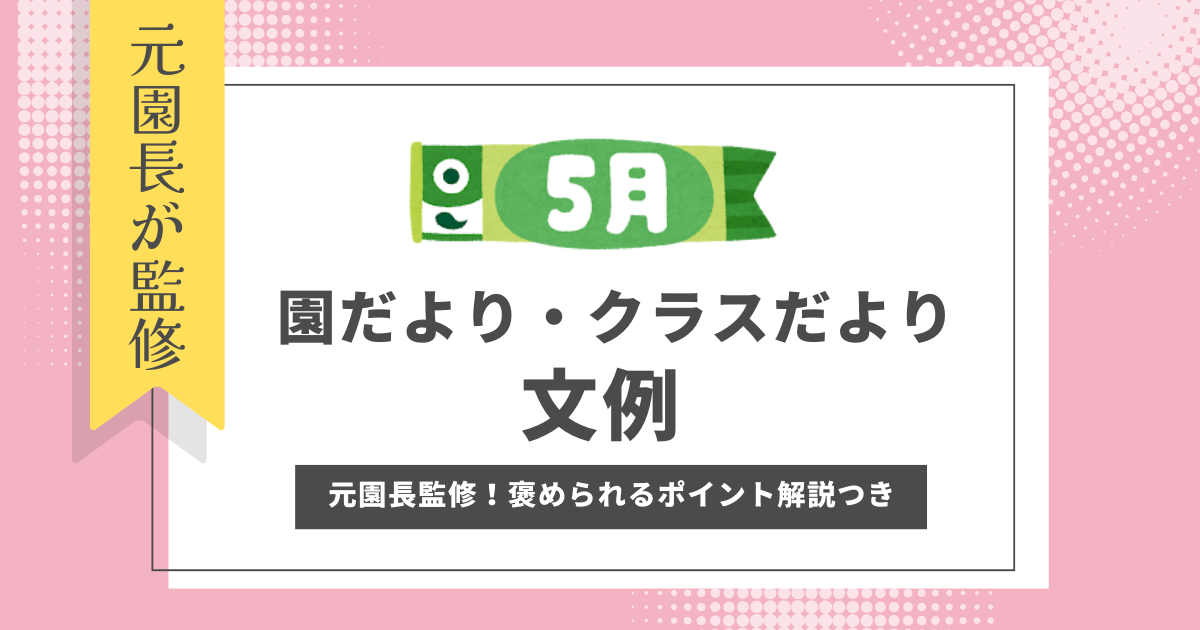連休がある5月。お休みは嬉しい反面、リズムが崩れたり、慣らし保育の疲れが見られたりする時期でもあります。こうした不安や疑問に寄り添えるようなお便りを作成し、お休み明けも安心して過ごせるようサポートしてあげたいですね。
いち早く文例をご確認したい方は「こちらのリンク」を押してください。

Aki 園長歴6年
保育士歴18年、園長歴6年。これまで多くのカリキュラム添削や、保育士さんたちの悩みに寄り添ってきました。この記事では園長として多くの月案・週案をチェックしてきた経験を活かし、 効率よく質が高い月案・週案を仕上げられるようサポートします。
ポイント解説を飛ばしいち早く文例をご確認したい方は「こちらのリンク」を押してください。
【全月共通】園だより/おたよりのポイント
園だよりはポイントを押さえておくことで、単なる「お知らせ」にならず、保護者に喜ばれる魅力的なおたよりを作成できます。
園長として数多くの園だよりを添削してきた経験から、保育士さんがつまずきやすいポイントをまとめました。
以下で解説する点を踏まえて、読み応えのある園だよりを作成していきましょう。
①専門用語や事務的な表現を使わない
・×「午睡」→ ○「お昼寝」
・×「発達段階に応じた遊び」→ ◯「子どもたちの成長に合わせた遊び」
・×「気温が低下するため」→ ○「寒くなるので」
園だよりは、全クラスの保護者に向けて発行するものです。
園を代表した文書のため、しっかりした文章を書かなきゃ…とプレッシャーに感じ、表現が事務的になってしまうことがあります。
しかし、事務的な表現は冷たい印象を与えてしまうことも。
子どもたちの魅力的な姿を十分に伝えられるよう、温かみのある柔らかい表現を心がけましょう。
また、文章を読むことに慣れていない保護者や、母国語が日本語以外の保護者のために、誰が読んでもわかるようなシンプルな言葉を使用するのも大切なポイントです。
②読む人がイメージしやすい文章を心がける
・×「いつものお散歩コース」→ ○「園近くの公園まで歩くお散歩コース」
・×「お外で遊びました」→ ○「砂場でお山を作ったり、追いかけっこをして遊びました」
・ ×「給食を食べました」→ ○「大好きなカレーを夢中で食べ、笑顔がいっぱいでした」
保護者は、園で子どもが何をして過ごしているのか、どんな小さなことでも知りたいと思っています。
しっかり伝わる文章を書くためには、読む人がその時々の情景を目の当たりにしているかのように感じられる表現を使用するのがポイントです。
具体的な描写を用いたり、場面ごとの感覚・匂い・味などの五感を活用したりすることで、より臨場感のある文章を作成することができます。
③誤字脱字や言葉の使い方を注意
<誤字脱字>
・×「食べれる」→ ○「食べられる」
×「見れる」→ ○「見られる」
・×「子供達」→ ○「子どもたち」
<言葉の使い方>
・×「してください」→ ○「しましょう」「していきましょう」
・×「安心感を感じる」→ ○「安心する」
<敬語>(二重敬語に気を付ける)
・×「お越しになられる」→ ○「お越しになる」
・×「お話しさせていただきます」→ ○「お話しします」
誤字・脱字や間違った言葉の使い方は、読み手にとって思った以上に気になるもの。
意図せず高圧的な物言いになっていたり、たびたび間違いがあるようでは、園への信頼を大きく失うことにも繋がります。
特に、パソコンで作られた文章は、思わぬ文字変換がされていることも少なくありません。
必ず複数名に確認してもらう、言葉使いや表現に自信がない場合には辞書で調べるなどを徹底し、正しい文章で作成できるよう十分に配慮しましょう。
【園長が体験】喜ばれたお便り/指摘されたお便り
 監修者
監修者ここでは園長として働く中で、実際に保護者の方に喜ばれた表現や、逆にご指摘いただいた表現について紹介します
・子どもたちの日常の様子が伝わってくる具体的な文章や写真の掲載
・日常の育児に活かせるコラム
・子どもたちに人気の遊びや給食のレシピ
・「お願い」ばかりの園だより
・高圧的、事務的な文章
・誰にでも当てはまるような文章や、丸々テンプレートの使用
日中、子どもと離れて過ごす保護者にとって、園の様子や子どもたちの成長を感じられるような園だよりは、楽しみにしていることの一つです。
子どもたちの日常が手に取るようにわかるものは、特に喜ばれます。
また、豊富なテーマのコラムや、子どもたちが喜ぶ給食メニューのレシピなど、日頃の育児に活かせる内容も園と家庭とをつなぐお守りのような存在になっているようです。
逆に、お願いばかりの内容や、圧を感じる文章では、読むのが嫌になってしまいます。喜んで読んでもらえるような内容を心がけて作成しましょう。
【5月】の園だより/おたよりのポイント
5月に入って早々にやって来る大型連休。
体を休めるには絶好の機会ですが、長いお休みで逆に不安定になってしまう子も多く、連休明けの登園を心配する保護者も少なくありません。
5月の園だよりでは、こういった保護者の「大丈夫かな?」に先回りして答えてあげましょう。
また、気温が高くなってくる時期でもありますので、園での過ごし方や必要な持ち物なども早めにアナウンスし、余裕をもって準備できるよう配慮しましょう。
①入園・進級からの子どもたちの様子を伝える
入園・進級から1ヶ月が経ち、少しずつ園生活のリズムを掴みつつある5月。
小さな子どもたちは、大好きな保護者のもとを離れ、新しい環境に慣れようと1ヶ月間頑張ってきました。
4月当初は、涙を見せたり不安そうな表情で登園した子どもたちも、笑顔で保育園に通えるようになり、保護者も心から安堵しているはずです。
大人でも緊張する新生活。
子どもたちの頑張りは、大人の想像を遥かに超えるものと言えます。
この1ヶ月間の園での様子を伝え、保護者と喜びを共有しましょう。
②連休明けに予想される姿を伝える
ようやく保育園に慣れた頃にやってくる大型連休。
また4月の様子に逆戻りしてしまうのでは…、と心配する保護者もいるでしょう。
しかし、新入児だけでなく、長年保育園に通う在園児であっても、連休明けの登園は寂しいもの。
行き渋りや登園拒否は、誰にでも起こりうるものです。
お休み前に心配しすぎてしまっては、せっかくの連休もリフレッシュができません。
安心して再登園の日を迎えられるよう、先回りして言葉をかけてあげましょう。
③気温の変化や、準備してほしいものなどを伝える
4月はまだまだ肌寒い日がありますが、5月に入ると一気に気温が上がり、汗ばむ陽気の日も出てきます。
戸外遊びが増え、着替えをする回数も多くなることが予想されますので、着替えを多めに用意してもらえるよう伝えましょう。
また、寒さで体調を崩すことを気にして、厚着をさせたり、保温効果のある下着を着せたりする保護者もいます。
園内は温かいことや、厚着をすると汗が冷えてかえって体調を崩す可能性があることなどを伝え、薄手の衣服を用意してもらえるように働きかけましょう。
それではここからは具体的な円だより/クラスだよりの文例を紹介していきます。
挨拶文・書き出しの文例
<短めの文例>
新緑が眩しい季節になりました。園庭で育てているイチゴも色づき、子どもたちは水やりをしながら、その生長を楽しみにしています。
園庭に飾ったこいのぼりが、5月の爽やかな風に乗って気持ちよさそうに泳ぎ、子どもたちを見守ってくれています。
新年度のスタートから1ヶ月が経過しました。響き渡っていた子どもたちの泣き声が、いつの間にか笑い声に変化し、園内を明るく照らしてくれています。
入園、進級から1ヶ月が経ち、徐々に保育園生活に馴染んできました。クラスのお友だちと楽しそうに笑い合う姿があります。
毎日の朝の会で歌う季節の歌を元気いっぱい歌う子どもたち。かわいらしい歌声が園内にこだましています。
春の陽気が心地よい季節になり、温かい日差しの下を楽しそうに駆けまわる子どもたち。園庭に笑顔の花が咲いています。
こどもの日を迎えるにあたり、園内にこいのぼりや五月人形を飾りました。初めて見る子もいたようで、興味津々に眺めています。
登園時、「おはようございます!」と元気いっぱい挨拶をしてくれる子どもたち。春の日差しと同じくらいキラキラと輝いた姿に、元気をもらえます。
<長めの文例>
爽やかな風が吹き抜ける5月がやってきました。入園・進級から早くも1ヶ月が経過し、徐々に新生活に馴染んできた子どもたち。明るく元気な声で園内が満たされ、日差し以上の温もりを運んできてくれています。
心地良い陽気の5月がスタートしました。子どもたちは元気いっぱいに戸外遊びを楽しんでいます。園庭で青虫を見つけた〇〇組さん。さっそく虫かごを用意し、お世話を始めました。何色のちょうちょに成長するのか、図鑑を見つめる姿はまるで博士のようです。
園庭に飾られた色とりどりのこいのぼりに見とれる子どもたち。「こいのぼり」の歌を歌いながら、5月の爽やかな風に揺られ、気持ちよさそうに泳ぐ姿を嬉しそうに見つめています。季節を全身で楽しんでいるようです。
保護者に伝えたいことに関する文例
これから長い連休に入ります。4月から、新しい生活に慣れようと頑張ってきた子どもたち。その姿をたくさん認め、たっぷり褒めてあげてください。おうちの方々からの愛情たっぷりの褒め言葉は、子どもたちにとって最高のプレゼントです。
連休中、大好きなおうちの方とたくさんの時間を過ごす子どもたち。連休明けの登園では、行き渋りや泣いてしまう姿が見られるかも知れません。これはとても自然な姿で、ご家庭で愛情をたっぷりもらった証です。心配なさらず、明るく保育園へ送り出してあげてくださいね。
これから楽しい連休が始まります。4月の疲れが見られる時期でもありますので、無理なくゆったりお過ごしください。また、万が一連休中に事故などが発生した際には、緊急連絡先までご連絡ください。
5月に入ると、ぐんぐん気温が上昇します。室内外問わず、日中体をたくさん動かして遊ぶ子どもたちは、汗をかくことが多くなり、着替えをする回数が増えます。薄手の着替えを多めに用意していただくようお願いいたします。



1つ注意として、保護者の方からするとお願いされることが多いと疲れてしまいます。お願いの数はあまり多くならないようにしましょう。
また、「〜してください」「〜気をつけてください」など一方的な書き方は高圧的に感じてしまうので気をつけましょう。
子どもたちの姿に関する文例
乳児期・幼児期共通の文例
入園・進級から1ヶ月が経ち、新しい環境に徐々に慣れてきた様子の子どもたち。保育者やお友だちと一緒に戸外でたくさん体を動かして遊び、おいしい給食をもりもり食べ、元気いっぱいに園生活を満喫しています。
園庭に大きなこいのぼりを飾りました。保育者たちが飾る準備をしていると、「これから何が始まるんだろう…」と興味津々に眺める子どもたち。風に乗って泳ぐ姿を目の当たりにし、「すごい!」「おっきい!」と大喜びでした。
プランターで育てているイチゴが色づいているのに気付いた子どもたち。指で優しく触ってみたり、匂いを嗅いでみたりと、夢中で観察しています。小さなクラスのお友だちに、「これはまだ食べられないよ」「赤くなるまで待っててね」と教えてあげる年長さんの姿も見られました。
乳児期向けの文例
不安な気持ちから、保育者に抱っこされ、片時も離れようとしなかった4月。1ヶ月がすぎ、不安そうな表情は徐々に笑顔に変わり、今では毎日にこにこ。保育者との信頼関係もできてきたようで、保育者の手を離れての探索活動を楽しんでいます。
心地良い陽気の中、戸外遊びを楽しむ子どもたち。保育者と手をつなぎ探索を楽しんだり、レジャーシートに座りお友だちと日向ぼっこをしたりと、思い思いに春を満喫しています。散歩車に揺られ、うたた寝する姿も。春のお散歩、気持ちがいいですね。
散歩中、様々な発見をする子どもたち。風に揺れる花、飛行機雲、鳥、昆虫など、どれも子どもたちにとっては新鮮で、見つけるたびに「あ!」と指を差し保育者に教えてくれます。「きれいだね」「大きいね」と共感するとにっこりと微笑んでくれます。
幼児期向けの文例
夏野菜の栽培をするため、子どもたちと何を育てたいかを相談しました。夏野菜にはどんなものがあるかを話し合い、〇〇と△△に決定!みんなで花屋さんへ苗を買いに行きました。花屋さんから、上手に育てるためのコツを聞き、さっそく実験しようと張り切っています。
戸外遊びが活発になり、全身を使って遊んでいます。気温が上がり薄着になった子どもたち。動きが益々活発になり、かけっこや鬼ごっこなどを満喫する毎日です。帰園後の身支度も、保育者の声掛けがなくても自発的に行なう姿に成長を感じました。
園庭で見つけた青虫を育てるため、みんなで図鑑を見ながらお世話の仕方を学びました。また、相談しながらお世話の当番を決め、毎日交代でその成長を見守っています。「どんなちょうちょになるかな」と虫かごと図鑑を見比べ、にらめっこする毎日です。
食育に関する文例
こどもの日
5/5は子どもの日。子どもたちの幸せを願い、健やかな成長をお祝いする日です。この日に食べられるメニューには、それぞれ意味が込められています。
ちまき…毒蛇になぞらえたちまきを食べることで、免疫力が付き、無病息災を祈願する。
柏餅…柏の木は、新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、子孫代々栄えるという意味が込められている
端午の節句と呼ばれる5/5は、子どもの成長をお祝いする日です。保育園では、こいのぼりやかぶとをかたどったメニューで、子どもたちの健やかな成長を応援します。メニューの詳細は写真で掲示しますので、おうちでもぜひ作ってみてくださいね。
旬の野菜について
初夏の味覚の代表であるそらまめ。ゆでたてのおいしさは格別で、お好きな方も多いのではないでしょうか。保育園では〇日に登場!子どもたちに皮むきをお手伝いしてもらい、おやつに塩ゆでしたものを提供します。
旬を迎えるアスパラガス。太陽の光をたっぷり浴びて育ったものはグリーンアスパラと呼ばれ、鮮やかな緑色をしています。アスパラガスはタンパク質、アスパラギン酸、ビタミンなどを多く含み栄養満点!ぜひ日頃のメニューに加えて、健康でおいしい食生活を楽しみましょう。
夏野菜の栽培
食育の一環として、園庭でプランター栽培を行なっています。今年は、〇〇組さんがミニトマトときゅうりを、●●組さんがナスとピーマンをそれぞれ育てることになりました。交代でお世話をしながら、みんなで生長を見守っていきます。
園庭で子どもたちが育てる夏野菜は、収穫したらみんなの給食メニューに並びます。お日様の光とみんなの愛情のシャワーをたくさん浴びて育つ夏野菜たち。おいしいこと間違いなし!どんなメニューに変身するのか、子どもたちは今からとっても楽しみにしています。
保健に関する文例
着替え
5月に入ると気温が上昇し、汗をかく日が多くなります。汗の始末をしないままで過ごしてしまうと、放置した汗で体が冷え、風邪をひきやすくなります。こまめな着替えができるよう、薄手の着替えを多めにご準備ください。
水分補給
汗をたくさんかく子どもたちは、知らず知らずのうちに体の水分を失い、水分不足に陥る危険があります。保育園では、日中こまめに水分補給を行なっていますが、麦茶に慣れていないお子さんは、味を嫌がり拒否することも。ご家庭でも、麦茶の味に慣れていけるようご対応をお願いいたします。
虫刺され
気温が高くなってくると、虫が多く出現し刺されやすくなります。園では、虫刺されの箇所を流水で十分に洗い、患部を冷やして症状が落ち着くのを待ちます。とびひになっていたり、患部が腫れあがっている場合には、ご家庭で塗り薬を塗る、患部を覆う、医療機関を受診するなどしてご対応ください。
行事に関する文例
こどもの日
5/5はこどもの日。子どもたちの健やかな成長をお祝いする日です。保育園では、〇日にホールで集会を行ないます。こどもの日の由来の紹介や、各クラスが作ったこいのぼりの紹介、歌を歌うなどして、こどもの日をみんなでお祝いします。この日の給食も、こどもの日特別メニューを提供!楽しみにしていてくださいね。
保護者会
〇日に保護者会を予定しています。入園・進級から1ヶ月が経ち、園生活に慣れてきた子どもたちの様子をお伝えすると共に、クラスごとに1年間の目標などをお話しし、保護者の皆様と内容を共有していきたいと思います。当日はどうぞよろしくお願いいたします。
母の日(ファミリーデー)
いつも優しく見守ってくれるおうちの方へ、子どもたちが心を込めてプレゼントを作ります。「喜んでくれるかな」「ありがとうって言って渡すんだ」と、今から張り切っている子どもたちです。どんな作品になるか、楽しみにしていてくださいね。
雑学に関する文例
こいのぼり
諸説ありますが、こいのぼりは中国の故事が由来となったと考えられています。山奥にある流れの速い滝を立派に登り切った鯉が龍になって天に上るという話から、逆境や苦難を乗り越えて出世する縁起物と考えられ、こいのぼりを飾るようになりました。
ゴールデンウィーク
ゴールデンウィークの「ゴールデン」には、「大切な」「特別な」という意味が込められています。たくさんの祝日が重なるこの期間をゴールデンウィークと呼び、みんながお休みを取って、お出かけをしたり、家族と過ごしたりする期間として1950年代頃から定着しました。みなさんもご家族で楽しい時間を過ごし、リフレッシュしてくださいね!
締め・まとめの文例
天気が安定し、戸外遊びが楽しい時期です。子どもたちと一緒にいろんな場所に出かけ、思いきり体を動かして遊びたいと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
新年度のスタートから1ヶ月が経ち、新生活に慣れた子どもたち。これから楽しい時間を一緒に共有し、信頼関係を築いて行きたいと思います。
装飾で使える!5月用のフリーイラスト素材
こいのぼりのイラスト
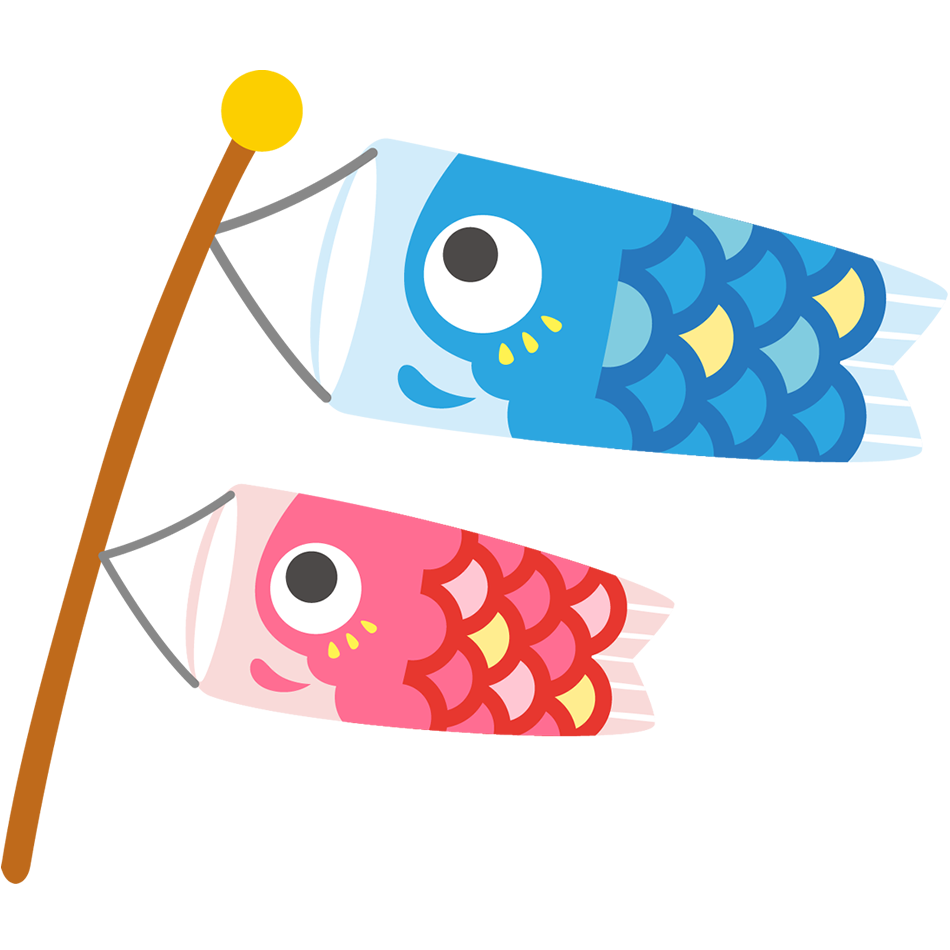
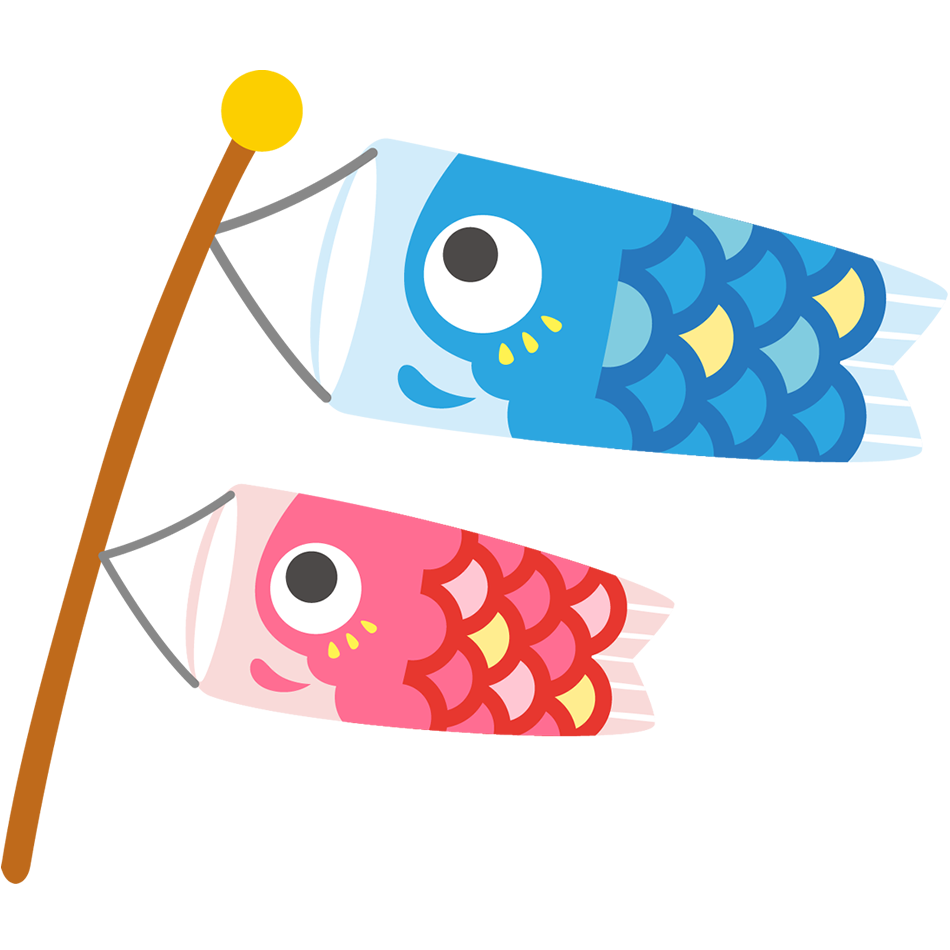
ダウンロードページURL:鯉のぼりのイラスト | 園だより、おたよりで使えるかわいいイラストの無料素材集【イラストだより】
カーネーションのイラスト
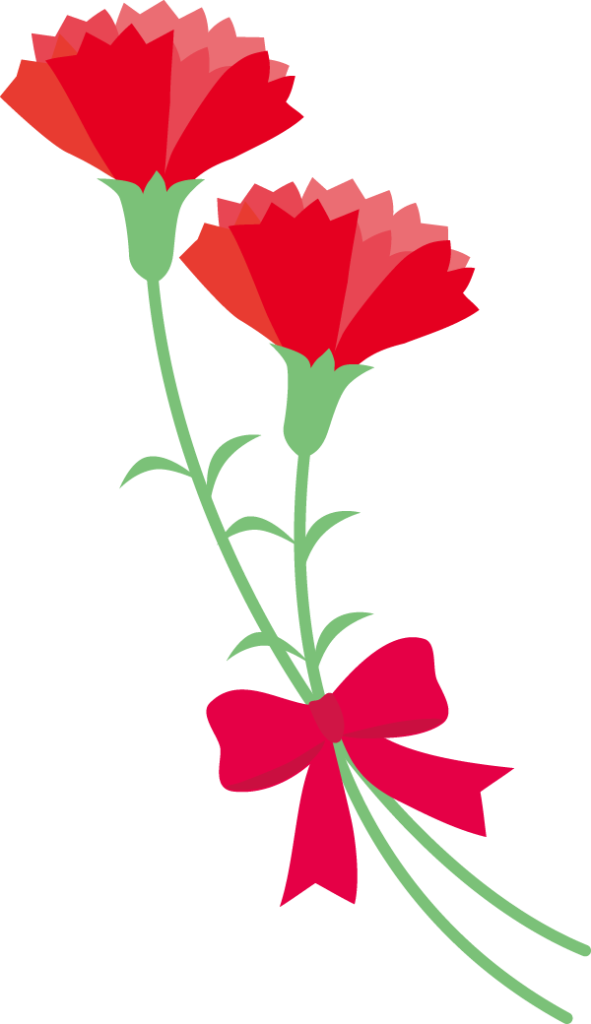
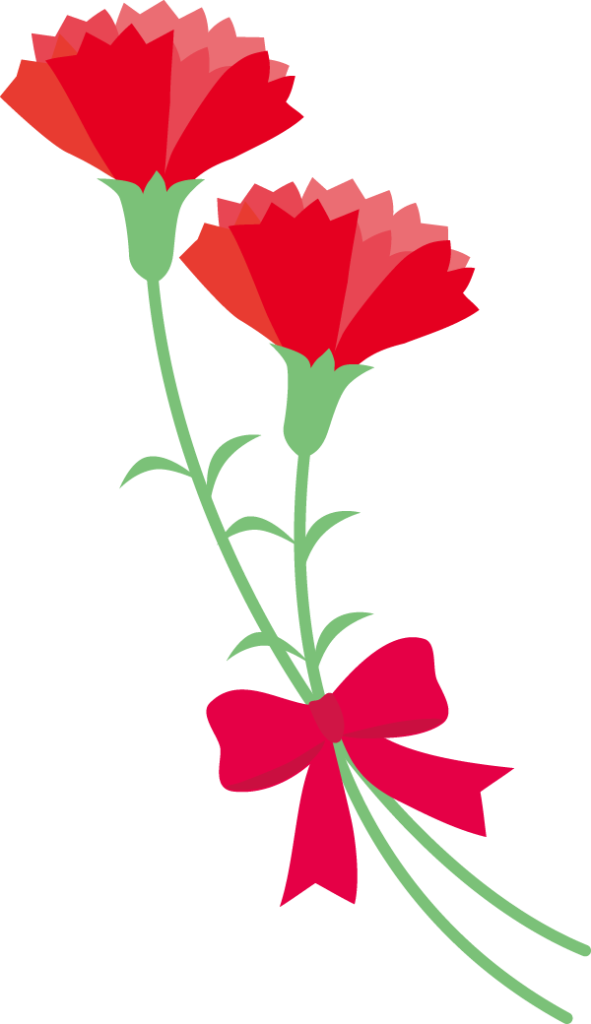
ダウンロードページURL:カーネーションのイラスト(母の日) | 園だより、おたよりで使えるかわいいイラストの無料素材集【イラストだより】
今回のまとめ
今回は、5月の園だよりを作成する際のポイントを解説しました。
入園・進級からの1ヶ月間の子どもたちの様子を盛り込むことで、我が子の成長を振り返ることができ、園生活への期待感を高めることにもつながります。
ぜひ今回の記事を参考にして、保護者に喜んでもらえる魅力的な園だよりを作成してくださいね。
そのほかの月の園だより/おたより文例
-


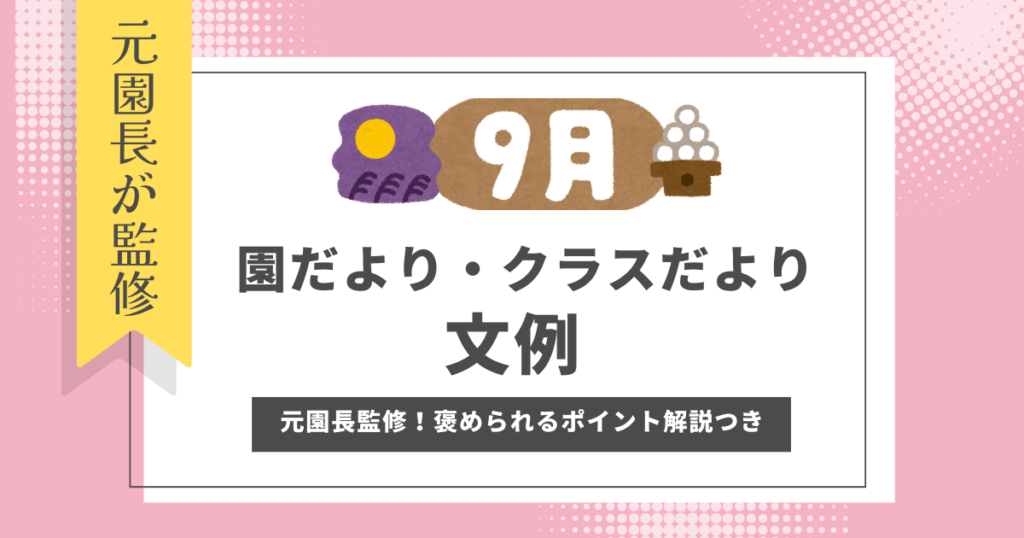
元園長監修【9月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


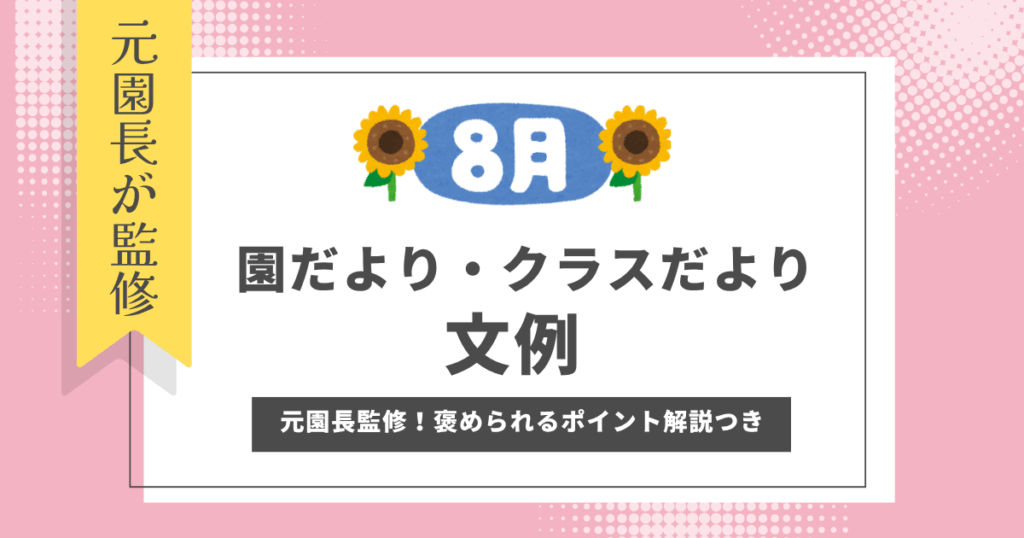
元園長監修【8月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


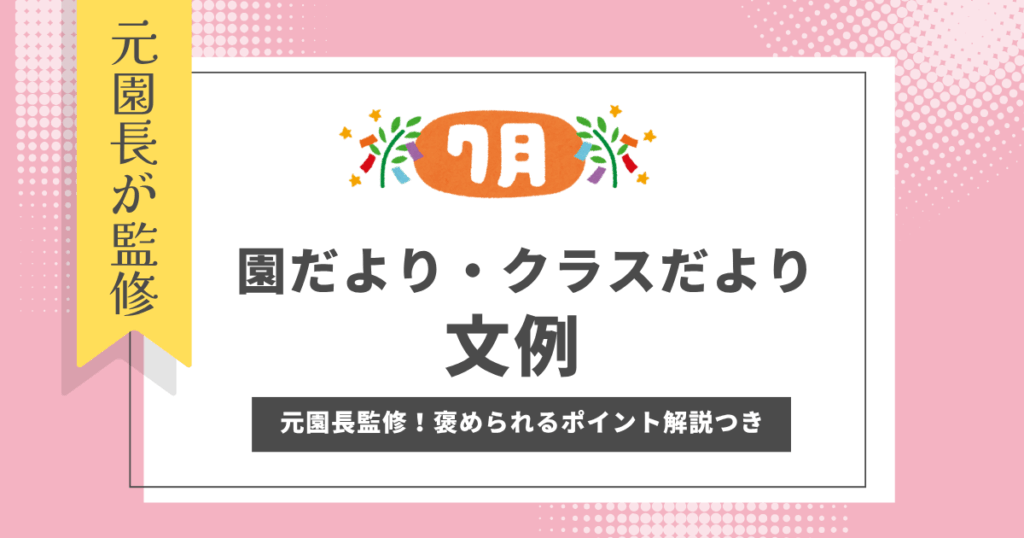
元園長監修【7月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


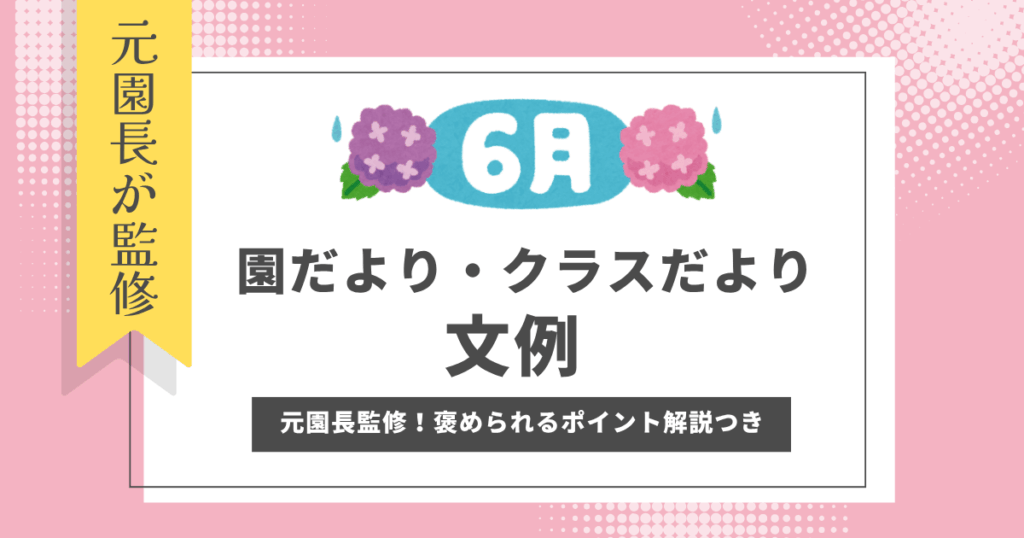
元園長監修【6月おたより文例】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア例文集
-


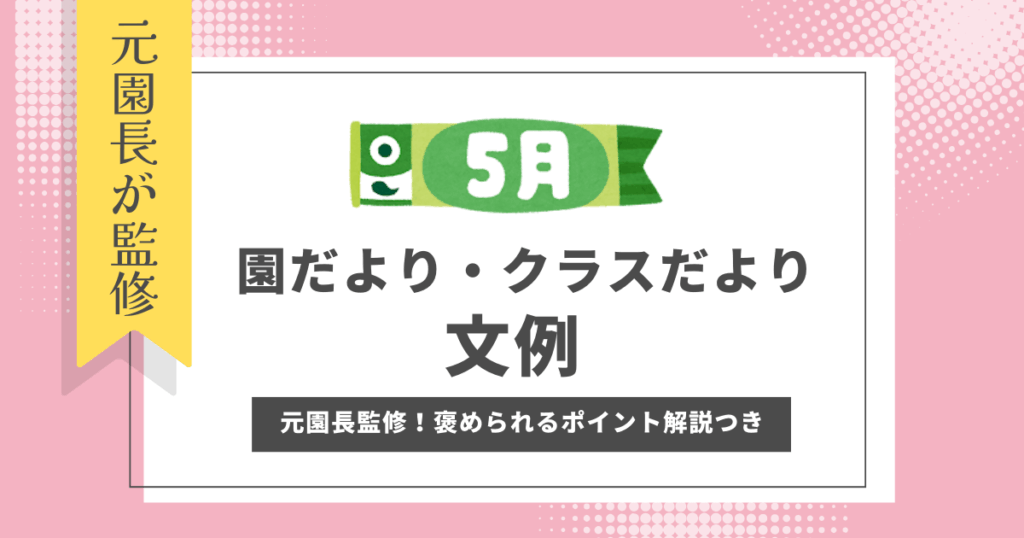
元園長監修【5月おたより】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア文例
-


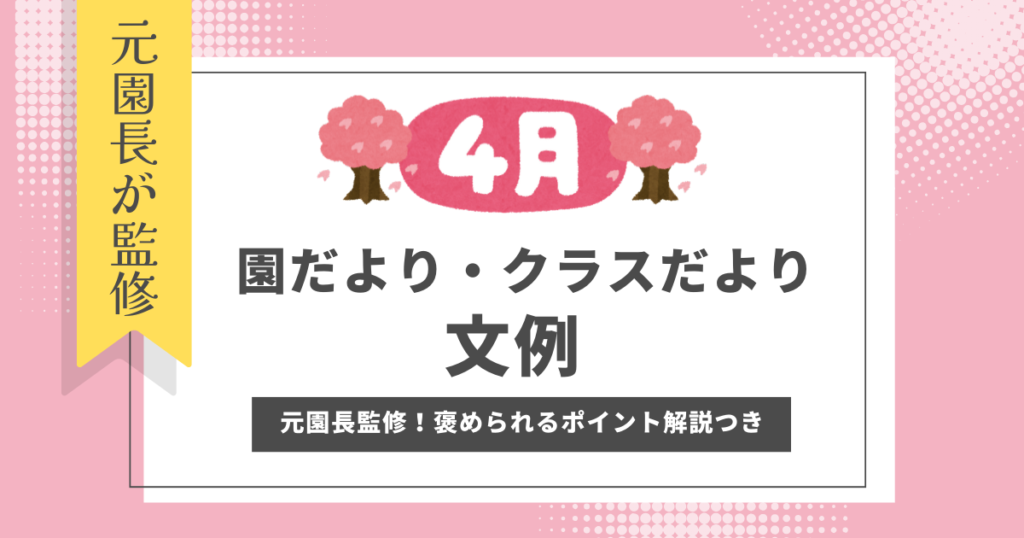
元園長監修【4月・おたより】園だより/クラスだよりの書き出し・アイデア文例